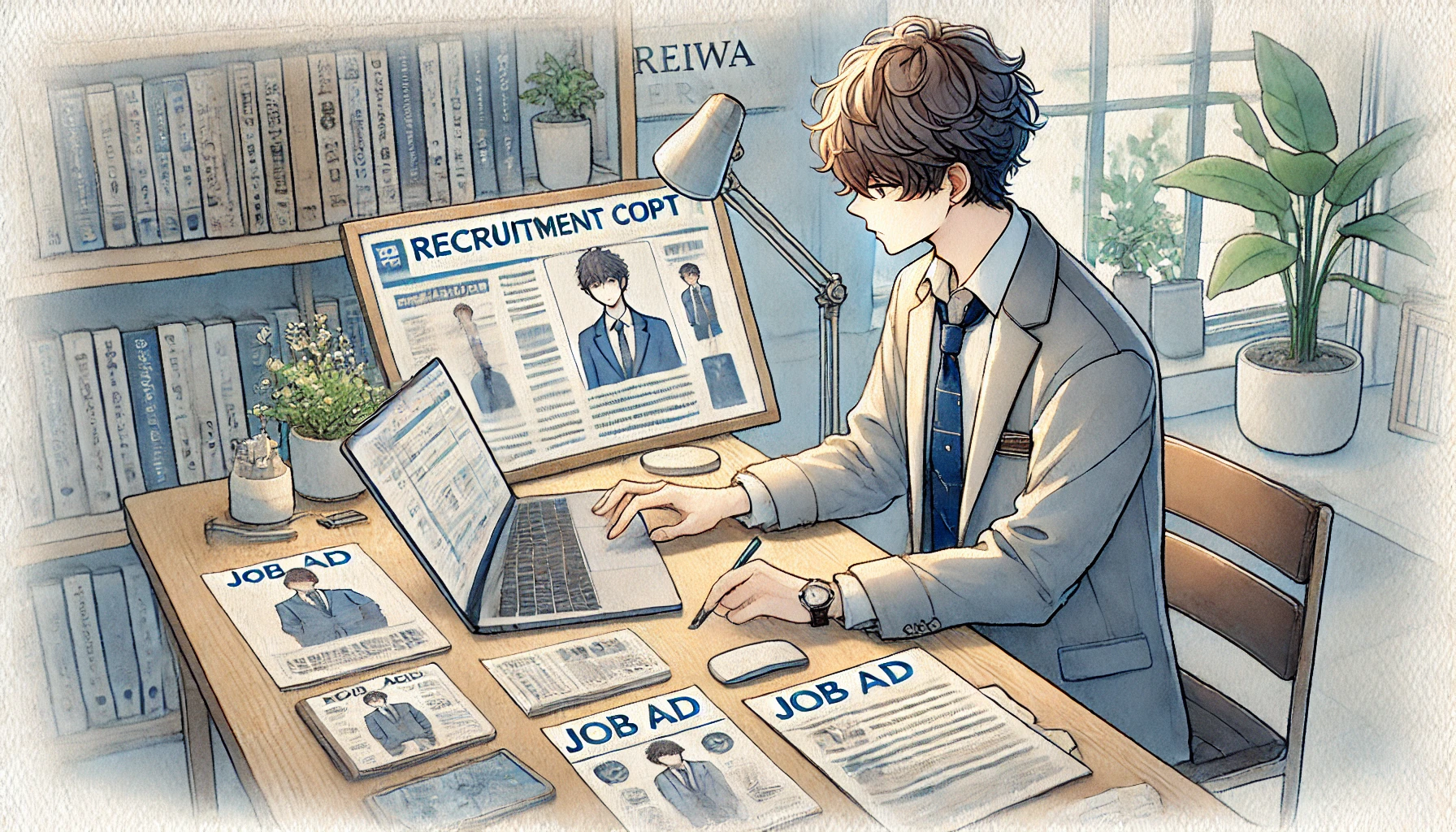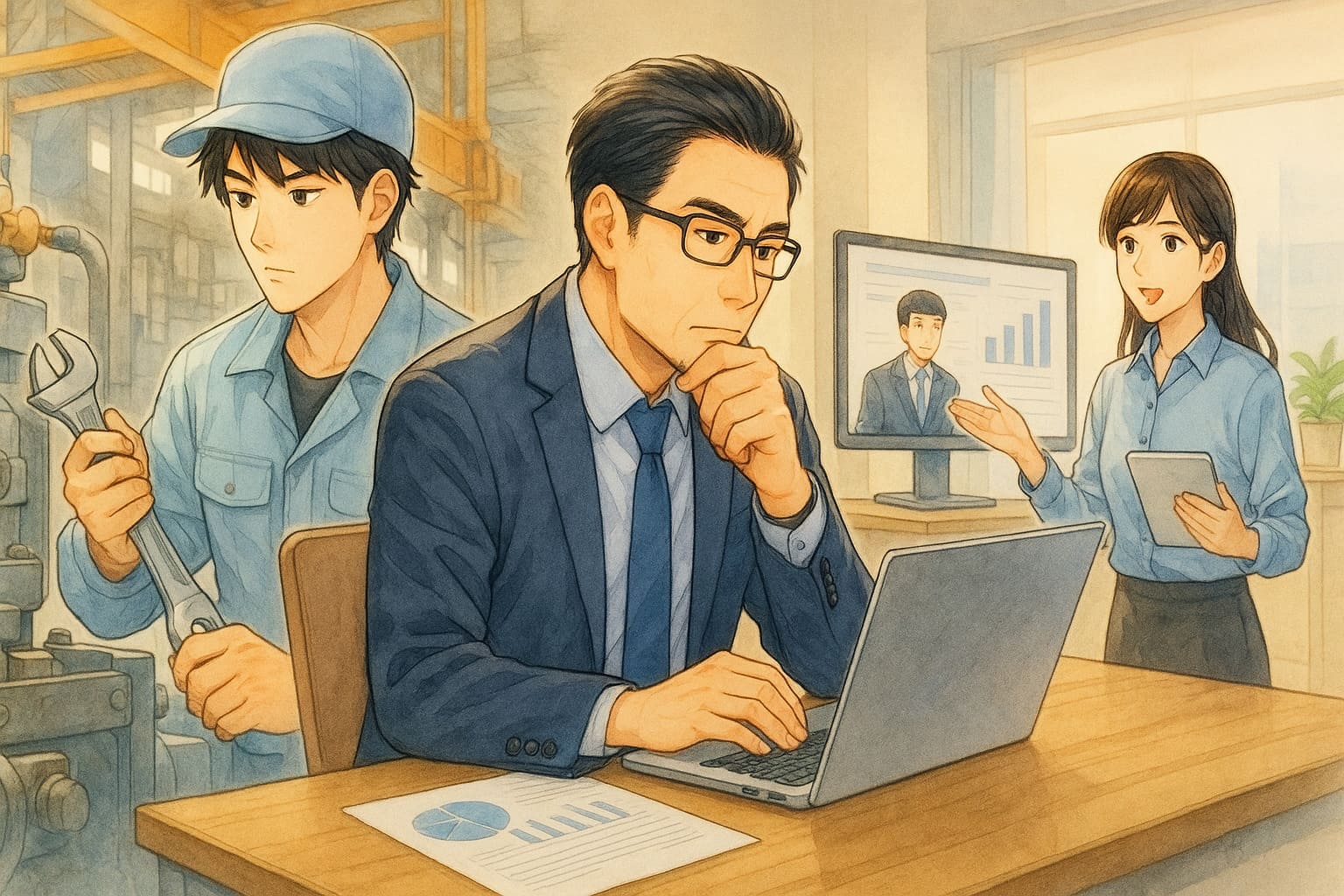「厳しいだけの指導」と「ハラスメント」はどこで分かれるのか。
この判断を誤ると、企業は法的リスクを抱えることになります。
人事担当者として、客観的かつ法的に正しい判断軸を持つことが重要です。
本記事では、厚労省の指針をベースに、現場での事例とともに解説します。
第1章 はじめに:境界線を見極める重要性

厳しい指導とパワハラの曖昧な境界
企業の現場では、「厳しい指導」と「パワーハラスメント」の線引きが非常に難しい場面が多く見られます。
特に管理職や上司による言動は、業務の成果を上げるための指導なのか、それとも人格や尊厳を侵害する不当な行為なのか、その判断が一筋縄ではいきません。
例えば、業務の納期が迫る中での叱責。
上司にとっては成果を出すための正当な指導でも、受け手には精神的攻撃として受け止められることがあります。
こうした「認識のズレ」が、ハラスメント問題の温床になります。

正直、このズレはどの会社でも起こり得るんですよね
人事担当者が誤った判断をした場合の企業リスク
人事担当者がこの境界線を見誤ると、企業は深刻なリスクに直面します。
代表的なものは以下の3つです。
-
訴訟リスク
パワハラが認定されれば、損害賠償請求や和解金の支払いが発生します。
また、裁判記録は公になる可能性があり、企業の社会的信用を損ないます。 -
行政指導リスク
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づき、ハラスメント防止措置義務違反があれば労働局からの是正指導が行われます。
これに従わない場合、企業名の公表という大きなダメージを受けることもあります。 -
評判低下リスク
社内外で「ハラスメント体質の企業」というイメージが広まると、採用力の低下や離職率の上昇に直結します。
特にSNS時代は、情報が一瞬で拡散されるため影響が甚大です。

人事の判断一つで会社の評判が左右されるって重い話ですね
本記事の目的:即判断できる軸の提示
本記事では、人事担当者や労務管理を担う方が、
「これは正当な指導なのか、それともパワハラなのか」を迅速かつ客観的に見極めるための判断軸を提示します。
そのために、法的定義や厚生労働省のガイドライン、具体的な判断基準、そして調査・証拠収集の実務まで段階的に整理していきます。
この記事を読み終える頃には、曖昧さに悩まされることなく、社内で確かな判断を下せる視点が身についているはずです。
第2章 上司によるハラスメントの法的定義と6類型

厚労省の定義とパワハラ防止義務
厚生労働省は、職場におけるパワーハラスメント(以下パワハラ)を次のように定義しています。
職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境を害するもの。
この3要件がすべて満たされた場合にパワハラと判断されます。
さらに、2020年6月施行(中小企業は2022年4月から義務化)の労働施策総合推進法により、企業はパワハラ防止のための雇用管理上の措置義務を負うことになりました。
この義務には、社内方針の明確化、相談窓口の設置、事後対応、再発防止策が含まれます。

法律で義務化されている以上、「放置」はありえなですね
6類型の概要と具体例
厚労省は、パワハラを具体的に理解しやすくするために、次の6類型を提示しています。
-
身体的攻撃
暴行や傷害など、直接的な身体的接触を伴う行為。
例:叩く、殴る、物を投げつける。 -
精神的攻撃
脅迫、中傷、侮辱、暴言など、精神的な苦痛を与える行為。
例:人格否定、必要以上の叱責、大勢の前での罵倒。 -
人間関係からの切り離し
業務上必要な範囲を超えて、特定の社員を孤立させる行為。
例:会議から外す、重要な連絡を意図的に伝えない。 -
過大な要求
明らかに遂行不可能な業務を命じる行為。
例:不可能な納期設定、担当外の大量業務を押し付ける。 -
過小な要求
本来の能力や経験から見て明らかに低い業務のみを与える行為。
例:専門職を雑用だけに従事させる、長期間にわたって責任ある業務を外す。 -
個の侵害
私的な領域に過度に立ち入る行為。
例:家庭状況や交際関係を執拗に尋ねる、プライベートに干渉する。
「指導」との境界が曖昧になりやすい類型
特に注意が必要なのが精神的攻撃と過大要求です。
これらは一見すると「業務指導」に見えるケースが多く、誤解や認識の相違が発生しやすい類型です。
例えば、成果を上げさせるための叱責が、内容や言い方次第では精神的攻撃に該当します。
また、チャレンジングな目標設定と、明らかに達成不可能な業務命令は、紙一重の差しかありません。

ここを間違えると、人事の信用も一気に失います
そのため、人事担当者は「業務目的」「方法の適正さ」「頻度や継続性」を必ず確認する必要があります。
これらの視点は、第3章で解説する判断基準にも直結します。
第3章 正当な指導とパワハラの境界線を判断する3つの基準

基準①:目的の正当性(業務遂行に必要か)
判断の第一歩は、その行為の目的が業務遂行に必要かどうかです。
例えば、納期を守るための残業指示や、品質を維持するための改善指導は、原則として正当な目的を持っています。
一方、感情的な苛立ちや個人的な好悪での叱責は、業務上の正当性がありません。
目的の正当性を判断する際は、
-
業務目標との関連性
-
業務遂行上の合理的必要性
を確認する必要があります。

感情で動いた時点で、指導は一線を越えてしまいます
基準②:手段の相当性(必要以上に人格否定や威圧がないか)
目的が正当でも、手段が必要以上に厳しければパワハラになります。
具体的には、人格否定や威圧的な言動、周囲の前での過度な叱責などです。
例えば、仕事のミスを指摘する際に、「このやり方は効率が悪い」という業務改善の指摘は相当な範囲です。
しかし「お前は本当に使えない」という発言は、業務改善ではなく人格否定です。
この基準では、指導の表現方法・場所・タイミングが大きなポイントになります。
冷静な言葉での指導は許容範囲でも、同じ内容を怒鳴りながら言えば相当性を欠く可能性があります。

指導内容より“どう伝えたか”の方が争点になりやすいんです
基準③:頻度・継続性(単発か、執拗か)
単発で業務上必要な指導を行う場合と、繰り返し同じ対象に執拗に行う場合では評価が異なります。
パワハラと認定されるケースの多くは、この「頻度と継続性」が高い事案です。
例えば、1度の残業命令は業務上やむを得ない場合もあります。
しかし、特定の社員だけに恒常的に長時間残業を課す場合、それは過大要求や不公平な扱いとしてパワハラに該当する可能性が高くなります。
実務での判断例:佐藤部長のケース
事例:
佐藤部長が、新入社員Aさんに対し、3か月間ほぼ毎日3時間以上の残業を命じた。
業務は通常の担当者であれば定時〜1時間程度で終えられる内容。
判断ポイント:
-
目的の正当性:納期や品質維持など業務上の必要性がなかった場合、正当性を欠く。
-
手段の相当性:他の社員と比べてAさんだけに過大な負担を課していれば不相当。
-
頻度・継続性:3か月間ほぼ毎日という継続性は、パワハラと判断されやすい。
このケースでは、目的・手段・頻度の3基準すべてで問題があり、パワハラ認定の可能性が極めて高い事案といえます。
この3つの基準を押さえることで、人事担当者は曖昧な状況でも客観的な判断が可能になります。
次章では、この判断を裏付けるための社内調査と証拠収集のポイントについて解説します。
第4章 社内調査の進め方と証拠収集のポイント

被害者・加害者双方の聞き取り方法
パワハラ疑惑が発生した際の社内調査では、公平性の確保が最優先です。
まずは被害者から事実関係を丁寧に聴取します。
この際、聞き取りには必ず人事担当者ともう1名(コンプライアンス担当など)を同席させます。
一方的な印象を避けるため、加害者側にも同様の条件で聞き取りを行いましょう。
聞き取り時のポイントは以下の通りです。
-
感情的な反応を避け、事実確認に徹する
-
発言は逐一記録に残す
-
推測や憶測ではなく、具体的な出来事を引き出す質問を行う

片方だけの話で判断すると後で必ず揉めてしまいます
メモ・録音・メールなど証拠の残し方
パワハラ案件の調査で重要なのは、客観的な証拠です。
人事担当者の印象や当事者の感情だけでは、後から検証ができません。
有効な証拠の例:
-
聞き取り内容の逐語記録(日時・場所・参加者名を明記)
-
当日の会話の録音(本人の同意を得た上で実施)
-
メールやチャットツールのやり取り(業務指示や叱責の記録)
-
目撃者の証言メモ(複数の証言が一致すれば信憑性が高まる)
証拠は日付順に整理し、後で第三者が見ても経緯がわかるようにまとめることが重要です。

証拠は時系列で並べると説得力が段違いです
調査チームの編成
社内調査は、個人ではなくチーム体制で行うことで公平性と客観性を担保できます。
一般的な編成例は以下の通りです。
-
人事担当者:調査全体の指揮と進行
-
コンプライアンス担当:法的観点からの助言
-
外部顧問(弁護士・社労士):調査方法や判断基準の妥当性確認
外部顧問の関与は、社内だけでは判断が難しいケースや、後に訴訟になる可能性がある場合に特に有効です。
実際に起こった社内事例
ある中堅メーカーでは、課長による部下への繰り返しの叱責が問題となり、被害者からの申告を受けて社内調査が始まりました。
当初は課長本人が「業務指導の一環」と主張していましたが、被害者と目撃者の証言、そして業務チャットに残された発言記録から、人格否定と取れる表現が多数確認されました。
この事例では、証拠の一貫性と第三者の証言が決め手となり、懲戒処分と再発防止策が実施されました。
次章では、このような初動調査で失敗するとどのような企業リスクを招くのか、具体例をもとに解説します。
第5章 初動対応の失敗が招く企業リスク

調査前に軽く扱ったことで訴訟になった事例
あるIT企業で、チームリーダーによる部下への叱責が繰り返し発生していました。
部下からの相談を受けた人事担当者は、「本人同士で話し合ってみてはどうか」と返答し、そのまま様子を見る判断をしました。
結果的に、その後もハラスメントと受け取られる発言が続き、被害者は心身の不調で休職。
最終的には損害賠償請求訴訟へと発展しました。
裁判では、初動で適切な調査を行わず、事実確認も証拠収集もしなかったことが企業の責任を重くしました。
この事例は、軽視した対応が法的リスクの火種になる典型例です。

「軽く扱う」は一番やっちゃいけない対応です
「様子見」や「個人間の問題」と片付けた結果の影響
もう一つ多いのが、「様子見しよう」「これは個人間の相性の問題だ」という判断です。
表面的には一時的に収まったように見えても、水面下では不信感が蓄積されます。
放置された被害者は「会社は守ってくれない」と感じ、モチベーション低下や退職につながります。
さらに、ハラスメント行為を行った側も「特に問題にならなかった」という誤った安心感を持ち、行動がエスカレートするケースもあります。
結果として、組織全体の風土悪化や離職率の上昇につながり、長期的な企業価値の毀損を招きます。

放置は加害者にも被害者にも悪影響しかないんです
人事担当者が押さえるべき初動の鉄則
初動対応は、スピードと正確さが命です。
以下の3つは必ず押さえておくべき鉄則です。
-
即記録
相談を受けた時点で、日時・場所・発言内容・関係者名を詳細に記録する。
メモやデジタル記録は、後の証拠としても活用可能です。 -
即報告
直属の上司や人事責任者、必要に応じてコンプライアンス部門へ迅速に共有する。
情報が滞ると、対応の遅れや証拠喪失の原因になります。 -
即対話
被害者側・加害者側の双方と早期に対話の場を設ける。
事実確認を先送りにすると、関係者の主張が変化したり記憶が曖昧になる恐れがあります。
初動対応の遅れは、企業リスクを倍増させます。
次章では、このリスクを回避し、長期的にハラスメントを防ぐための研修・規程改定の実務を解説します。
第6章 再発防止に向けた研修・規程改定の実務
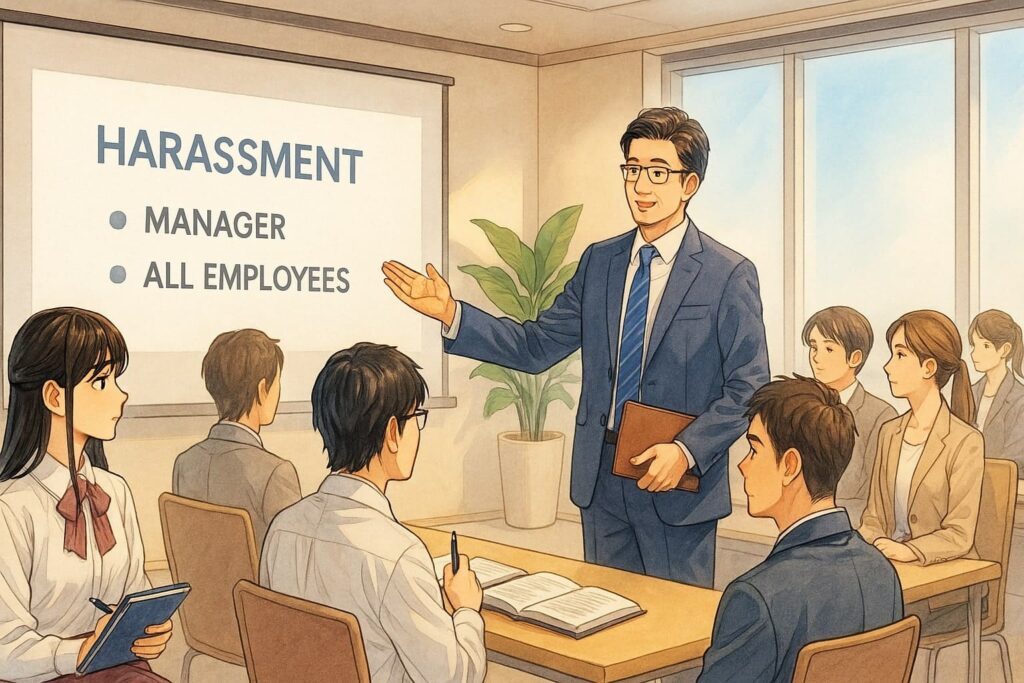
ハラスメント防止研修の設計ポイント
再発防止には、単発の注意喚起ではなく継続的な教育プログラムが欠かせません。
特に、管理職と全社員では研修の目的と内容を分けることが効果的です。
-
管理職研修
・部下指導の適正な方法と境界線の理解
・不適切行為の早期発見と報告義務
・事案発生時の初動対応手順 -
全社員研修
・ハラスメントの定義と6類型の理解
・被害者・目撃者としての適切な行動
・相談しやすい職場環境の作り方
研修は座学だけでなく、ロールプレイ形式で実際の会話例を体験することで理解度が高まります。

やっぱり現場での疑似体験が一番身に付くんです
規程の見直し:定義、相談窓口、懲戒規定の明確化
防止策の根幹は、社内規程の整備にあります。
見直すべき主なポイントは次の通りです。
-
定義の明確化
厚労省の定義をベースに、自社の業務内容や組織文化に沿った形で具体例を記載します。 -
相談窓口の設置
人事部門以外にも、複数の相談経路を用意することで利用率が上がります。 -
懲戒規定の明確化
行為の内容・程度に応じた懲戒処分の種類と基準を明文化し、社内に周知します。
これにより、発生時の対応が迅速かつ一貫性を持って行えるようになります。
実効性を高める仕組み
規程や研修だけでは機能不十分な場合があります。
実効性を高めるために、以下のような制度の導入が有効です。
-
匿名相談制度
匿名での通報を可能にし、心理的ハードルを下げる。 -
外部ホットライン
弁護士や外部専門家が直接対応する窓口を設置し、社内への不信感による通報抑制を防ぐ。 -
定期アンケート
職場環境や上司の行動に関する調査を定期的に実施し、傾向を把握する。

匿名性があるだけで相談件数は確実に増えます
他社の成功事例紹介
ある製造業の企業では、管理職向けのハラスメント防止研修を年2回実施。
さらに、匿名相談制度と外部ホットラインを組み合わせた結果、相談件数が前年比で2倍に増加しました。
これにより潜在的な問題を早期に把握でき、重大な案件に発展する前に対応が可能になった事例です。
また、IT系企業では、規程改定に合わせて懲戒規定を具体的に数値化(例:「同一対象に週3回以上の叱責が続いた場合は懲戒対象」)することで、判断基準の曖昧さを排除し、処分の公平性を高めています。
次章では、こうした社内対策に加えて、外部機関との連携方法と使い分けについて解説します。
第7章 外部機関との連携方法と使い分け

労働局あっせん制度の概要と利用ケース
労働局の「あっせん制度」は、労働者と事業主の間で発生した個別労働紛争を、第三者(あっせん員)が間に入って解決へ導く制度です。
パワハラ事案では、特に社内調査で結論が出ない場合や当事者間の溝が深い場合に活用されます。
特徴として、
-
利用は無料
-
当事者双方の合意が必要
-
裁判より迅速に解決できる
-
合意内容は法的拘束力はないが、履行率は高い
利用ケースの例:
社内調査で事実はある程度確認できたが、処分や謝罪方法について意見が対立し、平行線をたどった場合。

無料で使えるのに知らない人事担当者が多いんですよね
弁護士・社労士への相談タイミングと費用感
パワハラ問題が複雑化した場合、弁護士や社会保険労務士(社労士)への相談は非常に有効です。
相談タイミングの目安は以下の通りです。
-
弁護士:法的責任の有無や損害賠償請求の可能性がある場合
-
社労士:就業規則や懲戒規定の整備、労務管理体制の改善が必要な場合
費用感(目安):
-
弁護士相談:30分〜1時間で5,000〜10,000円程度
-
社労士相談:1時間5,000〜8,000円程度(顧問契約は月額2〜5万円程度)
顧問契約を結んでおくと、事案発生時に即時対応が可能となり、初動の遅れを防げます。
外部第三者の関与が有効なパターン
以下のような場合、社外の第三者を関与させることで調査の信頼性と透明性が高まります。
-
社内で利害関係が複雑な場合(経営層や複数部署が関与)
-
被害者が社内調査に不信感を持っている場合
-
重大な懲戒処分や損害賠償の判断が必要な場合
-
社外への情報公開や報道対応が懸念される場合
第三者を入れることで、「会社が隠蔽しているのでは」という疑念を払拭できます。

外部が入るだけで当事者の態度が変わることも多いんです
事例:社内調査で埒が明かず労働局に相談したケース
あるサービス業の企業では、店舗責任者による部下への精神的攻撃が疑われました。
社内調査を行ったものの、加害者側が強く否認し、証拠も一部しか揃わない状況。
このままでは対応方針が固まらないと判断し、労働局のあっせん制度を利用しました。
結果、第三者が介入することで双方の主張が整理され、加害者による正式な謝罪と異動、被害者の職場復帰支援という形で合意に至りました。
次章では、ここまでの内容を振り返りつつ、人事の判断力が企業を守る理由をまとめとしてお伝えします。
第8章 まとめと感想|人事の判断力が企業を守る

各章の要点整理
ここまで、上司によるハラスメントをめぐる境界線と対応の実務について8つの視点から解説してきました。
あらためて要点を整理します。
-
法的定義と6類型の理解(第2章)
厚労省の定義と労働施策総合推進法による防止義務を押さえ、身体的攻撃から個の侵害までの6類型を具体例とともに把握すること。 -
判断基準の明確化(第3章)
「目的の正当性」「手段の相当性」「頻度・継続性」という3つの軸で、正当な指導とパワハラを客観的に区別すること。 -
社内調査と証拠収集(第4章)
被害者・加害者双方の公平な聞き取り、メモ・録音・メールなどの証拠確保、チームでの調査体制が不可欠であること。 -
初動対応の重要性(第5章)
軽視や様子見は法的リスクや評判低下を招くため、「即記録・即報告・即対話」が鉄則であること。 -
再発防止策の導入(第6章)
管理職・全社員研修の実施、規程の見直し、匿名相談制度や外部ホットラインの活用など、継続的な仕組みを構築すること。 -
外部機関の効果的活用(第7章)
労働局あっせん制度や弁護士・社労士との連携で、調査の透明性と解決力を高めること。
人事の迅速かつ公正な判断が企業価値を守る
ハラスメント対応は、単なる労務管理の一部ではありません。
企業の信頼、採用力、社員の定着率といった企業価値そのものを左右する経営課題です。
人事担当者が迅速かつ公正に判断できる体制を整えることで、問題の早期解決と再発防止が可能になります。
その判断力は、単にトラブルを防ぐだけでなく、安心して働ける企業文化を育てる礎にもなります。

人事の一言が会社の将来を変えることだってあるんです
読者の皆さんへ
ハラスメントの判断に迷ったときは、必ず記録を残すことと第三者の目を入れることを忘れないでください。
感情や先入観に左右されず、事実に基づいた判断を重ねることが、最終的に企業と社員を守ります。
あなたの判断力と行動が、組織の信頼を守る最後の砦です。
今日からできる一歩として、社内の相談体制や規程、証拠記録の方法をあらためて見直してみてください。