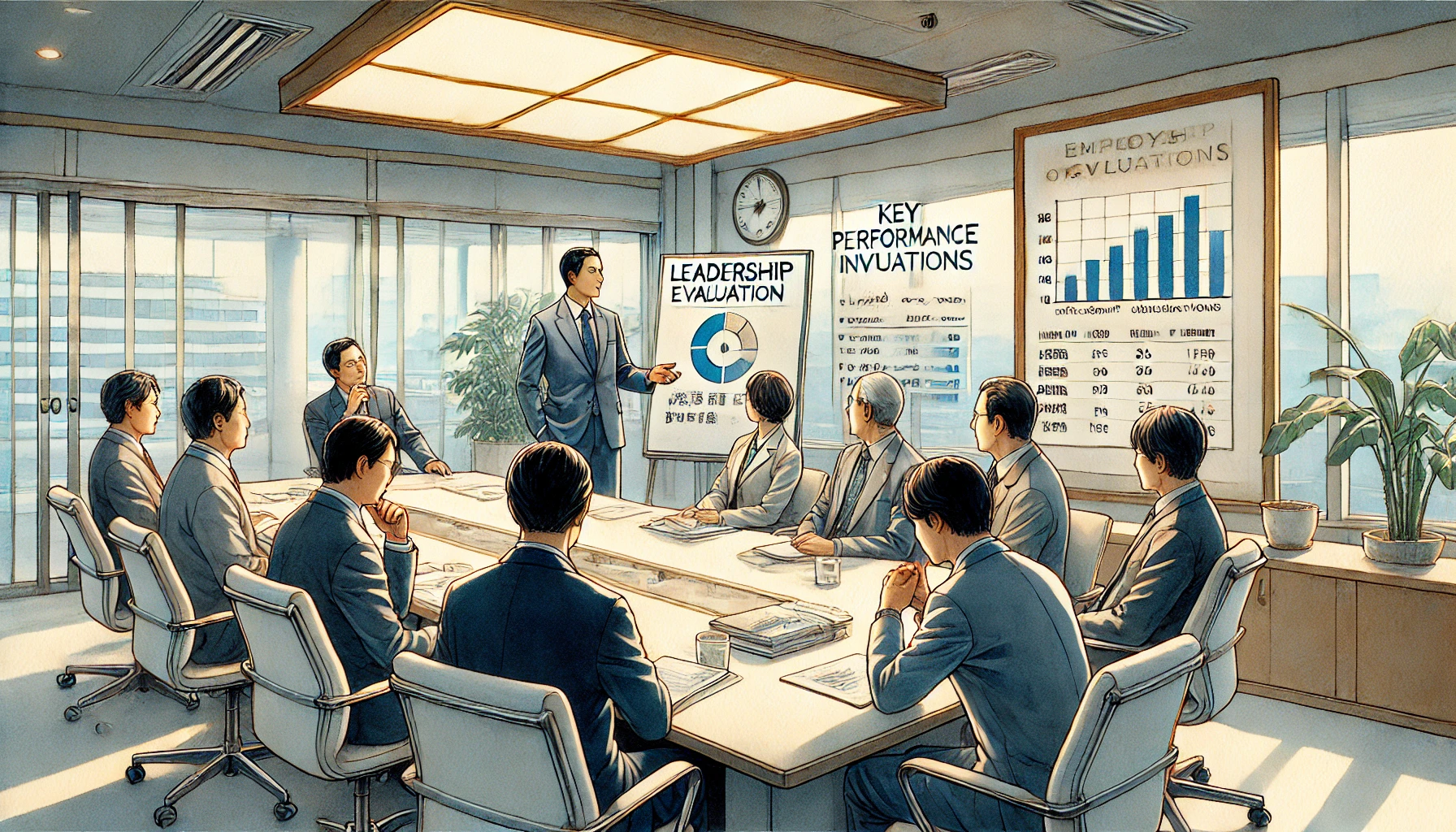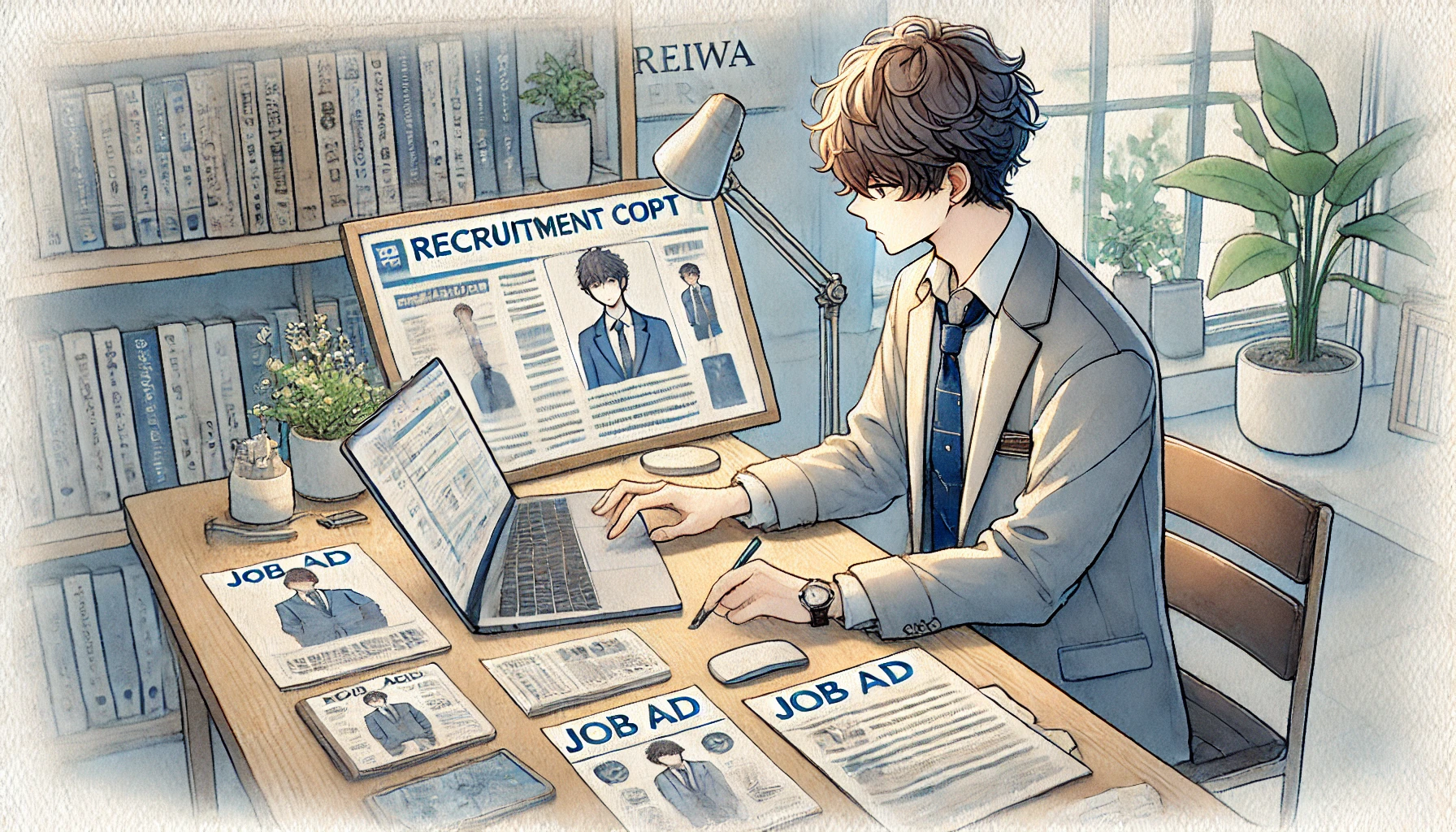「人手不足の仕事って本当に安定?」と疑問に思う方へ。
この記事では、厚生労働省や業界データをもとに、人手不足が深刻な業界とその理由を整理しています。
さらに、狙い目職種として未経験でも採用されやすい求人をピックアップ。
人事・採用担当者や転職準備中の皆様に、根拠ある意思決定をサポートします。
【第1章】人手不足が深刻化する本当の理由
業界別に見る「人手が足りない」現実
いま、日本全体で“人手不足”というキーワードが日常会話にまで浸透するほど、働き手の確保が深刻な課題となっています。
特に、以下の業界では構造的な人手不足が長期化しています。
■介護業界
厚生労働省の調査によれば、2040年には介護職員が約69万人不足すると推計されています。
高齢者人口の増加に対し、担い手となる若年層が不足しており、現場では「シフトが埋まらない」「夜勤に入れる人材がいない」といった声が日常的に上がっています。

現場に行くと、疲弊した表情の管理者が多いのが現実です。
■建設業界
国土交通省によると、建設業の就業者の約4割が55歳以上です。
つまり、10年先を見据えたとき、技能伝承の空白が確実に起こる業種といえます。
一方で、若手の定着率が低く、職人離れが加速しています。
■物流・運送業界
いわゆる「2024年問題」で注目されているのがこの業界です。
トラックドライバーに対する時間外労働の上限規制により、労働時間が減る=配送量も減るというジレンマが起きています。
特に中小の運送会社では、ドライバー確保が業績に直結する事態です。
■IT業界
デジタル庁創設やDX推進の流れを受けて、IT人材の需要は爆発的に増えています。
一方で、実務経験者が圧倒的に不足しており、特に中堅SEクラスの採用が困難です。
ITは“高スキルが必要・育成に時間がかかる”職種の代表でもあります。

「育てて戦力にする時間すらない」…そんな嘆きをよく聞きます。
採用難を生み出す「人口構造の変化」
少子高齢化の影響は、労働市場に大きく表れています。
生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少し続け、今後も加速度的に減っていくとされています。
結果、企業の間で人材獲得競争が激化。
特に地方都市やニッチ業種では、“そもそも応募が来ない”という現象すら日常になっています。
ミスマッチが人材供給をさらに困難に
企業が求める人物像と、求職者のニーズの間にギャップがあるケースも目立ちます。
たとえば、企業は「週5日・フルタイムで出勤できる人」を求めていても、求職者は「週3日」「在宅勤務希望」など、ライフスタイルを重視した働き方を求めている。
また、給与・待遇だけでなく、職場の雰囲気や柔軟な働き方といった“非数値的な条件”が決め手となる時代に突入しています。
企業がそれを理解せずに従来の求人スタイルを続けてしまうと、当然ながら応募も少なくなり、「募集しても集まらない」状態に陥ります。
本章のまとめ
人手不足の根底には、「人口構造の変化」「業界ごとの構造的課題」「採用ミスマッチ」の3つの要因が複雑に絡み合っています。
単なる“働き手不足”ではなく、“働き手と仕事の結びつきがうまくいっていない”という視点が重要です。
次章では、このような人手不足を背景に、「どの仕事なら採用されやすいのか」「どんな職種が今後も安定しているのか」といった実践的な視点で深掘りしていきます。
【第2章】すぐに働ける!人手不足職種7選
即戦力が求められる仕事の共通点とは?
「とにかく明日からでも働ける人がほしい」。
そんな声が現場から日々あがっているのが、いわゆる“人手不足職種”です。
共通点は以下の3つです。
-
業務がシンプルかつ現場ベースで完結する
-
高い専門スキルよりも“すぐ動けるか”を重視
-
スタッフの入れ替わりが激しい=常に求人が出ている

「履歴書不要」「面接なし」っていう求人も本当に多いですね。
こうした職種は、応募から採用までのスピードが速く、スキマ時間や短期間の仕事を探す人にもフィットしやすい傾向にあります。
未経験でも採用されやすい!人手不足7職種
それでは、実際に「採用されやすい」職種を具体的に紹介していきます。
いずれも現場ニーズが高く、未経験からでもチャレンジしやすい業界です。
① 介護職(訪問介護・施設スタッフなど)
慢性的な人手不足が続く代表例。
資格がなくても“補助業務”からスタートできるため、未経験でも始めやすい。
特に夜勤や早朝のシフト枠は採用されやすい傾向があります。
② 飲食店スタッフ(ホール・調理補助)
人の出入りが多く、年末年始や長期休暇前後に求人が急増。
短期バイトや副業ニーズにもマッチしやすく、未経験歓迎の職場が多い。
③ 清掃・ビルメンテナンス業務
体力は必要だが、接客不要・黙々と作業できることから一定の人気あり。
特に早朝・深夜帯の求人は採用率が高い。
④ 倉庫・物流(仕分け・ピッキング)
EC需要の拡大により、荷物の取り扱いは増加傾向。
特別なスキルを必要とせず、日払い・週払いに対応する企業も多い。

物流系は男女問わず多様な世代が活躍しています。
⑤ 建設・解体作業員
即戦力となる人材を常に求めており、未経験でも「手元作業」から始められる。
日給1万円以上の案件も珍しくない。
⑥ コールセンター
マニュアル完備・教育体制も整っており、未経験でもスタートしやすい。
在宅OKの求人も増加中で、柔軟な働き方を求める人にも人気。
⑦ 農業・漁業・短期季節労働
地域や時期に応じて短期募集が出やすい。
住み込み・宿泊補助つきなど、地方での仕事を希望する人にもチャンスがある。
短期・単発OKの仕事の特徴
「まとまった期間働けない」「まずは1日だけ試したい」という人に向けて、単発・短期求人が増えています。
特徴は以下の通りです。
-
登録型派遣やアプリを介したマッチングが主流
-
勤務条件が明確で、応募から当日勤務までが早い
-
給与支払いが早く、日払い・即日振込もある
代表的なサービスとしては、「タイミー」「シェアフル」「Worknow」などが挙げられます。
短期でも「仕事のブランクを埋めたい」「スキルより経験を積みたい」と考える人には、有効な選択肢となるでしょう。
本章のまとめ
人手不足の仕事は、「未経験歓迎」「短期OK」「即日勤務可能」など、応募ハードルが低い案件が多く存在します。
なかでも、物流・介護・飲食・建設といった現場系の仕事は、求人件数も豊富でマッチングのスピードが速いのが特徴です。
次章では、「人手不足=ブラック」なのか?という問いにも触れつつ、“採用されやすい仕事のリアルな裏側”を覗いてみましょう。
【第3章】安定性×将来性で選ぶならこの業界
将来もなくならない仕事の条件とは?
「AIに奪われる仕事」「消える職業ランキング」──
こうした話題が注目される今、仕事選びの軸として「将来性」は外せません。
では、どんな仕事が「なくならない」と言えるのでしょうか?
共通している条件は、以下の3つです。
-
対人サービスが中心で代替が難しい
-
インフラ・医療・教育など生活インフラに直結している
-
変化対応力が求められ続ける分野
このような仕事は、人が介在する価値が残りやすく、需要が安定しているのが特徴です。

「人がやらなきゃいけない仕事」は、AI時代の生命線だと思います。
「人手不足=成長産業」の真実
「人手不足」と聞くとマイナスのイメージを持つ方も多いですが、視点を変えるとこれは「成長している証拠」とも言えます。
需要があるからこそ供給が追いついていない。
特に下記のような業界は、今後の人口動態や技術革新を見据えてもニーズが拡大していくと予測されています。
-
医療・介護:高齢化社会で長期的な需要あり
-
IT・デジタル関連:DX推進、デジタル人材の不足が深刻
-
インフラ・建設:老朽化対策、災害復旧などで人手は必須
これらの業界では、未経験から育てる仕組みも整えられつつあり、中途採用者にも門戸が開かれています。

人手不足の裏には、企業が「今すぐにでも人がほしい」という本音が見えます。
キャリア形成視点でのおすすめ業界
「今だけの仕事」ではなく、「未来にも続く仕事」を選ぶには、キャリア設計の視点が欠かせません。
以下は、将来の安定性・スキル資産性の両面から見ても有望な業界です。
医療・介護業界
資格が必要な職種もありますが、未経験からステップアップ可能。
地域密着の安定職でもあり、全国どこでも働けるのが強みです。
IT・デジタル領域
未経験からのエンジニア育成講座や研修付き求人も増加中。
「学ぶ姿勢」があれば、キャリアの伸びしろが大きい業界です。
インフラ・公共事業関連
電気、ガス、水道、通信などの安定性は圧倒的。
また、社会貢献性が高く、仕事の意義を実感しやすいというメリットもあります。
次章では、「求人票に隠された企業の本音」について深掘りしていきます。
求人情報を正しく読み解けるようになることで、より良いマッチングが可能になります。
【第4章】求人票に隠された“本音”の見抜き方
「未経験歓迎」=チャンス?それともリスク?
一見ありがたく見える「未経験歓迎」の文字。
しかし、その裏にある企業側の意図を見落とすと、入社後に後悔することにもつながります。
「条件がいい」だけでは危ない。読み解く力が必要です。
この言葉が使われる背景には、主に以下のパターンがあります。
-
そもそも人が定着しない(常に採用している)
-
業務が単純・誰でもすぐに覚えられる
-
教育体制が未整備(自力でなんとかしてほしい)
もちろん、本当に未経験から育ててくれる会社もあります。
ただし、頻繁に同じ求人を出している企業には注意が必要です。

求人票は“広告”と同じ。表現の裏側まで読んでほしいですね。
「人を大事にする会社」の見極め方
求人票からは見えにくいですが、企業文化や人への向き合い方は、採用文言や福利厚生の設計に反映されることが多いです。
以下のようなポイントに注目すると、“人をコストではなく資産として見る企業”かどうかを判断しやすくなります。
-
丁寧な研修制度やOJT内容が明記されているか
-
キャリアパスや評価制度について具体的に書かれているか
-
福利厚生の「使いやすさ」に配慮があるか(例:取得率の高い有休、時短勤務制度など)
さらに、採用ページに社員インタビューがあるかもチェックポイント。
社員の顔が見える企業は、情報開示にも前向きな傾向があります。

“待遇”より“扱い方”のほうが、働き心地を左右します。
口コミ・離職率・定着率のリアルな活用法
企業の内部事情を知る上で、「口コミ」や「離職率」は非常に有用な判断材料になります。
離職率・定着率の見方
一般的に、新卒の3年以内離職率が30%前後と言われます。
中途採用であっても、1年以内に3割が辞めているような企業は要注意です。
口コミサイトはどう使う?
OpenWorkやen Lighthouseなどの口コミサイトでは、社員の声が生々しく記載されています。
ただし、個別のコメントに振り回されず、複数年・複数部門の傾向を見て総合判断することが重要です。
たとえば「営業部門の離職が多いが、技術部門は安定」といった“局所的な人手不足”も読み取れます。
次章では、どんな働き方が今後のスタンダードになるのかをテーマに、「安定性×将来性」のある働き方を紹介します。
転職は「条件」だけでなく、「生き方」とセットで考える時代です。
【第5章】実録!人手不足職種で働いた体験談
「“人手不足”はチャンスか?リスクか?」
現場のリアルをお届けします。
実録①:物流倉庫で働いた35歳男性(元営業職)
転職前は営業職だった佐藤智也さん(仮名・35歳)は、未経験で物流業界へ。
「営業成績に疲れていたが、体を動かす仕事なら気が楽だろう」と倉庫作業へ転職。
最初の印象は、「想像よりはるかに過酷」。
特に夏場は空調が効かず、1日中汗だく。
しかし、仕事はマニュアル化されており、1週間ほどで慣れたとのこと。
待遇面は決して高給ではないが、「時間通りに帰れる安心感」と「精神的な安定」を得たという。
キャリアアップとして、半年後にはリーダー職に昇格し、作業から管理側に回る道も拓けた。

体を使う職場はキツいが、“感情の疲れ”から解放される面もあるんですね。
実録②:介護施設で働いた28歳女性(元販売スタッフ)
「人手不足と聞いていたけど、想像以上に“人が足りていない”」と話すのは、介護施設で働く斉藤由美さん(仮名・28歳)。
前職はアパレル販売。もっと人の役に立つ仕事をしたいと、未経験で福祉業界に挑戦した。
最初は「利用者との距離感」や「業務量の多さ」に戸惑ったが、
資格取得支援制度を活用し、初任者研修を取得してからは仕事のやりがいが倍増。
「名前を覚えてもらったり、笑顔で感謝されると頑張れる」と笑顔を見せる。
給与面では、「正直、他業界より高くない」。
ただし、夜勤や資格手当などで月収が安定的に増える構造がある点に魅力を感じたという。

“人手不足=ブラック”とは限らない。支援体制次第で大きく違うんです。
実録③:短期バイトで入った食品工場(20代男性)
大学卒業後、就職せずフリーター生活をしていた田村健太さん(仮名・26歳)は、求人アプリで見つけた「日払いOK」の食品工場で短期バイトを体験。
「人手不足のせいか、採用のハードルはゼロに近かった」とのこと。
実際の仕事は、ライン作業でひたすらお弁当に具を載せ続けるというもの。
単調だが、時間があっという間に過ぎるという意外な“ラクさ”もあった。
「この手の仕事は、割り切れるかどうかがカギ」と振り返る。
人間関係のストレスがなく、副業やスキマ時間に稼ぎたい人には向いていると分析していた。
実録から見えてきた“リアルな価値”
実際に人手不足の職場で働いた人たちの声からわかるのは、次の3点です。
-
想像よりハードだが、慣れや支援制度でカバーできることも多い
-
人手不足だからこそ、昇格やスキル取得のチャンスが早く回ってくることもある
-
労働環境の差が激しいので、事前リサーチと職場見学が重要
求人票だけでは見えない“リアルな現場”の声が、選択のヒントになるはずです。
次章では、「人手不足の職場で後悔しない選び方」について、見落とされがちな視点を紹介していきます。
体験談だけで決めず、冷静に「戦略的な選び方」を身につけましょう。
【第6章】企業はなぜ“あえて”人手不足業界を狙うのか
中小企業が“人手不足市場”に挑む理由
「採用しづらい市場」にこそ、チャンスが眠っている。
一見すると“避けるべき”に思える人手不足の業界。
しかし、私が支援してきた中小企業のなかには、あえてこの市場に打って出る企業も少なくありません。
なぜか?
それは「競合が少ないから」です。
大手企業が人材確保に苦戦しているということは、裏を返せば同業他社も同じく苦戦している。
つまり、採用の“勝負どころ”を見誤らなければ、確実に採れるポジションが存在するのです。

難易度が高い市場ほど、逆にブルーオーシャンだったりするんですよね。
たとえば、介護や物流の現場では、待遇を見直し、採用戦略を最適化しただけで応募が3倍に増えた事例もあります。
「できる人がいない」のではなく、「見せ方が悪い」だけというケースは多いのです。
“採れにくい仕事”にこそ、採用戦略の差が出る
「人手不足」という状況は、決して“絶対的な無人地帯”ではありません。
多くの採用担当者が落ち入りがちなのが、「どうせ無理だから」と諦める癖がついてしまうことです。
しかし、採用戦略を設計し直すと、思わぬ突破口が見えてくる。
たとえば以下のような工夫が挙げられます。
-
求人票のタイトル・訴求ポイントを徹底的に磨く
-
地域密着のメディアやSNSを使ったブランディング
-
オンライン説明会や現場見学など、応募ハードルを下げる工夫
-
スキルや経験より「人柄」や「志向性」を重視した選考設計
こうした積み重ねが、“採れない”を“採れる”に変えるカギとなります。
スキマバイトサービス「Workyou」活用の可能性
いま注目を集めているのが、即日勤務OKの“スキマバイト”系サービスです。
なかでも「Workyou(ワーキュー)」は、採用単価を抑えながら必要な戦力を確保できるという点で企業からの支持が増えています。
Workyouの特徴は以下の通りです。
-
登録者は20〜40代中心で、就業意欲の高い層が多い
-
「1日単位」の仕事にも対応できる
-
評価システムによりマッチングの質が高い
-
募集〜シフト管理までがオンラインで完結できる
たとえば飲食や物流、イベントスタッフなど、“ピンポイント人材”を確保したい業界では相性が非常に良いです。
また、「繁忙期だけ」「突発欠勤への対応」など、正社員では難しい“補助的ニーズ”にフィットします。

“今すぐ動ける人材”が確保できるって、意外と大きな武器なんですよね。
人手不足だからこそ「人材育成」で勝負する
最後にお伝えしたいのが、人手不足の今だからこそ“人を育てること”が最大の差別化要因になるということです。
採用が難しいからこそ、入ってくれた人材には「辞めさせない」「育てる」意識を徹底することが不可欠です。
そのためには次のような取り組みが効果的です。
-
入社後のオンボーディング設計(初日〜1週間の動線整備)
-
スキルマップを用いたキャリアパスの可視化
-
定期的な面談・フィードバック文化の浸透
-
チームによるOJTと社内コミュニティの強化
こうした“人材育成力”こそが、結局は離職率の低下と採用コストの最適化につながっていきます。
次章では、「人手不足の現場で実際に働いてみた人たちの声」を紹介します。
リアルな体験談こそが、求人票では見えない“本当の実態”を教えてくれるはずです。
【第7章】まとめと感想|人手不足時代のキャリア戦略
本記事の要点整理
「“人手不足”という現実を、追い風に変えるために。」
ここまで6章にわたって、「人手不足 仕事」というテーマを多角的に掘り下げてきました。
改めて、押さえておきたいポイントを整理しましょう。
-
人手不足は一部の業界に偏って起きている構造的課題です。
とくに介護、建設、物流、IT分野では需要が増える一方で、労働供給が追いついていません。 -
未経験からでもスタートしやすい職種が存在し、中には短期・単発で即就労できるものもあります。
-
将来性のある業界(医療、IT、インフラなど)では、安定したキャリア形成が可能で、企業からの支援制度も充実してきています。
-
求人情報を見る際は、「未経験歓迎」などの言葉に潜む真意を見極める目が必要です。
口コミや定着率、フォロー体制など、情報の裏を読む力が重要です。 -
実際に人手不足の業界で働いた方々の体験談からは、意外な発見と現実が見えてきました。
やりがいと課題は紙一重ですが、それでも多くの方が成長を感じていました。 -
企業側から見た“人手不足市場”には採用戦略の工夫次第でチャンスがあることも分かりました。
スキマバイトなどの新サービスも加速度的に普及しています。
仕事を選ぶ=人生を設計すること
「働く場所を決める」という行動は、単なる“職探し”ではありません。
それはすなわち、自分の人生設計そのものです。
どんな業界で、どんな環境で、どんな人たちと働くか。
その選択の積み重ねが、自分の未来を決めていきます。
だからこそ、目先の条件だけでなく、「自分が何を大事にしたいのか」という軸を持つことが何より大切です。

“条件の良い仕事”より、“続けられる仕事”を選びたいですよね。
人手不足の今は、選ばれる側から“選ぶ側”に立つチャンスでもあります。
「どうせ今しか選べない」と思わず、「この機会にこそ、自分に合った道を考える」視点が必要です。
筆者メッセージ:「“人手不足”を逆手に取れ」
人手不足は、社会にとってはマイナスの側面を多く含んでいます。
しかし、個人にとっては“選択肢が広がる時代”でもあります。
なぜなら、これまで敷居が高かった業界にも「未経験可」「スキル不要」「すぐ働ける」などの門が開かれてきているからです。
さらに、多くの企業が「育てる前提」で人を採る動きにシフトしてきています。

誰もが“チャンスをもらえる”時代なんですよ。やるかどうかだけ。
転職や副業、キャリアチェンジを考えるには、今が絶好のタイミングです。
本記事が少しでも、あなたの次の一歩を後押しできたなら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
これからのキャリアを前向きに築いていくあなたを、応援しています。