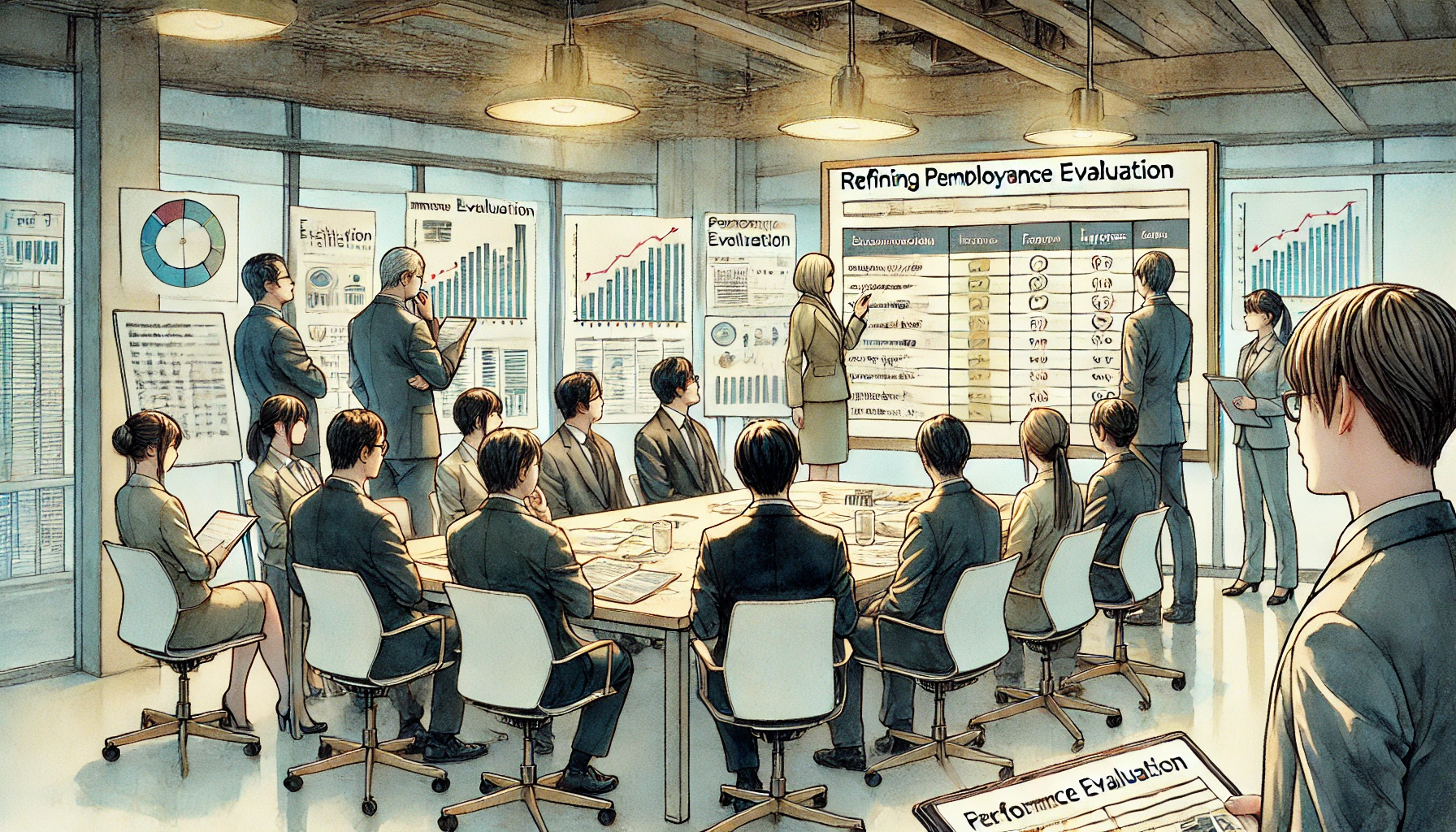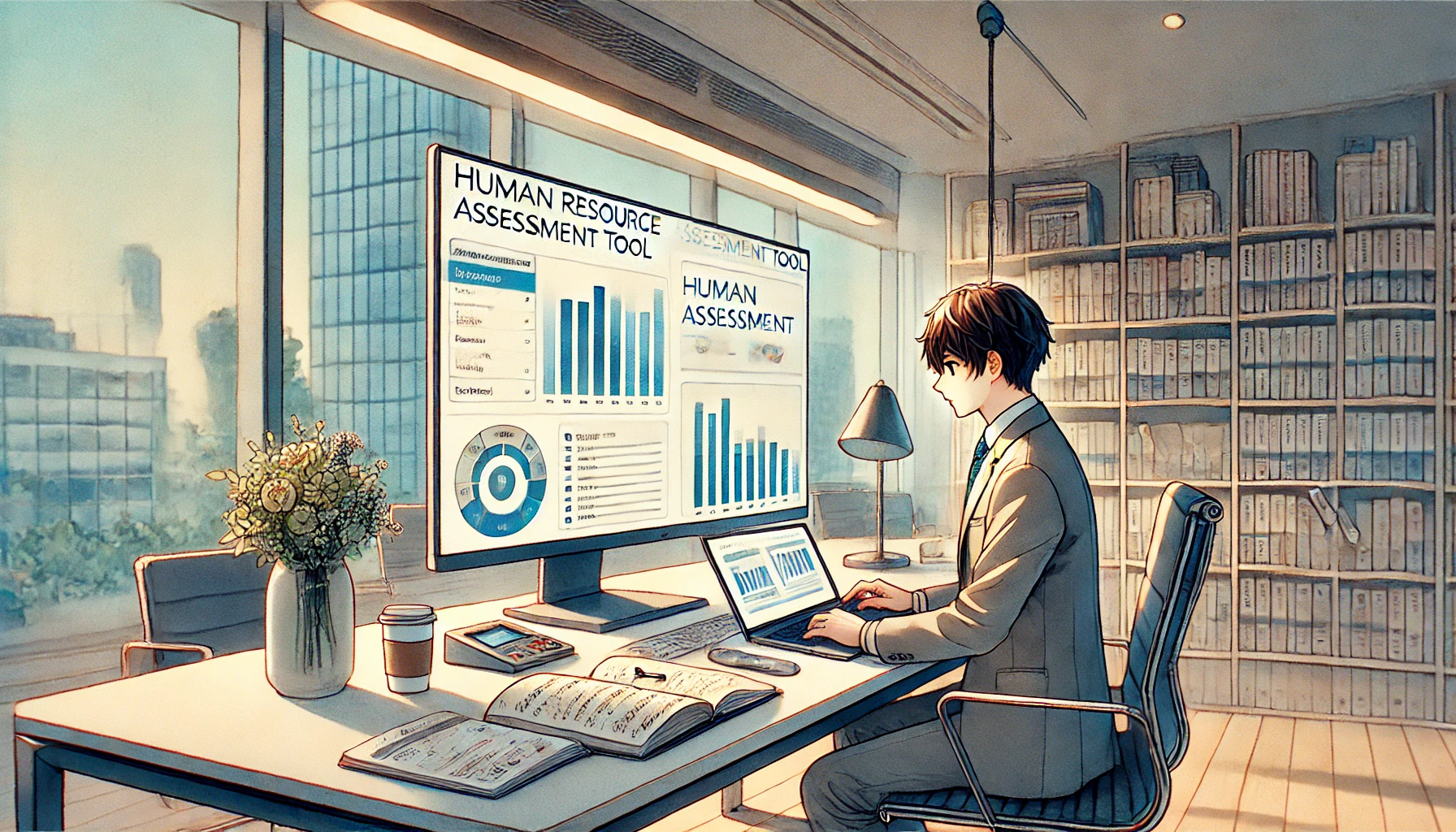今、どの業界が人手不足に苦しんでいるのか?
転職を考えている方も、採用担当者も、この問いは避けて通れません。
厚労省データや転職市場の動向から、特に人材ニーズが高い職業を整理し、今後のキャリア戦略や採用活動のヒントをお届けします。
【第1章】なぜ今「人手不足職業」が注目されるのか?
人手不足が深刻化する3つの背景
今、日本の労働市場で最も深刻化している課題の一つが「人手不足」です。
背景には大きく3つの要因が絡んでいます。
第一に、人口減少と高齢化です。
総務省統計局のデータによれば、日本の生産年齢人口(15歳〜64歳)は、1995年をピークに減少が続いています。
労働力人口の母数が減っている以上、企業間の人材獲得競争は激化せざるを得ません。
第二に、採用難の常態化です。
有効求人倍率はコロナ禍で一時下がったものの、2024年時点で再び上昇傾向に転じています。
特に中小企業や専門職では1人当たり複数の求人が競合する状況が日常となっています。
第三に、定着率の低下と離職リスクです。
若手人材は特に転職活動への心理的ハードルが低くなりつつあります。
キャリアの柔軟化が進む一方、企業にとってはせっかく採用した人材を引き留める難しさが年々高まっています。

「採っても辞める」現象が各現場で悩みの種になってますよね。
売り手市場は「企業も個人も活かせる時代」
この人手不足は企業にとって課題ですが、個人にとっては転職市場でのチャンスでもあります。
とりわけ「採用が難しい職業=転職希望者にとって内定率が高くなる職業」でもあるのです。
求人倍率が特に高い職種では、採用基準がやや緩和されたり、未経験採用の門戸が広がるケースも多く見られます。
もちろんスキルや適性は必要ですが、一定の学習意欲と準備さえあれば、「人手不足職種」へキャリア転換するルートは現実的に存在しています。

未経験歓迎の求人が増えてる理由は、まさにこの需給バランスの崩れですね。
転職成功率が高い職種には共通項がある
ここで転職成功率が上がりやすい職業にはいくつかの共通点があります。
それは以下の3つです。
- 今後も社会ニーズが安定して継続する職業(介護、医療、ITなど)
- 人材供給が追いつかない専門性・資格要件のある仕事
- 企業が即戦力を求めるが、未経験からでも育成しやすい職種
これらの分野は今後さらに需要が高まることが予想されています。
特にITエンジニア、物流管理職、介護福祉士、施工管理技士などはその典型例です。
この章では人手不足が注目される構造的背景を整理しました。
次章からは実際に「どの職種が今、人手不足なのか」をデータベースで具体的に見ていきます。
【第2章】統計で読む|人手不足が深刻な主要職種一覧
求人倍率で見る「本当に人が足りない職種」
厚生労働省「一般職業紹介状況(2025年最新版)」によると、全体の有効求人倍率は約1.3倍前後で推移しています。
ただし、これはあくまで全体平均です。
実際には職種によって大きな差があります。
たとえば以下のような職種は、求人倍率が3倍を超えるケースも珍しくありません。
| 職種 | 求人倍率(参考値) |
|---|---|
| 介護職 | 3.5倍 |
| 保育士 | 2.8倍 |
| 建設作業員・施工管理 | 4.2倍 |
| トラックドライバー(運輸) | 3.9倍 |
| ITエンジニア | 2.5倍〜3.0倍 |
これらの分野では、一人の求職者に対して複数の企業が奪い合う状況が常態化しています。

採用現場でも「応募ゼロ」はもはや珍しくないです。
介護・保育は社会インフラそのもの
介護と保育の人材不足は、完全に社会構造由来の慢性人手不足です。
特に介護分野では、団塊世代の高齢化に伴い利用者が急増。
一方で労働人口は減少するため、需給ギャップが埋まりません。
保育も同様で、共働き世帯の増加に伴い保育需要は高止まりを続けています。
自治体による保育所整備が進んでも、保育士の確保が追いつかないのが現実です。
建設・運輸は高齢化と新規参入難が壁
建設業は、高齢化が最も深刻化している業界の一つです。
厚生労働省の調査によると、現場作業員の平均年齢は45歳を超えています。
若手の新規参入が少なく、技能伝承や現場管理を担う人材が不足しています。
また、運輸業界でもトラックドライバー不足が全国的に広がっています。
物流量は伸び続けている一方、長時間労働や拘束時間規制(働き方改革関連法)により現役ドライバーの負荷は限界に近づいています。
結果として、物流2024年問題とも言われる深刻な人手不足要因に直面しています。

まさに「物流が止まる」リスクが現実味を帯びてきています。
ITエンジニアは構造的な供給不足
IT分野は一見すると華やかに映りますが、実は慢性的な技術者不足です。
経済産業省の試算では、2030年に最大79万人のIT人材が不足するとされています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)推進が叫ばれる一方、企業側は育成と採用の両面で苦戦しています。
特にシステムエンジニア(SE)、インフラエンジニア、セキュリティ、AI関連などの高度専門職は、世界的に引き合いが強く、日本国内での取り合いが続いています。
業界別の「慢性人手不足」の構造的要因まとめ
-
介護・保育:高齢化・共働き社会・低賃金構造
-
建設:技能継承の壁・高齢化・新規人材の敬遠
-
運輸:物流需要増・働き方改革・拘束時間規制
-
IT:技術革新速度に教育・供給が追いつかない
いずれも短期の施策だけでは解消が難しく、今後も高い転職需要が続く分野といえます。
次章では、これらの職種が「なぜ転職しやすいのか?」をもう少し深掘りして解説していきます。
【第3章】転職希望者におすすめの「有利職種」5選
採用されやすさ×将来性で狙い目を選ぶ時代
人手不足職種=どこでも転職しやすい、とは限りません。
重要なのは「現場が求めている人材像」と「今後も需要が伸び続けるか」の両軸です。
ここでは、転職希望者が現実的に狙いやすく、なおかつ将来性もある5つの職種を紹介します。

どこでも採用されやすい職種ではなく、伸び続ける業界を狙いたいですね。
① ITサポート・ヘルプデスク
IT系といえば高度なプログラミングを想像しがちですが、サポート職は未経験からでも参入しやすい窓口です。
具体的には社内ヘルプデスク、ユーザーサポート、システム運用監視など。
クラウド導入、SaaS活用が進む今、企業のIT運用は複雑化しています。
その結果、「現場で困っている人の代わりにITを回せる人材」が重宝されています。
ITパスポートやMOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)といった資格取得もキャリア形成に有効です。
② 物流管理・倉庫マネジメント
物流業界の人手不足はドライバーだけではありません。
物流センター・倉庫の管理職、在庫オペレーション担当、配送ルート管理など、現場と管理の橋渡し役が圧倒的に足りていません。
特にEC市場の成長に伴い、24時間365日動き続ける物流現場の司令塔役が求められています。
業界経験が浅くても、工程管理やコミュニケーション力が評価されるため、異業種出身者の採用も積極化しています。
③ 介護福祉士・介護職員
言うまでもなく慢性的な人手不足職種です。
とはいえ、国の支援策やキャリアパス制度が整備されつつあり、資格を取得しながら安定したキャリアを形成できる業界になりつつあります。
無資格でも入職可能な初任者研修から、介護福祉士、ケアマネジャーへとステップアップ可能です。
国の処遇改善加算により給与水準も底上げが進行中です。

介護は「しんどそう」と敬遠されますが、実は国家支援の恩恵が大きい分野です。
④ 建設施工管理・設備保守
建設作業員よりも、「管理監督ポジション」が今後の狙い目です。
施工管理技士、電気工事士、管工事施工管理技士などの国家資格は取得支援制度も整っています。
現場経験ゼロでも、20代・30代なら見習い採用枠を設けている企業も多く、育成前提での採用も活発です。
特にインフラ系の工事会社は長期安定性が高く、定年後も技術指導役として残りやすいのも特徴です。
⑤ 医療事務・病院クラーク
医療系は看護師・医師だけではありません。
診療報酬請求事務(レセプト業務)や、受付・カルテ管理といった医療事務系は女性を中心に安定志向の転職先として人気です。
資格取得は比較的短期間で可能(医療事務技能審査試験など)であり、産休・育休制度も整備が進んでいます。
高齢社会が続く限り、需要が減るリスクはほぼありません。
「成長産業×資格支援」がカギになる
まとめると、今の人手不足市場で転職希望者が狙いやすいのは以下のパターンです。
-
国家資格・民間資格が用意されている
-
未経験からでも育成枠が広い
-
業界成長と国の支援がリンクしている
ここに着目すると、短期だけでなく「10年後も生き残れる職種選択」が可能になります。
次章では、企業側の視点に立ち「なぜ人が集まらないのか?」の裏側も深掘りしていきます。
【第4章】企業側が知っておくべき採用戦略の視点
人手不足職種ほど「採用コスト上昇リスク」が高まる
人手不足が深刻化すると、当然ながら採用コストは高騰します。
求人広告費、紹介手数料、採用媒体の有料プラン、さらにはSNS広告や動画採用など、採用チャネルの多様化に伴う費用負担が増すのが現状です。
特に介護・物流・建設・IT系といった慢性的に採用難の業界は、1人あたりの採用単価が50万〜100万円超に達するケースも珍しくありません。

母集団形成の段階からお金がかかるようになってきました。
短期人材派遣Workyouの活用から正社員採用へ
採用難に直面した現場がすぐに取れる有効策の一つが「短期派遣」や「請負活用」です。
例えば、短期人材サービスを提供するWorkyouは、物流現場や飲食、イベント業界などで即日対応が可能なプラットフォームを展開しています。
こうしたスポット派遣は、一時的な人員補充として役立つだけでなく、「現場の仕事を可視化し直すチャンス」でもあります。
作業内容の標準化が進めば、次は正社員採用・育成計画への転換もしやすくなるのです。
採用ブランディング・教育体制強化が中小企業の勝負所
求職者は「給与」だけでなく「職場環境」「成長機会」「定着支援制度」まで含めて企業選びをします。
採用ブランディングの設計次第で、同じ給与水準でも応募数・内定承諾率に大きな差が生まれます。
以下のような施策が、特に人手不足職種では有効です。
-
キャリアパス明示(資格取得支援・昇給制度)
-
柔軟な勤務時間(時短正社員・交替制シフトの柔軟化)
-
職場見学・体験入社プログラム
-
上司・現場リーダーの面談体制強化
教育体制が整っているかどうかは、応募段階でほぼ必ず確認されるポイントになっています。

育成できる会社か?が、中途採用でもかなり重要視されています。
求人広告より重要なのは「働き方の魅力設計」
今や「求人広告を出せば人が集まる時代」は終わっています。
むしろ必要なのは、「入社後のイメージが明確に伝わる設計」です。
求人票では以下をしっかり記載したいところです。
-
配属先チームの雰囲気・人数構成
-
1日の仕事の流れ
-
教育研修の具体的な流れ
-
入社1年後に求める成果イメージ
応募者が知りたいのは 「入ったら自分はどうなるのか?」。
これが描けないと、いくら広告費を投下しても応募効果は限定的です。
人手不足時代の採用は「設計力」が勝負
まとめれば、企業側に必要なのは単なる採用活動ではありません。
採用戦略そのものの再設計=「設計力」が問われています。
-
外注活用
-
社内教育再構築
-
ブランディング改善
-
募集条件の柔軟化
これらをセットで進めることで、慢性的な人手不足から抜け出す突破口が見えてきます。
次章では、実際に採用成功事例が多い企業が「現場で何をしているか?」をさらに掘り下げていきます。
【第5章】現場の事例紹介|成功している転職・採用例
実例①:未経験ITエンジニア転職で年収UP
IT業界は慢性的な人手不足が続いており、未経験からの転職者を積極的に受け入れる企業が増えています。
ある30代男性Aさんは、前職が営業職でありながら独学でプログラミング学習を進め、オンラインスクールで基礎スキルを習得。
応募先は「ポテンシャル採用」を打ち出していたSIer系企業でした。
面接では「未経験でも、どんな学習をしてきたか」「現場に入った後も成長し続けられるか」が問われました。
結果、内定を獲得し、年収は前職より約80万円アップ。
ITエンジニアはスキル次第で市場価値が早く上がる職種の典型例です。

ITは転職市場で最も「学ぶ姿勢」を評価してくれる領域ですね。
実例②:外国人介護人材の積極採用成功事例
次は介護業界のケースです。
地方の中規模介護施設B社は慢性的な人材不足に悩み、外国人材の採用に踏み切りました。
活用したのは 「特定技能制度」。
フィリピンやベトナム出身の人材を受け入れ、入社後は日本語研修・生活支援制度を整備。
特に現場リーダーが定期面談を実施し、小さな悩みを拾い続けたことで離職率が低下。
導入2年後には外国人スタッフ比率が全体の20%を超え、サービス品質も安定する好循環に入っています。

「受け入れ体制」がカギ。ここを軽視すると定着しません。
実例③:建設業の採用ブランディング事例
建設業界は長年にわたり若手不足が課題でした。
そこでC社が取り組んだのが「職人のイメージ刷新」です。
-
SNSで現場動画を発信
-
若手社員が施工管理のやりがいを語る動画を作成
-
資格取得支援×キャリアパス制度を明示
結果、若手応募が前年の1.8倍に増加。
「泥臭い現場」という固定観念を打破する採用ブランディングが功を奏した事例です。
求人票で伝える情報だけでなく、「未来像を提示すること」が若手人材の心を動かしました。
まとめ:成功企業は「課題に正面から向き合った」
これら3つの事例に共通するのは、現実の採用課題から逃げず、具体策を講じたことです。
人手不足は避けられませんが、やり方次第で「採れる仕組み」に転換は可能です。
次章では、そうした成功企業の共通ポイントを総括してまとめます。
【第6章】まとめと感想|「人手不足」は実は“転職チャンス”でもある
人手不足業界の整理まとめ
ここまで見てきた通り、今まさに深刻な人手不足に直面している業界は以下の通りです。
-
介護・福祉
-
保育
-
建設業
-
運輸・物流
-
IT・エンジニア職
-
製造・技能職全般
これらは求人倍率が高水準で推移しており、今後も大きく改善する見込みはありません。
人口減少・高齢化の流れは続いていくため、むしろ人材獲得競争は今後さらに激しくなる可能性が高いと断定できます(厚生労働省「一般職業紹介状況」より)。
転職希望者には「狙い目」が増えている
人手不足は企業にとっては悩みの種ですが、**転職希望者にとってはむしろ「選択肢が広がる市場」**といえます。
特に次のような層には好条件の転職チャンスが訪れやすい状況です。
-
未経験から新たな業界に挑戦したい人
-
資格取得やスキルアップを積極的に行っている人
-
柔軟な働き方を希望する人

「不安だからこそ、今こそ市場をよく見ておくべきですね。」
企業側も門戸を広げているケースが多く、ポテンシャル採用・未経験採用・資格支援制度などが積極導入されています。
「経験が浅いから」と尻込みせず、成長意欲の高さをアピールする転職活動が鍵を握ります。
◆ 企業側は「採用競争力」こそ問われる時代
逆に、企業側には採用力そのものが競争力となる時代が来ています。
-
働き方柔軟性の提示
-
教育・育成制度の整備
-
キャリアパスの可視化
-
採用ブランディングの強化
-
外国人材やシニア活用の制度設計
こうした“働く側から選ばれる仕組み”を作れる企業が今後の勝者になるでしょう。

「求人広告だけ出せば人が集まる時代は完全に終わっています。」
「人手不足=悪」ではなく「市場の大きな動き」と捉える視点を持とう
人手不足は確かに大きな課題です。
しかし、採用・転職市場の見方を少し変えれば、新たなビジネス機会やキャリア形成のチャンスでもあります。
「できない理由」ではなく「どう活かすか」の視点で向き合うこと。
これが企業・個人のどちらにも求められている現実です。