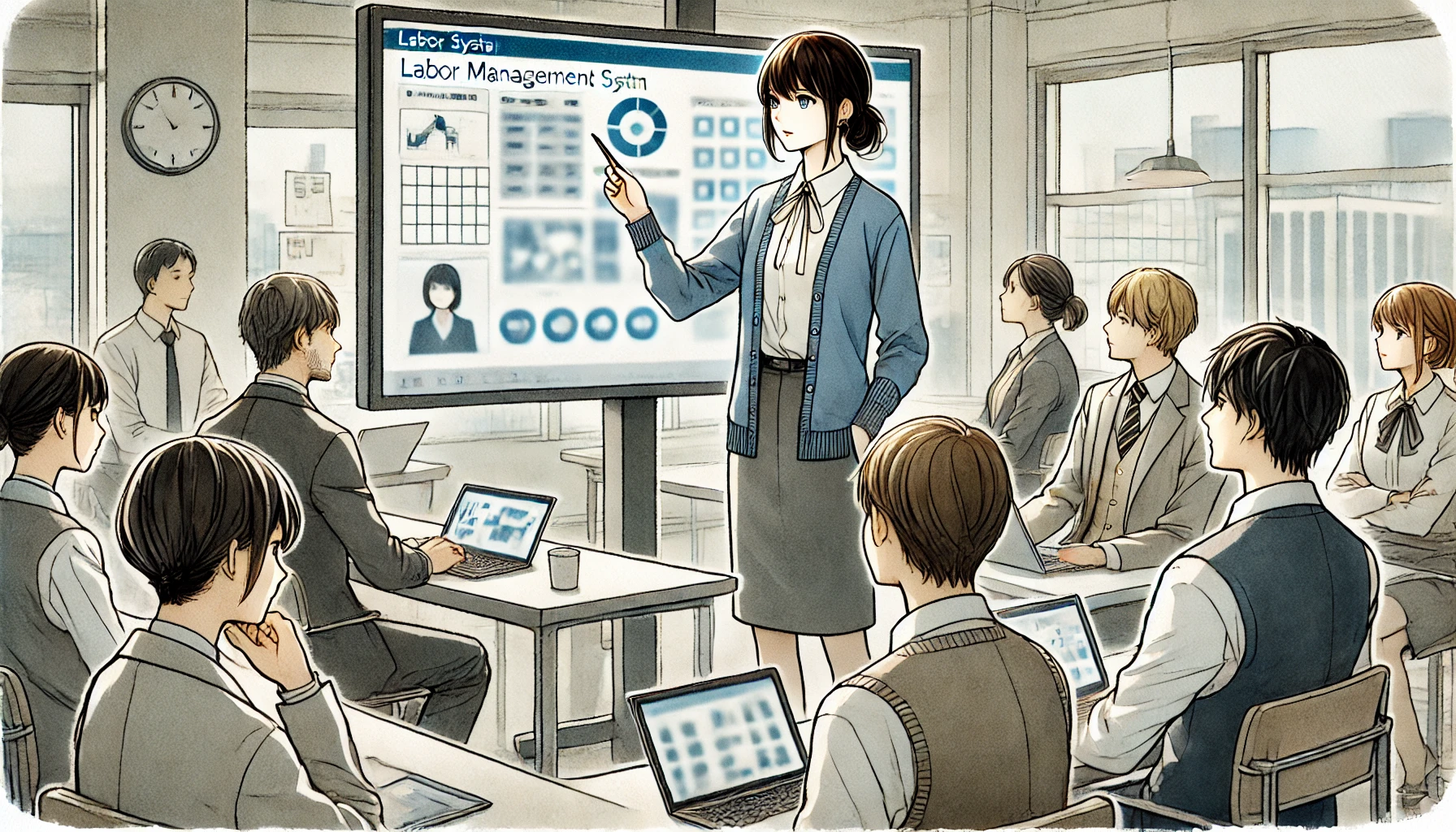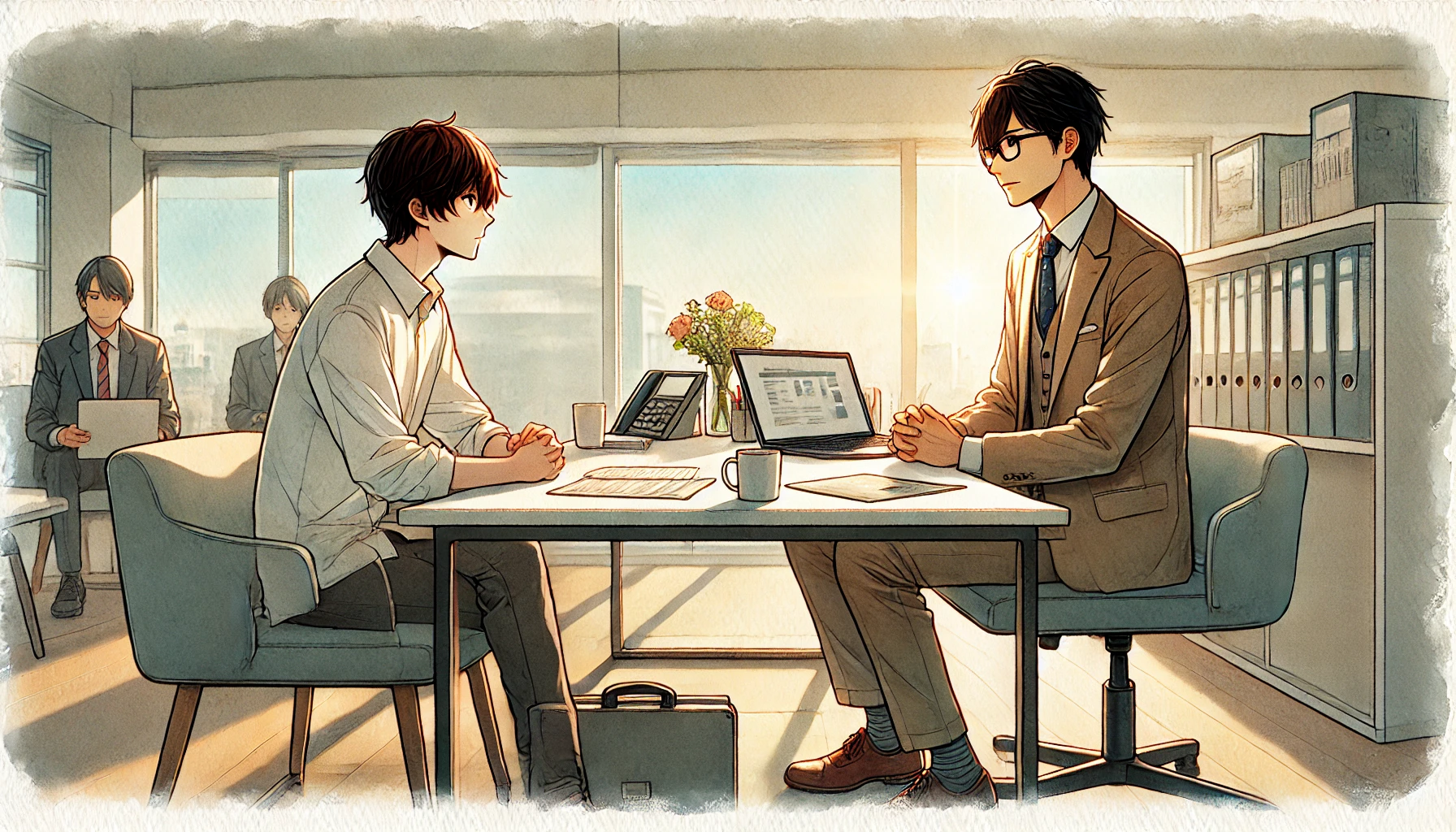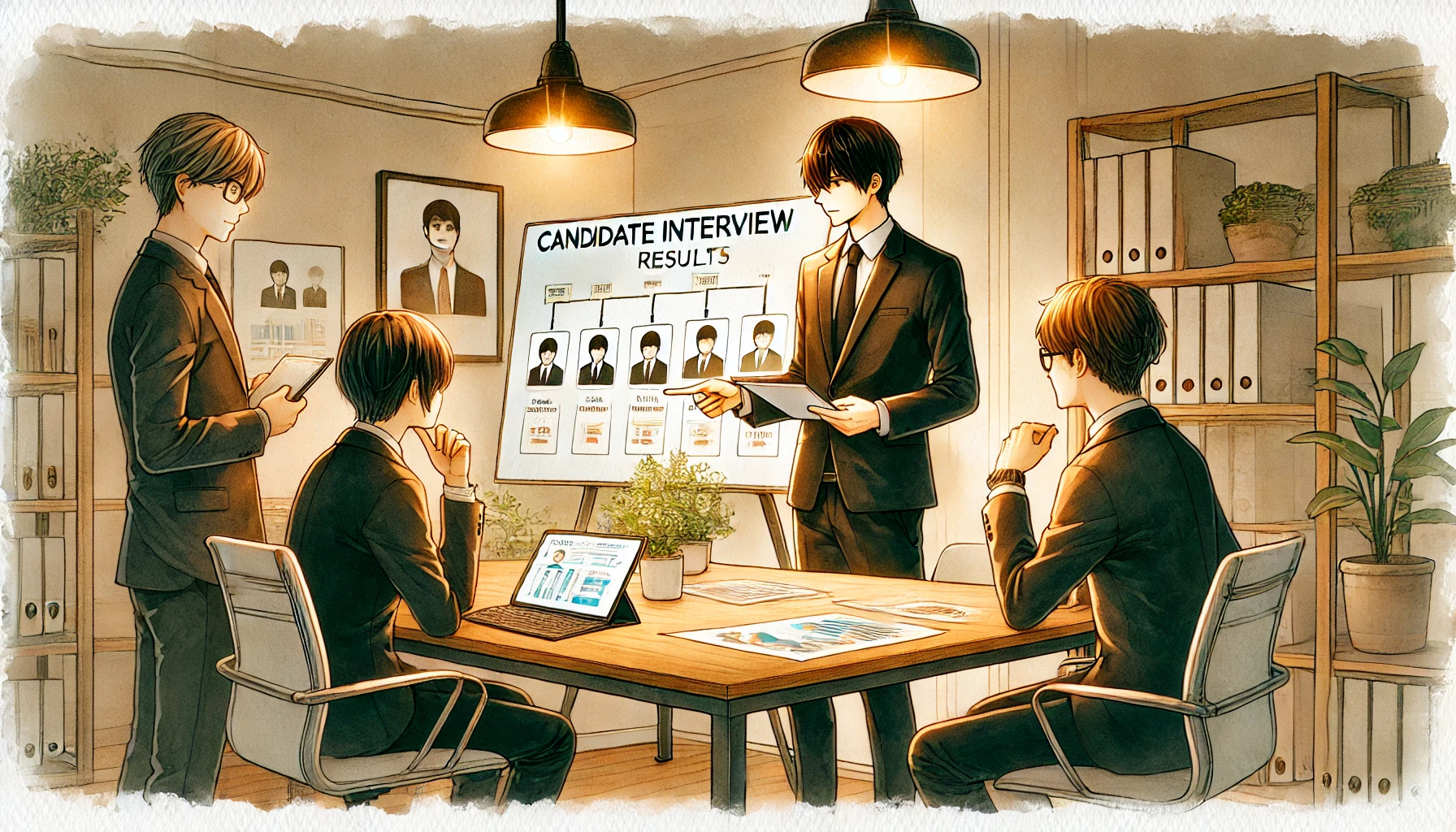2025年、求人市場はさらに“売り手市場”に。
中小企業はどう立ち向かうべきか──。
本記事では、今後主流となる採用戦略の最新トレンドを解説します。
採用ブランディング、SNS活用、オンライン面接、社員の魅力発信など、時代に即した“攻めの採用”を提案します。
第1章:採用戦略の基本と時代の変化
採用戦略とは何か?|“採用活動の設計図”という考え方
採用戦略とは、単に求人広告を出すことではありません。
「誰を」「いつ」「どうやって」「どの手法で」採用するのかという全体の設計図を描く行為です。
経営戦略と密接に連動し、今後の組織づくりを左右する要素でもあります。
人材要件の明確化、選考プロセスの設計、媒体の選定、ブランディング設計など、複数の要素を整理・統合する必要があります。

そもそも設計図がないまま採用を進めている会社、多いですよね。
実際、戦略の有無によって応募数や採用後の定着率が大きく変わることが、様々な企業事例からも報告されています(出典:リクルートワークス研究所)。
採用活動が「運任せ」になっていると感じているなら、それは“戦略”が存在していない証拠です。
媒体頼みからの脱却|2000年代〜2025年の変遷
2000年代から2010年代にかけて、求人活動の主流はハローワークや求人誌、ポータルサイトへの掲載でした。
当時は「掲載すれば誰かしら応募がある」時代だったのです。
しかし、2020年以降は大きく変わりました。
求職者側の選択肢が広がり、企業情報も多様化。
いわゆる“求職者が企業を選ぶ時代”に突入しています。
SNS、口コミ、動画、ダイレクトリクルーティングなど、採用チャネルが激増。
従来の媒体依存では通用しないフェーズに突入しています。

「媒体を変えれば採れる」は、もう通用しない時代なんですよね。
採用マーケティングという考え方が広がってきたのもこの10年です。
ブランディングやSNS運用、社員の顔が見える発信などを駆使する企業が成果を出しています。
中小企業でも、Instagramやnoteを活用して採用に成功している事例は増えています。
中小企業が直面する「人が来ない」現実
中小企業の採用現場で最もよく聞く声は、「応募が来ない」「来てもミスマッチが多い」というものです。
これは、単に待遇や職種の問題ではありません。
「どんな人に来てほしいのか」が言語化されていない、あるいは「伝え方」がずれているケースが非常に多いのです。
採用ペルソナの設計が不十分なまま、媒体に求人を掲載しても、ターゲットには響きません。
「求人票が見られていない」だけでなく、「見られてもスルーされている」可能性も高いのです。
これを打開するには、採用活動をプロジェクト化し、現場・経営陣・人事が一体となって目的を共有する必要があります。
採用は現場任せではなく、組織全体で取り組むべき戦略課題です。
現在地を見誤らないことが、最初の一歩
採用戦略を立てる上で最も重要なのは、“自社の現在地”を正しく把握することです。
競合の動向、自社の魅力、採用チャネル、歩留まり率、退職率――すべてのデータを整理して見える化することで、打ち手が見えてきます。
ここを飛ばして“採用広告にお金をかける”のは、例えるなら、地図なしで登山に出かけるようなものです。
中小企業にこそ、採用のPDCAをまわす意識が求められています。
この章では、採用戦略の基礎的な考え方と、過去からの変化、そして現在の課題を整理しました。
次章では、2025年に採用市場がどう変化していくのかを具体的に解説していきます。
第2章:2025年の採用環境|3つの変化とは
1. 採用市場の構造変化|“売り手市場”と若年層の減少
2025年の採用市場において、最も大きな前提は「売り手市場が常態化している」という点です。
特に、20代前半の若年層人口がピーク時と比べて約15%減少しているとされており(総務省統計局)、企業間の人材獲得競争は激化の一途をたどっています。
実際、厚生労働省の調査によれば、2023年度の有効求人倍率(正社員)は1.32倍と高水準。
これが意味するのは、「求人を出しても人が来ない」ではなく、「他社に先に取られている」という事実です。

競合他社との取り合いにすら参加できていない企業、少なくないですよね。
企業側の“選ぶ側意識”が残っている限り、戦いにすら参加できない状況に陥ります。
もはや採用は、「企業が選ぶ」のではなく「選ばれる」ことを前提に組み立てるべきフェーズに入りました。
2. 働き方の多様化|フルリモート、副業、職務限定
コロナ禍を経て、「働くこと」そのものに対する考え方が根底から変わりました。
テレワーク、フルリモート、副業、週3勤務など、多様な働き方を希望する求職者が年々増加しています。
特に若手・中堅層では、「ライフスタイルに合う働き方ができるか」が就職先を選ぶ大きな基準となっており、給与や福利厚生以上に柔軟な働き方へのニーズが高まっています。
パーソル総合研究所の調査では、20代〜30代の求職者のう47.2%が「出社義務のない企業を優先的に検討する」と回答しています。

“9時〜18時、週5出社”しか選択肢がないと、選ばれる土俵にも立てないかもしれません。
これは中小企業にとってもチャンスです。
大企業ほど硬直化していない分、“柔軟性”をウリにして差別化を図ることが可能です。
実際に、ある製造系の企業では「職務限定採用(現場のみ/営業のみ)」を導入し、ミスマッチが激減しました。
3. 情報格差の拡大|求職者リテラシーと企業のギャップ
2025年の求職者は、求人票だけで応募を決めません。
企業の公式サイト、SNS発信、口コミサイト(OpenWork、Googleクチコミなど)、YouTubeなど、複数の情報源を“同時にチェック”するのが当たり前の時代です。
一方で、多くの中小企業ではいまだに「求人票とコーポレートサイト」だけで情報発信を完結させているケースが多く、求職者との情報リテラシー格差が生まれています。
このギャップが、応募数の減少・採用後の早期離職という“目に見える形”で表面化しています。
「うちはちゃんと情報を出してる」と思っていても、求職者から見れば「見つけられない」「不安」という印象を与えてしまっているケースが多いのです。
データで見る採用成功率の現実
厚生労働省「雇用動向調査(2024年度版)」によると、中小企業の新規求人に対する充足率は全体で約65%に留まっています。
特に製造・サービス業では50%を下回るケースも珍しくありません。
一方、採用ブランディングやSNS発信に積極的に取り組む企業では、応募数・歩留まりともに120〜150%向上したという民間データ(エン・ジャパン/ビズリーチ調査)も報告されています。
つまり、やるべきことをやっている企業と、手を打っていない企業とで「結果に大きな差が出ている」のが今の採用市場です。
変化は“感覚”ではなく“数字”として明確に現れています。
この章では、2025年の採用市場における「構造変化」「働き方の多様化」「情報格差」という3つの視点から、現状を整理しました。
次章では、この環境変化をチャンスに変えるための“採用マーケティングとブランディング戦略”について解説していきます。
第3章:採用マーケティングとブランディングの実践
「売れる求人」とは?|採用マーケ視点の求人票の作り方
求人票には2種類ある。
「出すために作った求人票」と、「読まれるために作った求人票」だ。
売れる求人票とは、求職者にとって「自分ごと」として読めるコンテンツになっていることが前提だ。
事実情報(仕事内容・給与・勤務地)だけでなく、「誰と働くのか」「どんな価値があるのか」「何が面白いのか」といった感情に届く設計が求められる。
採用マーケティングとは、求人を“商品”としてとらえ、ターゲットに合わせた打ち出し方を考える戦略である。
採用ターゲットのペルソナ設計→ニーズの洗い出し→コンテンツの最適化というプロセスは、もはや採用活動の基本だ。

求人票は広告。読み手に“刺さる構成”にしなきゃ届かないってことです。
「何を言うか」ではなく「どう伝えるか」
採用ブランディングで重要なのは、“企業の魅力”を盛ることではない。
大切なのは、それを「どんな言葉と形で伝えるか」にある。
例えば「アットホームな職場です」という表現は、何の印象も残さない。
それよりも「毎週水曜はランチ持ち寄り会で、社長も雑談に混ざる文化があります」と伝えた方が、具体性と温度感が伝わる。
これはマーケティングでもいう「機能価値」と「情緒価値」の使い分けに近い。
中小企業こそ、大手にはない“空気感”や“距離の近さ”を言語化・ビジュアル化して届ける工夫が不可欠だ。

伝え方次第で“普通の会社”が“魅力的な会社”に見えるのが採用ブランディングの面白いところ。
【実例】製造業A社|社員インタビューで応募数3倍
ある地方の部品製造会社・A社では、これまで求人票と採用ページのみで採用活動を行っていたが、応募が月1〜2件しかなかった。
そこで取り組んだのが、社員インタビュー記事の公開だ。
特に、入社2年目の若手社員のリアルな声と、ベテランとの関わりをストーリーとしてまとめた内容は非常に反響が大きく、SNSでの拡散も進んだ。
結果として、3か月で応募数が3倍、内定承諾率も改善。
掲載したのはnoteと自社ブログ、さらにQRコード付きの名刺サイズパンフレットも地域イベントで配布した。
文章の内容はもちろんだが、“人の顔が見える”ことが信頼につながった好例だ。
【実例】IT企業B社|Instagramでエンジニア採用に成功
B社は都内の社員20名規模のITベンチャーだが、採用ページを強化せず、代わりにInstagramでの発信に注力。
オフィスの風景、開発合宿、エンジニア同士のカジュアルなミーティング、代表のQ&Aなど、日常を切り取った投稿が“自然な会社の空気”として注目を集めた。
採用に直接つながる投稿ばかりではない。
だが、DMから「一度話を聞きたい」という問い合わせが増え、結果として求人媒体経由よりも高い応募率と定着率を記録している。
Instagram採用は、特に20代〜30代の若手人材においては極めて効果的なチャネルとなっており、視覚的なブランド訴求が鍵になる。
まとめ
この章では、「売れる求人票」の考え方と、中小企業でも実践可能な採用マーケティング・ブランディングの方法を紹介した。
A社やB社のように、「規模ではなく“伝え方”」を変えるだけで、応募が増え、マッチ度も向上する。
次章では、採用DXと選考プロセスの最適化について解説していく。
どのツールを使い、どの工程に時間を割くべきか──現場がすぐに動ける具体策を紹介する。
第4章:採用DXと選考プロセスの最適化
採用DXとは?|“属人化”から脱却する第一歩
採用DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、採用活動にデジタル技術を取り入れ、業務の効率化・可視化・自動化を図る取り組みのことです。
特に中小企業では、担当者1人にすべてを依存する“属人化”が起こりやすく、業務がブラックボックス化しがちです。
代表的な採用DXツールには、以下のようなものがあります。
-
ATS(採用管理システム):応募~面接~内定のフローを一元管理
-
チャットボット:24時間応募者対応を自動化
-
オンライン面接:Google MeetやZoomでの面接により、移動や日程調整の負荷を削減
こうしたツールの導入は、応募者へのレスポンススピードを上げ、「ちゃんとした会社」という印象を与える効果もあります。

意外と“応募後の対応の遅さ”で離脱されてる企業、多いんですよね。
“選ばれる会社”になるには、工数の見直しが不可欠
採用は「数を打てば当たる」ものではありません。
むしろ、限られた人事リソースをいかに効率よく配分するかが重要です。
たとえば、書類選考や一次面接に毎回1〜2時間かかっているとしたら、それは他の重要業務を圧迫しているだけでなく、応募者対応にも遅れが出ます。
さらに、応募者にとって「レスポンスの遅い会社」は不安材料になります。
採用プロセス全体を可視化し、“どこに時間がかかっているか”を明確にしたうえで改善する。
これが、今後の採用活動における基本姿勢です。

人手が足りないからこそ、シンプルに、早く、確実にが鍵ですよね。
【実例】C社|Googleフォームで選考を自動化、歩留まり改善
東京都内の飲食チェーンを展開するC社では、採用担当が1名体制で業務過多になっていました。
そこで導入したのが、Googleフォームによる書類選考の自動化です。
フォーム上で基本情報・志望動機・過去の経験などを記入してもらい、条件に応じてスプレッドシートで自動振り分け。
さらに、一次通過者には自動で面接日程調整のメールが送られる仕組みを組みました。
結果、1人あたりの対応工数が60%削減。
応募者の「対応スピード満足度」も上昇し、選考途中離脱が激減しました。
ツールはすべて無料。
コストをかけずに、業務効率と応募者体験の両方を改善できた成功事例です。
無理なく導入できる無料ツール一覧
中小企業にとって、「コスト」と「習熟度」がDXの壁になりがちです。
そこで、導入しやすく、実際の現場でも使いやすい無料ツールを以下にまとめました。
| ツール名 | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| Googleフォーム | 応募受付・情報収集 | 無料・拡張性が高い |
| Notion | 面接進捗・候補者情報共有 | データベース+メモ機能で柔軟 |
| AirTABLE | 書類選考・選考進捗の可視化 | 見た目がカンバン風で直感的 |
| Calendly | 面接日程の自動調整 | 候補者が空き日程を選べる |
| ChatGPT | 質問回答のテンプレート作成など | 工数の削減+品質維持に活用 |
こうしたツールは、社内への浸透も早く、特別なITスキルがなくても扱える点で導入しやすいです。
採用管理の一元化は、将来的にデータ活用(例:どの媒体からどの層が来たか)にもつながり、PDCAを回す土台にもなります。
まとめ
この章では、採用DXの概要と、工数を減らしながらも“選ばれる会社”になるための手段を解説しました。
特に人手不足の企業ほど、仕組み化とデジタル活用が採用の成否を分ける時代です。
次章では、こうした土台を活かしつつ、実際に採用戦略をどう組み立てるのか、3ステップでの実践法をご紹介します。
第5章:中小企業が今すぐできる戦略設計3ステップ
ステップ①:採用ターゲットの明確化|職種と人物像を“絞る”
まず最初にやるべきことは、「誰を採用したいのか」を明確にすることです。
これは職種だけでなく、スキル・経験・志向性・性格傾向までを含めた“採用ターゲット設計”が重要になります。
ありがちな失敗は、「何でもできる人」や「明るく前向きな人」など、曖昧で抽象的な条件で採用を始めてしまうことです。
この状態では求人票の内容もブレ、応募者にも刺さりません。
例えば「未経験歓迎の営業職」であれば、
-
学生時代に接客・販売のバイト経験がある人
-
挑戦意欲があり、フィードバックを素直に受け取れるタイプ
-
SNSを使って情報収集する習慣がある
など、「これが当てはまる人が来たら戦力になりそう」という具体像を描ききる必要があります。

“いい人が来てくれたら”という願望では、採用は成功しません。
ステップ②:競合分析+自社の魅力の棚卸し
ターゲットが定まったら、次は“その人たちが応募しそうな会社”と自社を比較してみます。
競合は同業とは限りません。
たとえば小売業で接客経験者を狙うなら、飲食・介護・ベンチャー企業も比較対象になる可能性があります。
そして、「他社にない自社の魅力は何か?」を棚卸ししましょう。
「人の距離が近い」「裁量がある」「職人から学べる」など、キーワードでも構いません。
ポイントは、求職者が感じるメリット(情緒価値)まで掘り下げることです。
企業側の“当たり前”が、実は外部から見ると「強み」になるケースも多いです。
社員へのヒアリング、口コミの収集、自社の紹介動画や記事の閲覧ログ分析などからヒントが得られます。
ステップ③:訴求チャネルの選定とKPI設計
自社の魅力が言語化できたら、それをどの媒体や手段で届けるかを決めます。
-
若年層:SNS(Instagram、YouTube)、Wantedly
-
地域密着型:地元就職フェア、地域密着型メディア
-
経験者層:doda、ビズリーチ、LinkedIn
-
社員紹介:インセンティブ制度の整備
手段が増えすぎて迷う方も多いですが、大切なのは「ペルソナがどこにいるか」で考えることです。
発信力ではなく、“接触機会”を優先してください。
また、KPI(重要指標)を初期に設定しておくことで、PDCAが回せるようになります。
例:
-
月間応募数10件
-
書類通過率40%以上
-
面接設定までの対応時間:48時間以内
この数字があるかどうかで、戦略は“計画”になり、運任せではなくなります。
実践メモ:有限会社ワイズワークの戦略設計例(仮想事例)
業種:住宅リフォーム業(従業員12名)
採用職種:現場管理職(未経験可)
-
ターゲット像:20代後半〜30代前半、前職が飲食・小売。真面目で手に職をつけたい志向
-
競合想定:工務店、建材業、配送業、小規模建築事務所
-
自社の魅力:「毎週社長が現場同行」「資格取得支援あり」「家族との時間が取りやすい」
-
訴求チャネル:Instagram(日常発信)、ハローワーク(未経験層)、紹介制度(社員の兄弟)
-
KPI設計:月応募6件、書類通過率50%、1次面接から内定まで平均10日以内
これだけでも、採用戦略は“実行できるプラン”になります。

やるべきことが明確になれば、現場も動きやすくなるんです。
まとめ
この章では、中小企業が今日から始められる採用戦略設計を、3ステップで具体的に整理しました。
やみくもな施策ではなく、「誰に」「何を」「どう届けるか」を筋道立てて考えるだけで、採用の精度は一気に高まります。
次章では、これまでの内容を踏まえて、全体のまとめと現場への実装に向けたポイントをお伝えします。
第6章:まとめと感想|採用は“手段”であり“競争力”
本記事の要点3つ
ここまで読んでくださった方は、採用活動に真剣に向き合おうとしている方だと思います。
本記事でお伝えしたかったことは、大きく3つに集約できます。
-
採用戦略は「今後の事業」を左右する設計図であること
-
中小企業でも“伝え方”と“仕組み”で採用成果を出せること
-
リソース不足こそ、DXとマーケティング発想が武器になること
どれも難しいことではありません。
「明日から何を変えるか」が、すべての出発点です。

“採用は大企業だけの武器じゃない”。本気になった中小企業こそ、強いんです。
採用は「担当者任せ」ではなく「経営戦略の一部」
よく「うちは専任の人事担当がいないから…」という声を耳にします。
ですが、採用は人事部だけの仕事ではなく、経営の中核にある“未来をつくる行動”です。
たった1人の採用で、チームの雰囲気が変わり、売上が上がることもあります。
逆に、間違った採用で雰囲気が悪化し、数名が離職してしまうケースもあります。
だからこそ、「誰を、なぜ、どう採るか」は、社長や役員、現場リーダーを巻き込んだ全社戦略であるべきです。
短期で結果が出るとは限りません。
しかし、「採用に向き合っている会社」には、必ず“人が集まる理由”が生まれるのです。
小売業A社のエピソード|職人の退職危機から、再出発へ
ここで、ある相談事例をご紹介します。
関東地方のアパレル小売企業・A社。売上の中核を担っていた30代後半の男性職人が「辞めたい」と言い出したことが発端でした。
理由は、「人が育たない」「休めない」「未来が見えない」。
実は、5年以上まともな採用活動がされておらず、職人は育成もフォローも1人で背負っていました。
社長はこの事態を受け、筆者のもとへ相談に。
すぐに社内ヒアリングを行い、「職人の仕事の意味」「働く環境」「今後の仲間像」を可視化し、1か月後には採用活動を本格化しました。
社長自身がカメラの前に立ち、職人の横で「未来の仲間へ」語りかける動画を制作。
noteでインタビュー記事を公開、Instagramで現場風景を発信。
結果、初月で4名の応募があり、そのうち1名が今では“右腕”として育っています。
辞めたいと言っていた職人は、今では採用チームの中心メンバーです。
「やっと、未来を一緒に描ける仲間ができた」と話してくれました。

本気の採用は、社員の心まで動かすんですよね。
今こそ、採用に“本気”になるタイミング
採用はコストではなく、“未来への投資”です。
しかも、他の投資(設備・広告・店舗)と違い、「人」は自ら動き、価値を生み出し、未来を育ててくれます。
求人市場が厳しい今こそ、“やるべき企業”と“やらない企業”の差が明確に出てきます。
そして、やるべきことを淡々と、愚直に積み重ねる企業が、3年後には“選ばれる会社”になっているのです。
あなたの会社がその1社であることを、私は願ってやみません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
採用の現場で悩むすべての方の力になれるよう、これからもリアルな情報と知見を発信していきます。