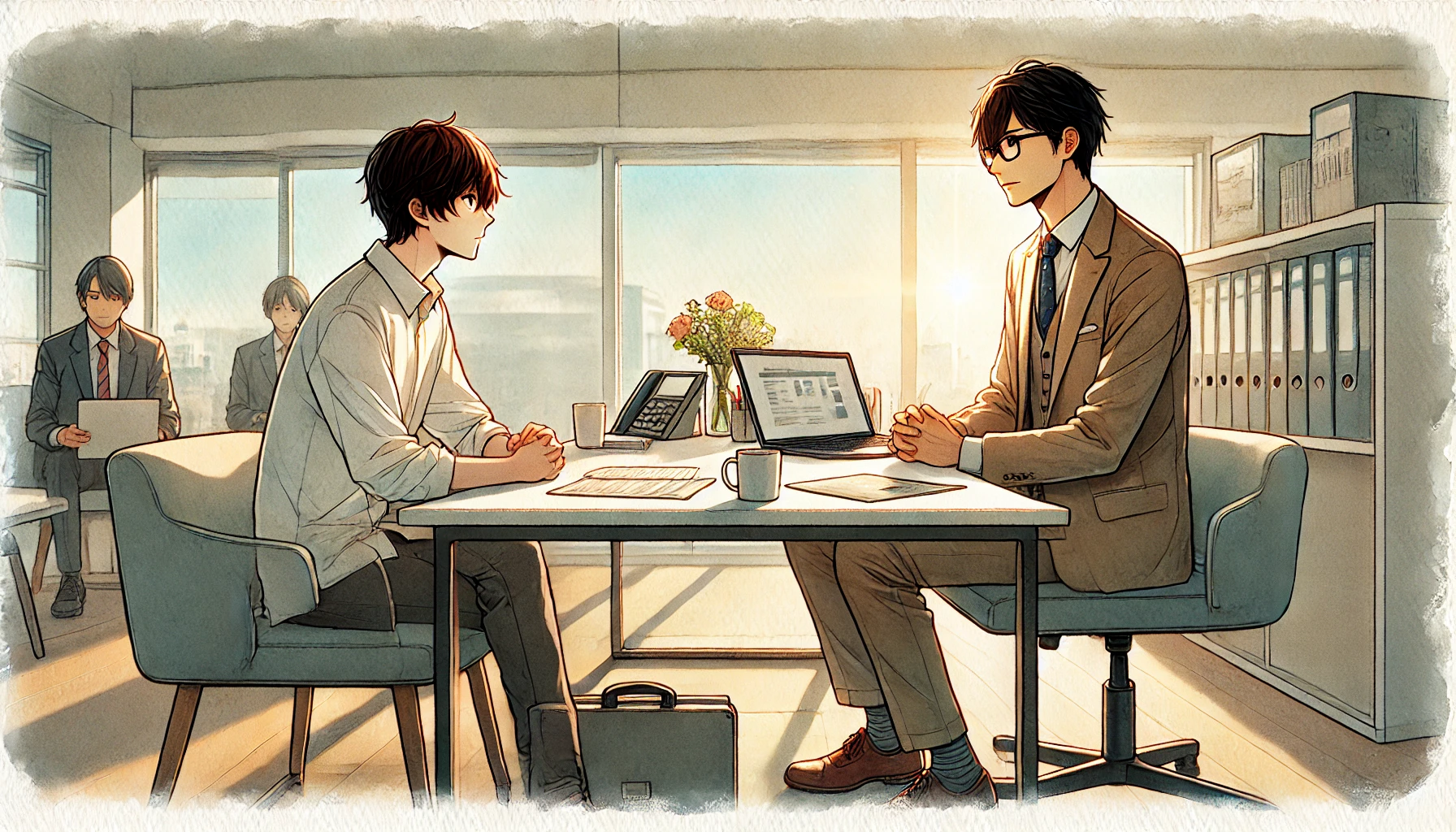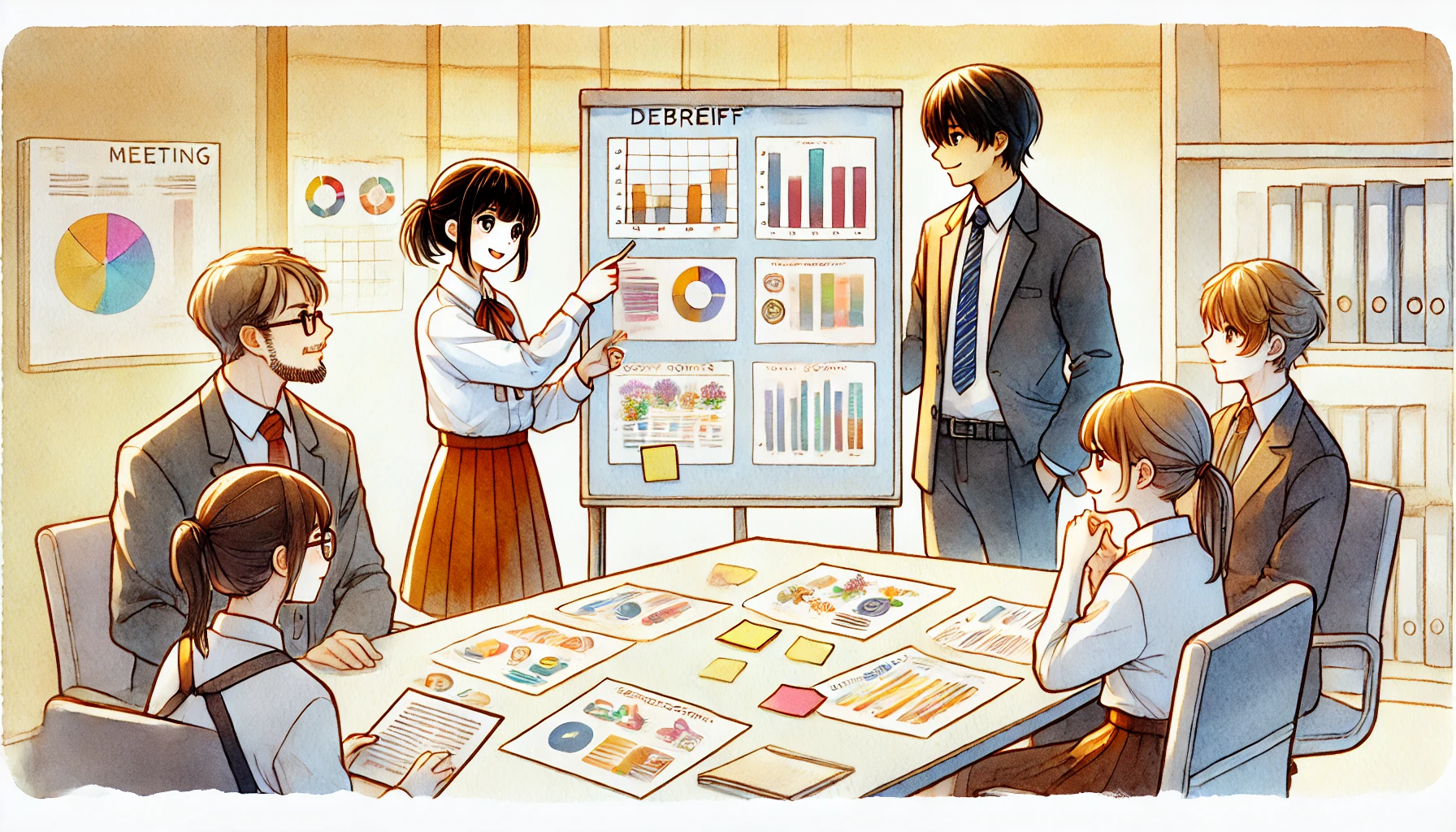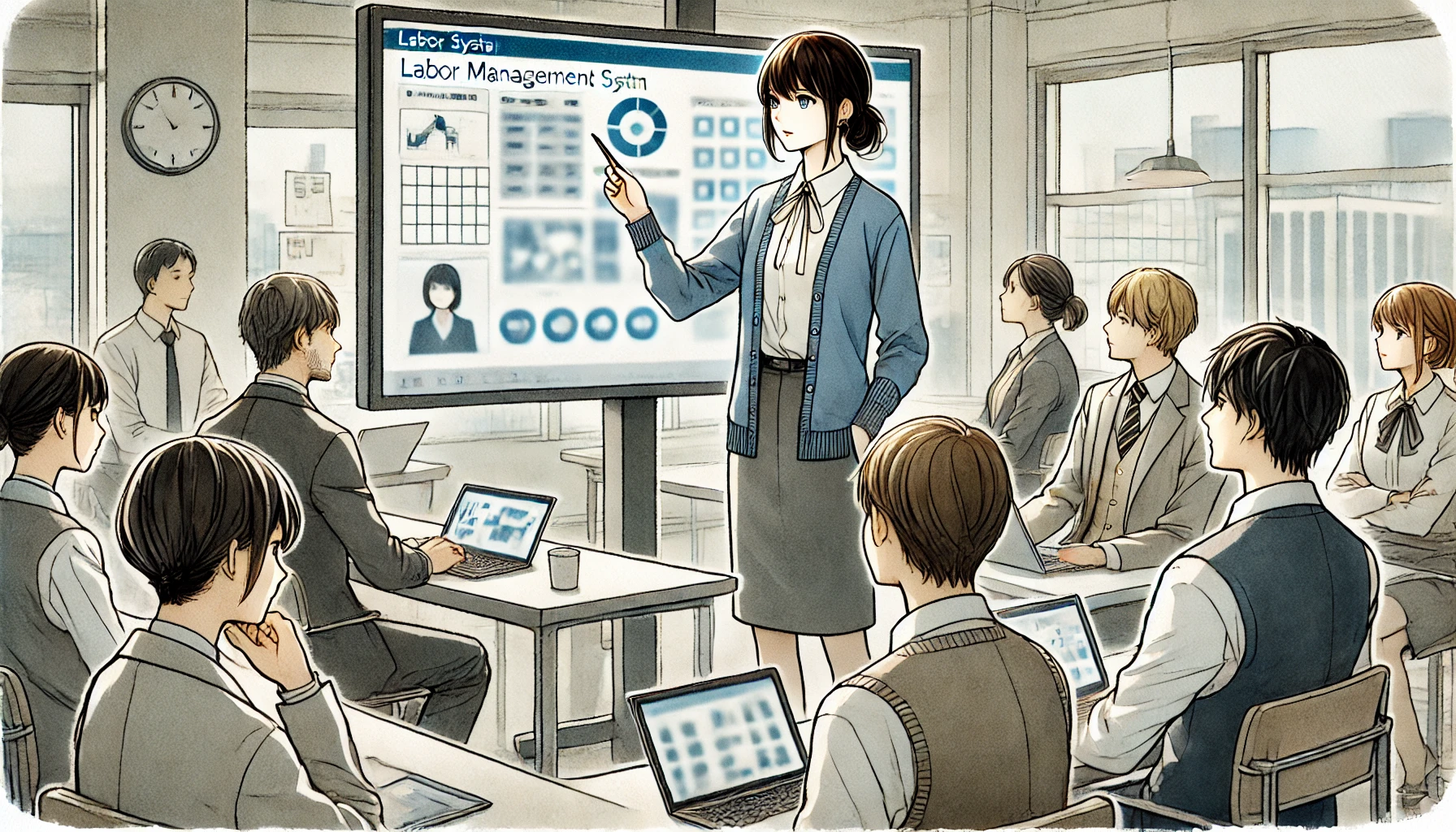形式だけの面接では、ミスマッチが増えるばかり。
特に中小企業では「相性」や「実行力」が重要です。
本記事では、実際によく使われている質問例に加え、「避けた方がよいNG質問」や「目的別の聞き方」も解説。現場で活用できるよう、テンプレートとしても使える構成にしています。
第1章:なぜ面接で「何を聞くか」が重要か
面接の成否は「質問の質」で9割決まる
採用面接において、「何を聞くか」は極めて重要な要素です。
その理由は明確で、質問の質によって応募者から引き出せる情報の質も変わってくるからです。
採用活動とは、書類だけでは見えない応募者の価値観、行動特性、仕事へのスタンスを見極めるプロセスです。
つまり、面接とは「見抜く技術」であり、その中心にあるのが“質問力”です。
「志望動機を教えてください」「自己紹介をお願いします」
これらの質問は悪くありませんが、定番だからこそ答えもテンプレート化されている傾向があります。
こうした“型通り”の質問だけでは、応募者の本音や適性はなかなか見えてきません。

定番質問を繰り返すだけの面接、やっていませんか?
中小企業こそ「一問一答」ではなく「見極め力」
特に中小企業においては、採用一人あたりのインパクトが大きくなります。
大企業のように「あとで調整すればいい」という余地はありません。
だからこそ、面接官には「この人は本当にうちに合うのか?」を見抜く力が求められます。
その判断材料となるのが、応募者に投げかける質問の設計です。
質問は「評価のためのツール」です。
一問一答のように形式的にこなすのではなく、「なぜそれを聞くのか?」という意図を明確に持っておくことが鍵となります。

質問に“狙い”がなければ、情報は表面で止まりますよね。
「形式的な質問」ばかりの落とし穴
よくある面接の失敗パターンが、「形式的な質問ばかりを並べること」です。
例えば、以下のような流れが典型的です。
-
自己紹介
-
志望動機
-
学生時代に力を入れたこと(新卒)
-
退職理由(中途)
-
長所と短所
これらは「聞いておくべき」質問である一方で、形式的に聞くだけではまったく意味を持ちません。
問題は、その後に「どう深掘るか」です。
表面的な回答を受け入れるだけでは、ミスマッチの可能性が高まります。
質問を“つなげていく力”、そして“違和感をキャッチする力”が求められるのです。
【事例】質問設計の甘さで早期退職を招いた失敗
ここで、実際にあった中小企業での失敗談をご紹介します。
製造業を営む有限会社A社では、営業職の中途採用を行いました。
面接は社長の佐藤圭一さんが自ら担当しました。
当日は履歴書に沿って形式的な質問を一通り行い、特に大きな問題も感じず採用を決定。
ところが、入社して3ヶ月で退職という結果に。
退職理由を確認したところ、「現場が思った以上にアナログで驚いた」とのこと。
社長の佐藤さんは、「そういえばITスキルの確認を一切していなかった」と後悔されたそうです。
このように、「当たり前のことを、当たり前に聞いていなかった」ことが大きな失敗につながったのです。
面接の成否は“質問の設計”で9割が決まる。
これは人事の現場で幾度となく証明されてきた真実です。
次章では、よくある基本質問をどのように活用すべきか、具体的に見ていきましょう。
第2章:採用面接でよく使われる基本質問10選
「定番質問」は意味がない? いいえ、設計次第で武器になります
「またこの質問か」と思われがちな面接の定番。
しかし、使い方次第では応募者の本質を見抜く“強力な武器”になります。
実際、私がこれまで支援してきた中小企業の面接現場でも、「定番をどう聞くか」で採用の質に差が出る場面を何度も見てきました。

ベタな質問を侮ると、痛い目にあいますよ。
それでは、ここからは「基本質問10選」とその意図、さらに“見抜く視点”まで一つひとつ解説していきます。
① 自己紹介をお願いします
意図:話の構成力・要点のまとめ方・話し方の癖を確認
見抜く視点:伝える順序、話の長さ、抑揚、目線などコミュニケーションの土台が見える
この質問で重要なのは「何を話すか」よりも「どう話すか」。
1分以内に要点を押さえて話せるかで、プレゼン力の基礎が見えてきます。
② 志望動機を教えてください
意図:企業理解と応募の本気度を確認
見抜く視点:ホームページの内容をなぞっていないか、言葉の中に自分なりの“意味”を込めているか
表面的な回答しか出ない場合、「なぜこの業界か」「他社ではなく弊社を選んだ理由は?」と深掘りしましょう。
③ これまでの職務経験を教えてください
意図:経歴を時系列で整理できるか、どのような成果を出してきたか
見抜く視点:成果の内容が「数字」「エピソード」「他者評価」で語られているか
実績をただ列挙するのではなく、「その仕事の背景」「成功要因」に触れられているかがポイントです。
④ 前職を退職した理由は?
意図:価値観とリスク要因を見極める
見抜く視点:「人間関係が合わなかった」「上司が…」など、他責の傾向がないか
この質問は慎重に扱う必要がありますが、逆に“本音”が見える可能性も高い質問です。

本音と愚痴の境目、よく見極めましょう。
⑤ 当社でどんな仕事をしたいですか?
意図:入社後のビジョンと適応性を確認
見抜く視点:自社の業務を理解したうえでの提案になっているか、具体性があるか
「何でもやります」タイプの回答には要注意。適性と希望の擦り合わせができるかが肝です。
⑥ 自分の強み・弱みは?
意図:自己理解と客観性の有無を確認
見抜く視点:「強み=業務への貢献」「弱み=改善策まで述べているか」に注目
強み・弱みは、それ自体よりも「どんな場面で発揮されたか/問題になったか」のエピソードが重要です。
⑦ チームで働いた経験について教えてください
意図:協調性・役割理解・対人スキルを把握
見抜く視点:自分の役割をどう捉えていたか、チーム内の立ち位置の語り方に注目
「自分ばかりが頑張った話」ばかりだと、チームワークに不安が残ります。
⑧ これまでに困難だった仕事と、その乗り越え方は?
意図:問題解決力と粘り強さの有無を確認
見抜く視点:課題への姿勢・失敗からの学び・行動プロセスが語られているか
具体的な行動と結果が語れるかどうかで、思考の深さが見えてきます。
⑨ 入社後にどう成長したいですか?
意図:向上心と自己成長意欲の確認
見抜く視点:具体的な目標があるか、自発的にキャリアを考えているか
「教えてもらえれば…」という受け身の回答だと、成長期待が薄い可能性があります。
⑩ 質問はありますか?
意図:企業理解の深度・関心の高さをチェック
見抜く視点:制度や待遇だけに偏っていないか、業務や組織への質問があるか
この質問への回答こそが、「その人の本当の関心領域」を表します。
逆に「特にありません」と言われたら、慎重に判断する必要があります。
【まとめ】基本質問こそ、設計力と深掘り力が試される
どれも見慣れた質問かもしれません。
しかし、「なぜこの質問をするのか」という意図を持ち、「どのように深掘るか」の視点があるだけで、面接の質は大きく変わります。
定番質問を“当たり前のように使う”のではなく、“意図的に使いこなす”こと。
それが、優秀な面接官とそうでない人の違いを生みます。
次章では、さらに本音を引き出す深掘り質問の具体例に進みましょう。
第3章:本音を引き出す深掘り質問テクニック
表面的な回答しか返ってこない理由
「志望動機は?」「強みは?」
こういった質問をしても、返ってくるのはどこかで見たような“きれいな答え”。
実はそれ、応募者が「こう答えるべきだ」と考えて作っている“演技”かもしれません。
なぜ本音が出てこないのか?
それは、面接官が「掘り下げていない」からです。
一問一答で満足し、そこで会話が終わってしまえば、相手は“当たり障りのない自分”だけを見せて終わります。

その場で終わる質問には、本音も終わります。
本音を引き出すには、「次に何を聞くか?」がすべてを左右します。
本音を引き出すには「二段階質問」がカギ
表面的な回答をそのまま受け取らない。
ここで使うのが、いわゆる「二段階質問」です。
たとえば、志望動機を聞いたときにこんな答えが返ってきたとしましょう。
「御社の理念に共感しました」
これで終わらせてはいけません。
その先にある“本人の価値観”や“本気度”を引き出す必要があります。
ここで有効なのが、「なぜ?」を3回繰り返す“3WHY”のテクニックです。
これは問題解決の現場でも使われる手法で、根本的な理由を掘り下げるために効果的です。
質問例:「なぜ?」を3回繰り返す
例)志望動機に対する会話フロー:
面接官:「なぜ弊社の理念に共感したのですか?」
応募者:「“人の役に立つ”という価値観に惹かれました」
面接官:「“人の役に立つ”ことが大事だと感じたのは、どういった経験からですか?」
応募者:「前職で、お客様から直接感謝された経験がありまして…」
面接官:「その経験で、特に印象に残っている場面はありますか?」
ここでようやく、応募者の中にある「動機の核」が見えてきます。
表面的な“理念共感”から、実体験に基づいた“価値観”の話へとつながっていくのです。
このように「なぜ?」を重ねていくと、次第に相手も“演技の自分”を脱ぎ、本当の顔を見せ始めます。

3回「なぜ」と聞くだけで、相手の空気が変わる瞬間があります。
【会話例付き】見抜くための対話フロー紹介
ここでは、よくある「強み」への質問から、深掘りの流れを具体例でご紹介します。
【テーマ】「あなたの強みは何ですか?」
面接官:「あなたの強みは何ですか?」
応募者:「行動力です」
面接官:「行動力を発揮した具体的な場面を教えてもらえますか?」
応募者:「前職で提案資料を翌日に出さなければいけないときに、社内調整を一晩で終えました」
面接官:「その場面で、なぜ“行動する”という選択ができたのでしょうか?」
応募者:「元々、納期に厳しいお客様だったので、信頼を失いたくなかったんです」
面接官:「その考え方は、いつごろから持つようになったのですか?」
この流れの中で、単なる“行動力”というキーワードが、
「納期や信頼に責任を持つスタンス」や「職務観」の話へとつながっていきます。
こうして深掘ることで、「この人は我が社で本当に機能するか?」という判断材料が具体的に得られるようになります。
【まとめ】“見抜く力”とは、“聞く力”の延長にある
面接で相手の本音を引き出すには、「次の質問」が何より重要です。
表面的な回答を受け流さず、なぜ?を繰り返すことで、本当の価値観・行動原理が見えてきます。
これは経験がものを言うスキルではありますが、再現性のある手法でもあります。
「二段階質問」「3WHY」などのテクニックを使いこなすことで、あなたの面接も確実に変わります。
次章では、新卒採用において、未来のポテンシャルをどう見抜くかをテーマにしていきます。
第4章:新卒採用で効果的な質問と注意点
新卒採用における面接は「過去」より「未来」を見る場
中小企業が新卒採用に取り組む際、多くの面接官が悩むのが「何を評価すればいいのか?」という点です。
なぜなら、新卒には職務経験がありません。
つまり、「実績で測れない」という制約があるのです。
このときに重要なのが、“未来志向”の質問です。
過去の経験を尋ねるのは入口にすぎません。
その経験をどう咀嚼し、社会人としてどう活かそうとしているか――そこにポテンシャルの核心があります。

過去より“これから”を聞くのが新卒面接の鉄則です。
質問例:「学生時代に力を入れたこと」→「それを社会人でどう活かす?」
よくある質問の一つに「学生時代に頑張ったことは?」というものがあります。
これは悪くありません。
しかし、それ単体では「過去の思い出話」で終わってしまいます。
この質問を“未来志向”に変えるには、こうつなぎます。
面接官:「その経験を、社会人になったときどう活かせそうですか?」
この追加の一言で、学生の視点が“振り返り”から“想像”に変わります。
将来像を自分の言葉で語れるかどうか。
そこに、自己理解の深さと“自走力”の片鱗が表れます。
また、「活かす場面を想定できるか」は、企業研究や業務理解が浅いかどうかのリトマス試験紙にもなります。
NG対応:「答えが型にはまっていない=悪」ではない
新卒面接でよくあるミスは、「正しい答え」を求めてしまうことです。
特に、面接官がベテランになればなるほど、型に当てはめたくなる傾向があります。
しかし、型どおりに答えられない学生にこそ、面白い可能性が隠れていることもあるのです。
たとえば、こんな学生がいました。
「学生時代に頑張ったことは?」という質問に対し、こう答えました。
学生:「特別に何かを頑張ったという意識はあまりないんです。ただ、アルバイトは休まず行っていました」
この答えだけを見れば“浅い”と感じるかもしれません。
ですが、「なぜ休まずに通えたのか?」「どんな思いで働いていたのか?」と問いを重ねると、
“責任感”や“継続力”という重要な資質が見えてくることもあります。

“普通の答え”の中に、本質が隠れていることって多いですよね。
【実例】「正解のない質問」で判断力をチェック
新卒採用でおすすめなのが、“正解のない質問”をあえて投げかけることです。
これによって、学生の思考力・柔軟性・誠実さを見ることができます。
質問例1:「自分より優秀な人とどう関係を築きますか?」
質問例2:「困難な仕事と、やりたい仕事、どちらを選びますか?」
これらに“正解”はありません。
でも、答え方や考えるプロセスを見れば、「どんな価値観で動く人か」が明らかになります。
ある学生はこう答えました。
学生:「やりたい仕事を選びます。でも、困難な仕事から逃げたいという意味ではありません。やりたい仕事なら、困難でも取り組む覚悟があります。」
このような回答には、言葉選び・論理の筋道・価値観がしっかり現れています。
こうした一問は、見抜く力を養う“訓練”にもなるのです。
【まとめ】新卒面接は「経験」より「思考」を問え
新卒採用において、見るべきは「完成された人物」ではありません。
むしろ、「どんな成長の可能性を秘めているか」。
そのためには、表面的な経験ではなく、考え方・視点・価値観に迫るような質問が不可欠です。
ポテンシャル採用に必要なのは、“未来を問う力”です。
次章では、中途採用で求められる質問の視点を、実務に即して紹介していきます。
第5章:中途採用で見極めたい質問と意図
中途採用で見落とされがちな「スキル以外」の重要性
中途採用では、つい「実績」や「スキルセット」に目が行きがちです。
しかし、採用後に活躍するかどうかを左右するのは、履歴書に書かれた“スペック”ではありません。
実務経験があるからといって、自社の環境でもうまく機能するとは限らないのです。
特に中小企業では「自走力」や「課題解決力」がものをいいます。
業務の仕組みや教育体制が整っていないケースも多く、自ら考え、動ける人材が求められるのです。

「即戦力」って、単なる経験者とは違うんですよね。
質問例①:「前職で成果を出した経験は?」
意図:成果の背景・過程・本人の貢献度を把握するため
見抜く視点:
-
「何を達成したか」ではなく「どう達成したか」に注目
-
一人称が多すぎないか?チーム貢献とバランスが取れているか?
例:
「売上120%達成」といった数字だけでなく、「どんな工夫をしたのか」「どんな壁があったのか」「他部署とどう連携したか」などのプロセスにこそ価値があります。
プロセスが語れない成果は、他人の手柄を借りている可能性も否定できません。
質問例②:「苦労したこと、それをどう乗り越えたか」
意図:課題にどう向き合うか、粘り強さや工夫力を見極めるため
見抜く視点:
-
「苦労の種類」が現実的か?(人間関係、納期、仕様変更など)
-
その時に取った行動に一貫性や自責の姿勢があるか?
この質問は、単に「つらかったこと」を聞いているのではありません。
むしろ、「どう考え、どう動いたか」を聞いています。
“問題”があったことは当たり前。そのときの“態度”にこそ人間性が出るのです。
質問例③:「なぜ前職を辞めたのですか?」
意図:転職の理由と、その背景にある価値観を確認するため
見抜く視点:
-
他責傾向の有無
-
現実逃避的な転職ではないか?
-
応募企業で同じ問題が起きたときにどう行動するかのヒントがあるか
この質問はセンシティブですが、正しく使えば非常に有効です。
コツは、問い方にあります。
NG例:「なぜ辞めたんですか?(圧迫感あり)」
適切な聞き方:「退職を選ばれた背景を教えていただけますか?」
前向きな転職理由には筋道があります。
逆に、具体性がなくフワッとした回答しか出てこない場合は注意が必要です。

辞めた理由が“浅い”と、またすぐ辞める可能性も…ありますよね。
【エピソード】「見た目は普通」でも、光る人材を見抜いた浅見健一さんの事例
製造業を営む株式会社ミヤシロ工機の部長、浅見健一さんは、3年前の中途採用で“社運を変える人材”を見抜きました。
その人物は、履歴書だけ見るとごく普通のキャリアで、学歴も高卒。
前職は現場監督補佐という地味なポジションでした。
しかし、面接の中で浅見さんはこう尋ねました。
浅見さん:「一番苦労した仕事は何ですか? それをどう乗り越えましたか?」
応募者は、豪雨で現場工程が3日遅れたとき、業者間の調整をすべて自分が担当したという話を語りました。
周囲からの信頼、連絡スピード、日々の丁寧なメモ習慣など、課題解決への“実直な努力”が明確に伝わってきたそうです。
採用後、彼はわずか1年で現場リーダーに昇格し、現在では若手の指導も担っています。
まさに「履歴書だけでは絶対に分からなかった人材」だったのです。
【まとめ】中途採用では「内面の筋肉」を見極める
スキルは見せかけだけでは測れません。
むしろ、課題にどう向き合ってきたか、自ら動けるか、言葉と行動が一致しているかを見極めることが、実務で活躍する人材を採る近道です。
次章では、こうした質問を「職種別」にどう応用すべきか、具体的にご紹介していきます。
第6章:職種別にカスタマイズすべき質問とは
すべての職種に同じ質問では、見抜けるわけがない
面接に慣れていない中小企業の現場では、全職種で同じような質問をしてしまうケースがよくあります。
「志望動機」「強み」「キャリアビジョン」などの汎用質問は確かに便利ですが、職種によって評価すべき資質はまったく異なります。
営業なら「数字への執着」、エンジニアなら「技術の選定理由」、バックオフィスなら「正確さと柔軟性」。
見るべきポイントがズレていれば、いくら質問を重ねても“評価軸のない雑談”になりかねません。

「誰にでも使える質問」は、結局誰の本質も見抜けないんですよね。
それぞれの職種に必要な質問の設計を見ていきましょう。
営業職に必要な質問と視点
営業職は、成果が数字で表れやすい分、回答も“盛られがち”です。
肝心なのは「結果」ではなく「プロセス」と「再現性」。
どんな視点で動いていたかが分かる質問が有効です。
質問例:
-
「目標達成できた要因は何ですか?」
-
「達成できなかったとき、どんな打ち手を試しましたか?」
-
「失注した案件で、どのように振り返りましたか?」
見抜くポイント:
・数字への感度が高いか
・失敗から何を学んでいるか
・継続的に改善しようという姿勢があるか
実際、成績優秀な営業でも「なぜうまくいったのか分からない」タイプは再現性が低く、定着率が悪い傾向があります。
エンジニアに必要な質問と視点
エンジニア職では、「技術力」そのものよりも、問題解決思考と学習姿勢のほうが重要になる場面が多いです。
現場に配属されれば、日々新しい技術や環境に対応する必要があるからです。
質問例:
-
「なぜその技術(言語・フレームワーク)を選びましたか?」
-
「最近学んだこと、取り組んでいることはありますか?」
-
「バグ対応やトラブル時に、どんな判断をしましたか?」
見抜くポイント:
・選定理由に“目的”や“業務目線”があるか
・学習が習慣化されているか(自走力)
・トラブル時の対応力=実務力の一端が見えるか
特に「技術選定の根拠」は、ロジカルシンキングの質を見る上でも非常に有効な質問です。

“何を使ったか”より、“なぜ使ったか”を聞けってことですね。
バックオフィスに必要な質問と視点
管理部門や事務職は、派手な成果が見えにくい分、プロセスや安定運用力、リスク回避力をどう見抜くかがカギとなります。
質問例:
-
「ミスを防ぐために工夫していることはありますか?」
-
「急な変更や依頼が来たとき、どのように対応していますか?」
-
「改善提案をした経験はありますか?」
見抜くポイント:
・細かい業務への意識と責任感
・ルーティンワークだけでなく“改善意識”があるか
・報告・連絡・相談(報連相)の意識が定着しているか
数字で語るのが難しい職種だからこそ、行動や工夫の具体性が重要な評価基準になります。
【職種別質問リストまとめ】
| 職種 | 質問例 | 見るべきポイント |
|---|---|---|
| 営業職 | ・目標達成の要因は? ・失注理由と改善策は? |
数字感度/改善力/自己分析力 |
| エンジニア | ・技術選定の理由は? ・最近の学習内容は? |
自走力/論理性/トラブル対応力 |
| バックオフィス | ・ミスを防ぐ工夫は? ・急な変更への対応は? |
安定運用力/柔軟性/改善への姿勢 |
【まとめ】職種ごとの質問設計が面接の質を高める
“職種が違えば、働き方も思考も違う”。
それを無視して、すべての応募者に同じ質問を投げるのは、まさに「魚に木登りをさせる」ようなものです。
面接で本質を見抜きたいなら、職種別に質問の視点を調整することが必須です。
次章では、見落としがちな“NG質問”について解説していきます。
意図せずハラスメントになる質問、法律的にアウトな聞き方、心当たりありませんか?
第7章:実はNGな面接質問とその理由
その質問、悪気はなくても違法になるかもしれません
面接の場では、つい「世間話」のような感覚で質問してしまうことがあります。
特に中小企業では、社長や現場責任者が面接官を兼ねており、「人となりを知りたい」という気持ちから、プライベートに踏み込んだ話題を出してしまうケースも少なくありません。
しかし、それが法律上NGとされる質問であることに気づいていないケースが非常に多いのです。
ここでいうNG質問とは、「本人の適性・能力に関係のない事項」に関する質問です。

気づかずに聞いていた質問が、実はアウト…って怖いですよね。
「聞いちゃいけない質問」例と具体的なNGワード
厚生労働省が示す「公正な採用選考の基本」によれば、以下のような質問は原則としてNGとされています。
-
「ご両親はどんなお仕事をされていますか?」
-
「兄弟は何人いますか?」
-
「結婚の予定はありますか?」
-
「お子さんは何人いらっしゃいますか?」
-
「彼氏(彼女)はいますか?」
-
「信仰されている宗教はありますか?」
-
「政治に関心はありますか?」
-
「地元はどちらですか?」
-
「実家は遠いんですか?通える距離ですか?」
-
「見た目がきっちりしてるね。育ちが良さそう」
-
「背が高いですね。スポーツやってました?」
これらはいずれも、業務遂行能力と無関係な質問であり、
本人が答えたくない情報を「強制的に開示させる」意図と受け取られる恐れがあります。
なぜNGなのか?厚労省ガイドラインに基づく根拠
厚生労働省の「公正な採用選考の基本的な考え方」では、採用選考において重視すべきは「応募者の適性と能力」であり、
これに無関係な要素を選考基準にしてはならないと明確に記載されています。
また、「採用選考における企業の責任」として以下が定められています:
応募者の基本的人権を尊重し、思想、信条、性別、年齢、家族構成などによって差別を行わないこと。
つまり、面接中にこれらの情報を「聞いた」だけでも、応募者にとっては「選考に影響した」と受け取られる可能性があり、
訴訟リスクやSNS炎上の引き金になることもあります。
うっかり聞いてしまいがちな質問ワードとその対処法
悪気なく聞いてしまう表現ほど、面接でトラブルを招きやすいものです。
以下に“言い換え”のヒントを紹介します。
| NGな表現例 | 適切な言い換え例 |
|---|---|
| 「通勤、大変じゃないですか?」 | 「入社後の通勤イメージはどうですか?」 |
| 「結婚の予定は?」 | ✕ ※言い換え不可。聞かないこと。 |
| 「家族の介護とかは大丈夫?」 | ✕ ※業務に支障があれば本人が申告します。 |
| 「地方出身なんですね」 | 「転勤や出張が必要な際、対応可能ですか?」 |
| 「お子さんの年齢は?」 | ✕ ※育児支援制度などの説明はOK、質問はNG。 |

“気遣い”のつもりが、一線を越えることってありますよね。
【体験談】ある中小企業での“うっかり質問”が炎上寸前に
東京都内のとある建築業の中小企業で、現場監督の採用面接中の出来事です。
面接官を務めたのは、総務部長の田口康弘さん。
応募者は30代の女性でした。
雑談の流れで田口さんは「お子さん、いらっしゃるんですか?」と何気なく聞いてしまいました。
応募者は苦笑いしつつもその場で返答しましたが、後日、別ルートから「その質問が不快だった」と人事経由で正式にクレームが入りました。
この件は社内でも問題となり、会社として面接マニュアルの見直しと、全管理職への研修を実施するきっかけになったそうです。
もしSNSなどで拡散されていたら、企業イメージの毀損にもつながりかねない事例でした。
【まとめ】“質問の意図”が明確でなければ、トラブルの火種になる
採用面接では「聞くこと」も重要ですが、「聞かない勇気」もまた必要です。
自社にとっては何気ない一言でも、応募者にとっては“不快”や“圧力”と感じられることもあるのです。
NG質問は、「言ってはいけないこと」ではなく「言わなくても評価できること」と捉えましょう。
次章では、こうした面接トラブルを防ぐために、事前に質問をどう設計すべきかというポイントに進みます。
第8章:面接前に準備しておくべき質問設計術
面接は「現場で考える」ではなく、「準備が8割」
「面接は会話だから、ぶっつけ本番でもなんとかなる」
そう思っていませんか?
実は、面接の成否は始まる前にほぼ決まっていると言っても過言ではありません。
何を聞くか、なぜ聞くか、その答えで何を見極めたいか。
この“設計図”がなければ、いくら質問を投げかけても、核心にはたどり着けません。

「とりあえず聞くか」で採れるほど、いい人材は残っていませんよ。
面接の準備は、「目的×質問」の設計から始まります。
質問を「5つの視点」で分類せよ
質問設計をする際には、次の5つの視点で質問を分類すると、目的が明確になりやすくなります。
① 動機(Motivation)
-
志望動機
-
なぜこの業界/企業を選んだのか?
② 経験(Experience)
-
これまでの業務内容と成果
-
苦労したこと・乗り越えた経験
③ 価値観(Values)
-
働くうえで大切にしていること
-
チームでの役割の考え方
④ 適性(Fit)
-
自社の文化・業務へのフィット感
-
自律性・コミュニケーション力の確認
⑤ 将来(Vision)
-
入社後にやりたいこと
-
3年後にどんな存在になっていたいか?
この5分類に沿って質問を準備すれば、質問が「目的」に直結する形になります。
また、面接後に評価する際も、「この人はどの視点で強みがあるのか」が整理しやすくなります。
以下は、質問設計を効率化するためのテンプレート例です。
評価項目と質問を紐づけておくことで、無駄のない面接が実現します。
| 評価視点 | 質問例 | 回答で見たいこと |
|---|---|---|
| 動機 | 当社を志望した理由は? | 業界理解、企業研究の深さ |
| 経験 | 成果を出した経験は? | 行動力、再現性 |
| 価値観 | 理想の職場とは? | 組織との親和性 |
| 適性 | チームでの役割は? | 協調性、自律性 |
| 将来 | 入社後にやりたいことは? | 方向性の一致、主体性 |
これを印刷してメモ欄を作っておくと、面接中のメモ取りや振り返りもスムーズになります。
「5W1H」で質問を磨く:すべては“目的ある設計”から
質問を精査する際は、5W1H(When/Where/Who/What/Why/How)の観点を意識しましょう。
例1:成果について深掘りする場合
-
What(何):どんな成果を出したか?
-
Why(なぜ):なぜその成果が出せたのか?
-
How(どうやって):どんな工夫をしたのか?
-
When(いつ)/Where(どこで):どの時期、どの現場での話か?
-
Who(誰と):誰と連携したのか? チームか個人か?
このように、漠然と「成果を教えてください」ではなく、具体的な視点で枝分かれする質問をあらかじめ設計しておくことが、本音を引き出すコツです。

1問1答じゃなくて、1問5視点。これが差を生みます。
【まとめ】設計なき質問は、目的なき面接になる
面接はただの「会話」ではありません。
企業にとっても応募者にとっても、お互いを見極める“選考の場”です。
その場を有意義なものにするには、事前の質問設計が欠かせません。
「聞くべきこと」と「その答えから何を見るか」を整理し、意図を持った質問で相手の本質に迫ること。
次章では、これまでの内容を総括し、面接で“見抜ける力”を高めるために大切な視点を振り返ります。
あなたの質問が変われば、採用の質は確実に変わります。
第9章:まとめと感想|質問力が採用の質を変える
「質問の質=会社の質」になる時代へ
採用面接は、ただ応募者を“選ぶ”場ではありません。
企業の価値観やカルチャーが、たった30分〜1時間の「質問」にすべて表れてしまう時代です。
だからこそ、質問の質は、会社の質そのものといっても過言ではありません。
見せかけの質問や、テンプレートだけの面接では、会社の本気も伝わらず、応募者の本音も引き出せないのです。

面接は“相互の本音を引き出す場”であってほしいですね。
見抜く力を持てば、ミスマッチは大幅に減らせる
人手不足が叫ばれる今、「とにかく採る」では長続きしないことを、多くの中小企業が痛感しています。
実際、私が関わった企業でも「急いで採ったが、3ヶ月で辞められた」「結局カルチャーに合わなかった」という声を何度も聞いてきました。
こうしたミスマッチの多くは、「質問の設計」が甘かったことに起因します。
相手の本音・行動・価値観・将来像をどう見極めるか。
つまり、見抜くための“質問力”が、採用成功のカギなのです。
【エピソード】佐藤明さんが語った「質問が変わると人が変わる」
東京都内で建設業を営む株式会社Kの社長、佐藤さん。
数年前まで採用に悩み、「来てもすぐ辞める」「面接で何を聞けばいいか分からない」と苦しんでいたそうです。
そこで佐藤さんは、面接質問の設計から見直しました。
質問を「志望動機」や「資格の有無」から、「過去の困難とその乗り越え方」「チームでの役割」などに変えていったのです。
すると、応募者の雰囲気も反応もガラリと変わりました。
形式的な受け答えが減り、本音が見え、採用後の定着率が大きく改善。
こう語ってくれました。
「質問を変えるだけで、来る人も変わった。質問って、会社の姿勢なんだと思いました」(佐藤さん)
この一言に、すべてが詰まっていると感じます。
明日からできる「問いの再設計」で、採用を変えよう
最後に、明日からすぐにできる面接改善のヒントをまとめます。
-
質問に「意図」を明記する(なぜ聞くのか?)
-
評価ポイントに応じて「5つの視点」で分類する
-
「なぜ?」を3回繰り返して本音に迫る
-
職種ごとに質問をカスタマイズする
-
聞いてはいけないNG質問を避ける(厚労省ガイドラインに準拠)
質問を変えることで、面接の質が変わる。
面接の質が変われば、採用の精度が上がる。
そして、採用の精度が上がれば、会社は確実に強くなります。
その第一歩は、「問いを再設計すること」。
この記事が、あなたの採用のあり方を少しでも変えるきっかけになれば幸いです。