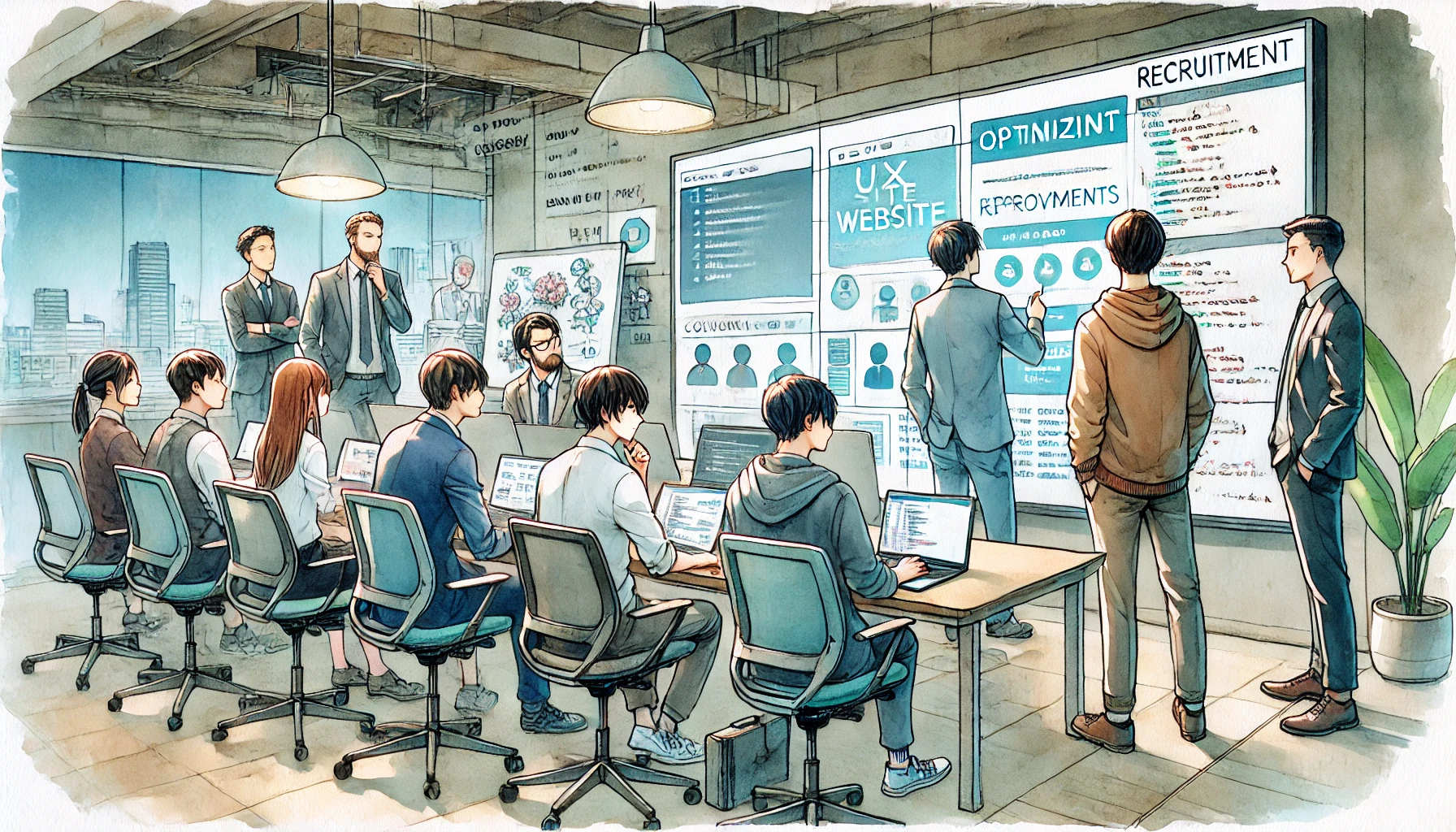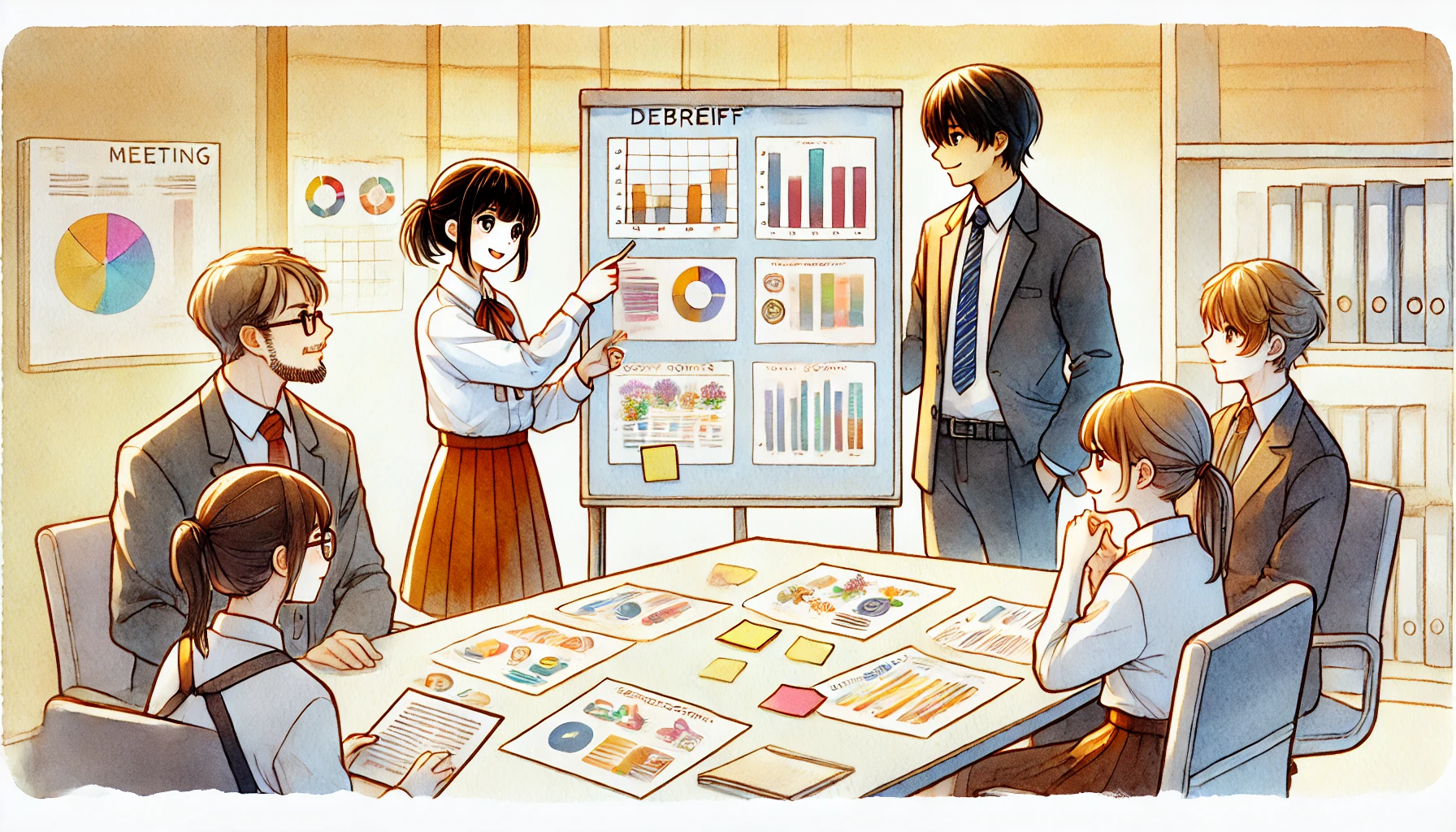社員から「上司の言動がパワハラかもしれない」と相談を受けた瞬間、あなたの一手が企業の命運を分けるかもしれません。
対応を間違えば、信頼の喪失や訴訟リスクも。
この記事では、初動で失敗しないために企業が“今すぐできる”5つの対策を、事例とともに紹介します。
現場で混乱しないための実務知識、しっかり押さえておきましょう。
第1章:その言動、指導?ハラスメント?境界線を知る
「部下に少し厳しく指導しただけなのに、ハラスメント呼ばわりされるなんて」
そう思ったことのある管理職の方も多いかもしれません。
しかし、その「少し」が致命的になるのが、今の時代の職場環境です。
企業のリスクマネジメントを担う人事・労務担当者であれば、このテーマから逃げるわけにはいきません。
この記事では、「ハラスメント」と「指導」の境界を明確にし、正しい対応の第一歩を踏み出すための視点を整理していきます。
ハラスメントの定義|3つの主な類型
まず、ハラスメントとは、職場における不当な言動により、相手に対し身体的・精神的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為を指します。
この定義は、厚生労働省や多くの判例においても一貫しています。
代表的なハラスメントには以下の3つがあります。
-
パワーハラスメント(パワハラ):上司などの優位な立場を利用し、業務の範囲を逸脱した言動で他者を苦しめる行為。
-
モラルハラスメント(モラハラ):無視・悪口・否定など、継続的な精神的攻撃によって人格を傷つける行為。
-
セクシャルハラスメント(セクハラ):性的言動により、相手を不快にさせる行為。性的冗談や容姿の話題も含まれる。
これらの中でも、職場で最も多いのはパワハラです。
実際、令和4年度の「個別労働紛争解決制度」によると、パワハラに関する相談件数は約88,000件以上と過去最多を記録しています(厚生労働省)。

これ、現場で想像以上に多いんです。ほんとに。
厚生労働省が示す「パワハラ6類型」
パワハラの具体的な行為については、厚生労働省が明確に6つの類型を示しています。これらは企業が判断する上でも非常に重要な基準です。
-
身体的な攻撃:殴る、蹴る、物を投げるなどの暴力行為
-
精神的な攻撃:人格を否定する発言、大声で怒鳴る、侮辱的な言葉を浴びせる
-
人間関係からの切り離し:無視する、隔離する、業務上の連絡を遮断する
-
過大な要求:明らかに遂行不可能な業務を課す
-
過小な要求:能力や役職に見合わない単純作業だけを任せる
-
個の侵害:プライベートに踏み込んだ質問や干渉
これらは、「業務上の適正な範囲を超えるもの」であることが条件です。
逆に、適正な業務指示・注意であれば、当然ながらハラスメントには該当しません。

この線引き、現場じゃほんと曖昧にされがちなんです。
指導とハラスメントの違いをどう見極めるか?
一番の悩みどころがここでしょう。
上司の指導が「適正な業務指導」か「精神的攻撃」か、その線引きは非常に微妙です。
判断基準となるのは以下の3つです。
-
言葉の内容:相手を叱る内容が、行動・結果に対する指摘になっているか、人格や感情を否定していないか
-
言い方や態度:冷静で建設的な口調か、それとも威圧的・怒鳴り口調になっていないか
-
頻度や継続性:一度きりではなく、何度も繰り返されていないか
このように、「指導」は相手の成長を目的に行われるものですが、「ハラスメント」は相手の尊厳を損なう行為になります。
現場で起きた事例:ただの「注意」では済まない
ここで、実際に私が関与した事例を紹介します。
ある中堅企業の製造部門で、50代男性の上司が若手社員に対して業務ミスを厳しく叱責。
「君みたいな人間がいると職場が乱れる」「仕事辞めたら?」といった発言が録音されていました。
上司本人は、「ただ注意しただけ。怒鳴ったのは1回だけ」と主張しました。
しかし、録音された音声と他社員からの証言で、「精神的攻撃」にあたると判断され、懲戒処分となりました。
ここで重要なのは、上司の意図ではなく、受け手がどう感じたかという点です。
あなたの職場は本当に“安全”ですか?
どんなに制度が整っていても、現場での言動が曖昧であれば、リスクはなくなりません。
指導のつもりが、社員から「攻撃」と受け止められた時点で、企業としては対応を迫られます。
リスクヘッジの第一歩は、“何がハラスメントに該当するか”を組織で共通認識にしておくことです。
次章では、実際に社員から相談を受けた時、企業がどう動くべきかを解説します。
初動対応を誤ると、被害は拡大し、組織の信頼も損なわれます。
しっかり備えておきましょう。
第2章:社員からの相談を受けた直後の対応とは?
職場でのハラスメントは、発覚した瞬間から企業としての「真価」が問われます。
特に、社員から直接相談を受けたときの初期対応は、信頼回復のカギを握ります。
ここを誤ると、社内外への波紋は想像以上に広がります。
今回は、相談を受けた“その瞬間”に人事や管理職がとるべき対応について、実務ベースで解説していきます。
初期対応フロー|まず何をすべきか?
社員から「上司の言動がつらい」と訴えがあった場合、対応の第一ステップは即時のヒアリングと記録です。
放置したり、後回しにしたりすると、被害者はさらに孤立感を深め、退職や外部通報に繋がりかねません。
以下の流れで対応することが基本です。
-
静かな場所で話を聞く場を設ける(即日が望ましい)
-
事実確認の前に“感情を受け止める”
-
相談内容を正確にメモする(日時、言動、状況など)
-
「調査・対応を行う」と明言し、タイムラインを伝える
-
必要に応じて、当事者同士の接触を一時的に避ける措置をとる
ここで大切なのは、「まず、聞く」という姿勢です。
事実かどうかよりも、社員が“安心して訴えられた”という感覚を得られることが、組織としての信頼を築く起点になります。

最初の5分、本当にで大事です。そこで会社の本気が伝わります。
絶対にやってはいけないNG対応とは?
初動で企業がやりがちな失敗は、主に次の3つです。
-
「そのくらい、よくあることだよ」と軽視する
-
「上司にも確認するから、少し待って」と加害者側にすぐ話す
-
「これはハラスメントじゃないから心配いらない」と断定する
これらの対応はすべて、被害者の信頼を即座に失う対応です。
特に2番目の「加害者に即ヒアリング」は、通報者への報復を招く恐れがあり、企業のリスクを爆発的に高めます。
相談者に寄り添うには、「調査に入る前の慎重な準備」が不可欠です。
焦って動かない。けれど、放置もしない。このバランスが重要です。
証拠とメモの扱い方|“残す”ことの意味
通報を受けた際の証拠管理と記録の保存は、後の調査・対応の正当性を裏付ける要素になります。
以下のような情報を漏れなく記録しましょう。
-
相談日・時刻・相談者の所属と立場
-
ハラスメントがあったとされる日時・場所・発言内容
-
相談者の心理的状態(泣いていた、混乱していた、淡々としていた、など)
-
証拠となりうる資料(録音、メール、チャット履歴、メモなど)の有無
これらは、調査や弁護士との連携時、あるいは労基署からの指導が入った際にも重要な資料となります。

メモ、あとで効いてくるんですよ。忘れるんで絶対残すべきです。
初動失敗が招いた炎上:株式会社A社の事例
とあるIT企業、仮に「株式会社A社」では、営業部の若手社員が部長によるパワハラを上司に相談しました。
ところが人事は、「部長は普段から厳しいけど部下思いだ」と発言し、即座に部長に伝えてしまいました。
結果、部長は該当社員をあからさまに冷遇し、プロジェクトから外すという報復行動に出ました。
これにより、社員は労基署に通報。社名がSNSで拡散され、企業イメージは大きく毀損しました。
原因は明確です。
「相談内容を真摯に受け止めず、加害者に伝えるタイミングを誤った」ことに尽きます。
人事が守るべきは、まず相談者の安全と安心です。
それがなければ、真実は引き出せませんし、企業としての防衛線も築けません。
聞く姿勢こそが企業の信頼を守る
結局、初動のヒアリングで企業が見られているのは「人としてどう向き合っているか」という部分です。
傾聴、共感、記録、対応の明示。
これらが揃って初めて、社員は「ここは声を上げても大丈夫な会社だ」と感じるのです。
そしてそれは、長期的に見れば離職率の低下、風通しのよい職場、企業ブランディングの向上につながります。
次章では、いよいよ加害者・被害者それぞれへの対応について掘り下げていきます。
誰の立場にも偏らない、公平で具体的な対処が求められます。
第3章:加害者・被害者それぞれへの配慮ポイント
ハラスメント案件の難しさは、「どちらかが完全な正義」という単純な構図にならない点にあります。
相談が寄せられた時点で、企業としては事実が判明するまで両者に対して慎重かつ公平な姿勢を貫く必要があります。
ここでの判断ミスは、被害者の不信感、加害者の逆恨み、さらには企業としての信頼の喪失に直結します。
今回は、事実確認中の加害者・被害者双方への正しい配慮と、その実務的なポイントを解説します。
事実確認中の両者への配慮方法
調査に着手する段階では、まだ「どちらの主張が正しいか」は判明していません。
そのため、対応には細心の注意が必要です。
以下は、企業として取るべき基本姿勢です。
-
被害者側には「話を信じている」と伝えつつも、事実確認が必要であることを丁寧に説明する
-
加害者側には、人格を否定せず、冷静に事情を聴く姿勢を見せる
-
お互いの接触を可能な限り避ける措置をとる(部署異動、業務分担の一時変更など)
重要なのは、「聞いた=信じた」と「判断した=処分した」を混同しないことです。
調査の段階でどちらか一方に過度に肩入れする姿勢は、組織内に新たな火種を生むリスクを高めます。

どっちの肩を持っても火種になる。だから“真ん中”でい続けるのが人事の役割。
「加害者にも人権がある」という原則
ハラスメントの対応にあたり、多くの担当者が忘れがちなのがこの点です。
いかに相談があったとはいえ、事実確認前に「悪者」として扱うことは許されません。
これは、労働法上も、就業規則上も、極めて重要な観点です。
万が一、調査の結果「事実に反する申し立てだった」と判明した場合、加害者とされた人物は、名誉や職場での信頼を大きく失います。
その損害について企業が責任を問われるケースもあります。
また、加害者とされた本人も、思わぬ形で精神的ダメージを受けることがあり、休職に至る事例も珍しくありません。
被害者へのケアと二次被害の防止策
もちろん、被害者への配慮を軽視することは論外です。
以下のような対応が求められます。
-
ヒアリングの都度、感情面のフォローを行う(必要に応じて産業医と連携)
-
報復を受けないよう、加害者と物理的・心理的距離を保てる体制を整える
-
事案終了後も継続的に様子を見守る体制を構築する
企業によっては、社外カウンセラーとの連携を導入しているケースもあります。
「話を聞いてくれる第三者がいる」ことは、被害者にとって非常に大きな安心材料となります。

“やった人”だけじゃなく、“やられた人”にもちゃんと着地させるのが大事ですね。
実例紹介:加害者を即処分しトラブルが拡大した企業
ある地方の製造業企業では、女性社員から「上司による継続的な叱責がつらい」との訴えが寄せられました。
会社側は、信頼のある社員からの通報であったこともあり、即座に上司を「懲戒解雇」処分。
しかしその後、当該上司が裁判を起こし、録音データや他社員の証言などから、業務上の指導の範囲内だったと判断され、企業側が敗訴しました。
この事例が教えてくれるのは、「感情的な判断がいかに企業リスクにつながるか」という点です。
処分は、あくまでも事実と手続きの両方を正確に踏まえて行う必要があります。
弁護士・社労士の見解から学ぶ対応の基準
社会保険労務士や労働問題に精通した弁護士の多くが強調するのは、以下の3点です。
-
事実確認のプロセスを社内で明文化しておくこと
-
初期対応の段階から専門家と連携して進めること
-
被害者・加害者双方の“将来の職場復帰”を想定して配慮すること
特に、中立的立場の第三者(社労士・外部調査会社など)によるヒアリングは、社内の信頼性を高め、後のトラブルを未然に防ぐ力を持ちます。
次章では、いよいよ「社内調査」の具体的な進め方について解説していきます。
ヒアリングの設計、調査資料の整理、判断基準の明確化。
対応の“質”が企業全体の信用力を左右します。
第4章:社内調査のやり方と注意点を徹底解説
ハラスメントの事実確認において、「社内調査」は最もセンシティブで、同時に重要なステップです。
対応を誤れば、被害者・加害者の双方に深刻な不信感を与え、企業全体への悪影響も避けられません。
一方で、正しい調査ができれば、事実に基づいた適切な判断が可能になり、信頼の維持・回復にもつながります。
今回は、実務的な視点から「社内調査の正しい進め方とその注意点」を徹底解説します。
調査の目的と段取り|押さえるべき基本手順
まず最初に確認したいのは、「なぜ調査を行うのか?」という原点です。
調査の目的は、懲罰のためではなく、事実を客観的に明らかにすることです。
この姿勢を関係者全員に共有することが、調査の信頼性を高める鍵になります。
調査の基本的な段取りは以下の通りです。
-
通報・相談内容の整理(事前ヒアリング記録の確認)
-
ヒアリング対象者の選定(被害者・加害者・関係者)
-
聞き取り内容の設計(質問リストの作成)
-
証拠の回収(メール、チャット、録音、周囲の証言など)
-
記録化・分析・対応方針の決定
このプロセスを、「公平性・中立性」を担保しながら進めることが求められます。

勢いで動くと、だいたいどっかで綻びます。段取り命ですね。
ヒアリング対象の選定と質問の組み立て方
ヒアリング対象者の選定は、調査の質を左右する極めて重要な工程です。
被害者・加害者は当然ですが、周囲にいた社員(第三者)や、過去にも類似の訴えがあった人物が対象になることもあります。
質問の組み立てには、以下のような工夫が必要です。
-
誘導しない質問:「〇〇さんは怒鳴ってましたよね?」ではなく、「〇〇さんの言動はどう感じましたか?」
-
事実を特定する質問:「どこで、誰が、何を、いつ、どうした?」を意識する
-
感情と状況を両方聞く:例)「その時、どう感じましたか?」「周囲の反応はどうでしたか?」
質問の順番にも注意が必要です。
いきなり核心に迫るのではなく、アイスブレイク→状況の確認→具体的行動→感情・認識の確認と段階を踏むことで、相手も安心して話しやすくなります。
調査時のよくある失敗:誘導質問と偏った証言
社内調査でしばしば見られる失敗が「誘導質問」です。
例えば、「この件って、やっぱり問題ありますよね?」というような聞き方は、回答にバイアスをかける原因になります。
また、調査者自身の先入観が強すぎると、都合のいい証言だけを採用する“確証バイアス”に陥るリスクもあります。
もう一つありがちなのが、被害者・加害者どちらかに偏ったヒアリング回数や質問の深さです。
これにより、「最初から結論ありきだった」と受け取られ、信頼性が損なわれる可能性があります。

誘導しないって、簡単そうで結構難しいんです。経験がモノを言いますね。
実例:匿名の通報が発端になった調査とその教訓
ある大手メーカーでは、社内の通報窓口に「上司の暴言が常態化している」との匿名通報がありました。
人事部は、対象の部署に対して抜き打ちでヒアリングを実施。
しかし、匿名の性質を軽視して「誰が言ったか」はっきりさせようとした結果、周囲の社員にプレッシャーがかかり、逆に誰も本音を言わなくなってしまったのです。
この事例が教えてくれるのは、調査方法そのものが職場環境に与える影響です。
情報の取り扱いと聞き取りの“空気作り”が非常に大切であるといえます。
外部機関と連携する判断基準
ケースによっては、社内だけでの調査が難しい場合もあります。
以下のような場合は、外部機関との連携を積極的に検討すべきです。
-
調査対象が管理職・役員など、社内での力関係が働きやすい場合
-
複数名からの通報があり、組織ぐるみの問題が疑われる場合
-
社内に調査のノウハウや人材が不足している場合
利用できる外部機関には、以下のような選択肢があります。
-
社労士・弁護士による調査代行
-
外部の第三者委員会の設置
-
産業医・メンタルヘルス専門家の関与
第三者調査のメリットは、中立性が担保されることと、調査のプロセス自体が透明化されることです。
調査の「見せ方」にも企業の誠実さが表れる時代です。
まとめ
社内調査は、単なる聞き取りではありません。
調査そのものが、企業の信頼を可視化するツールです。
だからこそ、段取り、姿勢、記録のすべてに高い精度が求められます。
次章では、いよいよ制度面からのアプローチ、「就業規則の整備」について掘り下げていきます。
制度がなければ、正しい調査も対応も形骸化してしまいます。
仕組みの整備は、“再発防止”の要です。
第5章:ハラスメント対策は就業規則の整備から
ハラスメント対策は、現場対応だけでは限界があります。
根本的に「発生させない職場」をつくるためには、制度としての土台づくりが不可欠です。
その中心にあるのが、就業規則の整備です。
本章では、就業規則でハラスメントをどう扱うべきか、企業として押さえるべきポイントを明確に解説していきます。
特に、法的義務との関係を正しく理解し、実際に活用できる規定づくりを目指しましょう。
就業規則に明記すべきハラスメント禁止条項とは?
まず大前提として、2022年4月より中小企業も含めて**パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)**が義務化されました。
これにより、企業にはハラスメント防止のための措置義務が明確に課されています。
就業規則に明記すべき最低限の内容は以下の通りです。
-
職場におけるパワーハラスメント・セクシャルハラスメント・マタニティハラスメントの禁止
-
ハラスメントを行った場合の処分規定(懲戒の種類と基準)
-
相談・通報した労働者に対する不利益取り扱いの禁止
条文例としては、厚生労働省が公開している「モデル就業規則」が参考になります。
これは後ほどリンクとあわせて紹介します。

この条文、形式だけで終わってる会社が多すぎますね。運用されてなんぼです。
処分の具体的な内容を明示する必要性
曖昧な規定では、ハラスメントが起きた際に適切な対応が取れません。
懲戒処分を行うためには、事前に就業規則でその根拠を明示しておくことが絶対条件です。
たとえば、次のような文言が必要です。
「パワーハラスメント行為を行った場合は、事実関係に基づき、けん責・減給・出勤停止・降格・懲戒解雇などの処分を行う」
さらに重要なのは、「懲戒処分は段階的に行う」といった運用ルールを定めておくことです。
この運用がぶれると、「えこひいきだ」「基準が不明だ」と社内不信を招きます。
処分の一貫性・公平性が、組織全体の信頼につながります。
社内通報制度・相談窓口の設置義務(法令対応)
パワハラ防止法では、企業に対し以下の対応が義務化されています。
-
社内相談窓口の設置
-
相談窓口の周知(就業規則やイントラでの案内)
-
相談者・通報者の秘密保持と報復防止措置
相談窓口は、複数の選択肢を用意することが望ましいです。
たとえば、人事部・総務部・外部の第三者(社労士や弁護士)など。
社内の関係性に配慮し、どこに相談しても受け止められる体制を整えることが重要です。
また、「相談しただけで左遷された」「報復された」という二次被害があっては意味がありません。
通報者保護の条文を必ず規定に含めておく必要があります。
中小企業でも導入できるひな形と実装例
「うちは中小企業だから難しい」という声も聞きますが、それは誤解です。
厚生労働省や都道府県労働局は、中小企業向けに無料のテンプレートや導入支援を行っています。
たとえば、以下のような具体的な取り組みが可能です。
-
厚労省のモデル就業規則から必要部分を抜粋・カスタマイズ
-
就業規則とは別に『ハラスメント防止規程』を社内規定として設ける
-
小規模でも実現できる通報フローの作成(メール専用アドレス、匿名フォーム等)
これらを従業員にわかりやすく周知することが、制度として“生きる”ポイントです。

規定つくって満足しがちだけど、大事なのは“周知して使えるか”なんですよね。
厚労省モデル規定へのリンクと解説
厚生労働省は、就業規則やハラスメント対応規定について、非常に実務的なモデルを提供しています。
特に以下の資料は、実装の際に必ず参照すべき内容です。
このモデルでは、先述した禁止条項、相談体制、処分方針のすべてが網羅されており、自社用にカスタマイズして導入することが可能です。
制度設計は、社内文化を支える骨組みです。
それがあるからこそ、現場での判断もぶれず、社員の安心感にもつながります。
次章では、就業規則を運用する現場、「組織文化」や「教育体制」の構築方法について詳しく見ていきます。
制度と運用、両輪で回してこそ、ハラスメントの根本対策が実現します。
第6章:ハラスメントを生まない組織文化の作り方
ハラスメント対策を「事後対応」だけで終わらせていては、同じ問題が繰り返されます。
真に企業に求められているのは、「ハラスメントが起きにくい土壌」を育てることです。
つまり、組織文化のアップデートです。
本章では、制度ではなく“空気”に着目し、ハラスメントを未然に防ぐ企業文化のつくり方について具体的に解説します。
“見て見ぬふり”を生まない心理的安全性とは?
Google社の調査「プロジェクト・アリストテレス」でも明らかになったように、チームの生産性に最も影響するのは“心理的安全性”です。
心理的安全性とは、「この職場では安心して意見が言える」「ミスや弱音を言っても否定されない」という状態を指します。
これが欠如した職場では、仮にハラスメントが発生しても「誰も何も言わない」。
これが、最も恐ろしい“見て見ぬふりの温床”になります。
ではどうすれば、この空気を変えられるのか。
答えはシンプルです。
日常の会話、反応、姿勢を上司から変えること。
たとえば、部下の提案を即座に否定しない。
失敗したメンバーに「それでもチャレンジしたのはえらい」と声をかける。
その積み重ねが、「この職場は何を言っても大丈夫だ」という空気を育てます。

部下が萎縮してる職場って、数字にもちゃんと表れますよ。やばいです。
管理職への教育と評価制度の見直し
組織文化を支えるのは、やはり現場の管理職です。
その管理職がハラスメントの加害者になってしまう構造こそ、根本から変えていかなければなりません。
ここで重要なのは、「管理職に求める役割」を明確にすることです。
単に数字や成果だけで評価するのではなく、以下のような行動指標を評価項目に加えることが効果的です。
-
部下との1on1ミーティングの実施回数
-
フィードバックの質(他者評価含む)
-
チームメンバーの定着率や満足度
さらに、「マネジメント研修」だけで終わらせず、現場での言動を継続的にフィードバックする仕組みが必要です。
これは、企業文化に“当たり前”として根づかせるための重要な仕掛けです。
定期的な社内研修が果たす役割
ハラスメント研修は、「一度やったから大丈夫」ではなく、継続的に繰り返すことが意味を持ちます。
むしろ、一度の座学研修だけでは意味がないと言ってもいいでしょう。
効果的な研修には以下の要素が含まれます。
-
自社の事例に近いシナリオを使ったロールプレイング
-
経営層自らのメッセージ発信(形式ではなく本音を伝える)
-
相談窓口の再周知・制度説明もセットで実施
また、定期的なアンケートやハラスメントに関する社内意識調査を行うことで、“自分ごと”として捉える土台が育ちます。

研修って、やらされ感満載だと逆効果なんですよね。設計大事です。
企業文化と価値観のアップデート
ハラスメントを根絶するためには、企業の“価値観そのもの”を更新する必要があります。
たとえば、以下のような価値観を社内で共有・浸透させる取り組みが有効です。
-
「お互いを尊重することは成果より優先される」
-
「相談することは弱さではなく勇気」
-
「変化に対応できる柔軟さこそが組織の強さ」
これらは、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の再定義という形で取り組む企業も増えています。
そして何より、それを日常業務や人事制度にちゃんと落とし込むことが成功のカギです。
実例紹介:社員満足度が向上したB社の取組み
最後に紹介したいのは、ある製造業B社の事例です。
同社は数年前、管理職によるパワハラ問題で離職率が20%を超えていました。
そこで取り組んだのが、以下の3つです。
-
管理職の“育て直し”プログラム(半年間の面談+コーチング)
-
現場主導の価値観ワークショップ(月1回)
-
社員の声を可視化する社内アンケートの定期実施
この取組みにより、離職率は8%まで減少。社員満足度も大きく改善されました。
制度よりも「人」の行動と関係性が変わることで、職場の空気が根本から変わったのです。
まとめ
組織文化は、一朝一夕では変わりません。
しかし、継続的なメッセージと行動によって、確実に変えることは可能です。
次章では、組織内で対応しきれないケースに備え、外部機関との連携方法や相談窓口の活用法について解説します。
「頼れる先」があることも、企業の信頼を守る重要なポイントです。
第7章:困ったときに頼れる外部機関と相談窓口一覧
どんなに制度や体制を整えていても、社内だけでは対応が難しいケースは必ず発生します。
被害者が強く精神的にダメージを受けている場合や、加害者が役員・経営層である場合、あるいは社内調査の公平性が問われる場面などです。
そんなとき、企業が知っておくべきなのが「外部の力を借りる判断と方法」です。
この章では、企業が活用できる外部相談窓口と支援機関を、状況別に整理して紹介します。
労働局や都道府県労働相談センター
まず、公的な相談窓口として最も利用しやすいのが「総合労働相談コーナー(厚生労働省)」です。
各都道府県の労働局や労働基準監督署内に設置されており、企業・労働者を問わず無料で相談可能です。
主な特徴は以下の通りです。
-
パワハラ・セクハラ・マタハラなど労働問題全般に対応
-
匿名相談・電話相談も可能
-
必要に応じて「あっせん制度」(当事者間の調整)を紹介される場合もある
窓口一覧は厚生労働省公式サイトから確認できます。
▶ 厚労省 総合労働相談コーナー一覧

まずはここに相談、って選択肢を人事部が持っておくの、大事です。
弁護士/社労士への相談が有効なケース
問題が複雑化した場合や、処分・対応に法的な裏付けが必要な場合は、弁護士や社会保険労務士(社労士)への相談が有効です。
たとえば、以下のようなケースです。
-
加害者・被害者の主張が大きく食い違っており、訴訟リスクがある
-
懲戒処分の妥当性について法的な見解が必要
-
就業規則や制度の法令適合性に不安がある
社労士は主に労務管理と制度設計の専門家であり、就業規則の整備・労働局対応にも精通しています。
一方、弁護士は訴訟対応・損害賠償問題など法的判断が求められる場面での相談に適しています。
外部の法律家と連携しておくことで、自社だけでは抱えきれない問題への備えができます。
専門サービス:ホットライン・調査会社の活用
企業によっては、外部の第三者機関にホットラインを委託するという方法も効果的です。
特に、社内の力関係や人間関係で相談しにくい環境がある場合、外部相談窓口の存在が「声を上げやすい職場」づくりに貢献します。
よく使われる外部サービスは以下の通りです。
-
外部ホットライン(匿名通報サービス)
└ 社員は直接企業にではなく、第三者に相談できる -
外部調査会社の活用
└ 客観性と中立性を保った聞き取りや報告書を作成
大手企業では導入が進んでいますが、中小企業でもコストを抑えた形で導入可能なサービスもあります。
「大ごとになる前に、外部の目を入れる」ことは、組織を守る知恵です。
社内で対応しきれない時の判断基準
「どこまで自社でやって、どこから外部に任せるか」
この判断は非常に重要です。以下の基準を目安に検討してみてください。
-
当事者の一方が管理職・役員など社内で強い立場にある
-
被害者のメンタル不調が深刻化しており、継続的ケアが必要
-
社内調査に関して公平性や信頼性への疑念がある
-
一度対応を誤り、外部通報(労基署・SNS等)のリスクが高まっている
これらに該当する場合は、「自社だけで抱えない」ことがベストな選択になります。
むしろ、「社内で処理しようとして事態が悪化した」例は数多く存在します。

ギリギリまで社内で抱えた結果、爆発するケース……何度も見ました。
緊急時の対応フロー|即動くための準備を
最後に、緊急時に即行動できるフローをあらかじめ整備しておくことが重要です。
例えば、以下のようなチェックリストを事前に準備しておくと安心です。
ハラスメント緊急対応フロー(例)
-
被害者からの通報受付 → メモと記録の作成
-
初期ヒアリング(1営業日以内)
-
社内担当者で緊急性を判断
-
外部相談窓口・法律家に一次確認(必要時)
-
加害者・被害者の接触制限措置
-
事実調査の着手と証拠保全
-
弁護士・社労士と連携して処分・対応検討
-
相談者・関係者への報告と再発防止策の実行
このような流れをマニュアル化しておくことが、危機回避の要になります。
全社に周知されていれば、現場での判断ミスも減らせます。
まとめ
ハラスメント対応において、「自力でなんとかしよう」とする姿勢は立派ですが、時にリスクになります。
外部の専門家や制度を“使いこなす”ことも企業の力です。
次章では、本記事の総まとめとして、ここまでのポイントと筆者の現場経験からの所感をお伝えします。
“初動”が変われば、組織は必ず変わります。
第8章:まとめと感想|“初動”が組織の未来を決める
ここまで全7章にわたって、「ハラスメント上司」への初動対応について実務的に掘り下げてきました。
組織として求められるのは、単なる“対応”ではなく、“誠実な姿勢”と“制度の実効性”です。
その出発点が、まさに最初の5分の対応=初動です。
ハラスメントの芽を見逃さないために、人事・管理職、そして経営層に必要なのは、「知識」だけではありません。
判断力と覚悟です。
初動対応で押さえるべき5つのポイント
この連載を通して見えてきた、初動対応で最も重要な5つの要点を以下にまとめます。
-
まず「信じて、聞く」姿勢を持つこと
-
加害者・被害者の双方に冷静かつ中立に対応すること
-
調査は構造的・客観的に進めること(記録・証拠を重視)
-
就業規則や制度が整備され、運用されていること
-
社内で限界を感じたら、外部機関と連携する勇気を持つこと
これらが揃ってはじめて、社員は「この会社なら安心して働ける」と感じてくれます。

何より“安心できる場”が、いい仕事の土台になりますからね。
放置することのリスクは想像以上に深い
ハラスメントは、放置した途端に組織の根幹を揺るがす存在になります。
離職、モチベーションの低下、SNSでの内部告発、裁判、企業イメージの失墜──。
そして何より、「信頼」が一度壊れると、簡単には戻りません。
初動の対応が誠実だったか、真摯だったか。
それだけで、その後の社内の空気もまったく変わってくるのです。
企業が守るべきは、被害者だけではありません。
「誠実なプロセス」を通じて、関係者全員と、組織そのものを守る意識が求められます。
見ないふりを、やめる一歩を
「うちは大丈夫」「そんなにひどい人はいないから」
そう思っている間に、現場では誰かが静かに傷ついているかもしれません。
ハラスメントが見えにくいのは、“形式上”ではなく、“文化”や“空気”の中に潜んでいるからです。
だからこそ、誰かが最初の一歩を踏み出さなければ変わりません。
人事・経営層であるあなたがその役割を担うことに、大きな意味があります。

「気づいてるけどスルーしてる」って、いちばん怖い状況です。
筆者からの一言|現場で見たリアルな真実
私はこれまで、数十社のハラスメント案件に関わってきました。
共通して言えるのは、“まさか自社で起きるとは”という驚きと戸惑いが、どの企業にもあることです。
けれど、そこから真剣に取り組んだ企業は、必ず「組織として強くなった」と実感できるようになります。
「どんな会社でも、明日は当事者になるかもしれません。備えておきましょう。」
皆さんの職場で、安心して声があげられる空気が生まれることを、心から願っています。