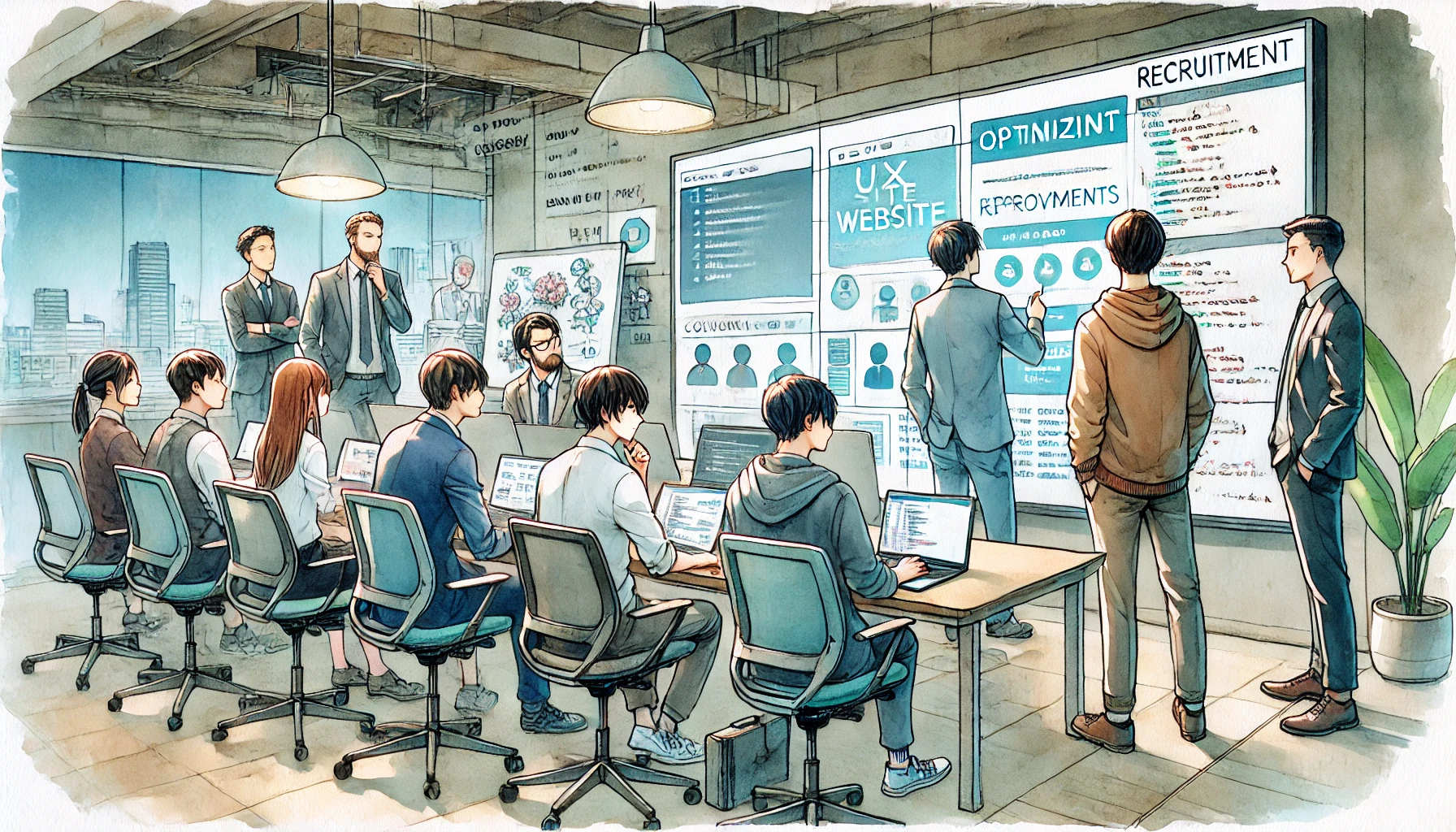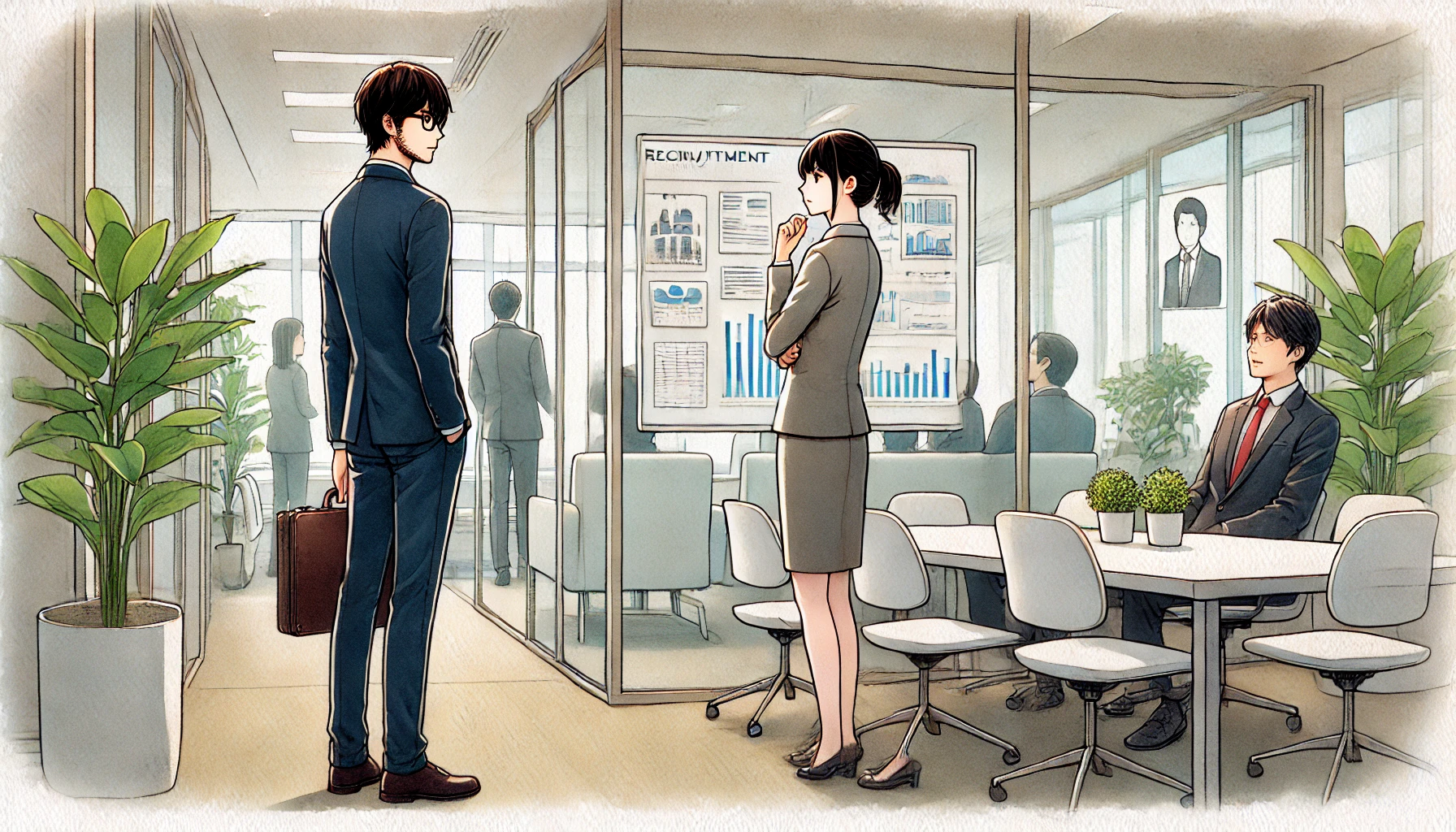正社員と業務委託の線引き、曖昧になっていませんか?
特にスタートアップや急成長企業では、雇用形態ごとの契約管理が後回しになりがち。
本記事では、正社員の雇用契約書で「外せない条文」と、業務委託と分けるべきポイントを実務目線で解説します。
【第1章】正社員と業務委託の法的な違いを押さえる
「契約書を交わせば安心」では済まない現実
企業の成長過程で避けて通れないのが「雇用形態の整理」です。
とくに、正社員(労働契約)と業務委託(委任契約・請負契約)の違いを曖昧なまま進めると、後々労働基準法違反や未払い残業代など、重大なリスクを招きかねません。
契約書のタイトルだけが「業務委託」になっていても、実態が労働者と見なされれば、企業は労働者保護の義務を負うことになります。
この章では、契約書の“肩書き”ではなく、中身と現場の実態が問われる法的構造について、基礎から整理していきます。
労働契約と業務委託契約の根本的な違いとは?
まず大前提として、労働契約は労働基準法に基づき、労働者の権利を保護する枠組みです。
正社員として雇用される場合は、企業が労働時間・業務内容・就業場所などを具体的に指示できる代わりに、最低賃金・残業手当・有給休暇などのルールが適用されます。
一方、業務委託契約(民法上の委任契約または請負契約)は、成果物や業務遂行を独立して担う個人や法人との契約です。
業務の手段や時間配分は原則、受託者の裁量に委ねられ、雇用関係ではないため、労働基準法の適用はありません。

「仕事のやり方を指示している時点で“委託”ではないこと、意外と見落とされがちです。」
「労働者性」は何で判断されるのか?
実務上の混乱の原因は、契約書が業務委託でも、実態が正社員と変わらない働き方をしているケースにあります。
この“労働者性”をどう判断するかについて、厚生労働省や裁判所では以下のような観点を重視しています。
-
指揮命令関係があるかどうか
-
業務時間・場所の拘束があるか
-
自社の業務組織に組み込まれているか
-
報酬が労務対価として支払われているか
これらを総合的に勘案し、実態が「労働契約に極めて近い」と判断されれば、契約書が“業務委託”であっても労働契約と認定される可能性があります。

「時間単位で指示し、勤怠も管理していた…って、もうアウトですからね。」
裁判・行政指導で争点になるポイント
ここで注意したいのが、実態を軽視した契約運用が“偽装請負”とされるリスクです。
たとえば、業務委託契約で人材を受け入れていた企業が、次のようなことでトラブルに発展しています。
-
勤怠管理をしていた(=時間拘束)
-
作業指示や評価をしていた(=指揮命令)
-
勤務場所を指定していた(=業務従属性)
このようなケースでは、契約違反だけでなく未払い残業代や労災適用の責任を問われる可能性があり、経営リスクとしては極めて重大です。
また、労働基準監督署や裁判所では、契約書の記載よりも「実態主義」が採られるため、
「契約書を交わしていたから安心」ではなく、現場レベルでの働き方の実情が審査対象になります。
まとめ|実態と契約書の“ズレ”が最大のリスク
本章では、「正社員(労働契約)」と「業務委託契約」の法的な違いを明確に整理しました。
企業として重要なのは、契約書と実態の整合性を保つことです。
雇用契約書を作る前に、まずはその人材が“誰の指示で、どこで、どんな風に働くのか”を確認しましょう。
契約の形を整えるだけでなく、現場とのギャップを埋める設計力が問われる時代です。
次章では、「雇用契約書と業務委託契約書の構成の違い」について詳しく掘り下げます。
【第2章】雇用契約書と業務委託契約書の基本構成比較
「契約書がある」だけでは不十分な時代へ
契約書に署名捺印がある。
それだけで安心してしまっていないでしょうか。
実は、正社員の雇用契約書と業務委託契約書では、そもそもの設計思想がまったく異なります。
法的な義務、記載項目、リスクの所在が違う以上、共通のフォーマットで済ませることはできません。
この章では、両者の基本構成と記載ポイントを並べて比較し、実務で見落としやすい論点まで掘り下げていきます。
雇用契約書:労基法で明確に定められた記載項目
まず、正社員との雇用契約書には「絶対に記載すべき項目」があります。
これは、労働基準法第15条および施行規則第5条で明示されている内容で、労働条件通知書の内容とも重複します。
最低限、以下の事項は明記する必要があります。
-
契約期間(期間の定めの有無)
-
就業場所・従事する業務の内容
-
始業・終業時刻、休憩、休日、休暇
-
賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払時期
-
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これに加え、就業規則に準じた整合性のある記載が求められます。
とくに、固定残業代制度や裁量労働制を導入している企業は、適正な明記を怠ると違法扱いになることもあります。

「“ひな形で済ませてる”では、リスクに気づけない時代です。」
業務委託契約書:成果物と責任範囲を明確に
一方で、業務委託契約書においては、成果物の定義や報酬との関連性を明文化することが中心になります。
記載のポイントは以下の通りです。
-
業務の範囲・内容(曖昧にしない)
-
成果物の仕様・納品形式・納期
-
報酬額・支払条件(中間払い・検収条件など)
-
秘密保持義務・個人情報管理
-
損害賠償・契約解除条件(瑕疵担保責任など)
ここでは“仕事をどう遂行するか”ではなく、“何を納品するか”が焦点です。
業務の指示・進行管理まで委託元が行うと、「偽装請負」と指摘される可能性があります。

「“人を頼む”のか、“仕事を頼む”のか、そこが最初の分かれ道ですね。」
共通して記載すべき重要条項もある
雇用契約書・業務委託契約書の違いは大きいものの、両者に共通して明記しておくべき重要項目も存在します。
それが、以下のような内容です。
-
副業可否・競業避止義務(特に兼業が一般化している昨今)
-
秘密保持契約(NDA)(業務の性質問わず重要)
-
成果物の著作権の帰属先(特にデザインやシステム開発等)
-
SNS・情報発信に関する規定(企業イメージ保護の観点)
これらは「法定義務ではないが、紛争の芽を摘むために不可欠な項目」です。
特に副業やテレワークが浸透する中で、情報の管理・範囲の明示は企業防衛としての契約書の役割を高めています。
雛形活用の落とし穴に注意を
インターネット上には、雇用契約書・業務委託契約書のテンプレートが数多く出回っています。
しかし、法的整合性・自社の業務内容・既存の就業規則との連携を考慮しなければ、
せっかく整備した書面が逆にリスクの火種になることもあります。
「無料テンプレを参考にして、自社にカスタマイズする」
この姿勢が、リスクを防ぎつつ実務に即した契約書を作る第一歩です。
第3章では、「“これだけは押さえるべき”雇用契約書の記載項目10選」と題して、
実務で特に重要な項目とその記載例を具体的にご紹介していきます。
【第3章】「うちは業務委託です」で済まないリスクとは?
書面よりも「実態」が見られる時代
「この人は業務委託だから、労働法は関係ない」。
そう思っている経営者や担当者は、意外と少なくありません。
しかし、労働基準監督署や裁判所が見るのは、“契約書の書き方”ではなく“働き方の実態”です。
形式的には業務委託でも、実質的に雇用関係にあれば、偽装請負と判断される可能性が高くなります。
偽装請負とは何か?違法とされる構造
偽装請負とは、実態が労働者であるにもかかわらず、業務委託として契約し、労働法の保護を回避している状態を指します。
たとえば、以下のような働き方は、偽装請負の疑いが強くなります。
-
発注元企業の社員から業務の指示・命令を受けている
-
勤務場所・勤務時間が固定され、出退勤管理もされている
-
使用するPCや備品、メールアドレスが会社支給
-
報酬が固定給で、納品物にかかわらず支払われている
このような場合、委託契約という名目ではあっても、実態としては“雇用”と見なされるリスクが非常に高くなります。

「“業務委託”って言えばセーフ、じゃ通らない時代です。」
偽装請負が招く企業側のリスクとは?
「バレなければいい」は、もはや通用しません。
実際に指摘されると、企業側には以下のようなリスクが降りかかります。
(1)行政指導・是正勧告
労働基準監督署からの指摘で、「雇用関係にある」と判断されれば、
未払いの残業代や社会保険料をさかのぼって請求されることがあります。
過去2年間の未払い残業代が対象になるケースが一般的です。
(2)労災トラブル
業務中のケガ・事故が起きた際、「業務委託だから労災は適用外」としても、
実態が雇用であれば労災認定される可能性があります。
逆に、労災申請されなかった場合、損害賠償請求につながることも。
(3)社会的信用の低下
公的機関との取引や上場審査において、「労務管理の不備」と判断されると、
企業としての信用・ブランドに重大なダメージを与えることになります。

「下請法・労基法の両方に引っかかると、事後対応が地獄です。」
契約書を曖昧にしていた企業のケース紹介
あるスタートアップ企業では、デザイナーやエンジニアを「業務委託」として雇い入れていました。
しかし、プロジェクトの進行管理、出社義務、業務時間の指定、すべてを自社でコントロール。
結果的に、1名から未払い残業代請求が起こり、
その後他の委託メンバーも追随し、総額300万円超の支払い命令が下ったという実例があります。
この企業は、契約書をテンプレで済ませていたうえに、
就業実態を記録していなかったことで、主張の裏付けが取れず全面敗訴となりました。
リスク管理において最も重要なのは「線引き」
雇用か業務委託か。
この線引きは契約書だけでは済まず、実務の運用とセットで考える必要があります。
中途半端な委託契約は、かえって雇用以上にリスクを抱えることになります。
契約前の設計段階で、法的な助言を得ることが、最終的にはコスト削減にもつながります。
第4章では「雇用契約書に絶対必要な10の項目と注意点」として、
雇用契約書作成の実務ポイントを具体例つきで解説していきます。
契約実務に携わる方は、ぜひ続けてチェックしてみてください。
【第4章】契約書テンプレートを活用する際の注意点
「テンプレだけで済ます」は危険信号
「とりあえずネットの雛形を使えばいい」
――そんな声を、現場ではよく耳にします。
確かに雇用契約書のテンプレートは、厚生労働省や社労士事務所のサイトなどで無料配布されており、
初めて契約書を作る企業にとっては、非常に便利なスタート地点になります。
しかし、そのままコピー&ペーストで済ませてしまうと、法務・労務トラブルの温床になりかねません。

「テンプレは“参考”にはなるが、答えではないんですよね。」
厚労省モデルの強みと限界
厚生労働省が公表している「モデル雇用契約書」は、労働基準法第15条に基づく法定記載事項(労働条件通知)をすべて網羅しています。
内容はシンプルで実用的ですが、以下の点に注意が必要です。
-
実務上よく出る副業やテレワーク、SNS利用の規定は含まれていない
-
法的には問題なくとも、企業独自の運用に合わない場合がある
つまり、モデルは最低限を押さえた“骨格”にすぎず、
実際の運用に耐える内容に仕上げるには、追加修正が必須というわけです。
契約形態ごとにテンプレを分けるべき理由
特に注意すべきは、正社員用と業務委託用で契約書テンプレートを分けることです。
両者は法的根拠が異なるため、項目の構成もまったく別物になります。
| 項目 | 雇用契約書(労基法) | 業務委託契約書(民法) |
|---|---|---|
| 労働時間 | 記載必須(始業・終業・休憩など) | 原則自由(納期・成果物で管理) |
| 報酬の支払い | 賃金として明記、月給制など | 請負・委任の報酬として記載 |
| 社会保険の扱い | 加入が法定義務(一定条件下) | 原則として対象外(自己責任) |
| 指揮命令系統 | 使用者の指揮命令下で就労 | 基本的には独立して業務遂行 |
このように、同じ“働いてもらう”関係でも、法的視点ではまったく異なるアプローチが必要になるのです。

「“とりあえず同じ書式で…”は一番危ないパターンですね。」
実務に即した追加条項:ここを押さえよう
近年、以下のようなテーマを巡って企業と社員がトラブルになるケースが急増しています。
テンプレートに追加しておくべき“現代型条項”を整理しておきましょう。
1. 副業・兼業に関する取り決め
-
許可制か自由か、条件付きで認めるか
-
勤務外時間の就労であっても、競業避止の範囲を明記
2. テレワーク時の勤務ルール
-
勤怠管理方法(PCログ・チャット記録など)
-
情報漏えい対策(自宅Wi-Fi使用時のセキュリティ)
3. SNS利用と会社情報の取り扱い
-
会社名や顧客情報の発信制限
-
ネット上での誹謗中傷の禁止と罰則
4. 秘密保持・知的財産権の明文化
-
業務上知り得た情報の第三者提供禁止
-
成果物(資料・プログラム等)の著作権の帰属先指定
これらは、法定義務ではありませんが、後々のトラブル予防には欠かせない要素です。
テンプレは「たたき台」レベルと認識すべき
契約書テンプレートは、白紙から作る負担を大きく減らしてくれます。
しかし、実際に運用するなら、自社の制度・文化・職種ごとに調整が不可欠です。
特にスタートアップ企業では、急成長フェーズで人の流動が多いため、
「とりあえず雇った」の先で火種を抱えやすい傾向にあります。
テンプレをそのまま渡すのではなく、
“今の働き方に合っているか?”という視点で1項目ずつチェックするクセを持ちましょう。
次の第5章では「契約書と就業規則の関係性とすり合わせポイント」に踏み込み、
“バラバラになりがちな制度”をどう一体化するか?を解説していきます。
契約書作成の整合性に悩む方、必見の内容です。
【第5章】就業規則との整合性を取る方法
「契約書と就業規則の優先順位」を整理する
雇用契約書を作るとき、意外と見落とされがちなのが「就業規則との整合性」です。
そもそも、契約書と就業規則が矛盾していた場合、どちらが優先されるのか。この疑問は、実務でもよく相談を受けます。
労働契約法第7条では、こう定められています。
「就業規則が労働者にとって不利益でない限り、労働契約の内容とする」
つまり、基本は雇用契約書が優先されますが、就業規則の方が有利な場合はそちらが適用されるというのが原則です。
たとえば、雇用契約書に「通勤手当は月1万円まで」とあり、就業規則では「実費支給(上限なし)」と書かれていた場合、後者のルールが優先される可能性があります。

「就業規則が“上書き”になるケースもあるのが落とし穴です。」
業務委託に就業規則を適用してはいけない?
これは、特にスタートアップや小規模企業で混乱しやすいポイントです。
業務委託(=民法上の請負契約・委任契約)の相手に、就業規則を「適用」することはできません。
なぜなら、就業規則は労働基準法に基づく「労働者」のための社内ルールだからです。
にもかかわらず、業務委託契約書に“始業・終業時刻”“服装の指定”“遅刻・早退の報告義務”などを記載し、
さらに「就業規則に従うこと」とまで書いてしまうと、実質的に労働契約とみなされてしまうリスクがあります。
この状態、法的には「偽装請負」と認定されるおそれがあり、
社会保険未加入や残業代未払いといった重大トラブルにつながることもあります。

「外部のプロ=自由契約の原則を忘れちゃいけません。」
クラウド人事労務ツールで整合性管理を効率化
整合性を手作業でチェックするのは、時間も手間もかかります。
そこで近年、活用が進んでいるのがクラウド型の人事労務管理ツールです。
たとえば「SmartHR」や「jinjer労務」などのサービスでは、以下のような機能が標準装備されています。
-
契約書と就業規則のバージョン管理
-
各種ひな形のカスタマイズと従業員ごとの配信
-
電子署名と法令改正対応の通知機能
-
労基署提出フォーマットへの変換支援
これにより、「最新版に更新したと思っていたら、配布文書は旧版だった」といったケアレスミスを防げます。
また、社内の規程やルールを一元管理できることで、人事担当者の属人化リスクも大幅に低減します。
整合性を担保するためのチェックリスト
最後に、実務で役立つ「整合性確認のチェックリスト」を紹介します。
雇用契約書を見直すときは、以下の項目を比較・すり合わせておくと安心です。
| 確認項目 | 契約書と就業規則で差異が出やすい点 |
|---|---|
| 労働時間 | 休憩・残業・フレックスタイムの有無 |
| 賃金 | 基本給・手当の定義、支払日 |
| 休暇 | 有給の取り方、計画付与、特別休暇制度 |
| 解雇・退職 | 手続きの流れ、自己都合・会社都合の定義 |
| 懲戒処分 | 注意・減給・解雇までのステップ |
まとめ
雇用契約書を整えることは、就業規則との“すり合わせ”とセットで考えるべきです。
整合性がとれていないと、いざというときに「どっちが正しいのか」が不明確になり、法的リスクが高まります。
特に複数の契約形態(正社員・業務委託・パートタイムなど)を採用している企業では、
それぞれに対応した規程設計と管理が求められます。
次章では、制度設計のプロとどう連携すればよいか?
「社労士・人事コンサルの活用法」に焦点を当てて解説していきます。
【第6章】社労士・弁護士に頼むなら?外部連携の活かし方
社労士と弁護士、どう違う?
雇用契約書を整備する際、「どこまで社内でやって、どこから外部に任せるか」は悩ましいところです。
特に中小企業やスタートアップでは、法務担当者がいないケースも多く、“契約書の正しさ”を誰が保証するかが課題になります。
まずは、社労士と弁護士の役割の違いを理解しておきましょう。
| 専門家 | 主な業務領域 | 特徴 |
|---|---|---|
| 社会保険労務士(社労士) | 雇用契約書の整備、労働基準法対応、就業規則の作成・改定 | 人事労務分野に精通。厚労省モデルをベースにしたアドバイスが得意 |
| 弁護士 | 契約書の法的リスクチェック、労働紛争対応、損害賠償請求など | 労務トラブルが発生した場合や、高度な条項(例:競業避止)の設計に強み |
契約書の整備段階では社労士が適任ですが、トラブルの予防や交渉力強化を見据えるなら弁護士の併用も有効です。

「小規模な企業ほど、“相談相手の選び方”で差が出ます。」
テンプレート+レビューだけでも大きな差に
「すべて外注は予算的に厳しい」
そんな声もよく聞きますが、“ひな形+スポットレビュー”だけでもリスクは大きく下がります。
たとえば、以下のような流れで連携するのがおすすめです。
-
厚労省や社労士団体のテンプレートをもとに、自社用の案を作成
-
弁護士や社労士にレビューを依頼(メール・Zoomで完結する場合も多い)
-
修正点と解説を受け、最終版として社内共有・配布
この方法であれば、10万円以内で十分な精度の契約書が整えられることも多く、費用対効果は高いと言えます。

「自力でゼロから作るより、“一度プロの目を通す”が安心です。」
相談時に準備すべき社内情報はこれだ
専門家に相談する際、「何から話せばいいのか分からない」というケースもあります。
以下のような社内情報を整理しておくと、話が早く、的確なアドバイスが得られます。
-
就業規則(最新版)
-
現在使用している雇用契約書のひな形(または白紙)
-
業務委託契約書(もしあれば)
-
採用予定の職種・働き方(リモート/フレックスなど)
-
副業やテレワークに関する社内ルールの有無
-
評価・報酬制度の概要(例:成果給、固定残業代)
このような情報があれば、単なるテンプレ提供ではなく、自社に合った“実践的な修正提案”が受けられるのです。
顧問契約?スポット相談?どう使い分ける?
最後に、社労士や弁護士との連携形態について補足します。
| 契約形態 | 向いている企業 | 特徴 |
|---|---|---|
| 顧問契約(月額) | 継続的に雇用関連の相談が発生する中規模以上の企業 | 定額で気軽に相談できる。制度設計や労基署対応も一任可能 |
| スポット相談(単発) | 契約書だけを整備したい小規模企業やスタートアップ | 必要なときだけ依頼できる。費用を抑えやすい |
近年では、「チャット型顧問」「クラウド契約書レビュー」など、ITと連動した柔軟なサービスも増えています。
企業の成長フェーズに応じて、「固定費より成果報酬型」など、賢く選びたいところです。
次章では、契約書の曖昧さが生んだリアルトラブルを紹介しつつ、実例で学びながら紹介していきます。
【第7章】実例で学ぶ!契約書の曖昧さが生んだリアルトラブル
契約書は「形式さえ整っていれば問題なし」と思っていませんか?
実際には、“中身の曖昧さ”や“運用とのズレ”が、重大なリスクを引き起こす原因になります。
この章では、実際に起きたトラブル事例から、なぜ契約書の整備が重要なのかをひもといていきます。
【事例1】スタートアップが誤って「業務委託契約」にした結果…
ある設立2年目のIT系スタートアップでは、初期メンバーとの関係を「業務委託契約」でスタート。
代表は「自由な働き方を尊重したい」と話していましたが、トラブルは半年後に発生しました。
勤怠管理をSlackで行い、タスク管理はNotion。
しかも「出勤時間」「業務開始前の報告」まで求めていたため、業務の実態が“雇用”に限りなく近かったのです。
結果として契約終了後、元委託者から未払い残業代の請求。
労基署との調整を余儀なくされ、バックペイ(遡り支払い)と和解金を合計で数百万円支払うことに。

「“雇用っぽい業務委託”が、いちばんリスク高いです。」
【事例2】「業務委託なのに勤怠管理」→労働者性認定の落とし穴
もう一つの例は、広告制作会社B社。
外部のデザイナーと“業務委託契約”を交わしていたにもかかわらず、社内の勤怠システムへの打刻を義務づけていました。
また、定例ミーティングは週3回必須。
作業時間も「10時〜19時」を基本とし、自由裁量の範囲は極めて限定的。
これが労働者性を認定される要因となり、委託ではなく“雇用”として判断された結果、労災保険や社会保険の未加入問題が浮上。
このケースでは、会社が過去2年分の保険料を負担することになり、大きな痛手となりました。

「勤怠管理してる時点で、“委託じゃない”と見なされるんですよね。」
【事例3】曖昧な契約がもとで訴訟→最終的に和解金を支払うことに
最後は、ある中堅製造業C社のケース。
従業員との雇用契約書が不完全で、「雇用期間」「就業場所」「副業制限」「成果物の帰属」などが全て口約束。
ところが退職後、元従業員が副業先にてC社と同様の技術を使い、営業活動を開始。
C社は「秘密保持違反」「競業避止違反」として訴訟を起こしたものの、契約書に具体的な記載がなかったため、裁判所ではほぼ認められず。
最終的には、和解金100万円を支払って終結しました。
このケースで問題となったのは、「期待していたこと」が契約書に書かれていなかったこと。
“口頭の取り決め”では法的拘束力が極めて弱いのです。
トラブルの共通点は「ズレ」
これらの事例に共通しているのは、以下の3点です。
-
契約の形式と業務実態の不一致
-
曖昧な条文や不備のあるテンプレートの流用
-
トラブル発生後に初めて“契約書を見直す”という遅さ
法的リスクとは、起きてからではなく、起きる前に潰しておくもの。
契約書の不備は、企業の信用や資金繰りにまで影響します。
次章では、この一連の内容を振り返りながら、「今できる対策」をお届けします。
【第8章】まとめと感想|雇用契約書は“守る”ための設計図
雇用契約書や業務委託契約書は、ただの「紙の書類」ではありません。
それは、会社と従業員・委託者の関係を正しく設計し、トラブルから会社を守るための“最前線の盾”です。
この最終章では、これまでの内容を振り返りながら、実務に活かすポイントを整理します。
各章のポイントを一気におさらい
-
第1章:法的な区分の理解が出発点
雇用契約(労働基準法)と業務委託契約(民法)は法的根拠が異なる。
「労働者性」を誤って判断すると、偽装請負などの重大リスクに。 -
第2章:契約書の構成は目的が違う
雇用契約書には法定記載項目(労基法第15条)が必須。
業務委託契約では「業務内容・成果物・対価」が中核。 -
第3章:実態が“雇用”なら契約は無効になる
いくら「委託契約書」と書いていても、内容次第では雇用と認定される。
実務の運用と契約内容を常に一致させる必要がある。 -
第4章:テンプレートは“万能”ではない
厚労省のモデルや社労士監修のひな型は便利。
しかし、企業の実態に合ったカスタマイズが不可欠。 -
第5章:就業規則との整合性が必須
労働契約と就業規則の優先順位や適用範囲を明確に。
委託者に規則を無理に適用するのは逆効果。 -
第6章:外部専門家との連携で精度UP
社労士・弁護士のレビューだけでも、契約リスクは大きく軽減される。
「テンプレをもとにプロに見てもらう」が王道。 -
第7章:曖昧な契約が生んだリアルトラブル
委託なのに勤怠管理/口約束に頼った契約——実例から学ぶべき点は多い。
今すぐできる3つのアクション
-
契約書の雛形を再確認する
厚労省や社労士会の最新フォーマットを見直し、自社のものと照合してください。 -
業務委託の“実態”を見直す
委託者との働き方が、実は雇用に近くなっていないか?
勤怠管理や指揮命令の有無をチェックしましょう。 -
専門家に「初回レビュー」だけでも相談する
社労士・弁護士に1時間だけでも契約書をチェックしてもらう価値は十分にあります。
無料相談を活用するのも手です。
最後に:契約書は“攻め”ではなく“守り”の最前線
多くの経営者は、攻めの事業戦略に意識を向けがちです。
しかし、契約書は攻めではなく「守り」。
そして、“守りの甘さ”が攻めの足を引っ張ることもあるのです。
特に正社員・業務委託の契約区分は、法律や判例のアップデートも多く、一度整備して終わりではないというのが実情です。
だからこそ、定期的な見直しと、専門家との連携が大切になります。
「守りを固めることが、攻めの自由度を高める」
これが、契約書における最大の教訓です。
次のステップは、皆さんの会社の契約書を1ページ開くことから始まります。