従業員の価値観が多様化した令和の時代。
画一的な福利厚生では物足りない、という声も増えています。
企業はどう応えるべきか?
本記事では、実際に導入されて話題になった面白い制度を中心に紹介し、導入プロセスや人事施策との相性についても解説します。
【第1章】面白い福利厚生とは?その定義と役割
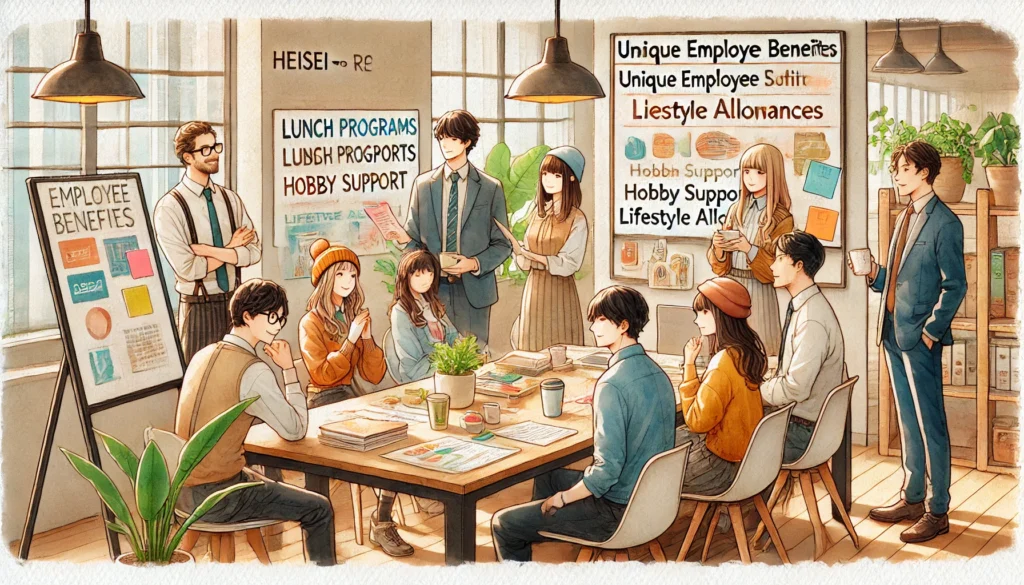
「面白さ」が福利厚生に求められる背景
今、福利厚生に求められるのは「安心」だけではありません。
従来型の住宅手当や通勤補助に加え、社員の“気持ちを動かす”ユニークな制度、つまり「面白さ」が重視され始めています。
背景には、働き方や価値観の変化があります。
たとえば、Z世代やミレニアル世代は、給与や安定性以上に“企業文化”や“働く楽しさ”を重視しています。
その企業で働くことが楽しいか、自分らしくいられるか。
そんな問いに応えるのが、ユニークな福利厚生です。

制度に「感情価値」を持たせることが問われる時代ですね。
制度を通して「会社が社員をどう見ているか」が伝わります。
結果として、制度は単なる手段ではなく、企業のスタンスそのものを映す鏡になります。
企業にとっての“ユニーク制度”の意味
「面白い福利厚生」と聞くと、一見“遊び”や“余裕”の象徴に思われがちです。
ですが、本質は違います。
ユニークな制度とは、企業が社員に「あなたの価値観を理解していますよ」と示すメッセージであり、エンゲージメントの起点でもあります。
たとえば「推し活休暇」や「副業サポート制度」は、社員のプライベートやライフスタイルを尊重する文化の現れです。
導入には明確な目的と設計思想が必要で、決して気まぐれで作られるものではありません。

制度の“面白さ”は、設計者の“本気”が見えた瞬間に伝わります。
社員の心を動かすのは、制度そのものより“その背景”です。
働く人の価値観が変わった今、なぜ必要なのか
経済的安定より、自己実現。
出世より、自由な働き方。
昭和・平成の“当たり前”が、もはや全員には当てはまりません。
たとえば、ある若手社員は「給与よりも、推しのライブに行く時間が大事」と話します。
別の社員は「月曜の午前は集中できないから“ゆる出勤制度”がありがたい」と。
企業がこの価値観に応えなければ、優秀な人材ほど静かに離れていきます。
ユニークな福利厚生は、そんな“人の心をつなぐ”ための現代的なインフラです。
実際、GoogleやGMO、サイバーエージェントなどは、独自制度によって人材の獲得・定着で先行しています。
採用競争が激化する今、「制度そのものが採用ツール」になっているのです。
企業ブランディングと制度の結びつき
福利厚生は、社内だけの話ではありません。
求人広告、企業サイト、SNS、メディア掲載など、外部への“魅力発信装置”としても力を発揮します。
たとえば「100円ランチ制度」や「子連れ出勤OK制度」は、企業の“人への投資姿勢”を如実に表します。
こうした制度は、求人で目にした求職者に「この会社、他と違うな」と思わせる強いインパクトになります。
また、社内文化を表すシンボルにもなります。
制度がきっかけで「うちの会社、いいよね」と社員同士が語るようになると、ブランディングは社外以上に“社内”に根付いていきます。
制度は制度で終わらせず、「文化」へと昇華させること。
それが本当に“機能する”福利厚生のあり方です。
【第2章】導入事例に学ぶ!注目の面白い福利厚生10選

食事・休憩支援系|満足度もコスパも抜群
1. 100円ランチ制度(株式会社アプティ)
社員食堂のランチが“1食100円”で食べられる制度です。
食事補助によって社員の健康と満足度を同時にケアできる上、ランチを通じた社内コミュニケーションの場としても機能しています。
「食」による福利厚生は最も導入しやすく、効果も高いカテゴリーです。
2. ドリンクバー・お菓子食べ放題(GMOインターネット)
24時間365日利用できる社員カフェ「GMO Yours」では、ドリンク・軽食がすべて無料。
業務の合間にリフレッシュできる空間があり、創造力とチームのつながりを自然と育てます。

「リフレッシュの質」はパフォーマンスを左右しますね。
3. パワーナップ制度(パナソニック、サイボウズなど)
午後の眠気対策として注目される「仮眠制度」。
就業時間中に15〜20分の仮眠を推奨する企業が増え、集中力回復や生産性向上に効果があるとされています。
趣味・娯楽系|社員の“推し活”を応援
4. 推し活休暇(サイボウズ)
「推しのライブに行きたい」という理由で有給が取得できる制度。
趣味に理解のある企業文化は、若手社員の共感を呼び、定着率にも貢献します。
5. ゲーム部支援制度(株式会社グッドパッチ)
ゲームを愛する社員たちのコミュニティ活動を会社が支援。
部活動に補助金を出すことで、部門を超えたつながりや発想の転換を生み出しています。

“遊び心”がある会社は、なぜか強い。ほんとに感じます。
家族・ライフスタイル支援系|社員の人生に寄り添う
6. 子連れ出勤制度(サイボウズ)
保育園に預けられない日でも、安心して出社できる仕組み。
オフィスに子ども用スペースが設けられ、子育てと仕事の両立を応援しています。
7. 恋愛応援手当(カヤック)
なんと「恋人ができたら手当を支給」する制度。
個人の幸福を会社が本気で応援する姿勢は、話題性もあり、企業イメージ向上にも貢献します。
8. 同性パートナーにも配偶者手当支給(DeNA)
多様な価値観を受け入れる姿勢を制度として明文化し、ダイバーシティ&インクルージョンの実践例として高評価を得ています。
離職防止につながった成功企業の実例
9. 温泉付き保養所制度(星野リゾート)
社員が無料または低価格で利用できる温泉施設を整備。
心身のリフレッシュと家族サービスを両立できるとして、満足度が高く、離職防止にもつながっています。
10. 入社記念日休暇制度(freee株式会社)
毎年「入社記念日」は特別休暇として扱われる制度。
“あなたがこの会社を選んでくれた日”を大切にする文化が根付き、社員のロイヤルティ向上につながっています。
まとめ|“面白さ”は戦略的にデザインできる
面白い福利厚生とは、単なる“ウケ狙い”ではありません。
社員の生活・価値観・人生に寄り添い、「この会社で働く理由」を作る制度です。
成功企業の共通点は、「社員視点」で制度を考え、「実際に機能させている」こと。
次章では、そうした制度を“どう選ぶか・どう設計するか”を掘り下げていきます。
【第3章】制度づくりの前に|企画段階で押さえる3つの視点
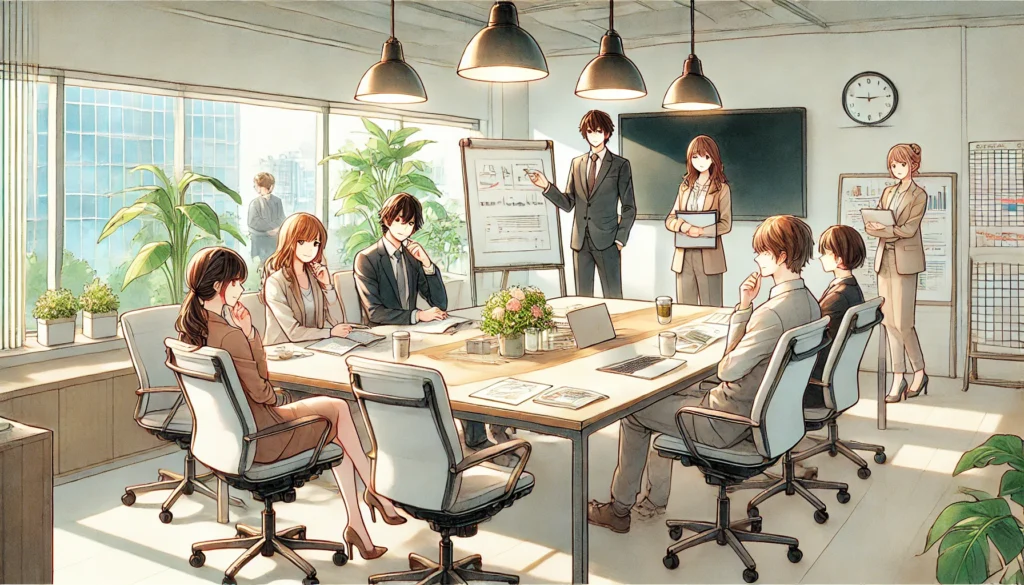
ユニークな福利厚生を作るとき、いきなり制度を考えるのは危険です。
最初にやるべきは、「社員に本当に求められているか」「会社にとって意味があるか」「ちゃんと続けられるか」。
この3つの視点が揃って初めて、“機能する面白さ”が生まれます。
1. 社員ニーズを知る|アンケートと面談は必須
「社員が喜びそうだから」
「若い人が好きそうだから」
そうした“思い込み”で制度を作ってしまうと、空振りになるリスクが高まります。
おすすめは、匿名アンケート+少人数ヒアリングの組み合わせ。
アンケートでは全体傾向を掴み、面談では具体的な声や感情を拾います。
質問の工夫も重要で、「ほしい福利厚生」よりも「最近嬉しかった職場のこと」など、体験ベースの質問が本音を引き出しやすいです。

うちのクライアントでも、ヒアリングから“全然違う施策”が出てきたことがあります。
2. 自社文化や事業との整合性を考える
「面白い制度を作りたい!」という熱意は素晴らしいですが、会社の“らしさ”とズレると、現場に受け入れられません。
たとえば、年齢層が高めで落ち着いた雰囲気の製造業で、「ゲーム大会」や「推し活支援」だけを先行導入すると、「ノリが合わない」と戸惑いの声が出るかもしれません。
逆に、柔軟な雰囲気のITベンチャーなら、「硬すぎる福利厚生」は浸透しにくい傾向もあります。
制度は、「自社のDNA」に馴染むように設計することが鍵です。
会社のビジョンや事業戦略とリンクした制度設計が、導入後の定着力を左右します。
3. 費用対効果と実現可能性を見極める
「福利厚生に予算が割けない」という声もよく聞きます。
ですが、大切なのは“予算の多さ”より“見せ方と設計”です。
たとえば、既存の制度を少しアレンジして「名前を変える」だけでも印象はガラリと変わります。
「誕生日休暇」よりも「あなたを祝いたい日休暇」の方が、感情に響くのです。
また、少額で導入できる制度(100円ランチ補助・ありがとうカード制度など)でも、設計次第で従業員満足度は大きく変わります。
小さく始めて、効果検証して広げていくのが、長続きする福利厚生の鉄則です。
【エピソード】“面白さ重視”で空回りした失敗例
あるIT企業では、「面白くしよう!」と社員のリクエストを募り、「筋トレ応援手当」や「変顔選手権休暇」などを導入しました。
最初はSNSで話題になり注目されましたが、社内では「ノリについていけない…」「制度が内輪向けすぎる」と距離を置く人も。
結果的に、制度の一部は自然消滅。
「楽しいけど、仕事に直結していない」「評価や制度とどうつながるのか不明確」などの声が多く、制度設計と現場の文化が噛み合っていなかったのです。

“面白さ”は、地に足ついた戦略に落とし込まないと空回りしますね。
まとめ|制度は「企画」が9割
面白い制度を作るには、最初の段階で「ニーズ・文化・コスト」の3点をしっかり設計することが不可欠です。
目立つ制度よりも、“機能する制度”を目指す。
それが、社員の心に残る福利厚生をつくる第一歩です。
次章では、実際の設計・運用フェーズに進み、制度を「仕組み」として回していく方法を紹介していきます。
【第4章】面白い制度を「制度」として定着させる方法
面白い福利厚生は、作っただけでは終わりません。
制度として“定着”してこそ、効果を発揮します。
この章では、制度を実際に活用される仕組みにするための具体的な方法をご紹介します。
キーワードは「目的」「見せ方」「運用」「伴走」です。
制度設計のフレーム|“目的なき面白さ”は形骸化する
制度づくりは、「ネタ」ではなく「経営施策」です。
だからこそ、以下の3つの柱を明確に設計する必要があります。
-
目的(なぜやるのか)
例:従業員の心理的安全性向上、離職防止、部門間交流促進など -
運用ルール(どう使うか)
対象者・申請方法・頻度・予算など、利用のルールを明文化します。 -
評価(効果をどう見るか)
定量(利用率・満足度アンケート)と定性(感想・社内声)で測定し、改善に活かす視点を組み込みます。
この3点を押さえて初めて、「制度」として扱われるようになります。

面白くするより、“意味づけ”する方が難しいんですよね。
社内広報の工夫|ネーミングとストーリー性がカギ
制度を導入しただけでは、なかなか使われません。
そこで重要になるのが「社内への伝え方」です。
特に、以下の2つは効果的です。
-
ネーミングに“感情”を込める
例:ただの「資格取得支援」より、「なりたい自分応援制度」の方が心に刺さります。 -
ストーリー性を持たせる
制度ができた背景や想いを共有すると、共感が生まれやすくなります。
「〇〇さんの声から生まれた制度」など、社員を主役にした説明も効果的です。
“面白い”を“共感できる”に変換することで、制度は文化になります。
「お遊び」で終わらせない運用管理
面白い制度には、どうしても“遊びっぽさ”がつきまといます。
その“ゆるさ”を活かしつつ、しっかりと「運用」に落とすことが必要です。
ポイントは以下の通りです。
-
月ごと・四半期ごとの実施・利用状況のモニタリング
-
定期的なフィードバック機会(座談会・匿名アンケート)
-
「制度利用レポート」や「エピソード集」を社内に発信
制度は生き物。
運用して初めて見える課題もあるので、アップデート前提で管理する姿勢が大切です。
活用率を上げる人事の伴走方法
「制度があるのに使われない」。
そんな悩みをよく聞きます。
その原因は、制度だけに任せきりで、伴走する人がいないからです。
人事がすべきは、“制度の案内役”から“制度の活用支援者”になること。
たとえば以下のような関わりが効果的です。
-
制度利用を促す「リマインドコミュニケーション」
-
利用者の声を集めて「周知の輪」を広げる
-
利用率の低い部署にヒアリングして「理由」を探る
人事が制度と社員の“橋渡し役”になってこそ、制度は機能します。

人事が“使われ方”まで見てこそ、福利厚生は生きてくるんですよね。
まとめ|「制度」化するには、運用が9割
福利厚生制度は、ネーミングや内容よりも「どう浸透させるか」が勝負です。
目的に紐づけ、社内に共感を生み、使われる仕掛けを整えたとき、それは“面白いだけじゃない、本物の制度”になります。
次章では、実際の効果検証や社員のリアルな反応をもとにした「制度の育て方」へと話を進めます。
【第5章】採用広報に効く!ユニーク制度の発信とSNS活用

面白い福利厚生は、導入しただけでは終わりません。
「どう発信するか」で、採用への効果は大きく変わります。
この章では、ユニークな福利厚生を採用ブランディングに活かす方法を、SNSや自社メディアでの展開も交えて解説します。
福利厚生が採用ブランディングになる理由
福利厚生は、もともと社内向けの制度。
けれど近年では、社外への情報発信の「コンテンツ」としても注目されています。
理由は明確で、求職者の価値観が多様化しているからです。
給与や休日だけでは見えない「その企業らしさ」を、福利厚生が伝えてくれるのです。
とくに、以下のような視点で評価されます。
-
社員をどれだけ大切にしているか(人への投資)
-
社風や価値観との一致度(カルチャーフィット)
-
楽しそうに働けるかどうか(心理的な魅力)

採用は“相性探し”なので、福利厚生は立派なラブレターですね。
若年層が響く“見せ方”と“伝え方”
Z世代やミレニアル世代の採用では、制度そのもの以上に「共感」が鍵になります。
そのために有効なのが、リアルでラフな語り口と、ビジュアルです。
具体的には以下のようなアプローチがあります。
-
制度の背景や想いを語る社員インタビュー(動画・記事)
-
制度を実際に使っている様子の写真やレポート(Instagram・noteなど)
-
導入ストーリーをストリーテリング型で発信(マンガ、スライド投稿など)
制度の“名称”や“内容”だけでなく、
「どんな人が、どんなふうに、どんな気持ちで使っているか」を伝えると、確実に印象が強くなります。
自社サイト・求人媒体・SNSの使い分け
ユニーク制度の情報発信には、伝えるメディア選びも重要です。
目的に合わせて発信先を使い分けましょう。
| 媒体 | 特徴 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| 自社サイト(採用ページ) | 会社の世界観を一括で表現できる | 専用ページを作って複数制度を紹介する |
| 求人媒体(Wantedly・マイナビ等) | 求職者の目に入りやすい | 制度と“仕事とのつながり”をセットで掲載 |
| SNS(X、Instagram、TikTok等) | 拡散力・親近感が強い | 写真やショート動画で“体験”を見せる |

制度の“内容”より“伝え方”の方が大事な時代になってきましたね。
拡散された事例から学ぶ失敗と成功の境界線
ユニーク制度は拡散されやすい反面、誤解や炎上のリスクもあります。
成功した事例と、やや批判を受けた事例の違いから学ぶポイントは次の通りです。
成功例:株式会社アプティの「100円ランチ制度」
-
目的・背景・社員の声を丁寧に発信
-
利用者の満足度が高く、実態と発信が一致
失敗例:SNSでバズった「推し活休暇」導入企業
-
「遊びすぎでは?」という外部の批判
-
社内での運用ルールが不明確で炎上
この差は、「制度の意図と実態の一貫性」にあります。
つまり、制度を“見せる前”に、社内でしっかり機能させることが、最大の防衛線になります。
まとめ|面白さは「戦略的に」伝えてこそ効果的
面白い福利厚生は、戦略的に発信すれば採用力を劇的に高めるツールになります。
求職者の目線に立ち、制度の背景・人のストーリー・使い方のリアルを丁寧に伝える。
これが、“制度の中身”と“外への伝え方”のギャップを埋めるコツです。
次章では、制度の効果測定と改善プロセスについて、実践的に掘り下げていきます。
【第6章】導入支援・アウトソース先をどう選ぶ?
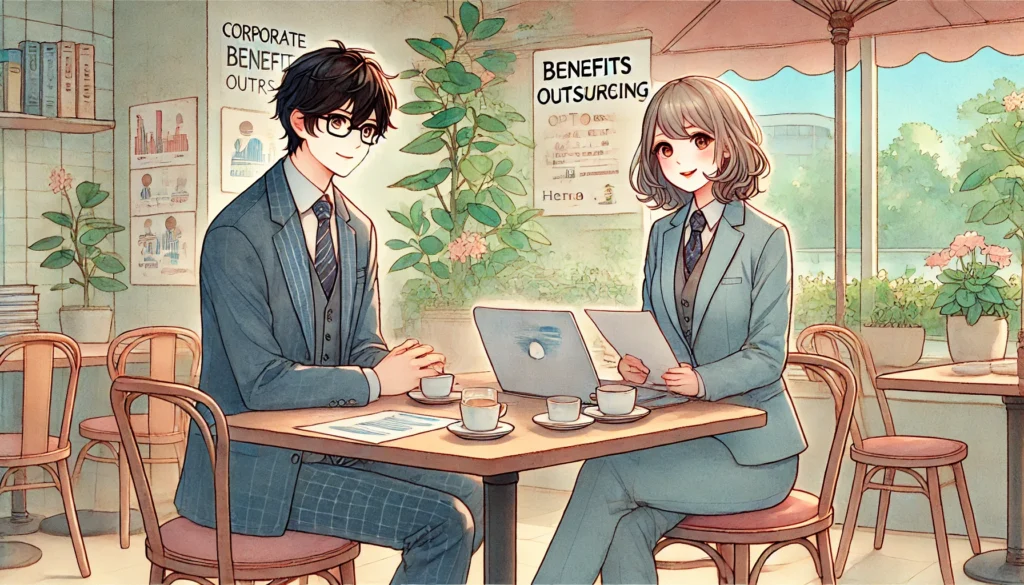
面白い福利厚生を導入したい。
でも、「自社だけで企画・運用するのは正直キツい」――そんな声をよく耳にします。
この章では、福利厚生の導入支援やアウトソーシング先の選び方を解説します。
社外リソースを上手に活用することで、負担を減らしながら成果を出す仕組みを構築できます。
福利厚生支援企業・コンサルの活用法
最近では、福利厚生の設計・導入・運用までサポートする専門会社やコンサルティング企業が増えています。
代表的な支援内容には、以下のようなものがあります。
-
社員ニーズに基づく制度企画のコンサルティング
-
他社事例をもとにした導入パッケージの提供
-
社内説明用のマニュアル・研修コンテンツ作成
-
継続的な活用率・満足度の分析と改善提案
たとえば、福利厚生プラットフォーム「ベネフィット・ワン」や、「リロクラブ」などは、導入コストを抑えつつ選択肢を広げたい企業に人気です。

全部自社で作るより、外部の知見を借りた方が早いです。
社外サービスとの連携でコストダウンを実現する方法
ユニークな制度を“ゼロから構築”しようとすると、開発コストや運用負担が重くなりがちです。
しかし、外部の既存サービスと組み合わせることで、費用対効果を高めることが可能です。
例えば
-
健康支援系なら:フィットネスクラブの法人契約、オンライン健康相談ツール
-
食事系なら:100円ランチ代補助×提携弁当会社の導入
-
趣味支援なら:eラーニング+推し活応援ポイント制度の連携
自社の色を出しつつ、「面白さ」と「合理性」のバランスを保てるのが、外部連携の強みです。
アウトソーシングする場合のチェックポイント
外部委託を検討する際は、以下の点を必ず確認してください。
-
自社の制度コンセプトに合っているか - 提供される内容が、企業文化や社員層とマッチしているか。
-
導入後のサポート体制があるか - トラブル対応や、社員からの問い合わせ窓口などが整備されているか。
-
利用状況の“見える化”が可能か - レポート機能や活用データの提供があると、改善にも活かせます。
-
契約内容とコスト構造が明瞭か - 初期費用・月額費用・オプション料金など、隠れコストに注意。

“入れて終わり”じゃなく、“使われ続ける仕組み”まで考えたいですね。
他社の導入パッケージの活用事例
参考になる事例として、以下の企業が挙げられます。
-
株式会社ロフトワーク
自社のクリエイター支援文化とマッチするよう、外部イベント参加支援制度を外部パートナーと設計。
企画から運用までのパッケージをカスタム利用し、社内浸透にも成功。 -
アソビュー株式会社
余暇支援のプラットフォームを提供している自社サービスを、社員にも福利厚生として提供。
外部向けと内部向けをうまく統合した“二刀流”モデルが注目されました。 -
某中堅建設会社(匿名希望)
社員の健康管理を目的に、福利厚生アウトソーサーと連携し、ストレスチェック→産業医相談→面談記録までを一貫支援。
「手間なく専門家の助けを借りられる体制」に現場も安心。
こうした事例に共通するのは、外部の知見と内部の課題をうまく融合していることです。
自社のオリジナリティを失わずに、プロと組んで制度を洗練させる姿勢がカギになります。
まとめ|“外部を巻き込む”ことも戦略のひとつ
面白い福利厚生を、手間をかけずに、効果的に導入するなら、外部支援の活用は欠かせません。
自前主義にこだわる必要はありません。
制度の“面白さ”も“継続性”も、“社外のプロ”と手を組むことで格段に向上します。
次章では、導入後に効果を最大化するための改善・検証フローについて掘り下げていきます。
【第7章】まとめと感想|面白い福利厚生が組織を変える
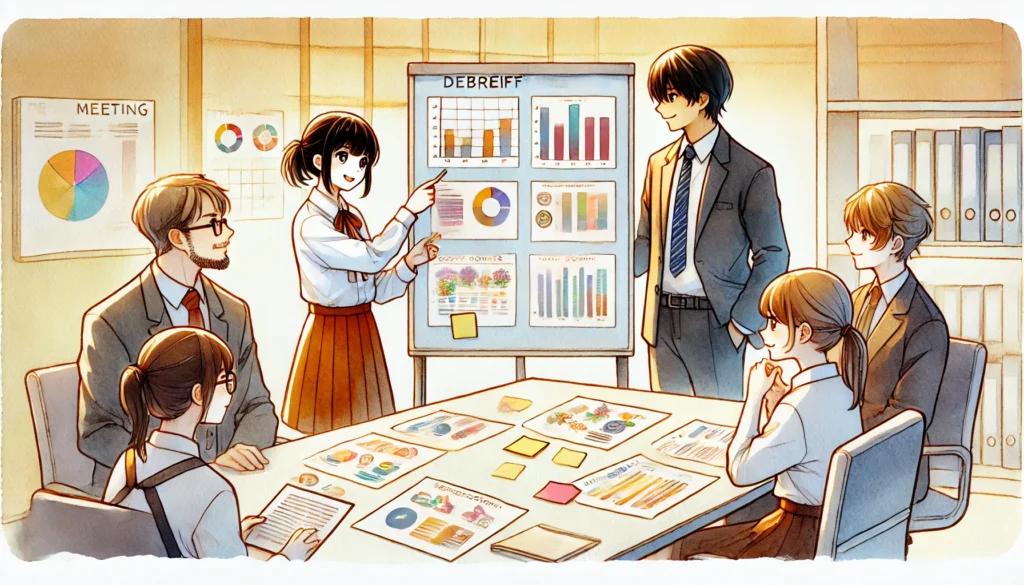
“面白い福利厚生”というと、どこか遊び心や話題性ばかりが先行しがちです。
ですが、本質は「制度を通して、働く人の心を動かせるかどうか」にあります。
本章では、ここまでの要点を振り返りながら、明日から動き出せる3つのアクションと、筆者からの締めのメッセージをお届けします。
本記事の要点振り返り
ここまでの章でお伝えしてきたのは、以下の通りです。
-
面白い福利厚生とは何か?
⇒ 働き手の価値観変化に応える、感情に寄り添う制度のこと。
ブランディングや離職防止、エンゲージメント向上に直結する。 -
他社の事例に学ぶ、注目の制度
⇒ 100円ランチ、推し活休暇、恋愛手当など、多様な方向からのアプローチが可能。 -
制度づくりの“地ならし”が成功の鍵
⇒ 「社員ニーズ」と「企業文化」の接点を見極めること。 -
制度を制度として“生かす”工夫
⇒ 名前の付け方から運用ルール、社内広報までが効果に直結。 -
採用・発信で制度を“武器化”する方法
⇒ 求人広告やSNSでの見せ方が採用効果を左右する。 -
外部支援の活用で導入・運用の負担を減らす
⇒ 社外リソースとの連携がコストダウンと定着率の両方を実現する。

制度そのものより、“制度が何を叶えるか”の方が重要なんですよね。
今すぐ取り組める3つのアクション
ユニーク制度の導入に「完璧な設計」はいりません。
まずは、以下の3つのステップから始めてみてください。
① 社員アンケートを実施して声を集める
社内ニーズを知らずに制度を設計するのは、的外れなプレゼントを渡すようなもの。
簡単なGoogleフォームでも十分です。
「どんな制度があったらうれしい?」の一言で、企画の糸口は生まれます。
② 他社制度を社内で共有し「これやりたい」を引き出す
成功企業の事例をそのまま取り入れる必要はありません。
でも、刺激を与える材料としては効果的です。
社内ミーティングやチャットで「他社の事例ニュース」を流してみてください。
「面白そう」「うちもできる?」の声が自然と出てきます。

とにかく“ネタを見せる”っていうのが、想像力を刺激する第一歩です。
③ 小さくても実行に移すことで「行動」へつなげる
制度は、「考えているだけ」では何も変わりません。
まずは、小規模なトライアルでOK。
たとえば
・月に一度の「好きなお菓子持ち寄りデー」
・推し活手当1,000円分だけ先行導入してみる
・新入社員に「欲しい制度1案」提出してもらう
このような“小さな成功体験”を積み重ねることが、制度定着の最短ルートです。
最後に|ユニーク制度は“目的”ではなく“手段”であることを忘れない
面白い福利厚生は、採用でも社内満足度でも、非常に強い武器になります。
ただし、それはあくまでも「社員が生き生きと働ける環境をつくるための手段」であるべきです。
制度が話題になった。
メディアに載った。
それだけで終わっては、何も意味がありません。
社員の声を拾い、制度に魂を吹き込み、そして“使われる制度”に育てる。
そのプロセスこそが、組織をゆるやかに、でも確実に変えていきます。




