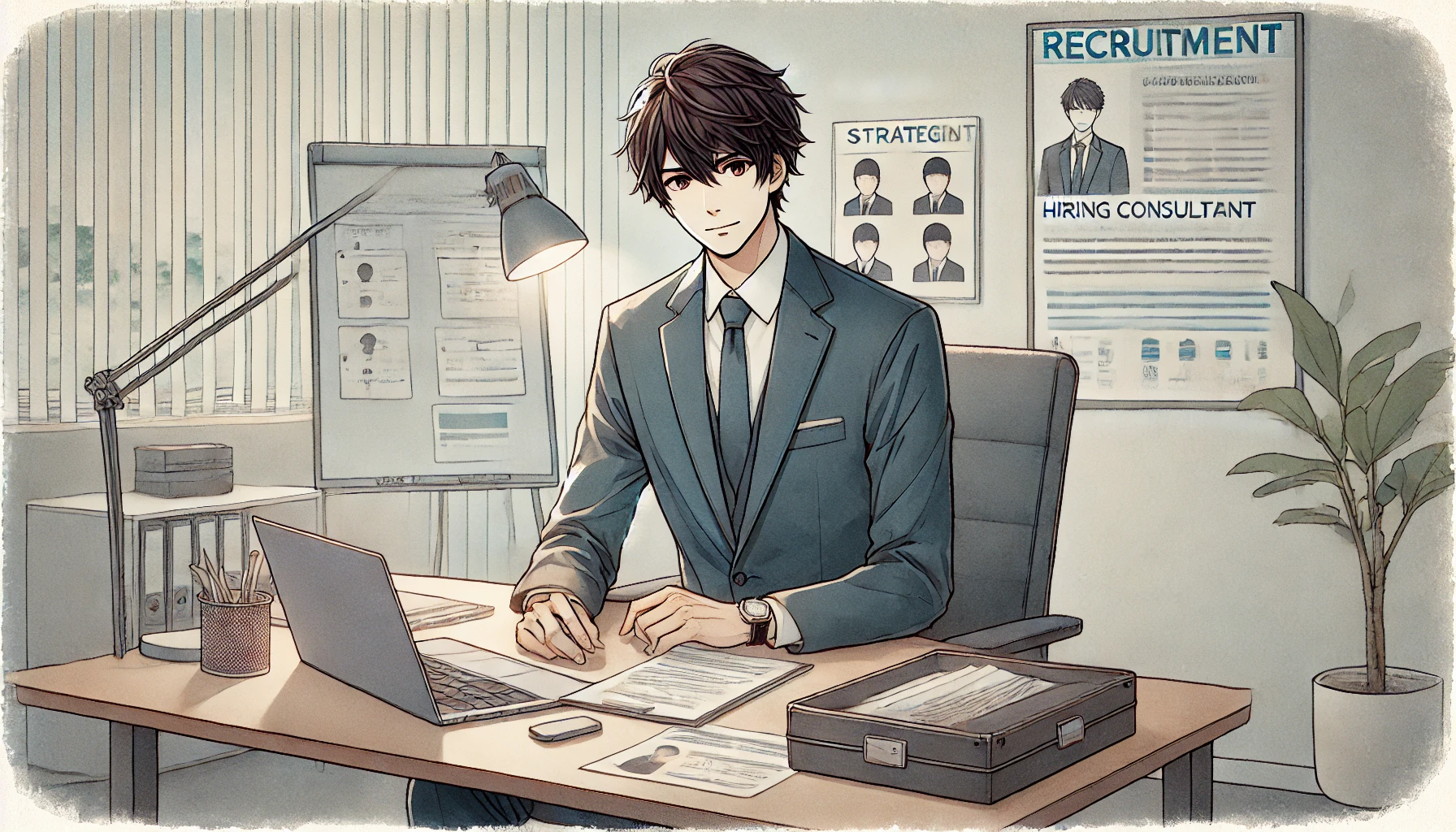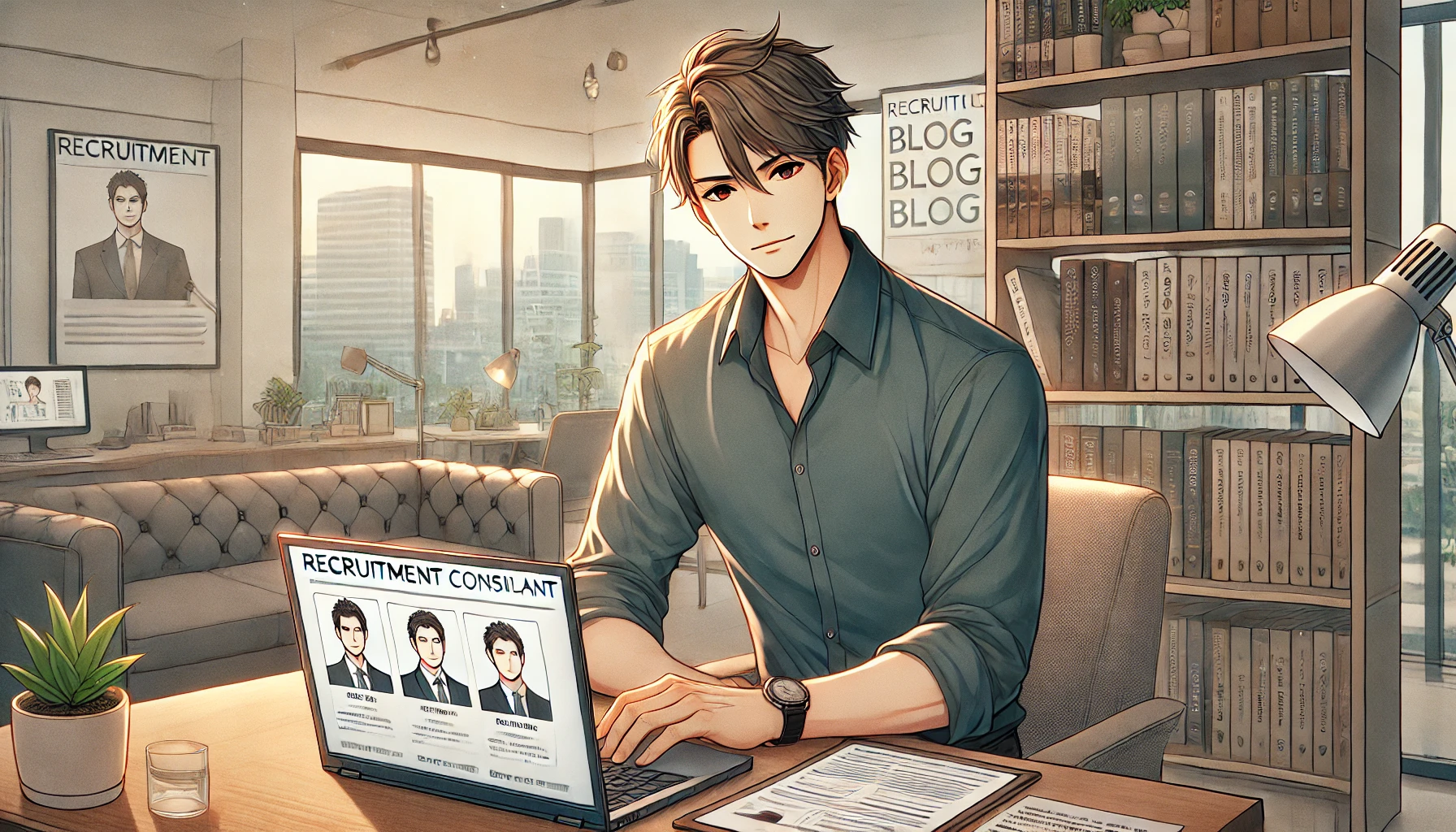「そもそも採用オウンドメディアって何?」「本当に効果があるの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
従来の求人広告や転職サイトと何が違うのか、導入することでどんなメリット・デメリットがあるのか。
本記事では、採用オウンドメディアの基本を押さえた上で、企業が導入すべきかを判断するためのポイントを解説します。
第1章:採用オウンドメディアとは?基本を解説

採用オウンドメディアの定義とは?
近年、「採用オウンドメディア」が注目されていますが、そもそもどんなものなのか?
簡単に言えば、自社の「採用ブランディング」を目的とした情報発信メディアのことです。
企業が独自に運営し、「採用サイト」や「コーポレートブログ」、「SNS」を活用して、企業の魅力や働く環境を求職者に伝える役割を果たします。
従来の求人広告とは異なり、一時的な募集ではなく、長期的に「企業文化」「社員の声」「仕事内容」などを発信し続けることで、求職者に自社を深く理解してもらう狙いがあります。
特に、応募前の「情報収集フェーズ」にある求職者に対し、企業の実態を伝えることができるため、入社後のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。

「求職者の3割以上が”企業の実態が見えない”と不安を感じているらしい。情報発信の重要性は高まるばかりですね。」
これまでの採用手法(求人広告・転職サイトなど)との違い
これまでの採用手法と比較すると、採用オウンドメディアには大きな違いがあります。
1. 求人広告との違い
求人広告は「即効性」が特徴です。
掲載すれば一定期間で多くの求職者に情報が届きます。
しかし、掲載期間が終了すれば求職者の目に触れる機会はなくなり、継続的な認知にはつながりにくいというデメリットがあります。
一方、採用オウンドメディアは「資産」として蓄積され、長期的に効果を発揮します。
たとえば、過去に投稿した社員インタビュー記事が検索され、半年後に応募につながるケースも珍しくありません。
2. 転職サイトとの違い
転職サイトは、求職者が積極的に「転職活動」をしているタイミングで利用するメディアです。
企業が求職者のデータベースを活用してスカウトメールを送るなど、直接的なアプローチが可能です。
しかし、転職活動をしていない潜在層にはリーチできません。
採用オウンドメディアは「転職を考え始めたばかりの層」や「今すぐ転職はしないが興味がある層」に対しても情報を届けられるのが強みです。

「転職サイト頼みの採用だと、どうしても”今すぐ転職したい人”しかターゲットにできないんですよ。」
なぜ今「採用オウンドメディア」が注目されているのか?
ここ数年、採用オウンドメディアに力を入れる企業が増えている理由はいくつかあります。
1. 求人広告のコスト増加
求人広告の掲載費用は年々上昇傾向にあります。
大手転職サイトでの掲載は、数十万円〜数百万円かかることも珍しくありません。
しかし、その費用をかけても必ずしも質の高い応募が来るわけではないのが現実です。
一方、採用オウンドメディアは初期投資こそ必要ですが、運用を継続することで長期的にコストを抑えつつ、ターゲットとなる求職者にアプローチできます。
2. ミスマッチを防ぐための情報発信が重要に
「入社したけど思っていた会社と違った」というミスマッチが起こると、早期退職につながります。
企業としては、採用コストだけでなく、教育コストや業務の引き継ぎなど、さまざまな損失を抱えることになります。
採用オウンドメディアを活用すれば、企業のリアルな情報を発信できるため、「社風が合う人材」を採用しやすくなります。
3. ダイレクトリクルーティングとの相性が良い
最近は、企業が求職者に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」が増えています。
しかし、求職者が企業からスカウトメールを受け取った際、企業の情報を調べても詳しい情報が出てこないと、応募をためらうことがあります。
採用オウンドメディアがあれば、企業の情報をしっかり伝えられるため、スカウトメールの反応率が向上するというメリットもあります。
採用市場の変化とオウンドメディアの役割
近年、採用市場は大きく変化しています。
特に、以下の3つのトレンドが採用オウンドメディアの重要性を高めています。
1. 求職者の情報収集行動の変化
求職者は、求人サイトの情報だけでなく、企業の公式サイト、SNS、口コミサイトを総合的に調べた上で応募を決める傾向が強くなっています。
つまり、企業側が積極的に「採用情報」「社風」「社員の声」を発信しなければ、興味を持ってもらえない時代になっているのです。
2. 採用競争の激化
少子高齢化が進み、特に専門職やIT人材の採用競争は激化しています。
優秀な人材を確保するためには、「企業の強み」や「働きがい」をしっかりアピールする必要があります。
そのためのツールとして、採用オウンドメディアが活用されるようになっています。
3. 企業ブランディングの重要性
採用活動は、「単なる人材募集」ではなく、「企業のブランド価値を高める活動」として捉えられるようになっています。
求職者だけでなく、顧客や取引先からも「この会社はどんな価値観を持っているのか?」が注目される時代です。
採用オウンドメディアは、企業のブランドを確立する重要な手段の一つになっています。
まとめ
採用オウンドメディアは、従来の採用手法とは異なり、企業の魅力を自ら発信することで、長期的に優秀な人材を確保できる手段です。
求人広告や転職サイトだけに頼るのではなく、企業が持つ「リアルな魅力」を伝えることが求職者との信頼構築につながります。
これからの採用活動では、「採用オウンドメディアの運用」が欠かせない時代になっているといえるでしょう。
第2章:採用オウンドメディアのメリットと効果

採用活動の効率化とコスト削減が可能
採用オウンドメディアを導入することで、採用活動の効率が格段に向上します。
特に、求人広告や転職エージェントに頼らず、自社で継続的に採用情報を発信できる点が大きなメリットです。
1. 求人広告の掲載費を削減できる
求人広告の掲載には、数十万~数百万円のコストがかかります。
しかし、掲載期間が終われば求人情報は消え、求職者の目に触れることはなくなります。
一方、採用オウンドメディアなら、一度作成した記事やコンテンツが蓄積され、継続的に求職者へ情報提供が可能です。

「広告費をかけ続けるのはキリがない。オウンドメディアなら”資産”になるのがデカいですね。」
2. 繰り返し使えるコンテンツで効率UP
例えば、「社員インタビュー記事」を作成すれば、長期間にわたって求職者の興味を引くことができます。
さらに、同じコンテンツをSNSや採用説明会、会社説明資料などにも活用でき、採用広報全体の効率を高められます。
求職者に企業のリアルな姿を伝えられる
求職者は、単なる募集要項ではなく、「どんな会社なのか?」「どんな人が働いているのか?」といった情報を求めています。
採用オウンドメディアなら、企業のリアルな姿を伝えることが可能です。
1. 働く環境や企業文化を具体的に発信
求人広告には、限られた文字数しか掲載できませんが、採用オウンドメディアなら企業の理念、働き方、福利厚生などを詳細に伝えられます。
「社内の雰囲気」「仕事のやりがい」「チームの様子」など、リアルな情報を発信することで、求職者にとって魅力的な職場であることをアピールできます。
2. 社員の声が求職者の共感を生む
求職者にとって、「実際に働く社員の声」は最も信頼できる情報の一つです。
社員インタビューやブログを通じて、入社のきっかけや仕事のやりがい、成長のエピソードを発信することで、求職者に共感を持ってもらいやすくなります。

「社長の想いより、現場のリアルな声の方が求職者に響くんですね。」
長期的なブランディングと採用力の向上
採用オウンドメディアは、単なる求人情報を掲載するだけではありません。
長期的に企業の魅力を発信することで、採用力の向上につながります。
1. 企業ブランドを強化し、優秀な人材を惹きつける
企業の知名度が高い大手企業であれば、特に採用オウンドメディアがなくても応募が集まるかもしれません。
しかし、中小企業やスタートアップでは、知名度の低さが採用のハードルになることもあります。
採用オウンドメディアを活用すれば、企業の理念やビジョンを求職者に浸透させ、応募意欲を高めることができます。
2. 「転職検討層」にもアプローチできる
採用オウンドメディアは、「今すぐ転職したい人」だけでなく、「転職を考え始めたばかりの層」や「良い会社があれば転職したい層」にも情報を届けることができます。
例えば、定期的に更新されるブログや社員のインタビュー記事を読んで、求職者が企業に興味を持ち、将来的に応募につながるケースも多いです。
採用以外のメリット(PR・広報との相乗効果)
採用オウンドメディアは、単に採用活動だけに貢献するものではありません。
企業のPRや広報活動にもプラスの影響を与えます。
1. 顧客や取引先の信頼向上
採用オウンドメディアに掲載するコンテンツは、求職者だけでなく、顧客や取引先の目にも触れます。
例えば、「社員がどのような価値観で働いているか」「どんなプロジェクトに取り組んでいるか」を発信することで、企業の信頼性を高めることができます。
2. 社内のエンゲージメント向上
採用オウンドメディアに社員のインタビューや活躍事例を掲載すると、社内のモチベーションアップにもつながります。
自分の仕事が社外に発信されることで、「自分の働きが評価されている」という実感を持てるようになります。
まとめ
採用オウンドメディアには、以下のようなメリットがあります。
- 採用活動の効率化とコスト削減ができる
- 求職者に企業のリアルな姿を伝えられる
- 長期的なブランディングと採用力の向上
- 採用以外のPR・広報にも役立つ
これからの時代、採用は「企業が一方的に選ぶもの」ではなく、「求職者に選ばれるもの」になっています。
企業の魅力をしっかり発信し、優秀な人材を惹きつけるために、採用オウンドメディアを積極的に活用していきましょう。
第3章:採用オウンドメディアのデメリットと課題
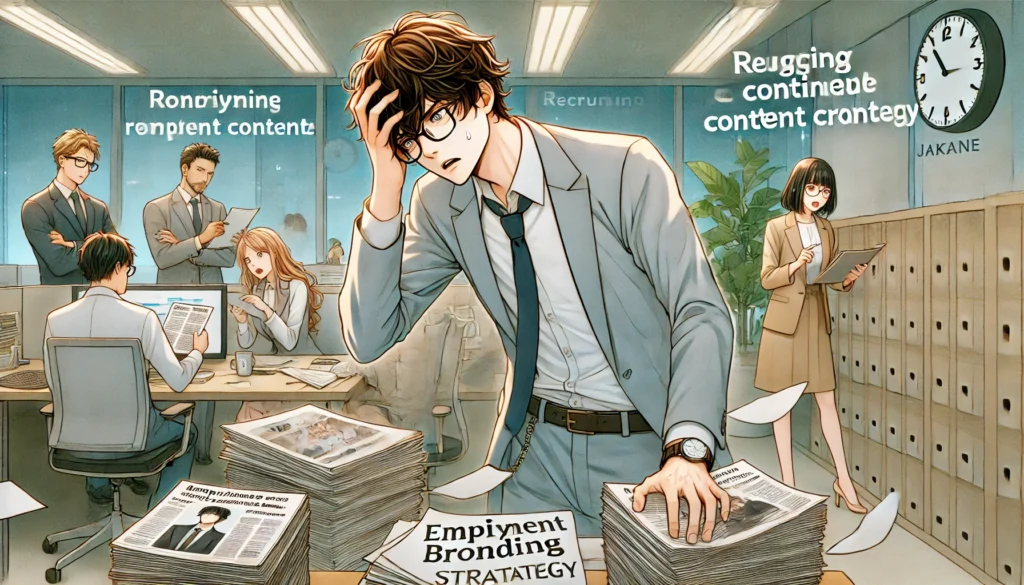
立ち上げに時間とコストがかかる
採用オウンドメディアを導入する際、多くの企業が最初に直面する課題は「立ち上げのハードルの高さ」です。
まず、メディアを設計するには、以下のような準備が必要になります。
- 目的の明確化(ターゲットとなる求職者は誰か?どのような情報を発信するのか?)
- サイト構築やデザインの選定(自社サイトの一部として運用するのか?新たにメディアを立ち上げるのか?)
- コンテンツの企画・制作(記事、写真、動画など、どのような形式で情報を伝えるのか?)
これらを整えるには、それなりの時間とコストがかかります。
1. サイト構築・運営の費用
採用オウンドメディアは、簡単なブログ運営と異なり、しっかりとした設計が必要になります。
WordPressやCMSを活用すればコストを抑えられますが、それでもデザインやSEO対策、セキュリティ対策などの費用が発生します。
また、外部の制作会社に依頼する場合、初期費用として50万円〜200万円ほどかかることもあります。
さらに、記事の制作や撮影など、運営コストも発生するため、継続的な予算の確保が必要になります。

「”とりあえず始める”ではなく、長期的な計画が大事ですね。」
2. 社内リソースの確保が必要
採用オウンドメディアは「一度作って終わり」ではなく、継続的に情報を発信し続けることが重要です。
しかし、日常業務が忙しい中で、専任の担当者をつけられる企業は限られています。
そのため、「採用担当者」「広報担当者」「現場社員」などを巻き込みながら、運営チームを作ることが理想的です。
継続的なコンテンツ運用が必要
採用オウンドメディアの本質は、「長期的な情報発信」です。
つまり、一度記事を公開して終わりではなく、定期的に新しいコンテンツを追加し続ける必要があります。
1. 更新頻度が低いと、求職者の関心が薄れる
例えば、1年前に更新されたままの採用ページを見た求職者はどう思うでしょうか?
「この会社、本当に採用活動してるの?」と不安を感じるかもしれません。
企業の最新情報や社員の声を定期的に発信することで、「この会社は活気がある」「成長している」といったポジティブな印象を与えることができます。
2. どんなコンテンツを作るべきか悩む
「最初は意気込んで記事を作ったけど、ネタが尽きて更新が止まった」というケースも少なくありません。
採用オウンドメディアで求職者に響くコンテンツの例として、以下のようなものが考えられます。
- 社員インタビュー(仕事内容・入社の決め手・会社の雰囲気など)
- 企業のカルチャー紹介(オフィス環境・社内イベント・働き方のリアル)
- 仕事のやりがい(実際のプロジェクト事例・成功体験など)
- 社長・人事担当者の想い(どんな人と働きたいのか?採用の方針とは?)
これらを定期的に発信し続ける体制を作れるかが、成功のカギとなります。
成果がすぐに出るわけではない
採用オウンドメディアは、短期間で成果が出る施策ではありません。
求人広告なら掲載してすぐに応募が来る可能性がありますが、オウンドメディアは「じわじわと求職者の関心を集め、エンゲージメントを高める」ものです。
1. 最低でも半年〜1年は必要
オウンドメディアの効果を実感するには、最低でも半年〜1年の運用が必要です。
「記事を数本公開しただけでは、ほとんど流入がない」というのは当たり前の話です。
記事が検索エンジンに評価され、求職者の目に触れるまでには時間がかかります。

「短期的な成果を求めすぎると失敗する。気長に育てる意識が大事なんです。」
2. 継続的な分析と改善が必要
効果が出るまでに時間がかかるからこそ、定期的な分析が欠かせません。
例えば、以下のようなデータをチェックし、改善を繰り返す必要があります。
- どのコンテンツがよく読まれているか?
- サイトの流入経路(検索・SNS・ダイレクトなど)
- 応募につながったコンテンツは何か?
データをもとに、「反応の良い記事を増やす」「流入経路を強化する」といった対策を講じることで、より効果的なメディア運営が可能になります。
専門的な知識(SEO・マーケティング)が求められる
採用オウンドメディアを成功させるには、「作るだけ」ではダメです。
求職者に見つけてもらうためには、SEOやマーケティングの知識が求められます。
1. SEO対策が必須
検索エンジンで「〇〇(業界名) 求人」「〇〇(職種) 転職」と検索したとき、上位に表示されなければ、せっかく作った採用オウンドメディアも誰の目にも触れません。
そのため、以下のようなSEO対策を実施することが重要です。
- 適切なキーワードを入れる(求職者が検索しそうなワードを記事内に含める)
- 記事タイトルや見出しを工夫する(クリックしたくなるタイトルをつける)
- 内部リンクを活用する(他の記事へスムーズに誘導する構成にする)
2. SNSとの併用が効果的
オウンドメディア単体では、最初はなかなか閲覧数が伸びません。
そこで、Twitter(X)やLinkedInなどのSNSを活用し、記事を拡散するのが有効です。
社員がシェアすることで、より多くの人にリーチできます。
まとめ
採用オウンドメディアは、長期的な採用力を高める強力なツールですが、以下の課題があります。
- 立ち上げに時間とコストがかかる
- 継続的なコンテンツ運用が求められる
- 成果がすぐに出るわけではない
- SEO・マーケティングの知識が必要
導入を検討する際は、「どのくらいのリソースを割けるか?」を事前にしっかり考え、戦略的に運用していくことが成功のカギとなります。
第4章:採用オウンドメディア成功のための運用ポイント

ターゲット(ペルソナ)を明確にする
採用オウンドメディアの運用で最も重要なのは、「誰に向けて発信するのか?」を明確にすることです。
ターゲットを定めずに記事を作成すると、求職者に響かない内容になり、応募につながりません。
まず、採用したい人材像(ペルソナ)を具体的に設定しましょう。
1. 採用ペルソナの設定
例えば、「エンジニアを採用したい」のか、「営業職を採用したい」のかで、発信する内容が大きく変わります。
エンジニアなら「技術ブログ」や「プロジェクト事例」、営業職なら「顧客との関係構築」「営業のやりがい」を伝える記事が求められます。
ペルソナを設定する際は、以下のような項目を整理すると分かりやすくなります。
- 職種・経験年数(例:Webエンジニア・3年以上)
- 求職者の悩みや課題(例:技術の幅を広げたいが、成長できる環境が見つからない)
- 転職の動機(例:リモートワークを希望している、企業文化が合う会社を探している)

「自社に合う人材を引き寄せるには、”求職者の目線”で考えることが大事ですね。」
ペルソナが決まれば、「この求職者が知りたい情報は何か?」を基に、コンテンツの方向性が見えてきます。
採用に特化したコンテンツ企画の立て方
採用オウンドメディアを運用する上で、単なる求人情報だけでは求職者の関心を引くことはできません。
「ここで働きたい!」と思わせるための魅力的なコンテンツを企画することが重要です。
1. コンテンツの種類
採用オウンドメディアに適したコンテンツには、以下のようなものがあります。
- 社員インタビュー(仕事内容・キャリアパス・働く環境)
- 企業カルチャー紹介(ミッション・バリュー・オフィスの雰囲気)
- 仕事の進め方・プロジェクト事例(具体的な業務の流れや成功事例)
- 社内イベント・福利厚生の紹介(社員旅行・研修制度・ワークライフバランス)
2. 「求職者の疑問」に答えるコンテンツを作る
求職者が最も気にするのは、「この会社で自分が成長できるのか?」という点です。
そのため、実際の仕事内容やキャリアアップの事例を紹介する記事を用意するのも有効です。
また、「未経験からでも活躍できる?」「社内の教育制度は?」といった疑問に答えるQ&A記事を作るのもおすすめです。
社員を巻き込んだコンテンツ制作の工夫
採用オウンドメディアの成功には、「リアルな情報」が欠かせません。
そのためには、社内の社員を巻き込み、現場の声を発信することが重要です。
1. 「社員発信型コンテンツ」を作る
企業の採用担当者が発信する情報よりも、「実際に働いている社員の声」の方が求職者には響きます。
そのため、以下のような形で、社員が参加できる仕組みを作るとよいでしょう。
- ブログ形式で現場社員が記事を投稿(仕事のやりがいや技術ブログ)
- 社員インタビュー記事の掲載(キャリアパス・仕事内容の紹介)
- SNSで社員が会社の様子を発信(オフィス風景・社内イベントの様子)
2. 「文章を書くのが苦手」な社員でも参加できる仕組み
「文章を書くのは苦手…」という社員が多い場合は、動画コンテンツを取り入れるのも有効です。
例えば、短い動画で社内の雰囲気や社員の一日を紹介すると、よりリアルな情報を求職者に伝えることができます。

「社員のリアルな声ほど、求職者に刺さるものはないんです。」
SEOとSNSを活用した集客戦略
せっかく作った採用オウンドメディアも、誰にも見られなければ意味がありません。
求職者に情報を届けるために、SEO(検索エンジン最適化)とSNSの活用が欠かせません。
1. SEO対策で検索流入を増やす
求職者が検索するキーワードを意識して記事を作成することで、検索エンジンからの流入を増やせます。
例えば、以下のようなキーワードを取り入れると効果的です。
- 「〇〇(職種) 転職」(例:「Webエンジニア 転職」)
- 「〇〇(業界) 仕事」(例:「IT業界 仕事内容」)
- 「〇〇(企業名) 働き方」(例:「〇〇株式会社 社風」)
また、記事のタイトルや見出しには、求職者が検索しそうなワードを入れるようにしましょう。
2. SNSとの連携で拡散を狙う
採用オウンドメディア単体では、最初のうちは閲覧数が伸びにくいものです。
そこで、Twitter(X)やLinkedIn、Instagramを活用し、記事を拡散するのが有効です。
特に、以下のような施策が効果的です。
- 社員が記事をシェアする(社員が投稿すると、求職者の信頼度が高まる)
- 定期的にSNS投稿を行う(採用情報・社内イベントの報告など)
- ハッシュタグを活用する(「#採用オウンドメディア」「#転職したい」など)
SNSを活用することで、「転職活動をしていない層」にも企業の情報を届けることができます。
まとめ
採用オウンドメディアを成功させるには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- ターゲット(ペルソナ)を明確にする(どんな人材を採用したいのかを明確にする)
- 求職者が知りたい情報を発信する(仕事内容・キャリアパス・企業文化など)
- 社員を巻き込み、リアルな情報を届ける(社員インタビュー・SNS投稿など)
- SEOとSNSを活用して認知を拡大する(検索流入・SNSシェアの強化)
採用オウンドメディアは「作って終わり」ではなく、「継続的に運用し、求職者との接点を増やす」ことが成功のカギになります。
この戦略を実践し、自社に合った優秀な人材を確保していきましょう。
第5章:まとめと感想|採用オウンドメディアの未来

採用オウンドメディアの重要性を再確認
ここまで読んで、「採用オウンドメディア、うちでもやるべきなのか?」と考えた方も多いのではないでしょうか。
結論として、 長期的に優秀な人材を獲得し、採用コストを削減したい企業にはおすすめの施策です。
採用市場は年々変化しており、企業が「選ぶ立場」から「選ばれる立場」になりつつあります。
求職者は、単に待遇や仕事内容だけでなく、「どんな価値観の会社なのか?」「社員はどんな働き方をしているのか?」といった企業のリアルな情報を求めています。
こうした情報を、企業側が自ら発信し、求職者とのミスマッチを防ぐための手段が採用オウンドメディアなのです。

「企業が”情報発信しない”という選択肢は、もはや通用しなくなってきていますね。」
導入すべき企業の特徴と適性判断
とはいえ、どの企業でも採用オウンドメディアが向いているわけではありません。
導入を検討する際は、自社の状況やリソースを考慮することが重要です。
1. 採用オウンドメディアが向いている企業
- 長期的に採用ブランディングを強化したい企業
- 頻繁に採用活動を行う企業(特に成長フェーズの企業)
- 採用広告費を抑えつつ、優秀な人材を集めたい企業
- 自社の魅力や社風をしっかり伝えたい企業
例えば、IT企業やスタートアップでは、エンジニアやデザイナーなどの専門職の採用が常に課題になります。
こうした企業では、「技術ブログ」や「社員のキャリアストーリー」を発信することで、求職者の関心を引くことができます。
また、知名度が低い企業ほど、採用オウンドメディアの効果が大きいです。
大手企業ならブランド力で応募が集まることもありますが、中小企業は「情報発信をしなければ、そもそも求職者に認知されない」からです。
2. 採用オウンドメディアが向いていない企業
- 短期間で採用成果を出したい企業(即戦力採用が中心)
- リソースが確保できず、継続的な運用が難しい企業
- 求人広告やエージェント経由の採用で十分な成果が出ている企業
採用オウンドメディアは「即効性のある施策」ではありません。
今すぐ人材が欲しい場合は、求人広告や転職エージェントの活用が現実的です。
また、「とりあえず始めたけど、更新が続かず放置状態…」となると、逆に企業の信頼を損なう可能性もあります。
しっかりと運用できるかどうか?を事前に検討することが重要です。
今後の採用市場の変化とトレンド
採用市場は今後、さらに「情報の透明性」が求められる時代へとシフトしていきます。
特に以下のようなトレンドが進むと考えられます。
1. 企業の「採用広報」が当たり前になる
これまでは「採用活動=人材募集をかけること」でしたが、これからは 「採用活動=企業の情報発信」へと変わります。
実際、すでに大手企業を中心に「採用広報専門のチーム」を立ち上げ、積極的に情報発信を行うケースが増えています。
求職者に選ばれる企業になるためには、 採用オウンドメディアの運用が今後ますます必須になっていくでしょう。
2. SNSとの連携が重要に
近年、X(旧Twitter)やLinkedIn、Instagramなどを活用した「SNS採用」も増えています。
求職者が企業の公式アカウントや社員の投稿をチェックするのが当たり前になりつつあるため、 オウンドメディア+SNSの組み合わせがスタンダードになっていくでしょう。
特に、動画コンテンツの活用も注目されています。
社内の雰囲気や社員の働き方を動画で伝えることで、より求職者に響く採用コンテンツを作ることができます。

「動画の時代が本格的に来ます。YouTubeやTikTokを採用に活かす企業も増えそうですね。」
これから始める人事担当者へのアドバイス
「採用オウンドメディアを始めたいけど、何から手をつければいい?」という人事担当者も多いでしょう。
そこで、最初にやるべきステップをシンプルにまとめました。
1. 目的とターゲットを明確にする
- どんな人材を採用したいのか?(ペルソナ設定)
- どんな情報を発信すれば求職者の心に響くのか?
2. 小さく始めて、改善しながら運用する
「完璧なサイトを作るまで公開しない」のではなく、 まずは簡単なコンテンツから始めて、徐々に改善していくのが成功のコツです。
例えば、最初は「社員インタビュー記事を1本公開する」といった形でもOKです。
運用しながらデータを分析し、求職者の反応を見ながらブラッシュアップしていきましょう。
3. 社員を巻き込んで継続的に運用する
採用オウンドメディアは「人事だけの仕事」ではなく、「会社全体のプロジェクト」という意識が大事です。
社内の社員を巻き込みながら、長期的に育てていく体制を作りましょう。
まとめ
- 採用オウンドメディアは、長期的に優秀な人材を確保し、採用コストを削減できる施策である
- 特に、成長フェーズの企業や知名度の低い企業にとっては大きな武器になる
- 一方で、即効性はなく、継続的な運用が必要になるため、リソース確保が重要
- 今後は「採用広報」が当たり前になり、情報発信が採用成功のカギを握る
- まずは小さく始め、社員を巻き込みながら継続的に育てていくことが成功のポイント
採用オウンドメディアは、単なる「採用活動」ではなく、「企業のブランドを強化する戦略」です。
これからの時代、求職者に選ばれる企業になるために、ぜひ積極的に取り組んでみてください。