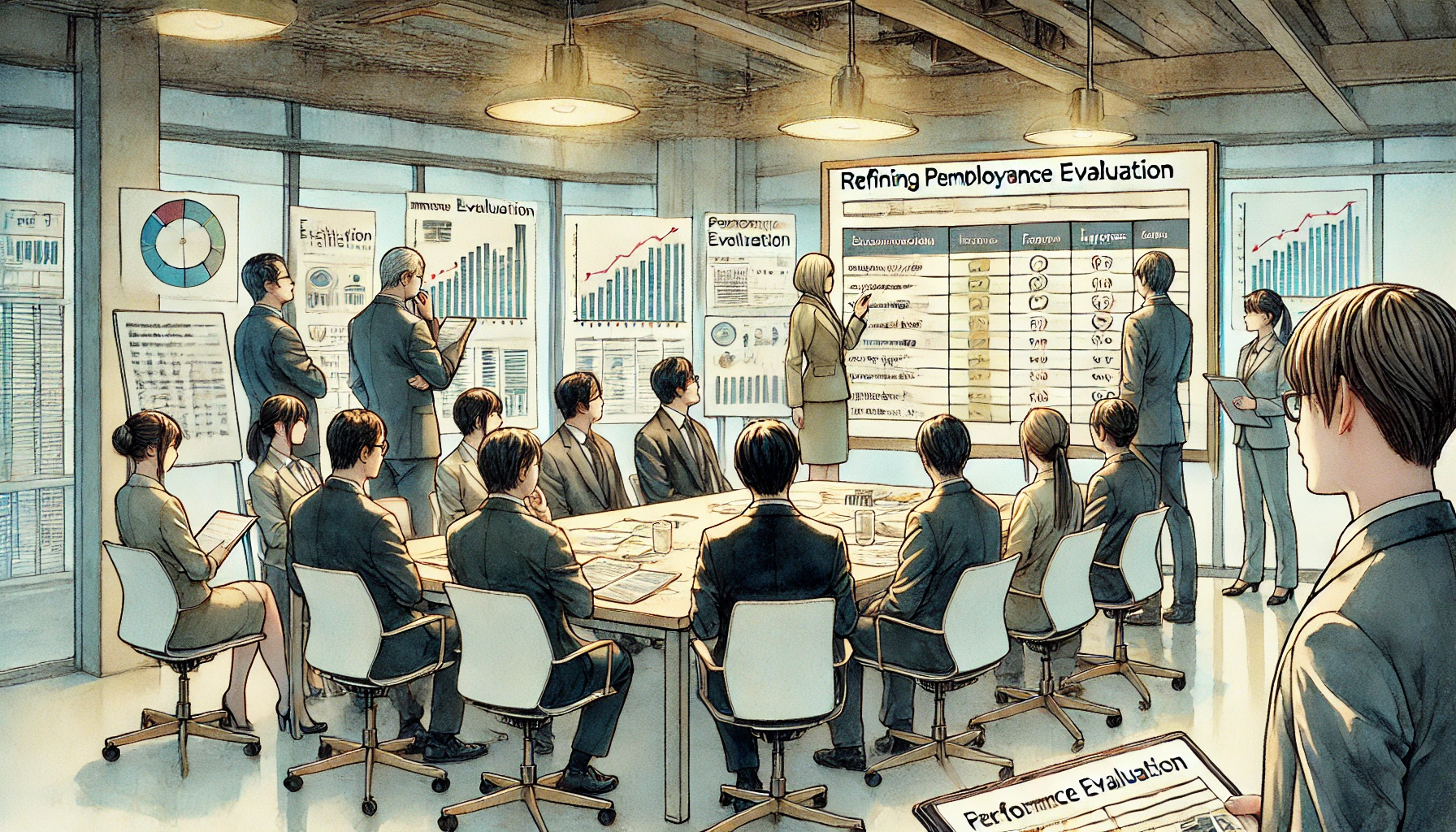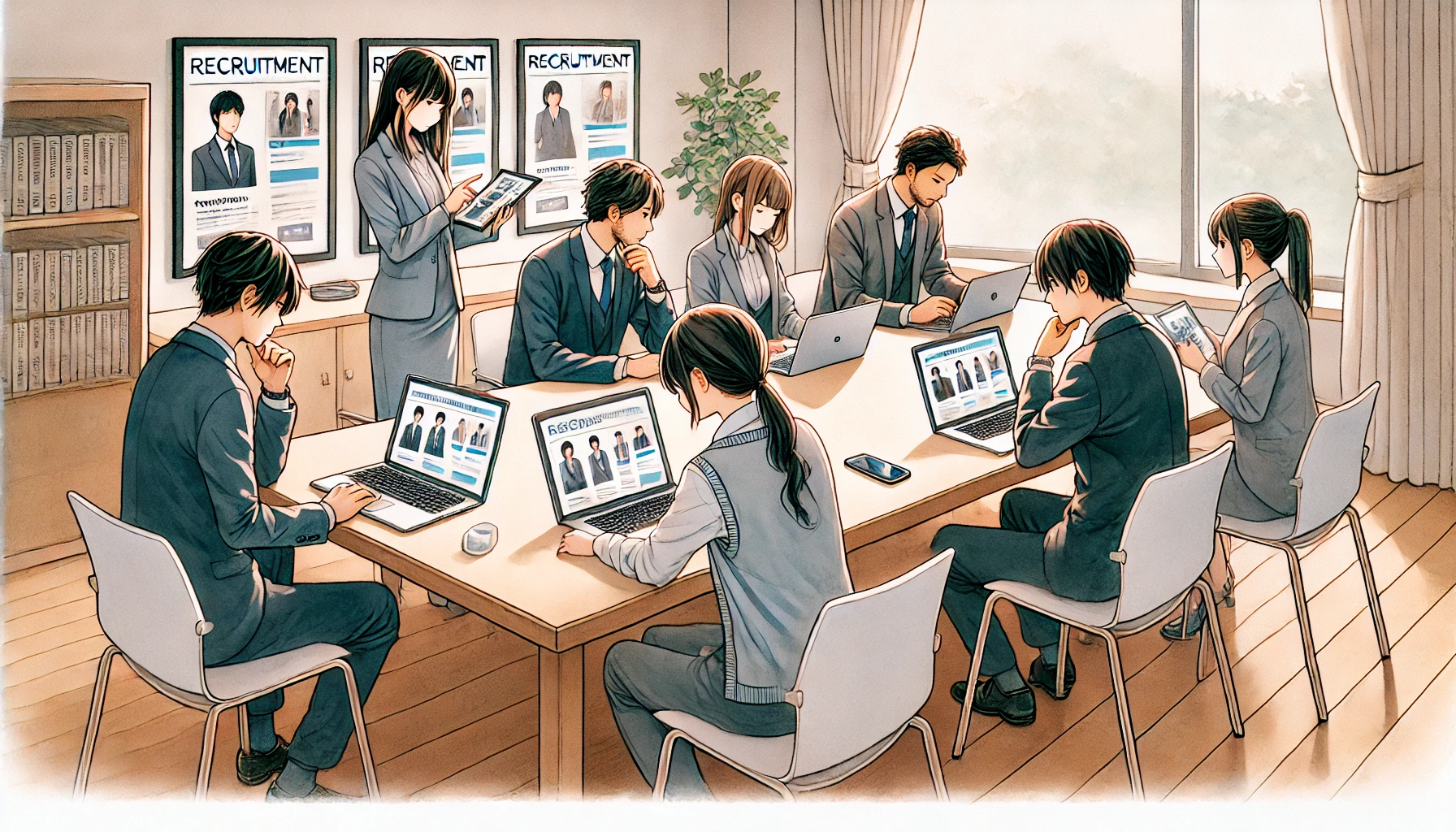「人手が足りない」。中小企業の現場で今、一番多い悲鳴です。
新たに採用しても追いつかず、採用コストも高騰するばかり。
私も採用支援の現場で、毎月こうした経営者・工場長・人事部長の悩みに向き合っています。
本記事では、採用だけに頼らない即効性のある「人手不足解消策」を、具体例を交えながらわかりやすく整理します。
【第1章】人手不足が加速する3つの背景要因
労働人口減少と高齢化の加速
日本の人手不足の根本には「労働人口の急激な減少」が横たわっている。
総務省の統計によれば、生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少を続けている。
現在も年に数十万人規模で減り続け、今後も加速度的に縮小していくとされている。
しかも、若手世代の減少に加え、現場で重要な戦力だった40代後半〜50代の熟練層も定年期に差し掛かっている。
新たな人材が育つ前に、ノウハウを持ったベテランが抜けていく現象が各業界で進んでいる。

ベテランの引退が一番痛いんですよね。現場力が一気に落ちるんです。
この構造的な人手不足は、企業の努力だけではどうにも埋めにくくなっている。
そのため、今後も省人化や外国人採用、アウトソーシングの活用が重要性を増す背景になっている。
採用難の常態化|求人倍率上昇・採用コスト高騰
次に深刻なのが「採用活動自体が難しくなっている」現実だ。
有効求人倍率はコロナ禍から回復し、特に製造、物流、介護、IT、建設といった現場系職種では高止まり傾向が続いている。
ハローワークや求人媒体に出しても応募が集まらない。
広告費をかけても母集団形成ができない。
さらに、採用成功のために提示する給与条件も上げざるを得なくなっており、採用単価がじわじわ高騰している。

広告出しても応募ゼロ。これが今の現場のリアルなんです。
こうして「求人出しても人が来ない」「来ても定着しない」という悪循環が多くの中小企業で起きている。
採用力は企業規模の差がますます拡大しており、大手志向が強まる若手層の動向も拍車をかけている。
業界別に深刻化する人材確保の現実
人手不足の度合いは業界によっても濃淡がある。
厚生労働省のデータを参考にすると、次の業界では特に深刻度が高まっている。
-
製造業:技能人材の高齢化と若手離れが進行中。ライン作業員確保も困難。
-
物流業:ドライバー不足が慢性化。2024年問題(残業規制強化)でさらに拍車。
-
介護業界:慢性的な有効求人倍率3倍超。資格要件も影響。
-
飲食業:長時間労働敬遠、外国人依存度の高まり。
-
建設業:高齢職人の引退加速、技能実習生枠でもカバーしきれない状況。
これらの現場型ビジネスでは「応募が来ない」「離職率が高い」という悩みが日常茶飯事になっている。
社内改善だけでは追いつかず、多くの企業がアウトソーシングやテクノロジー導入に踏み切りつつあるのが現状だ。
【第2章】即効策①|「スポット派遣・請負」で急場をしのぐ
短期派遣・日雇い派遣の活用場面
人手不足が深刻でも「恒常的に人を雇うのは難しい」という企業は少なくない。
繁忙期、季節要因、大型案件など、短期間だけ人手が必要になる場面では短期派遣・日雇い派遣の活用が有効になる。
たとえば、以下のようなケースが典型だ。
-
年末年始の物流倉庫でのピッキング作業
-
大型商業施設のイベント運営スタッフ
-
繁忙期の工場ライン増強要員
-
飲食店の短期ホールスタッフ
短期派遣のメリットは、即日〜数日単位で人員調整が可能な点だ。
正社員採用のように長期雇用リスクを背負わず、必要な時だけ最適な人数を揃えられる。

人が必要な時だけ頼める「人材のサブスク」的感覚に近いですよね。
法規制面でも、2020年改正労働者派遣法以降、一定の条件下で日雇い派遣も活用しやすくなっている。
ただし、事前に派遣会社との契約整備や法令順守を徹底する必要がある。
請負(アウトソーシング)導入のポイント
派遣と並び、もう一つの有力な即効策が「請負(アウトソーシング)」だ。
派遣は自社が現場管理するが、請負は一定業務を丸ごと外部委託する形になる。
例えば、以下のような業務が請負化しやすい。
-
倉庫内仕分け業務一式
-
製造工程の一部ライン作業
-
IT運用・ヘルプデスク業務
-
店舗の棚卸・棚替え作業
請負を活用すれば、自社の社員がやるべきコア業務に集中でき、現場負担を大幅に軽減できる。
ただし、「丸投げ」で品質が下がらないよう、外注先の実績確認や業務分担の設計が重要になる。

請負は契約設計が甘いと「やってくれるはずだったのに」と揉めがち。慎重に設計を。
請負導入では、外部に求める成果指標(納期・品質基準・稼働人数など)を明確に設定しておくことが肝になる。
実例:繁忙期の物流現場での短期人材派遣|Workyouの活用事例
たとえば、ある物流企業A社では年末商戦のたびに人手不足が深刻化していた。
通常の派遣依頼では間に合わず、短期のアルバイト募集も反応が悪かった。
そこで活用したのが、スキマバイト系マッチングサービスのWorkyouだった。
Workyouでは、1日単位・短時間から登録スタッフをアサインできる仕組みが整っている。
A社では、ピーク期前に「ピッキング」「仕分け」「出荷準備」などの職種と必要人数を事前登録。
登録スタッフからの応募が即時集まり、前日までに人員確保が完了する仕組みを構築した。
結果的に、昨年までの欠員発生ゼロで繁忙期を乗り切ることができた。
こうした「即応型の人材確保手段」は、今後ますます現場型ビジネスで普及していくはずだ。
【第3章】即効策②|外国人労働者の採用活用法
外国人採用は今や中小企業でも一般的に
国内の人手不足が慢性化する中で、外国人労働者の活用は有力な解決策になりつつある。
特に飲食、介護、宿泊、製造、農業、建設といった現場型ビジネスでは、既に欠かせない戦力になっている。

現場を歩くと、もう日本人だけで回ってる職場の方が珍しいくらいです。
外国人採用と言っても、制度や在留資格によって活用の形は大きく分かれる。
ここでは中小企業が今すぐ導入可能な3つの枠組みを紹介する。
特定技能制度の活用
2019年に新設された「特定技能制度」は、まさに人手不足業界向けの制度設計となっている。
現在、以下の14分野で受け入れが可能だ(法務省資料より)。
-
介護
-
外食業
-
ビルクリーニング
-
宿泊
-
農業
-
漁業
-
製造(産業機械、電気電子、素形材、鋳造など)
-
建設業 など
特定技能1号では、最長5年間の就労が可能となり、基本的に即戦力人材が求められる。
技能試験や日本語能力試験に合格する必要はあるが、既に日本国内にいる留学生等の切り替えも活発だ。
技能実習制度の活用
技能実習制度は元々「技能移転」を目的とした制度だが、実質的に人材確保策として活用されているのが実情である。
製造・建設・農業などの単純作業系職種では導入事例が多い。
ただし、技能実習制度は国際的な批判もあり、2027年を目途に新制度へ移行予定とされている。
導入に際しては監理団体との契約や、法令順守、労働条件整備を丁寧に行う必要がある。
留学生アルバイトの活用
比較的ハードルが低く、今すぐ導入できるのが「留学生アルバイト」の採用だ。
在留資格「留学」では週28時間以内の就労が許可されており、特に飲食・小売・物流業界で多く活躍している。
時間制限はあるが、日本語もある程度習得しており、比較的教育コストが抑えやすいメリットがある。
卒業後に正社員登用につなげる事例も増えている。

短期バイト→正社員化の流れはかなり王道になってきた印象です。
外国人受け入れ体制づくりの注意点
外国人雇用で成功するには、制度だけでなく社内体制の整備が重要になる。
-
日本語教育や通訳支援
-
生活面(住居・銀行口座・行政手続き)のサポート
-
宗教・文化への配慮(食事・休日など)
-
ハラスメント防止・相談窓口設置
単に「労働力」としてではなく、「戦力化・定着化」の視点が成果を左右する。
実例:飲食業での外国人スタッフ戦力化事例
たとえば、都内の焼肉チェーンを展開するB社では、コロナ後の採用難が深刻化していた。
日本人アルバイトが集まらず、営業継続すら危うくなったタイミングで、留学生のアルバイト採用に着手。
当初は日本語の壁もあったが、メニュー写真付きのオーダーシステムや研修動画を整備し、習熟スピードを向上。
1年後には外国人スタッフ比率が店舗全体の30%を超え、店舗運営の中核戦力へと育っていった。
この事例のように、「業務設計×教育設計×生活支援」をセットで行うことで、外国人採用は即効性のある打ち手となる。
【第4章】即効策③|省人化・自動化ツールの導入(RPA・DX)
採用だけが人手不足対策ではない
人手不足というと「採用する」「人を補充する」発想に偏りがちだ。
しかし近年、多くの企業が取り組んでいるのが 「省人化=人手そのものを減らす」 というアプローチだ。
ここでカギを握るのが RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) と 自動化設備の活用 である。

採る前に“減らせる工程”がないか確認する。これ基本です。
RPA導入による事務工程削減
RPAは、簡単に言えば「ホワイトカラーの単純作業を自動でやってくれるソフトウェア」だ。
経理、総務、人事、営業事務、受発注管理などの定型業務で多く導入が進んでいる。
たとえば以下のような業務で成果を上げている。
-
請求書データの入力・転記
-
勤怠データ集計
-
在庫管理システムの更新
-
発注書の自動作成・送信
-
採用応募者データの自動振り分け
RPAはプログラミング不要で導入できる製品も多く、月額数万円から使える中小企業向けパッケージも出てきた。
「人を増やすよりRPA1ライセンス導入」の方が安くつくケースも珍しくない。

RPAは“新人1人雇うより安い”のが現実です。
工場現場での自動化ライン・ロボット活用事例
製造や物流現場でも 機械化・ロボット導入 による省人化が加速している。
-
搬送ロボット(AGV・AMR)で部品や材料の自動運搬
-
ピッキングロボットによる仕分け自動化
-
自動梱包機による包装工程の省力化
-
組立ラインの協働ロボット導入
たとえばある電子部品工場では、人3人で回していた搬送作業をAGV4台で完全自動化。
結果、現場の作業員を加工工程に再配置でき、生産性全体が20%改善した。
もちろん、設備投資額は一定の負担となる。
ただし、省人化効果を年単位で試算すれば、多くのケースで 「3年償却ライン」 に収まってくる。
中小企業でも導入可能な価格帯のロボットソリューションが増えてきた今、検討の価値は十分にある。
コスト比較:採用と機械投資の損益分岐
実際、経営判断の場では「人を採る」か「機械に任せる」かを定量的に比較することが重要になる。
| 項目 | 人的採用 | 自動化導入 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 採用コスト10〜50万円/人 | 数十万〜数百万円 |
| ランニング | 人件費20〜30万円/月 | 保守・電気代 数千〜数万円 |
| 定着リスク | 退職リスクあり | なし(故障時は修理) |
| 習熟速度 | 数ヶ月 | 即稼働可能 |
当然、全てを置き換えるのは難しいが、工程分解をすれば 「一部だけでも省人化できる領域は広い」 ことが分かる。
省人化・自動化は「採用の補完策」ではなく、「経営戦略の一部」として本格検討すべき時代に入っている。
【第5章】即効策④|社内制度改革で「辞めさせない」
「採る」前に「辞めさせない」が最も効率的
人手不足の現場では、多くの経営者が 「新しく採用する」 ことばかりに目を向けがちだ。
だが、最も即効性が高く、かつコスト効率の良い打ち手は 「辞めさせない」=定着率の改善 である。
離職が続けば、いくら採用しても常に人が足りない状態が続く。
その悪循環を断ち切るのが社内制度改革だ。

採用よりも“今いる人を残す努力”がコスパ高いですよ。
業務分担の見直しと属人化解消策
現場でよく見かけるのが 「●●さんじゃないとできない仕事が多すぎる」 という状態だ。
属人化は、本人のプレッシャーにもなり、離職リスクを高める原因となる。
そのために有効なのが以下の施策だ。
-
業務マニュアルの整備(動画マニュアル化も効果的)
-
教育・OJTの仕組み化(新人即戦力化の加速)
-
ダブル担当制の導入(複数人で担当領域を共有)
-
スキルマップによる業務範囲の見える化
属人化が減ると、本人も周囲も心理的負担が軽くなる。
「辞めたくなる理由」を潰していくことが、実は最大の人手不足対策になる。

属人化解消は「今すぐ誰でもできる改革」なんですよ。
定着率向上のための柔軟な勤務制度・働き方改革
もう一つのカギが 働き方の柔軟化 だ。
多くの離職理由は「仕事そのもの」ではなく「働き方の融通が利かないこと」にある。
現場に導入しやすい柔軟策は以下だ。
-
短時間勤務制度の導入(育児・介護・副業との両立支援)
-
勤務シフトの自由度向上(曜日希望・固定休の導入)
-
有給休暇取得の促進(取得率を数値管理)
-
通勤負担軽減策(自宅最寄りへの配属見直し)
こうした工夫で「辞めたくなるきっかけ」を減らせば、慢性的な人手不足に歯止めがかかる。
実例:時短勤務・シフト柔軟化で定着率が向上した事例
筆者が支援したある飲食チェーンでは、常にホールスタッフが不足し、採用費が膨らんでいた。
そこで導入したのが 「1日3時間からOKの短時間シフト制度」 だった。
これにより、
-
主婦層やダブルワーク希望者が応募
-
欠勤時の代替出勤が柔軟に
-
早退・延長も現場裁量で可能に
結果、半年で 定着率が約15%向上し、採用コストも2割削減 できた。
「採る」よりも「辞めさせない」戦略の方が即効性が高かった好例である。
【第6章】まとめと感想|「人が足りない時代」の考え方を変えよ
採用一本足では、もはや限界に来ている
人手不足が慢性化している今の時代。
「人が足りないなら採用すればいい」――この考え方はすでに限界を迎えている。
求人広告を出しても応募が来ない。
来ても定着しない。
そのたびに広告費や人材紹介フィーが積み重なり、経営を圧迫していく。
現場責任者や人事担当者の多くが、いままさにこの壁にぶつかっている。

まさに「採っても採っても足りない地獄」ですよね。
経営課題としての「人材戦略設計力」が問われている
いま企業に必要なのは、採用テクニックの小手先ではなく、
経営戦略の一部としての「人材戦略設計力」 である。
ここでいう「人材戦略設計力」とは、例えば以下の視点だ。
-
採用/定着/育成/配置の全体最適化
-
業務プロセスの標準化と分業再設計
-
外部リソースの積極活用(派遣・請負・外国人・RPA等)
-
社員一人あたりの生産性最大化
つまり、「いかに人に依存しすぎない仕組みを持てるか」 が経営の生命線になってきている。
これは製造・物流・介護・建設・飲食など、あらゆる現場型ビジネスに共通する課題である。

結局、社内の“設計ミス”が人手不足を生み続けてるんですよ。
人手不足は「人材活用の視野拡大」が鍵
私は人事コンサルの立場で多くの現場を見てきた。
その中で強く実感しているのは、
「採用枠の外にも人材はいる」 という事実だ。
-
外国人材、シニア層、主婦パート、短時間労働者、副業人材
-
派遣・請負・業務委託・クラウドソーシング
-
RPA・AIなどの省人化テクノロジー
これらを 「使える経営者」 だけが、
人手不足時代でも安定した事業運営を実現している。
採用偏重の発想を抜け出せるかどうか。
今後ますます企業の「人材活用力」の差が、事業の明暗を分けていくだろう。