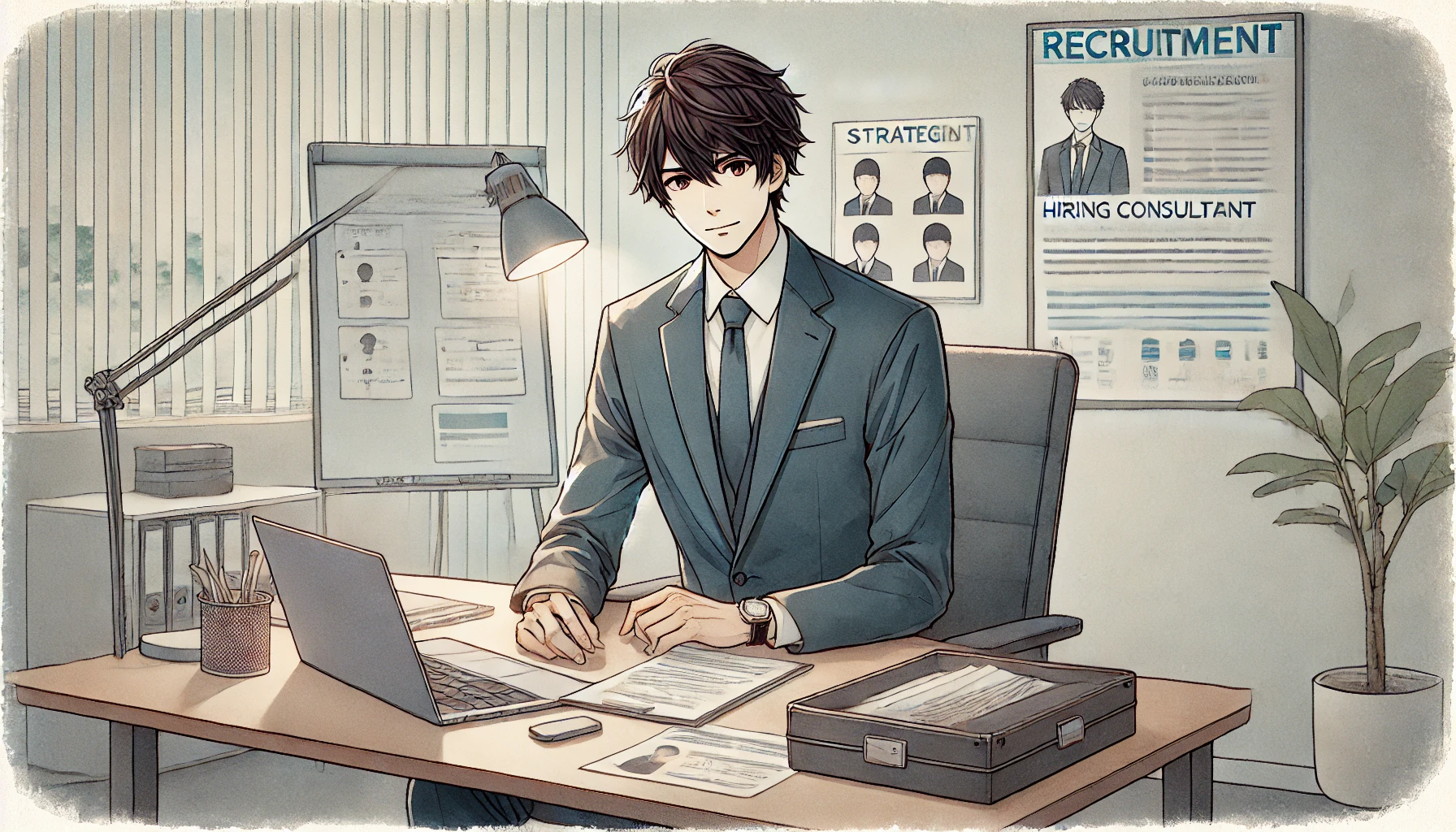「求人を出しても応募が来ない…」「いい人材と出会えない…」そんな悩みを抱える採用担当者へ。
実は、求人票の書き方ひとつで応募数が大きく変わるんです。
さらに、SNSを活用すれば、優秀な人材と効率よく出会える可能性も!
今回は、応募が集まる求人のコツを徹底解説。
今すぐ取り入れられるポイントをチェックして、採用成功へとつなげましょう!
第1章:なぜ応募が集まらないのか?原因を探る
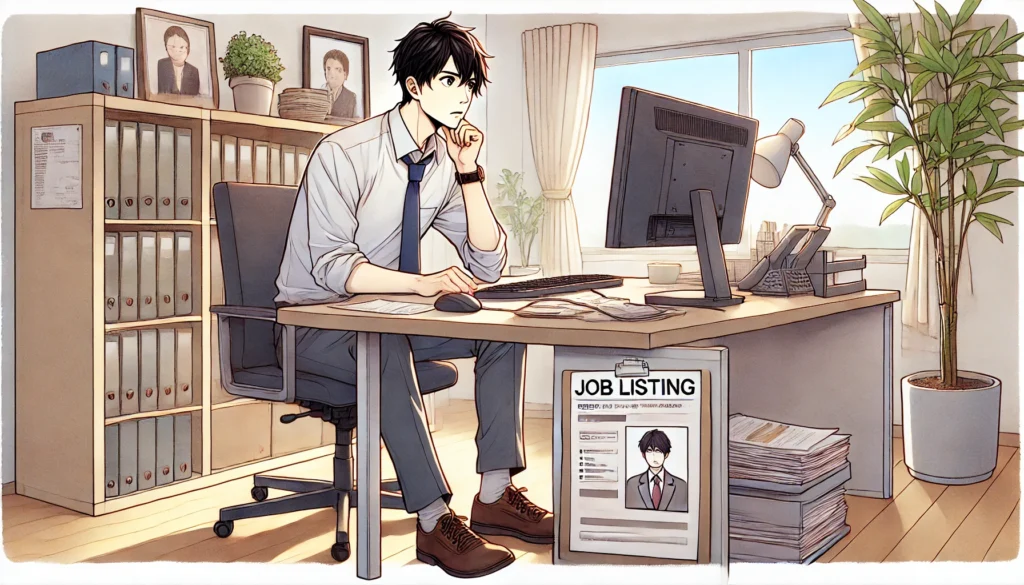
「求人を出しても応募が来ない…」よくある悩み
「人が足りない!今すぐ採用しなければ!」と焦って求人を出したのに、応募がゼロ。
そんな経験をしたことがある企業は多いはずだ。
特に中小企業では、大手と比較して人材獲得が難しいと言われる。
しかし、ただ「中小企業だから応募が来ない」と嘆くのは早い。
実は、応募が来ない企業には共通する原因がある。
「募集を出せば誰かしら来るだろう」と安易に考えている企業ほど、思い通りの採用ができずに苦しんでいるのが実情だ。
ここでは、応募が集まらない理由を明確にし、解決策を探っていく。
企業側の視点 vs. 求職者側の視点のズレ
まず、多くの企業がやりがちなミスの一つが、「自社の都合だけで求人を作成してしまうこと」だ。
企業としては「こんな人が欲しい」「即戦力がいい」と考えて求人を出すが、求職者が何を求めているかを無視してしまうと、当然ながら響かない。
例えば、以下のような求人をよく見かける。
求職者は求人を見て、「自分に合っているか?」「安心して働けるか?」を考える。
ところが、上記のような求人では自分の未来が想像できないため、応募につながらない。
一方で、求職者目線に立って考えた求人は、同じ職種でも応募が集まりやすい。

「アットホームな職場です!」って、何のアピールにもなってないんです。
失敗例:「条件だけ並べた求人」「ターゲット不明確」
鈴木太郎さん(仮名)は、都内で30人規模のIT企業を経営している。
最近、人手不足が深刻化し、プログラマーを募集することにした。
ところが、1か月経っても応募がゼロ。
「給与も市場相場に合わせているし、条件も悪くないのに…なぜ?」
鈴木さんの求人票を見せてもらった。
【求人内容】
「プログラマー募集!スキル:Java、Python、PHP経験者。勤務時間9:00~18:00、給与20万円~40万円(能力に応じる)。アットホームな職場で、チームワークを大切にしています。」
これを見て、あなたは応募したいと思うだろうか?
おそらく、多くの求職者はスルーするはずだ。
なぜなら、この求人には「ターゲットが不明確」「魅力が伝わらない」という問題があるからだ。
✔ ターゲットが不明確
「経験者」と書いているが、実務経験3年の人と10年の人では、求めるスキルが違う。
✔ 魅力が伝わらない
「アットホームな職場」ではなく、「どんな文化があるのか」「どんなチームで働くのか」を具体的に書くべきだ。
鈴木さんには、「ターゲットを明確にして、具体的な魅力を伝えよう」とアドバイスした。
応募が集まる企業の共通点とは?
では、応募が集まる企業は何が違うのか?
以下のポイントを押さえている企業は、優秀な人材を確保しやすい。
- ターゲットが明確
「新卒OK」「未経験可」「実務経験5年以上」など、誰が対象か一目で分かる。 - 仕事内容が具体的
「Webシステムの開発に携わる」よりも「ECサイトの開発を担当し、Javaを使用したバックエンド開発を行う」と書いた方が伝わる。 - 待遇や働き方を明確にする
「給与は20万円~40万円」より「月給25万円+インセンティブあり」の方が印象に残る。 - 求職者のメリットを伝える
「アットホームな職場」ではなく「週1回、勉強会を開催。最新技術を学べる」など、具体的に伝える。

求職者は「その会社で働く未来」が想像できる求人に応募するんですよね。
まとめ
求人を出しても応募が集まらない原因は、企業目線だけで求人を作成し、求職者の視点を考えていないことが多い。
✔ ターゲットを明確にする
✔ 仕事内容や待遇を具体的に書く
✔ 求職者にとってのメリットを伝える
この3つを押さえれば、求人の魅力は格段にアップする。
次の章では、「ターゲット設定」の具体的な方法について掘り下げていく。
第2章:人材募集の成功はターゲット設定から
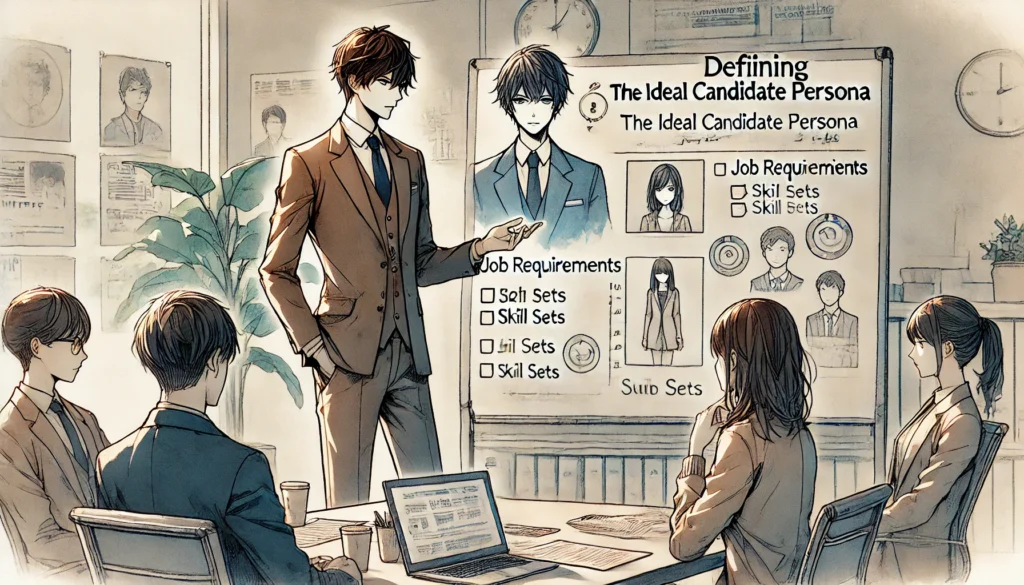
「誰に来てほしいか」が明確でない求人は失敗する
「とりあえず求人を出せば、いい人が応募してくるだろう」
そう考えていないだろうか?
もし心当たりがあるなら、今すぐその考えを捨てたほうがいい。
人材募集は、「誰でもいいから来てくれ!」ではなく、「この人に来てほしい!」を明確にすることが成功のカギだ。
ターゲットが曖昧なまま求人を出すと、以下のような問題が発生する。
- 応募が少ない(どんな人を求めているのか伝わらない)
- ミスマッチが増える(会社が求める人材と、応募者の意識がズレる)
- 採用後の定着率が低くなる(入社後に「思っていた仕事と違う」と言われる)
逆に、ターゲットが明確な求人は、求職者に「これは自分のための仕事だ」と思わせる力を持つ。
つまり、「人が足りないから募集する」のではなく、「理想の人材を引き寄せるために募集する」という意識が必要だ。

「誰でもいい」は、結局「誰も来ない」ってことなんですね。
採用ペルソナを作成するメリットとは?
採用で成功している企業の多くがやっているのが、「採用ペルソナの作成」だ。
採用ペルソナとは、簡単に言えば「自社が求める理想の人材の詳細なプロフィール」のこと。
これを明確にすることで、以下のようなメリットがある。
- 求人が魅力的になる
求職者にとって、「自分のことを求めている会社だ」と感じやすくなる。 - 応募者の質が向上する
ターゲットが明確になれば、適した人材が集まりやすくなる。 - 面接のミスマッチが減る
ペルソナに基づいた選考ができるため、「思っていた人と違う」というズレが減る。
たとえば、「即戦力のエンジニアを採用したい」と考えた場合、「経験者募集」だけでは弱い。
「Web開発経験3年以上」「PHP・Laravelを使用した実務経験必須」と明確にすることで、狙った人材が応募しやすくなる。
具体的なペルソナの作り方(年齢、経験、スキル、志向性)
では、具体的にどのように採用ペルソナを作ればいいのか?
以下の項目を細かく設定することで、「誰に向けた求人なのか」が明確になる。
✔ 基本情報(年齢、性別、居住地)
例:「30代後半~40代の男性、都内在住」
✔ 職歴・経験
例:「BtoBの法人営業経験5年以上」
✔ スキル・資格
例:「新規開拓営業経験があり、交渉力に自信がある」
✔ 仕事に求めるもの(志向性)
例:「安定よりも挑戦できる環境を重視する」
✔ 現在の悩み・転職理由
例:「現在の会社ではスキルアップが難しいと感じている」
このように具体的な人物像を想定すると、求人に何を盛り込むべきかが明確になる。
成功事例:「ターゲットを明確にしたら応募が増えた!」
ここで、実際にターゲットを明確にしたことで応募が増えた事例を紹介する。
佐藤花子さん(仮名)は、もともと大手メーカーで営業職をしていたが、成長の機会を求めて中小企業への転職を考えていた。
しかし、求人を探していても、大手企業のように具体的な情報が書かれていない中小企業の求人が多かった。
例えば、こんな求人だ。
「営業職募集!経験者優遇!アットホームな職場です!」
これでは、「どんな仕事をするのか?」「どんな経験が求められるのか?」が分からないため、応募する気になれなかった。
ところが、ある会社の求人に目が止まった。
「BtoB営業経験3年以上の方歓迎!当社はIT業界向けのマーケティング支援を行っており、提案型営業を得意とする方を募集しています。新規顧客の開拓や、長期的な関係構築が得意な方を歓迎!」
これを見て、佐藤さんは「この会社は、自分の経験を活かせそうだ」と感じ、応募を決めた。
結果として、この企業は応募数が1.5倍に増え、採用成功率も向上した。

「経験者優遇」って書いてるだけじゃ、誰にも刺さらないんです。
まとめ
人材募集の成功には、「誰に応募してほしいのか?」を明確にすることが重要だ。
✔ ターゲットが曖昧な求人はスルーされる
✔ 採用ペルソナを作成することで、求人の訴求力が上がる
✔ 成功している企業は、具体的な仕事内容や求める人物像を明確にしている
次の章では、「応募が増える求人原稿の書き方」について詳しく解説していく。
第3章:応募が増える求人原稿の書き方
求人原稿の「5秒ルール」:最初の数行で引き込め!
求人を探している求職者は、1つの求人をじっくり読むと思うだろうか?
答えはNOだ。
求職者が求人を見る時間は、平均してたったの5秒。
つまり、最初の数行で「この求人は自分向けだ!」と感じなければ、スルーされてしまう。
これを「5秒ルール」と呼んでいる。
では、5秒で引き込むにはどうすればいいのか?
- 求職者のメリットを最初に伝える
「20代未経験者が3年でリーダーへ昇格!実力主義の社風でキャリアアップ可能」 - 共感を生むキャッチコピーを使う
「スキルアップしたいあなたへ。社内勉強会&資格支援で成長を応援!」 - 「仕事のやりがい」を冒頭で伝える
「100社以上の企業の経営を支援!クライアントの成功を自分ごとにできる仕事」
ありがちなのが、最初に「会社概要」を書いてしまうパターン。
「設立〇年、従業員〇人、資本金〇円…」
これ、求職者は興味ない。
まずは「あなたがこの仕事をすると、こんな未来があります」と伝えることが大事だ。

5秒で「つまらなそう」と思われたら終わりですね。
企業の魅力を伝える「ストーリー型求人」
「当社は、〇〇業界のリーディングカンパニーとして…」
こんなありきたりな求人を見ても、求職者は心を動かされない。
そこで効果的なのが、「ストーリー型求人」だ。
✔ ストーリー型求人の例
「未経験だったAさんが、3年でチームリーダーに!」
Aさんは3年前、営業未経験で当社に入社しました。最初は商談に緊張していた彼も、先輩の指導と実践経験を積みながら成長。
今では新規顧客開拓チームのリーダーとして活躍し、後輩の指導にも力を入れています。
「社員の成長を全力で支援する」それが当社の方針です。
このように、「この会社で働くとどう成長できるのか?」をストーリー仕立てで伝えると、求職者の興味を引きやすい。
ストーリーには以下の要素を入れると効果的だ。
- 実際の社員の成長ストーリー
- 「入社前の不安 → 成長して活躍」という流れ
- 求職者が自分に置き換えやすいエピソード

「数字や条件」より「リアルなストーリー」の方が響くんですよ。
絶対に入れるべき3要素:「仕事のやりがい」「成長の機会」「社風」
求人原稿を書くときに、最低限「仕事のやりがい」「成長の機会」「社風」の3つは必ず入れるべきだ。
- 仕事のやりがい
「ただのルーチンワークではなく、課題解決型の提案営業ができる」 - 成長の機会
「未経験でも、入社3か月で即戦力に。充実した研修とOJTでスキルアップ可能」 - 社風
「チームで協力しながら成長する文化。社員同士のサポートが手厚い」
この3つを具体的に伝えることで、求職者が「自分がここで働くイメージ」を持ちやすくなる。
ありがちなNG例:「業務内容の羅列」「抽象的すぎる表現」
多くの企業がやってしまいがちなのが、「業務内容を淡々と羅列するだけ」の求人だ。
例えば、こんな求人があったとする。
「営業職募集!既存顧客対応、新規開拓、書類作成、営業事務作業」
…何をアピールしたいのか、まったく伝わらない。
また、抽象的すぎる表現もNGだ。
「やる気がある人歓迎」「頑張り次第で評価されます」
これでは求職者のモチベーションは上がらない。
NG例の改善ポイント
✔ 業務内容を具体的に
「既存顧客への提案営業が中心。顧客の課題をヒアリングし、最適な解決策を提案する仕事です。」
✔ 評価基準を明確にする
「半年ごとの成果評価で、営業成績に応じたインセンティブあり。」
成功事例:「求人原稿を改善したら応募が2倍に!」
田中商事(仮名)は、製造業向けのシステムを開発している企業だ。
彼らも以前は「営業職募集!経験者優遇!」といった漠然とした求人を出していた。
しかし、なかなか応募が来ず、来てもミスマッチが多かった。
そこで、以下のように求人原稿を改善した。
✔ 最初に求職者の興味を引くキャッチコピーを入れる
「IT未経験から3年でリーダーへ!成長を支援する営業職募集」
✔ 業務内容を具体的に記載
「お客様の業務効率化をサポートするシステムの提案営業。ニーズをヒアリングし、最適なシステムを紹介します。」
✔ 社員の成長ストーリーを追加
「前職はアパレル販売だったBさん。未経験から始めて3年でチームリーダーに。先輩の手厚いフォローがあるから、未経験でも安心です。」
結果、応募数は2倍に増加!
さらに、ターゲットに合った応募者が増えたため、採用後の定着率も上がったという。
まとめ
応募が増える求人原稿のポイントは、「求職者にとって魅力的に見えるか?」を意識することだ。
✔ 「5秒ルール」を意識し、最初の数行で引き込む
✔ ストーリー型求人で企業の魅力を伝える
✔ 「仕事のやりがい」「成長の機会」「社風」の3つを必ず入れる
✔ 業務内容の羅列や抽象的な表現は避け、具体的に書く
次の章では、「ハローワーク・求人サイト・SNS どれが最適?」について掘り下げていく。
第4章:ハローワーク・求人サイト・SNS どれが最適?
求人媒体を選ぶポイント:無料 vs. 有料、即効性 vs. 継続性
求人募集をする際、最も重要なのが「どの媒体を使うか?」という選択だ。
「とりあえず求人を出せばいい」という考えでは、費用対効果が悪くなり、採用の成功率も下がる。
求人媒体には、大きく分けて「無料か有料か」「即効性があるか継続性があるか」という2つの軸がある。
| 求人媒体 | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| ハローワーク | 無料 | 幅広い求職者にアプローチできるが、マッチング精度が低い |
| 求人サイト(Indeed・リクナビNEXT) | 有料 | 求職者が積極的に応募するため、即戦力を採用しやすい |
| SNS採用(Twitter・LinkedIn) | 無料 or 低コスト | 企業のファンを増やし、長期的な採用につなげやすい |
どの媒体が最適かは、採用する職種や企業の方針によって異なる。
では、それぞれの媒体について詳しく解説していこう。
ハローワーク:コストゼロだが求職者の層に注意
ハローワークの最大の魅力は「無料で掲載できる」という点だ。
特に中小企業にとって、広告費をかけずに求人を出せるのはありがたい。
しかし、ハローワークには以下のような特徴がある。
- 幅広い層の求職者が登録している
- 職種によっては応募が多くなる(介護・製造業など)
- 即戦力よりも未経験者や転職回数が多い人が多い
一方で、デメリットもある。
- 求職者の本気度にバラつきがある(とりあえず応募する人も多い)
- 即戦力を求める場合、マッチング精度が低い
- 職種によっては応募がほとんど来ないことも
例えば、ITエンジニアやマーケティング職などの専門職を採用する場合、ハローワークではなかなか適した人材が見つからないケースが多い。
とはいえ、「未経験でもOKな職種」や「採用コストをかけたくない場合」には、有効な選択肢になる。
求人サイト(Indeed・リクナビNEXTなど):幅広くリーチできるがコストがかかる
求人サイトは、ハローワークと違って「転職意欲の高い求職者」が集まりやすいのが特徴だ。
例えば、以下のような求人サイトがある。
- Indeed(検索エンジン型で幅広い求職者にリーチ)
- リクナビNEXT(転職者向け。即戦力採用に強い)
- doda(スカウト機能があり、優秀な人材に直接アプローチできる)
求人サイトを使うメリットは次のとおり。
✔ 求職者が積極的に応募するため、採用の確率が高い
✔ スカウト機能を使えば、優秀な人材にアプローチ可能
✔ エンジニア・デザイナー・営業職など、専門職の採用に強い
しかし、デメリットもある。
✔掲載費用がかかる(数十万円~)
✔人気のある求人に埋もれてしまうことがある
たとえば、リクナビNEXTに掲載する場合、最低でも20万円以上のコストがかかる。
また、「うちの会社は知名度が低いから、他の企業に埋もれてしまうのでは?」という懸念もある。
そのため、求人サイトを活用する場合は、「魅力的な求人原稿」を作成し、競争力を高めることが必須となる。
SNS採用(Twitter・LinkedIn・Instagram):企業の魅力を発信しながら採用できる
最近、特に注目されているのがSNSを活用した採用だ。
従来の求人媒体と違い、SNSでは「企業の魅力を伝えながら、求職者と自然に関係を築ける」 という点が大きな強みになる。
- Twitter(X):企業の文化や社員の日常を発信し、親しみを持たせる
- LinkedIn:ビジネス向けSNSで、転職意欲の高い層にアプローチできる
- Instagram:職場の雰囲気や社員の様子をビジュアルで伝えられる
SNS採用のメリットは次のとおり。
✔ 低コスト(ほぼ無料)で運用できる
✔ 企業の認知度を高め、応募につながる
✔ 求人媒体では出会えない人材と接点を持てる
しかし、すぐに効果が出るわけではなく、継続的な発信が必要になる。
成功事例:「Twitterを活用し、1ヶ月で優秀なエンジニアを採用!」
A社(仮名)は、少数精鋭のITベンチャー。
ある日、社長がTwitterで以下のようなツイートを投稿した。
「自社プロダクトの開発メンバーを募集中!小規模ながら、技術にこだわる環境です。興味ある方はDMください!」
すると、たった1日で数十件の問い合わせがあり、その中から実際に優秀なエンジニア1名を採用できたという。
なぜこの方法が成功したのか?
- エンジニアの多くがTwitterを利用して情報収集していた
- 会社の技術スタンスが明確で、共感を生んだ
- 直接DMでやり取りし、スピーディーに話を進められた
SNS採用は、うまく活用すれば求人サイトに頼らずとも、優秀な人材を確保できる可能性がある。
まとめ
求人媒体の選択は、職種・採用ニーズ・予算によって最適な方法を選ぶことが重要だ。
✔ ハローワーク:無料で掲載できるが、即戦力採用には向かない
✔ 求人サイト(Indeed・リクナビNEXTなど):コストはかかるが、応募の確度が高い
✔ SNS採用(Twitter・LinkedInなど):低コストで企業のファンを増やし、長期的な採用戦略に有効
次の章では、「応募者の質を上げるブランディング戦略」について掘り下げていく。
第5章:応募者の質を上げるブランディング戦略
企業ブランディングとは?求職者に「選ばれる企業」になる方法
人材募集で苦戦する企業の多くは、「採用は求人を出せば終わり」と考えている。
しかし、優秀な人材を採用するためには、「企業のブランディング」が欠かせない。
採用市場は、企業が求職者を選ぶだけでなく、求職者も企業を選ぶ時代だ。
「この会社で働きたい!」と思わせるには、企業の魅力を正しく発信することが重要になる。
企業ブランディングを成功させるためには、以下の3つの施策が効果的だ。
- オウンドメディアを活用する(採用ブログ・社員インタビュー)
- YouTubeやTikTokで職場の雰囲気を伝える
- 社員の声をSNSで発信する
これらの施策を活用することで、「応募の数」だけでなく「応募者の質」も向上する。

「会社を知ってもらう努力をしないと、いい人材は集まらないんです。」
オウンドメディア活用:「採用ブログ」「社員インタビュー」
オウンドメディアとは、企業が自ら運営するメディアのこと。
採用活動において、特に効果的なのが「採用ブログ」や「社員インタビュー記事」だ。
✔ 採用ブログの活用例
- 「現場社員の1日を密着取材」
- 「未経験者が3年でリーダーになったストーリー」
- 「会社の文化や価値観を伝える記事」
このようなコンテンツを発信することで、求職者が「この会社で働くイメージ」を持ちやすくなる。
また、社員インタビューを掲載することで、求職者の不安を解消し、応募の後押しができる。
例えば、こんなインタビュー記事があると効果的だ。
「異業種からの転職。未経験でも活躍できる理由とは?」
「この会社に入って、自分が成長できたと感じる瞬間」
求職者は「実際に働く人の声」を気にする。
だからこそ、オウンドメディアで「社員のリアルな声」を届けることが、応募者の質を上げるカギとなる。
YouTube・TikTok活用:動画で職場の雰囲気を伝える
テキストだけでは伝わらない会社の雰囲気を発信するには、YouTubeやTikTokを活用した動画コンテンツが有効だ。
例えば、以下のような動画が求職者に刺さる。
✔ 「1日密着!社員のリアルな仕事風景」
✔ 「社員が本音で語る!この会社を選んだ理由」
✔ 「社内イベントやオフィスの様子を紹介」
実際に動画を活用して採用に成功した企業の事例もある。
成功事例:「社内の雰囲気が伝わる動画で応募者が増えた!」
B社(仮名)は、従業員50名規模の中小企業。
以前は求人広告を出しても、応募がなかなか集まらなかった。
そこで、「社内の雰囲気をリアルに伝えよう」と考え、採用向けのYouTubeチャンネルを開設。
最初に公開したのは、「新入社員の1日密着動画」だった。
「入社1年目のAさんに密着!1日の流れをご紹介」
この動画はSNSで拡散され、再生回数が1万回を突破。
結果、動画を見た求職者からの応募が増え、3か月後には5名の採用に成功した。
動画を活用することで、「この会社で働くイメージ」がしやすくなり、結果として応募者の質が向上したのだ。

「文章だけより、動画のほうがリアルな雰囲気が伝わるんです。」
社員の声をSNSで発信:リアルな情報が信頼を生む
求職者は企業の公式サイトだけでなく、SNSでの情報もチェックする。
企業のアカウントだけでなく、実際に働いている社員が発信する情報が求職者の信頼につながる。
例えば、社員がTwitterやLinkedInでこんな投稿をすると、企業の魅力が伝わる。
✅ 「今日は社内勉強会でした!新しい技術を学べる環境が最高!」
✅ 「未経験から入社して3年、ついにリーダーに!成長できる環境に感謝!」
企業公式アカウントが発信する情報は「企業の視点」になりがちだが、社員の声はリアルで求職者の共感を得やすい。
SNSでの社員の発信を活用することで、企業文化を求職者に伝え、ミスマッチを防ぐことができる。
まとめ
企業ブランディングは、単なる求人広告の掲載ではなく、「求職者に選ばれる企業」になるための戦略だ。
✔ オウンドメディアで、企業の魅力を発信する
✔ YouTube・TikTokで、職場の雰囲気をリアルに伝える
✔ 社員の声をSNSで発信し、求職者との距離を縮める
次の章では、「面接で辞退されないための工夫」について掘り下げていく。
第6章:面接で辞退されないための工夫
採用担当者の印象で応募者の意欲は激変する
面接は、企業が応募者を選ぶ場だと思っている人は多い。
しかし、実際は 「応募者も企業を選ぶ場」でもある。
特に、転職市場で優秀な人材ほど、複数の企業と面接をしており、「どの会社を選ぶか?」の視点で面接を受けている。
つまり、採用担当者の態度や会社の雰囲気次第で、応募者の意欲は大きく変わる。
実際、応募者の約半数が、面接官の態度や企業の雰囲気を理由に辞退を決めるというデータもある(リクルート調査)。
企業側が 「面接は採用の最終関門」と思っているなら、それは間違いだ。
むしろ、「面接こそが最も重要な応募者へのアピールの場」と考えるべきだろう。

「面接官が横柄な態度だと、それだけで応募者の気持ちは冷めてしまいます。」
「面接は企業も評価されている」意識を持つべき
企業側は、応募者を評価する立場にあると思いがちだが、実は応募者も「この会社は自分に合うか?」を見ている。
特に以下のような点で企業の「評価」が決まることが多い。
- 面接官の態度や話し方
(雑談を交えながら、リラックスした雰囲気を作れるか) - 会社の雰囲気
(社員がギスギスしていないか、職場環境が整っているか) - 採用のプロセスがスムーズか
(面接後の連絡が遅い、対応が雑だと印象が悪くなる) - 仕事の魅力が伝わるか
(「どんな仕事をするのか?」が具体的に説明されているか)
応募者が感じた違和感が、そのまま辞退につながるケースは珍しくない。
例えば、こんな失敗例がある。
- 失敗例:「圧迫面接」になってしまったケース
「うちは厳しい会社だけど、やっていける?」といった圧迫的な質問をしたことで、応募者が不安になり、辞退。 - 失敗例:「面接官が会社の愚痴を言ってしまったケース」
「うちの会社、残業多いんだよね(笑)」と冗談のつもりで言った一言が、応募者に悪い印象を与えてしまった。
面接官は、「企業の顔」でもある。
応募者に「ここで働きたい」と思わせるためには、「面接の目的は口説くこと」 だと意識する必要がある。
応募者が「ここで働きたい!」と思う面接のコツ
では、どんな面接が応募者の心をつかむのか?
以下のポイントを押さえることで、面接の質が向上し、辞退率が下がる。
✔ 冒頭でアイスブレイクを入れる
「今日は暑いですね」「どのような業界を見ていますか?」など、簡単な雑談から入ると、応募者がリラックスしやすい。
✔ 会社の魅力を具体的に伝える
「当社の強みは〇〇で、他社と比べて△△の環境が整っています。」と、応募者が知りたい情報を明確に伝える。
✔ 仕事のやりがいを説明する
「この仕事のやりがいは〇〇です。実際に社員の成長事例もあります。」と、ポジティブな情報を伝える。
✔ 応募者のキャリアに寄り添った質問をする
「〇〇さんは、どんな環境で働くのが理想ですか?」と、応募者の価値観を引き出す質問をすると、好印象を持たれやすい。
特に重要なのは、「仕事の魅力が伝わる面接にすること」。
企業のことを知らない応募者に、「この仕事をやってみたい!」と思わせることが大切だ。
内定辞退を防ぐフォローアップの重要性
面接で好印象を持ってもらったとしても、それだけで安心してはいけない。
「内定を出したのに辞退された…」というケースは珍しくない。
辞退の主な理由は以下の通り。
- 他社の内定と比較して、魅力が伝わりきらなかった
- 面接後のフォローがなく、不安を感じた
- 内定までのプロセスが遅く、他社に決めてしまった
これを防ぐためには、面接後のフォローが非常に重要だ。
- 面接後、すぐにフォローメールを送る
「本日はお時間をいただき、ありがとうございました。〇〇さんの経験を活かせる場があると感じました!」と一言加えるだけで印象が変わる。 - 内定後も連絡を取り、入社までの不安を解消する
「何か不安な点はありますか?」と、フォローアップの連絡を入れるだけで、辞退率は大きく下がる。 - 社員とのカジュアルな交流を設ける
例えば、「内定者懇親会」や「先輩社員との座談会」を用意することで、入社への不安を減らすことができる。
失敗事例:「第一印象が悪くて応募者が辞退…」
C社(仮名)は、エンジニア採用を行っている中小企業。
優秀な応募者が面接に来たものの、結果的に辞退されてしまった。
理由を聞いてみると、こんな回答が返ってきた。
「面接官の態度が冷たく、雑談もなく淡々と進んだので、働くイメージが持てなかった」
C社は、この失敗を受けて、面接のやり方を見直した。
- 面接冒頭に、アイスブレイクの時間を作る
- 会社のビジョンや成長事例を、具体的に伝える
- 面接後のフォローを徹底する
その結果、内定辞退率が30%から10%に改善された。
面接は、単なる採用プロセスではなく、応募者の心をつかむ場だと考えるべきだ。

「応募者の気持ちを考えた面接ができているか、今一度見直すべきですね。」
まとめ
応募者が辞退しないためには、面接のやり方を工夫することが重要。
✔ 面接官の態度や話し方が、応募者の印象を左右する
✔ 「面接は企業も評価されている」という意識を持つ
✔ 仕事の魅力を伝え、応募者の意欲を高める
✔ 面接後のフォローアップを丁寧に行うことで、内定辞退を防ぐ
次の章では、「まとめと感想」をお伝えする。
第7章:まとめと感想
この記事で学んだことの振り返り
ここまで、「応募が殺到する人材募集のコツ」について、具体的な手法を紹介してきた。
採用活動は、「とりあえず求人を出せばOK」ではない。
むしろ、「どのように人材を惹きつけ、マッチする人材を確保するか?」という戦略的な視点が求められる時代になっている。
このブログを通じて、以下のポイントを押さえてもらえたはずだ。
- ターゲットを明確にすることで、応募の質を上げる
- 魅力的な求人原稿を作成し、求職者に刺さる情報を発信する
- 適切な求人媒体やブランディングを活用し、採用成功率を高める
これらを実践することで、「ただの人材募集」ではなく、「企業の魅力を伝え、求職者に選ばれる採用活動」へと変わっていく。
応募を増やすための3つのポイント
ここで、今回紹介した「応募を増やすための3つのポイント」を整理しよう。
① ターゲットを明確にする
✔ 「どんな人に来てほしいか?」を明確にする
✔ 採用ペルソナを作り、求職者のニーズに寄り添う
✔ ターゲットに合ったメッセージを発信する
採用活動において、「誰でもいいから応募してほしい」はNG。
むしろ、「この人に来てほしい!」とターゲットを絞ることで、求職者の興味を引きやすくなる。

「ターゲットを決めると、結果的に応募者の質も上がるんですよ。」
② 魅力的な求人原稿を書く
✔ 「5秒ルール」を意識し、最初の数行で惹きつける
✔ ストーリー型求人を活用し、企業の魅力を伝える
✔ 仕事のやりがい・成長の機会・社風の3要素を明確にする
求人原稿は、「ただの情報の羅列」ではダメだ。
求職者が「この仕事をやってみたい!」と感じるようなストーリーやメリットを伝えることで、応募率は大きく変わる。
③ 適切な媒体とブランディングを活用する
✔ ハローワーク、求人サイト、SNSなど、職種や目的に応じて媒体を使い分ける
✔ オウンドメディア・YouTube・SNSで、企業の魅力を発信する
✔ 面接やフォローアップの工夫で、内定辞退を防ぐ
「求人広告を出して終わり」ではなく、企業のブランディングを強化することで、長期的な採用力を高めることが重要だ。
たとえば、SNSやYouTubeを活用すれば、「求職者に選ばれる企業」へと変わることができる。
採用は「待つ」時代から「攻める」時代へ!
以前は、「求人を出せば応募が来る」という時代だったかもしれない。
しかし、今は違う。
- 求職者は「働く環境」を重視し、企業を選ぶ時代
- 企業は「待つ採用」から「攻める採用」へシフトすべき
つまり、「ただ求人を出す」のではなく、「求職者に選ばれるために、企業が何を発信できるか?」が鍵になる。
「うちの会社には、こんな魅力がある!」と積極的にアピールしなければ、優秀な人材は他の企業に流れてしまう。
だからこそ、採用もマーケティングの一部と考え、しっかり戦略を立てることが必要だ。
次の一歩をどう踏み出すか?
さて、ここまで読んで「よし、やるぞ!」と思った方もいるだろう。
しかし、「何から始めればいいか分からない…」という人もいるかもしれない。
そこで、まずはこの3つから実践してほしい。
STEP1:ターゲットを決める
「どんな人に来てほしいか?」を具体的に考える。
STEP2:求人原稿を見直す
ターゲットに刺さる魅力的な内容になっているかチェック。
STEP3:発信を始める
オウンドメディア、SNS、動画など、企業の魅力を発信してみる。
この3つを実践するだけでも、「応募が増える企業」へと一歩近づけるはずだ。
最後に…
人材募集は、単なる「採用活動」ではなく、企業の未来をつくる大切なプロセスだ。
「どうすれば、求職者に選ばれる企業になれるのか?」
この視点を持って、ぜひ「攻めの採用」に挑戦してほしい。
さあ、今日からできることを、一つずつ始めてみよう。