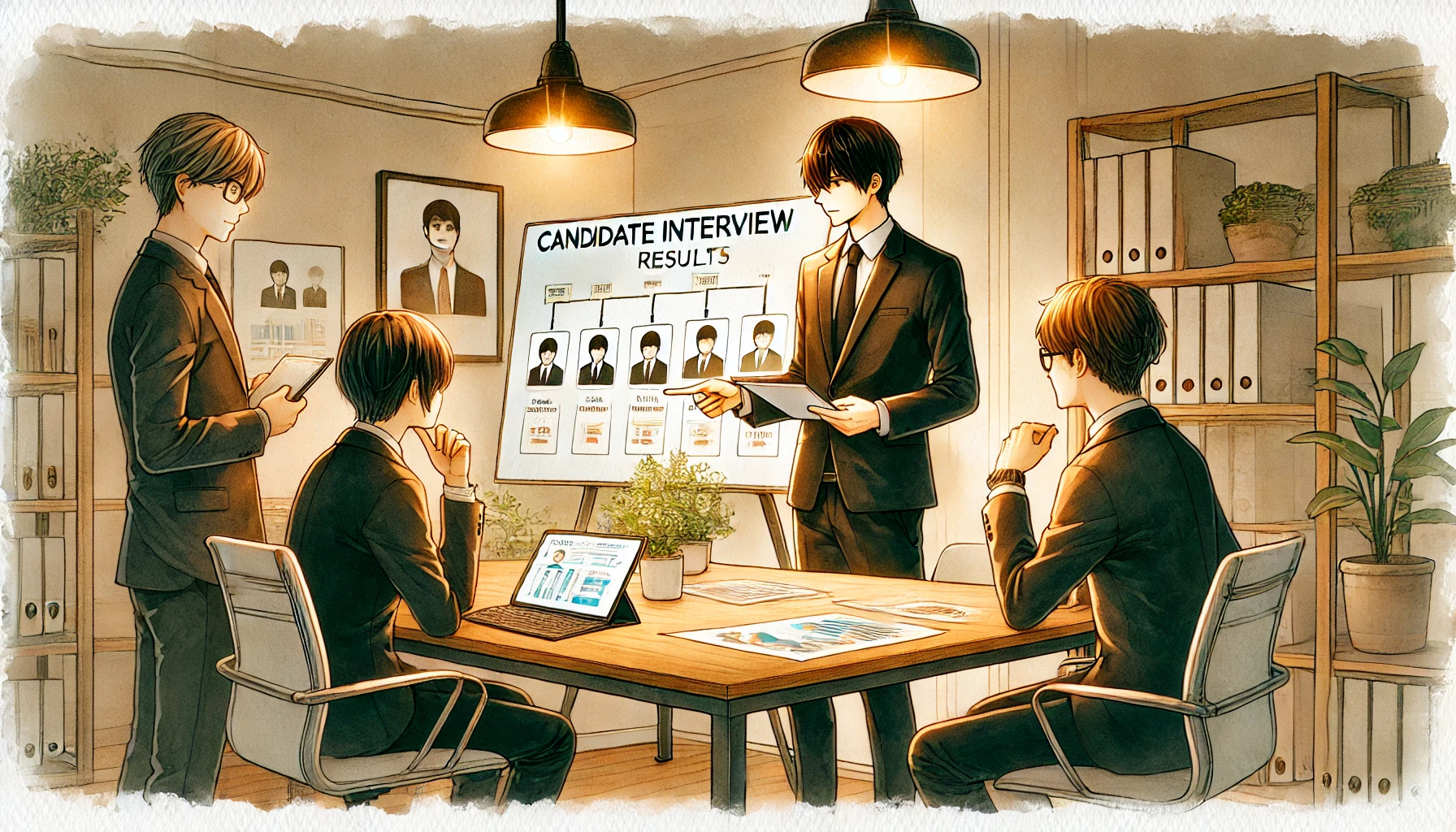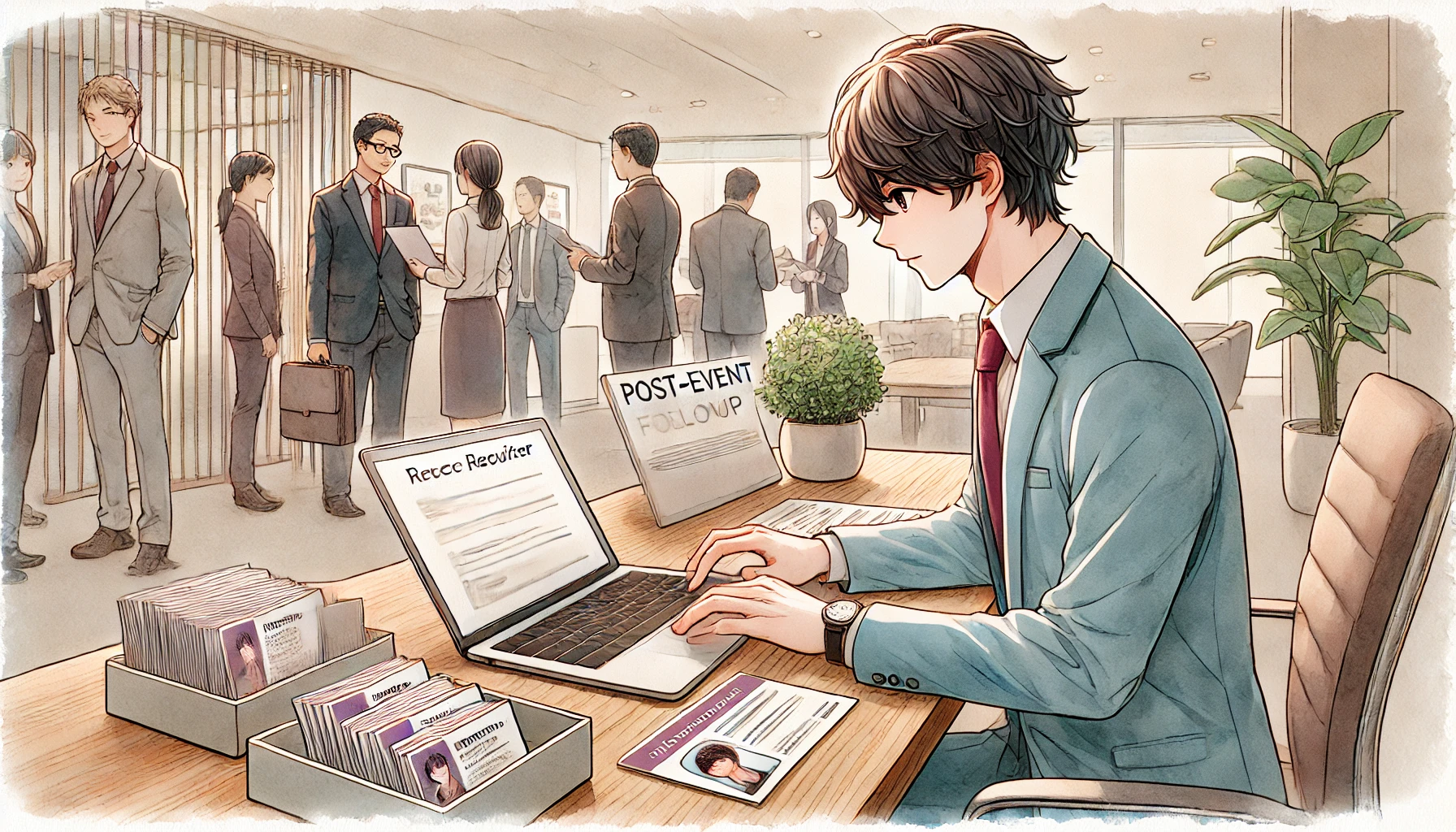「一生懸命頑張っていた」って、言われてうれしいですか?
実はそのコメント、相手に何も届いていないかもしれません。
本記事では、よくある評価コメントのNG例を取り上げ、「何がまずいか」「どう言い換えるべきか」を具体的な文例つきで解説します。
第1章:よくある評価コメントNG表現5選
なぜNGコメントは生まれるのか?
人事評価コメントでつまずく理由の多くは、「評価=義務的な作業」として処理してしまっていることにあります。
本来、評価コメントは部下への“言葉によるフィードバック”です。
それが、毎期のルーチン業務として「とにかく書けばいい」という姿勢になると、言葉が浅くなり、伝える力が失われてしまいます。
上司の“なんとなく褒めたつもり”が、部下には何も残らない。
むしろ誤解や不信感につながる。
それが、評価コメントで最も避けるべき失敗です。

書く側が義務感で書くと、読む側にもそれは伝わるもんです。
NG例①:抽象的すぎて意味がない
例:「頑張っていました」「問題なく業務を遂行していました」
一見、問題なさそうなコメントに見えます。
ですがこれでは具体性がなく、評価としての機能を果たしていません。
どの業務を、どのように頑張ったのか?
“問題ない”とは、何を基準に判断したのか?
読んだ本人が、「自分のどこが評価されたのか」を理解できなければ、それは評価ではなく“文章の空振り”です。
NG例②:上から目線で刺さりにくい
例:「よくやったほうだと思います」「まあ合格点でしょう」
このような表現は、上司が一方的に“評価者の立場”を強調してしまうパターンです。
結果として、部下に「見下された」と感じさせ、信頼を損ねるリスクがあります。
評価コメントは、“一緒に働いてきた事実”に基づいたフラットなフィードバックであるべきです。

上から目線の評価って、褒めてもなぜか反感を買うんですよね。不思議と。
NG例③:曖昧でフォローにならない否定
例:「改善の余地があります」「もっと努力が必要です」
悪い評価を書きたくない気持ちはわかります。
しかし、“意味がぼんやりした否定”は、指導にもならず、本人も何をどうすればいいかわからない。
結果として、モヤモヤだけが残ってしまいます。
指摘を避けたいなら、「どこをどう工夫すればよりよくなるか」まで言い換えるのがマネジメントの基本です。
NG例④:「いつも」や「全体的に」で逃げる
例:「いつも丁寧に仕事に取り組んでいる」「全体的に見て安定している」
こうした言葉は、一見好意的ですが、具体的な根拠がないため印象が薄くなる傾向があります。
また、部下本人にとって「いつの、どんな行動が該当したのか」が分からず、記憶にも残りにくい。
評価は“定点観測”です。
具体的な時期や成果にひもづけたコメントがあることで、受け取り手の納得感が上がります。
NG例⑤:結果のみで終わってしまう
例:「売上が前年比110%で素晴らしい」「業務量をしっかりこなしていた」
成果を評価するのは大事ですが、それだけで終わってしまうと評価が“点”になり、プロセスや努力が評価されません。
また、成果が出せなかった社員への評価が難しくなる副作用もあります。
「なぜ成果が出たのか」「どういう姿勢が支えていたのか」まで記述してこそ、部下の自己理解にもつながります。
NGコメントの共通点とは?
ここまでの5つのNG例に共通するのは、次の3つです。
-
評価の根拠が不明確(抽象的)
-
受け手の行動変化につながらない
-
“上司からの一方通行”で終わっている
評価コメントは、部下にとって「自分はどう見られているか」を知る貴重な手がかりです。
その一文が、1年間の行動を変えることもあるのです。
この章では、「ありがちだけど伝わらないNG表現」を整理しました。
次章では、それらをどう言い換えれば“伝わるコメント”に変わるのか、使える表現パターンとともにご紹介します。
第2章:そのまま言い換え!無難で伝わる表現集
“言い方を変えるだけ”で評価は伝わる
評価コメントは、内容そのものより“どう伝えるか”で印象が大きく変わります。
特に、評価に慣れていない人ほど抽象的・断定的になりやすく、それが「伝わらない」「反感を買う」原因になります。
そこでこの章では、第1章で紹介したNG表現をベースに、無難で伝わる言い換え例を紹介します。
“そのまま使える”コメントにしつつ、相手への印象をやわらげ、かつ行動につなげるフレーズを揃えました。

使う言葉が変わるだけで、評価の意味ってまったく違って届くんですよね。
NG例:「頑張っていました」
→ 具体性がなく、何を評価しているのかがわからない。
言い換え例:
「顧客対応において粘り強く改善提案を続ける姿勢が見られました」
「月初の売上が低調だった中でも、諦めずに新規開拓に取り組む姿勢が印象的でした」
NG例:「よくやったほうだと思います」
→ 上から目線かつ曖昧で、本人に刺さらない。
言い換え例:
「トラブル時にも冷静に対処し、プロジェクトの遅延を最小限に抑えることに貢献していました」
「営業活動において、常に数字だけでなくチーム全体の成果を意識した動きが印象に残りました」
NG例:「改善の余地があります」
→ 何をどう改善すればいいのかがわからない。言いっぱなしで終わる印象。
言い換え例:
「報連相のタイミングにもう少し早さが加わると、全体の調整がよりスムーズになります」
「ミスのリカバリー対応は的確なので、事前の確認ステップが加わることでミス自体が減らせそうです」

言いにくいことこそ、“具体+未来形”で伝えると、素直に受け取ってくれます。
NG例:「いつも丁寧」
→ どの場面で?何に対して?が不明。
言い換え例:
「毎月の請求業務でミスが少なく、ルーティン作業に対する丁寧な対応が安定していました」
「来客対応では、名刺交換やお茶出しのマナーも含めて、細やかな配慮が継続されていました」
NG例:「結果だけを褒める」
→ プロセスが評価されないと、他者との比較で終わる。
言い換え例:
「営業エリアごとのリスト見直しや、提案資料の工夫といった取り組みが、結果として売上向上に繋がりました」
「既存顧客へのアフターフォローが丁寧だったことが、リピート増加に貢献していました」
言い換えの鉄則は「事実+姿勢+提案」
この章で紹介した言い換え例には、すべて次の3要素が含まれています。
-
事実(何があったか)
-
姿勢・価値(どんな取り組みだったか)
-
提案・期待(どうすればさらに良くなるか)
この3つを入れることで、評価コメントは一方通行の“上司目線”から、“成長を後押しする対話”へと変化します。
次章では、さらに一歩進んで、よくある評価項目ごとに整理された例文テンプレートをご紹介します。
書くときにそのまま使える“骨格”が欲しい方は、ぜひご覧ください。
第3章:評価項目別|例文テンプレートまとめ
コメント作成を“定型化”すれば、迷わなくなる
評価コメントの悩みの多くは、「何をどう書けばいいかわからない」「言い回しに詰まる」ことです。
しかし、よく使われる評価項目に対して定型の構成とフレーズの型を押さえておけば、毎回ゼロから悩まずに済みます。
この章では、以下の5つの主要項目について、
-
「良いパターン」
-
「改善が必要なパターン」
-
「使い回し可能なコメント骨格」
をまとめてご紹介します。
① 業務遂行力
■良いパターン
「毎月の処理件数を安定して維持しつつ、納期遵守に対する意識も高く、業務に対して計画的に取り組んでいた」
■改善パターン
「突発的な業務に対しての対応にやや遅れが見られたため、優先順位付けの強化が今後の課題である」
■汎用コメント骨格
「◯◯の業務において、[成果/課題]に対して[具体的な行動]が見られた。今後は[改善・期待ポイント]が鍵となる。」
② 協調性
■良いパターン
「他メンバーとの情報共有が丁寧で、業務全体のスムーズな進行に貢献していた」
■改善パターン
「意見の発信はあるが、他メンバーへの配慮や歩調合わせがやや弱く、連携に課題が残った」
■汎用コメント骨格
「チーム内での[連携/共有/配慮]に対して、[評価すべき点/改善点]があった。引き続き[協力姿勢/視野拡大]を意識してほしい。」
③ 主体性
■良いパターン
「与えられた業務だけでなく、自ら業務改善案を出し、実行に移すなど主体的な行動が目立った」
■改善パターン
「指示された内容には対応できているが、自発的な行動や提案がやや少なく、受け身の姿勢が残っていた」
■汎用コメント骨格
「[与えられた業務/新たな取り組み]に対する[主体性の度合い]が[具体的にどうだったか]。さらなる[提案/前向きな姿勢]が期待される。」
④ リーダーシップ
■良いパターン
「メンバーの育成や進捗管理を自ら引き受け、状況に応じた指示出しやフォローが適切に行えていた」
■改善パターン
「指示は出せているものの、メンバーの意欲や状態を把握する配慮に欠け、場面によってはフォローが不足した」
■汎用コメント骨格
「チームに対する[支援/牽引]の動きが[どのような形で発揮されたか]。より[状況把握/感情への配慮]を意識することで効果が高まる。」
⑤ 課題解決力
■良いパターン
「顧客クレーム対応において、原因分析と再発防止策を迅速に実行し、対応力と改善力を発揮していた」
■改善パターン
「課題に対しての対処はできていたが、根本的な原因分析が浅く、同様のミスが繰り返される場面もあった」
■汎用コメント骨格
「[問題/課題]に対して、[対応内容や姿勢]が[どう機能したか]。今後は[深掘り/再発防止]の視点が求められる。」
汎用化で“迷わず書ける”仕組みを
評価コメントをスムーズに書くには、「定型フレーズ+具体例」の組み合わせが最も有効です。
今回ご紹介した骨格をベースに、自社の実情や本人の成果に応じて言葉を足すだけで、毎回一定のクオリティが保てます。

型があると、一気にラクになります。文章の“設計図”が手元にあるような感覚です。
次章では、こうした定型表現を“ただ書くだけ”で終わらせず、伝わる言葉にするためのコツや意識すべき順番をお伝えします。
第4章:評価コメントを“伝わる言葉”にする3つのコツ
評価コメントは「書けば終わり」ではない
評価コメントにおいて最も大切なのは、「書いたことが、部下の行動にどう影響を与えるか」という視点です。
そのためには、評価をただの“文章入力”にとどめず、伝わる工夫・伝え方の順番・未来志向を意識する必要があります。
この章では、明日から使える3つの実践コツを解説します。
コツ①:相手視点で書く(「どう感じるか」を意識する)
コメントを書くとき、つい“上司目線”に偏りがちです。
しかし、受け取るのは部下です。つまり、「どう読まれ、どう感じられるか」が最重要です。
以下のように、「読み手の解釈」を意識して書き直すと、評価の印象が大きく変わります。
▽Before(上司目線)
「営業成績が思うように伸びなかった」
▽After(相手視点)
「目標達成には届かなかったが、顧客との関係構築に粘り強く取り組む姿勢があった」
→結果だけでなく、「努力を見てくれていた」と伝わる評価に。

“自分が言われてどう感じるか”って、一度置き換えると文章が変わりますね。
コツ②:抽象→具体→事例の順で構成する
伝わらないコメントの多くは、抽象表現で止まっています。
「丁寧だった」「安定していた」では、どんな行動がそうだったのかがイメージできません。
そこでおすすめなのが、「抽象 → 具体 → 事例」の順に並べる構成です。
【構成例】
① 抽象(まとめ):「安定感があった」
② 具体(中身):「業務進行や納期管理に波がなかった」
③ 事例(根拠):「特に繁忙期の納品対応では、他メンバーの調整も率先して行っていた」
この順序にすることで、「自分がどう見られていたか」が明確になり、納得感が高まります。
コツ③:未来につながる言葉で締める
評価コメントは、“過去の出来事”を書く場ではありますが、本質的には“これからの行動”を促すメッセージでもあります。
そのため、コメントの締めくくりには、「未来への期待」や「成長の方向性」を示す一文を添えると効果的です。
▽締めの例
-
「この取り組みを継続することで、今後さらに信頼の厚い営業担当へ成長できると感じる」
-
「次のステップとして、後輩指導にも挑戦してほしい」
-
「丁寧さを維持しながら、業務スピードの向上にも期待したい」
これらの表現は、“課題指摘”にも“賞賛”にも使える万能型です。

未来へのひと言があるだけで、ただの評価が“応援”に変わる感覚、ありますよ。
「伝える」で終わらず、「届く」コメントへ
部下の行動を変えるのは、評価の点数ではなく、評価コメントに込められた“言葉の力”です。
具体性・順番・未来志向、この3つを意識するだけで、評価は「伝えっぱなし」から「届く言葉」に変わります。
この章では、評価コメントを“行動に結びつける”ための伝え方のコツをお届けしました。
次章では、本記事のまとめと、コメントを通じてマネジメントの質を上げるための考え方を実例とともに紹介します。
第5章:まとめと感想|評価コメントはマネジメントそのもの
コメントは“紙の文章”ではなく“人との対話”
評価コメントを書くとき、私たちはつい「書類だから」「様式だから」と構えてしまいがちです。
けれど本来、コメントとは一方通行の文字情報ではなく、“部下との関係性を築くためのコミュニケーション”です。
その言葉一つが、
「この人はちゃんと自分の仕事を見てくれている」
「頑張りを理解してくれていた」
「課題にも期待にも触れてくれた」
と、部下の信頼を生み出す起点になるのです。

コメントって、“伝えるため”じゃなく“つながるため”にあるんですよね。
コメントの質は、現場への理解と比例する
評価コメントには、書き手の“マネジメント精度”が如実に表れます。
的確に書ける人は、日頃から部下の仕事を観察し、理解している。
逆に言葉に詰まる人は、見ていない、関わっていない、関心が薄いというサインになってしまうことも。
部下はコメントの文面から、「この人は自分の仕事をどう見ていたのか」を敏感に感じ取ります。
だからこそ、評価コメントには“その人の仕事に対するリスペクト”を滲ませてほしいのです。
人事・管理職の役割は「伝え方を設計すること」
人事や管理職に求められるのは、人を見る力だけではありません。
同時に求められるのが、「見たものをどう伝えるか」の設計力です。
感情や印象ではなく、事実と行動を元にして、“言葉”で組み立てる力。
それが、現代のマネジメントに不可欠なスキルだと私は考えています。
そして評価コメントは、その訓練の場として最も適しています。
紙1枚、100文字ほどの言葉に、管理職としての“視点”と“責任”が詰まっているからです。

言葉にできないものは、評価してないのと同じなんですよね。そこが肝です。
筆者からのひと言|“言葉の責任”を持つ時代へ
これまで100社以上の人事制度や評価運用を支援してきましたが、現場で最も悩みが深いのが「評価コメント」でした。
評価制度の整備も重要ですが、最終的に部下に届くのは“コメントの中身”です。
制度の外枠よりも、一文一文の質が、組織を変える力を持っている。
そう確信しています。
評価コメントは、あなたの“言葉の責任”を見られる場です。
数字では測れない「信頼」や「期待」を伝える機会でもあります。
だからこそ、形式的に済ませるのではなく、「伝える・つなげる・育てる」視点で向き合ってみてください。
【最後に】
本記事でご紹介した
-
NGコメントの避け方
-
無難で伝わる言い換え例
-
評価項目別のテンプレート
-
伝える技術と順番の工夫
これらすべてが、あなたの評価コメントの“型”となり、“力”になるはずです。
評価は紙仕事ではなく、マネジメントの真髄です。
その言葉に、あなたらしい誠実さと敬意を込めてください。