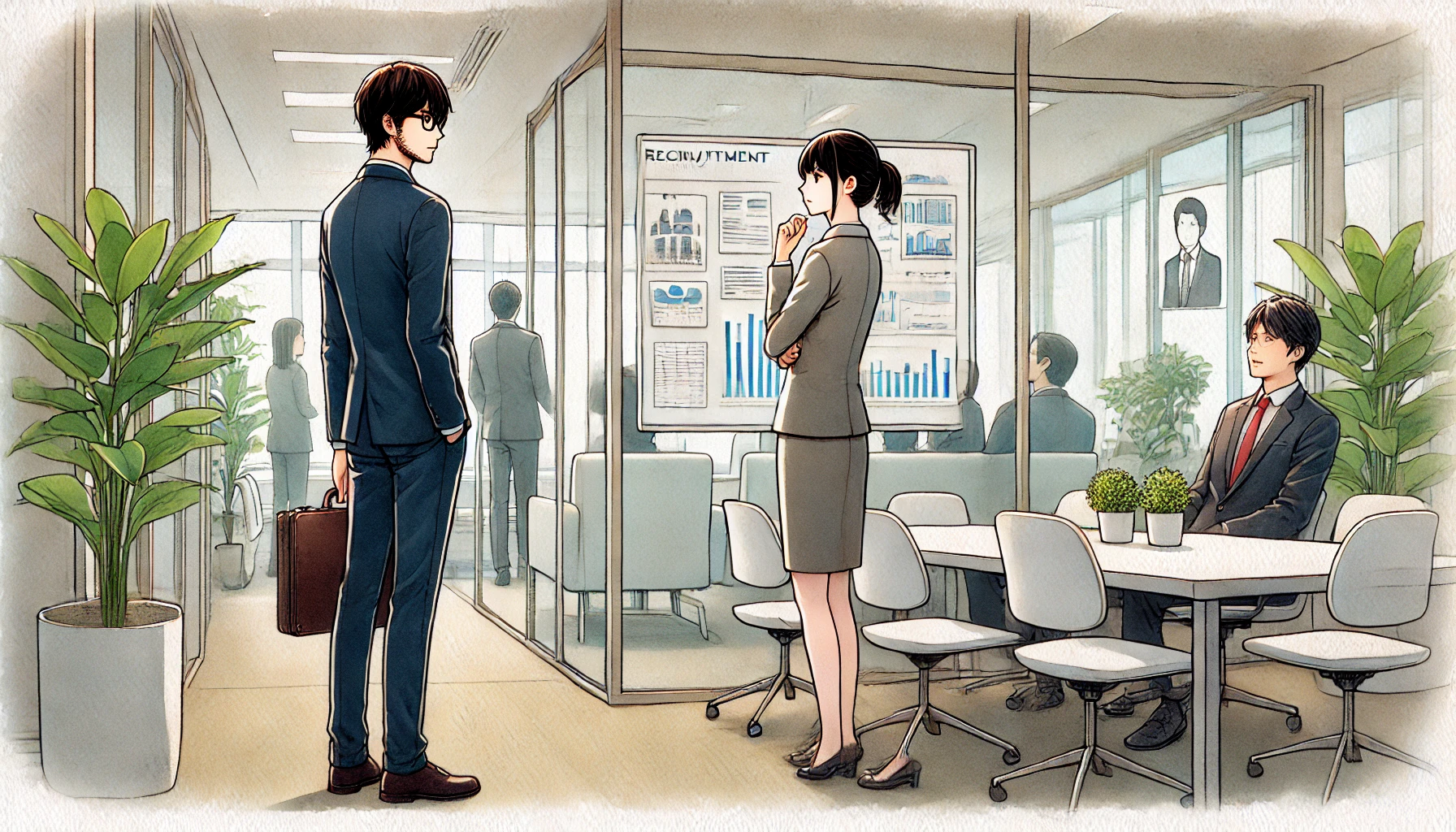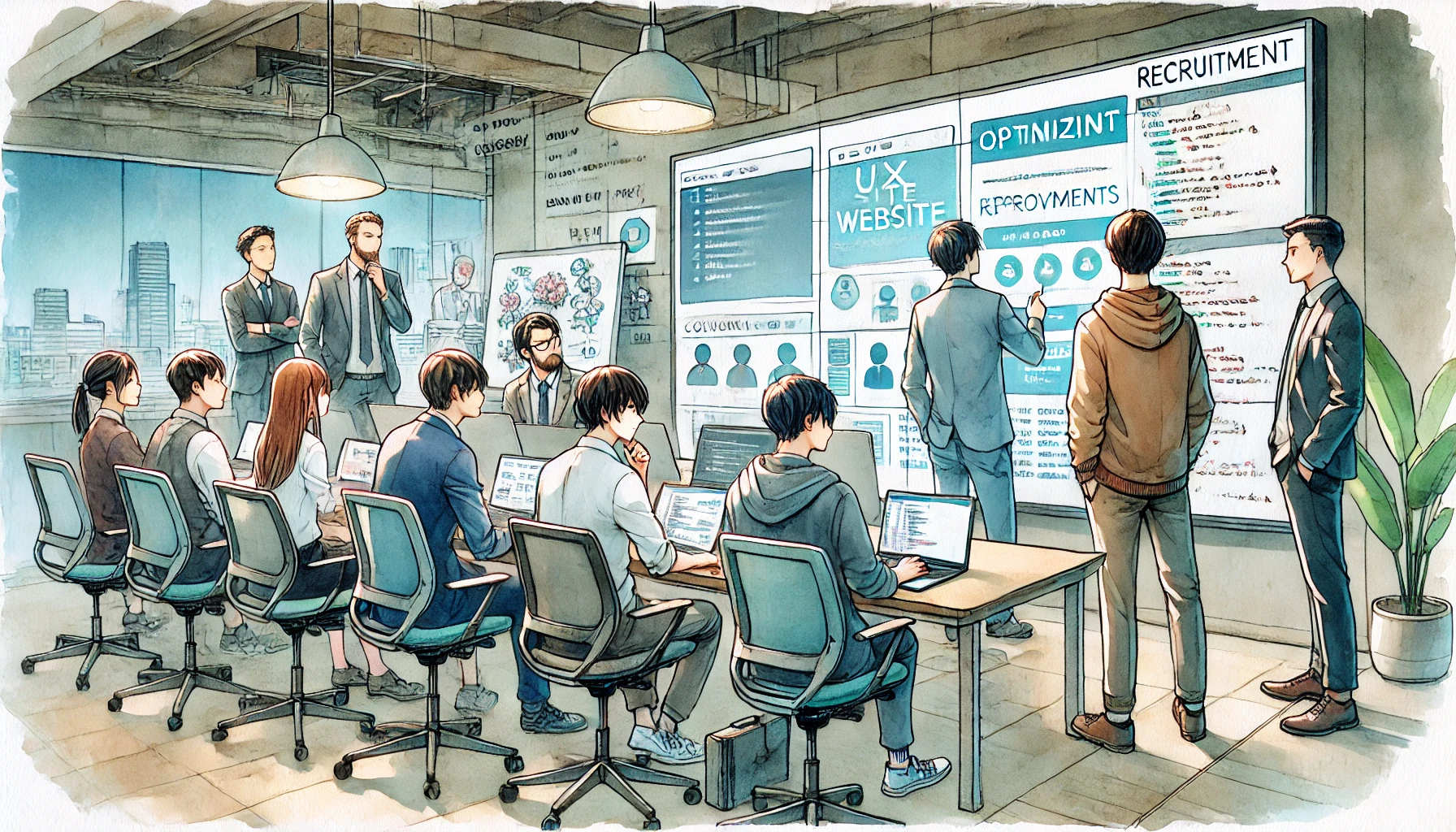「即戦力が欲しいなら中途? 未来の幹部を育てるなら新卒?」
企業の採用計画において避けて通れない「新卒と中途の違い」。
人事・採用担当者にとって、この選択は組織の未来を左右すると言っても過言ではありません。
この記事では、両者の違いや特徴を明確にし、自社の成長段階や事業戦略に最適な採用方針を見極める視点をご紹介します。
【第1章】そもそも新卒と中途の定義とは?

新卒採用と中途採用の違いを“採用側”から整理する
企業の採用活動において「新卒採用」と「中途採用」はしばしば並べて語られますが、両者の定義や制度的な違いをきちんと理解しているかというと、意外に曖昧なまま運用されているケースも少なくありません。
新卒採用とは、一般的に学校を卒業予定の学生を対象とした一括採用の仕組みを指します。企業説明会、エントリー、面接といった一連のフローを、一定の時期に合わせて実施するのが特徴です。厚生労働省の定義では「卒業後3年以内で正社員としての就労経験がない者」も“新卒扱い”とされることがあり、この点は実務上のポイントになります。
一方、中途採用はすでに社会人経験を持つ人材を対象とした通年採用です。職歴や専門スキルをもとに即戦力として期待されることが多く、ポジションや部門単位での個別採用になるのが通例です。

この3年以内ルール、意外と知られていないですよね。
制度的な境界線はどこにあるのか?
日本では新卒採用の文化が強く、特に大手企業では“新卒一括採用”が慣例化しています。その背景には、学校教育から就職へのスムーズな移行を支援する国の制度設計や、企業内の人材育成モデルが関係しています。
「卒業後3年以内の既卒者を新卒枠として扱っても差し支えない」とする厚労省の方針もありますが、これは義務ではなく“努力義務”に近いものです。実際の運用では、企業ごとの方針に委ねられているのが実情です。

努力義務って便利だけど、誤解も生みやすいんですよね。
雇用形態や待遇に差はあるのか?
雇用形態に関しては、新卒・中途ともに基本的には正社員(無期雇用)での採用が多いですが、中途では試用期間後に契約社員や業務委託に切り替えるケースも存在します。
待遇面では、初任給の設定が典型です。新卒採用は学歴ごとに一律設定されるのが一般的ですが、中途採用では「前職の給与」「職務経験」「スキルレベル」などが加味され、個別に提示されます。
この“個別交渉型”の中途採用では、評価制度や昇給ルールが複雑になりやすい点にも注意が必要です。
採用チャネルにも違いがある
新卒採用では、リクナビ・マイナビなどの就職ナビサイトを活用した母集団形成が中心です。
大学とのリレーションやインターンシップ、内定者フォローなど、接点のつくり方にも一定のノウハウが求められます。
中途採用では、dodaやビズリーチのような転職サイト、エージェント、スカウト型サービスが主流となります。また、SNS採用やリファラル(社員紹介制度)などのダイレクトリクルーティング手法も浸透しつつあります。
採用チャネルの多様化によって、「人材とどう出会うか」という視点は、新卒・中途で大きく異なるのです。
次章では、それぞれの採用方式のメリット・デメリットをより実践的な視点から深掘りしていきます。
【第2章】新卒採用のメリットとデメリット
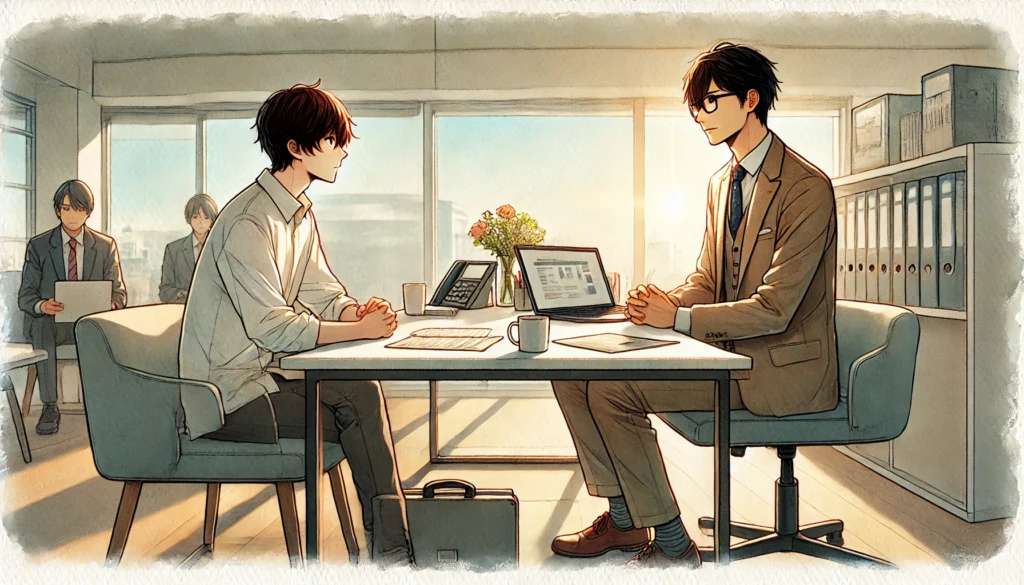
「育成前提」の人材投資としての新卒採用
新卒採用の最大のメリットは、将来の幹部候補を自社で育てられるという点にあります。
特定の知識や経験に染まっていないからこそ、自社独自の価値観や業務フローに対する吸収力が高く、「育てがい」がある存在といえます。
新卒は、就業経験がない分、良くも悪くも“まっさら”な状態です。
そこに研修・OJT・評価制度といった企業の人材育成資源を投下することで、会社の未来を担うコア人材に育て上げていく——この設計は、多くの日本企業が長年磨いてきたスタイルです。

この“まっさら”が、やっぱり一番の魅力ですよね。
社風・文化への順応性はやはり高い
新卒で入社した社員は、その会社での仕事の進め方、価値観、組織風土を“最初の常識”として身につけます。
このことが、社内の一体感やロイヤリティの醸成に大きく寄与します。
特に、終身雇用やメンバーシップ型の職場文化が色濃く残る企業においては、「一から教える」ことが前提であるため、新卒社員のほうがフィットしやすいという声も多く聞かれます。
また、新卒は社内コミュニケーションの活性化にもつながります。
先輩社員が教育に関わることで組織に“循環”が生まれ、OJTを通じて教える側の成長機会にもなります。

「教えることで学ぶ」って、現場にとっても大事な機会です。
ただし即戦力としては時間がかかる
新卒採用の最大のデメリットは、採用してすぐには戦力にならないという点に尽きます。
業界知識、社会人マナー、業務の進め方…すべてゼロから教える必要があるため、初年度は“学びの年”として捉える覚悟が求められます。
実際、育成にかかる工数やコストは相当なものです。
加えて、初期離職のリスクが常につきまとうことも見逃せません。
厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況(令和4年公表)」によれば、大卒新卒の3年以内離職率は約30%。
せっかく育成した人材が、定着するとは限らない現実があります。
採用市場での競争は年々激化している
かつては「新卒=大量採用」の時代がありましたが、現在では大手企業による新卒争奪戦が常態化しています。
特に優秀層・理系人材・IT人材といったカテゴリでは、中堅・中小企業がアプローチする前に、ナビサイトやダイレクトスカウトで先に押さえられてしまうことも珍しくありません。
また、近年は「24卒から採用広報ルールが撤廃された」影響で、企業によっては大学3年の春からインターン・説明会を展開する動きもあります。
この早期化・長期化に対応できない企業にとって、新卒採用は「コストが高い割に成果が読みにくい」選択肢になりつつあります。
次章では、中途採用の特徴とメリット・デメリットを比較しながら、新卒との違いをより明確にしていきます。
【第3章】中途採用のメリットとデメリット
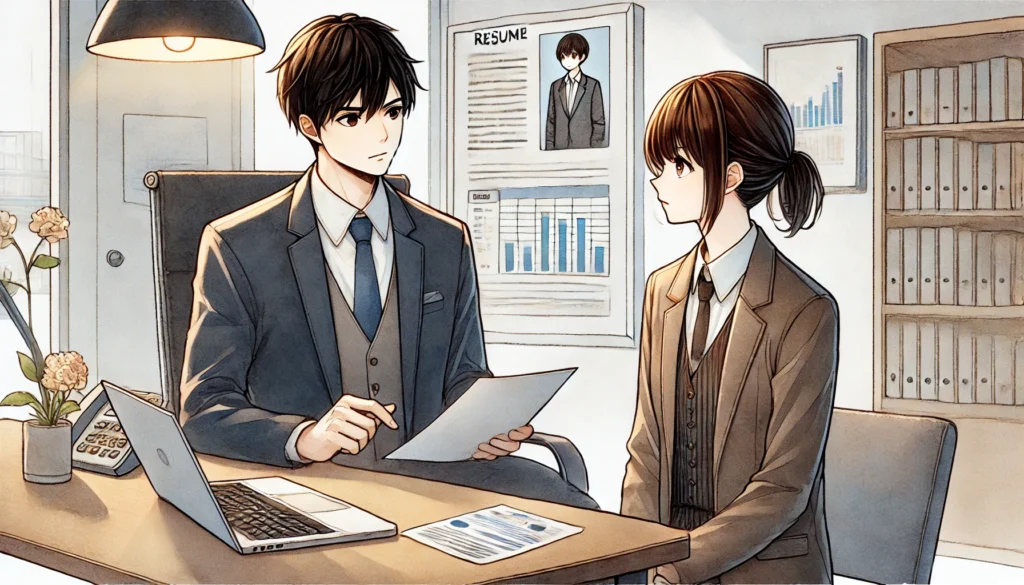
即戦力として「すぐ働ける」が最大の利点
中途採用の最大の強みは、即戦力としての導入スピードと成果期待です。
すでに業務スキルや業界知識を持っている人材を採用することで、短期間で戦力化できるのは、経営現場にとって非常に魅力的なポイントです。
例えば、営業職であれば前職での顧客対応経験、エンジニアであれば使用言語や開発環境への即応力など、実績ベースの採用判断が可能になります。
このスピード感は、新規事業の立ち上げや人員補填が急務のタイミングでこそ真価を発揮します。

「すぐ動ける人が欲しい」現場の声、よく聞きます。
適材適所を狙える経験者採用の強み
中途採用では、業務内容にマッチした人材をピンポイントで採用できるのが大きなメリットです。
新卒採用のように“将来のポテンシャル”に期待するのではなく、あくまで「いま必要な能力や経験」があるかどうかを判断軸とします。
このため、部門やポジションの空きに対し、即フィットする人材を採用できる確率が高くなるのです。
特に専門職や管理職など、ハイスキルが求められるポジションでは、新卒より中途採用のほうが合理的な選択肢となるケースが多くなります。
また、他社での経験を持つ人材が入ることで、新たな知見や業界のトレンドを社内に持ち込む効果も期待できます。

現場を知ってる人の視点って、やっぱり強いですよね。
適応への壁とカルチャーフィットの難しさ
一方で、中途採用には組織文化や価値観への適応に時間がかかるというデメリットがあります。
特に「前職のやり方」と「今の会社のやり方」が大きく異なる場合、最初の3カ月でミスマッチを感じてしまうケースもあります。
これは、「前職で培った自信」がかえって新しい職場の柔軟な対応を妨げることがあるからです。
さらに、既存社員との信頼関係づくりや社内ネットワーク構築に時間がかかるため、孤立や早期離職のリスクも無視できません。
実際、厚生労働省の「中途採用者の早期離職率データ」では、3年以内離職が3割を超える企業もあり、文化的なギャップがパフォーマンスに影響を与える事例は後を絶ちません。
採用単価の高さと人件費への影響
中途採用は、採用コスト・人件費ともに高くなりがちです。
人材紹介会社を利用する場合、紹介料は採用者の年収の30%程度が相場。
たとえば年収500万円の人材であれば、150万円の紹介料が発生する計算です。
また、中途採用者は“経験に見合った給与”を前提とするため、同職種でも新卒よりも高い給与水準を設定する必要があります。
これは給与レンジのばらつきや、社内の報酬バランスへの影響を生む原因にもなります。
さらに、採用難易度が高まる分、内定辞退や競合他社との取り合いも起きやすくなり、採用活動そのものにかかる時間と労力も見逃せません。
次章では、「新卒」「中途」それぞれの特徴を踏まえたうえで、企業がどのように採用戦略を設計すべきかを掘り下げていきます。
【第4章】採用戦略としての選択基準は何か?
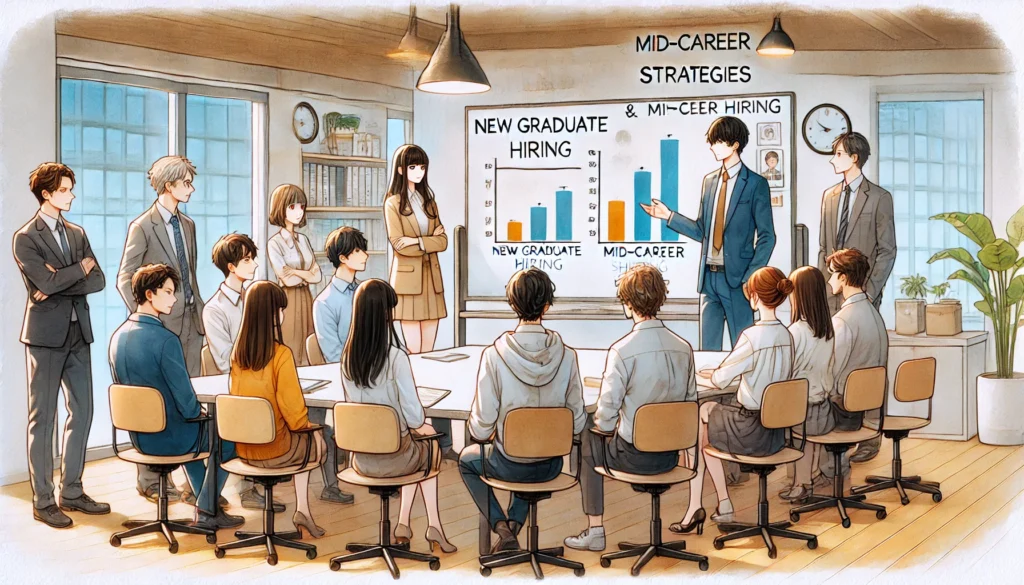
企業が「新卒」か「中途」かを選ぶ際、最も重要なのは“今、自社に何が必要か”という観点です。
どちらにもメリットとデメリットがあるからこそ、採用戦略は企業フェーズや経営課題に応じた合理的な判断軸が求められます。
創業期・成長期・安定期での違い
企業のライフステージによって、採用すべき人材像は大きく変わります。
創業期(0→1のフェーズ)
この時期は「即戦力」が圧倒的に求められます。
立ち上げメンバーに近いポジションで動ける中途人材を採用することで、プロジェクトが一気に進むことも少なくありません。
採用失敗が経営に直結するリスクもあるため、経験者による“確実な一手”が重要です。
成長期(1→10のフェーズ)
新卒と中途の“ハイブリッド型採用”が効果的なフェーズです。
中途で即戦力を獲得しつつ、新卒を数年かけて育成し将来の柱とする。
組織拡大に必要な“量”と“質”をどうバランスよく確保するかがカギとなります。
安定期(10→100のフェーズ)
安定成長を続ける中堅〜大手企業では、文化醸成や組織一体感を重視した新卒採用が軸になります。
中途採用はピンポイント補強や専門職などに限定されるケースが多くなります。

「今の組織フェーズ、ちゃんと見えてますか?」
「即戦力」か「育成重視」かという視点
採用戦略はシンプルに、“即戦力か育成重視か”という二軸で考えると整理しやすくなります。
-
即戦力が必要=中途採用
-
育成・文化づくりが目的=新卒採用
特に、中小企業やベンチャー企業は「即戦力偏重」になりがちですが、
育成投資によって長期的に利益を生む“人材の仕込み”も必要です。
逆に、大企業であっても即戦力の中途人材をチームに注入することで、変化に強い組織を作るきっかけになることもあります。

育成の“コスト”じゃなく、“資産化”と考えてみては?
採用予算・教育体制・リソースの有無
採用の選択肢は、「人・物・金」の状況によって現実的な限界もあります。
例えば、育成を重視したくても、OJT体制が整っていなければ新卒を活かしきれません。
逆に、中途人材を採っても、フォローや業務引き継ぎが甘ければ活躍の芽を摘むことにもなります。
採用にかけられる予算・教育工数・受け入れ体制の整備状況を可視化することで、
「今の自社に合った採用方法はどれか?」という現実的な判断が可能になります。
人事部門と経営陣の方針共有がカギ
採用戦略は、人事の独断ではなく、経営方針と合致していることが最も重要です。
「3年後の事業規模を見据えて新卒を仕込むべきなのか」
「1年以内に成果を出す中途人材を先に入れるべきなのか」
このような視座の共有がなければ、採っても活かせない、続かない、という悪循環に陥ります。
特に採用計画を立てる際は、経営者や部門責任者との定例ミーティングを設け、
現場ニーズと中長期戦略の両面から判断する体制づくりが必要です。
次章では、「新卒」「中途」それぞれの採用における成功事例と失敗パターンを比較しながら、より具体的な判断材料を提供していきます。
【第5章】他社事例に学ぶ「効果的な使い分け」

採用戦略には正解がありません。
しかし、同じ悩みを抱えていた企業が、どのように「新卒」「中途」を使い分け、どのような成果や課題に向き合ってきたかを知ることで、自社のヒントは必ず見つかります。
ここでは、成長ベンチャーから老舗企業、スタートアップまで、リアルな事例を紹介します。
成長ベンチャーA社:中途メインから新卒重視へ移行した理由
IT業界で急成長中のA社は、創業当初から中途採用を中心に即戦力人材を集めていました。
少数精鋭で結果を出していた一方、事業が軌道に乗るにつれて「属人化」と「文化のばらつき」が課題になったといいます。
そこで人事責任者の藤井一馬さんが動きました。
新卒採用に切り替え、「A社らしさ」を育てる幹部候補を育成する方針に転換。
2年目には人事制度を刷新し、新卒育成を組織戦略の中核に据えたのです。

ベンチャーだから新卒採らない、はもう古い発想かもです。
結果、数年かけて文化的な一体感が生まれ、離職率が改善。
現在では新卒と中途のバランスを7:3にすることで、柔軟かつ持続可能な組織運営に成功しています。
老舗メーカーB社:新卒比率80%で若手幹部育成に成功
創業50年を超える製造業のB社は、地元密着型で採用活動を続けてきました。
その中でも特徴的なのは、「新卒比率80%」という極端ともいえる構成です。
理由はシンプルです。
「技術は一朝一夕では身につかない。だから10年かけて自社で人を育てる」という、明確な哲学があったのです。
実際、現場リーダーや部長職のほとんどが20代のうちに入社した社員で構成されており、
内部昇格によって価値観の共有が組織に根付いています。

“採用は投資”という言葉を、この会社は体現していますね。
とはいえ、中途を全く採っていないわけではありません。
生産技術など専門スキルが必要な領域では、ピンポイントで中途採用も取り入れています。
スタートアップC社:中途+業務委託を戦略的に活用
創業3年目のC社は、正社員数10名ほどのスタートアップ。
資金もリソースも限られるなかで、“人を雇う”という選択肢を柔軟に考えたことが鍵になりました。
具体的には、営業・開発・マーケティングなどそれぞれの領域で、
「中途社員1人」+「フリーランス2人」というチーム編成を採用。
固定費は抑えながらも、必要な専門性と機動力を担保しています。
代表の宮田弘樹さんはこう語ります。
「中途は“推進力”、業務委託は“拡張力”。最終的に新卒を迎える体制も見据えています。」
このように、採用手段を組み合わせることが、結果的に人材戦略のリスク分散につながっている好例です。
事例に見る、混在型採用のメリットと注意点
3社の事例に共通するのは、「自社の経営フェーズと文化」にあった採用の“使い分け”がなされていることです。
新卒・中途・業務委託、それぞれに役割を明確にすることで、人材活用がより戦略的になります。
一方で、混在型採用における注意点もあります。
-
処遇格差による不満が出やすい
-
育成方針が曖昧だと、全員が迷子になる
-
評価制度が統一されていないと、組織がバラバラになる
このような問題を防ぐには、“等しく成長できる環境”と“フェアな制度設計”が欠かせません。
次章では、実際に「どのような職種・場面で新卒・中途を選ぶべきか」という実務的な判断軸を解説していきます。
【第6章】採用支援サービス・外部連携の活用法
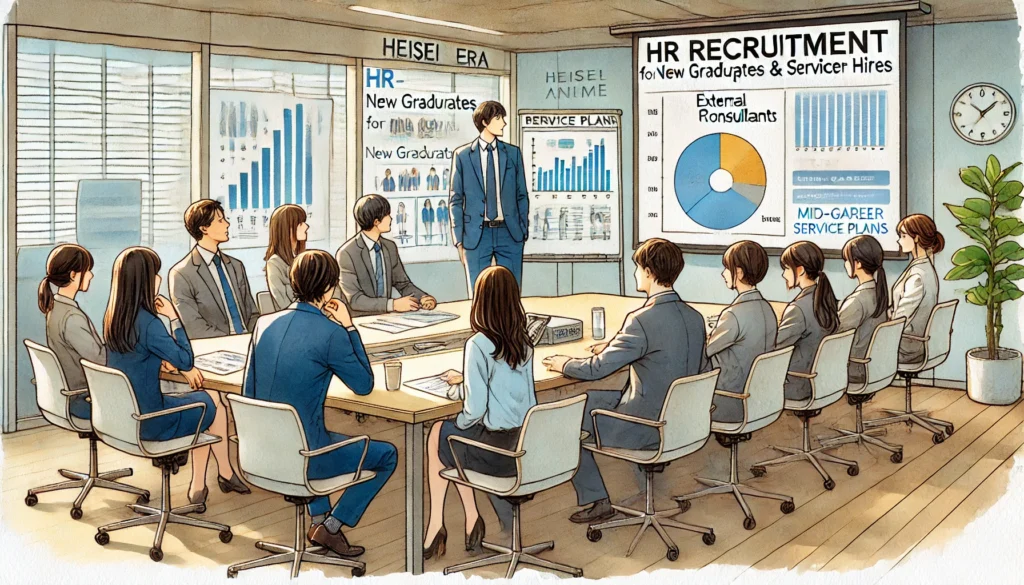
採用活動を成功させるには、社内の努力だけでなく、外部との連携が極めて重要です。
特に人的リソースが限られる中小企業やスタートアップにとっては、信頼できる外部パートナーの活用が「採れる・採れない」を左右するといっても過言ではありません。
採用コンサルや人材紹介会社との連携ポイント
まず考えたいのは、「自社に足りない採用機能をどう補完するか」です。
ここで力を発揮するのが、採用コンサルタントや人材紹介会社です。
-
採用コンサルタントは、採用戦略の設計や母集団形成、選考フローの改善まで、上流設計に強いのが特徴。
-
人材紹介会社は、実際の候補者紹介に強く、即戦力人材が欲しい中途採用で特に効果を発揮します。
連携する際に大切なのは、「自社の採用課題を具体化してから依頼すること」です。
「とりあえず良い人がいれば…」では、費用対効果が出づらく、採用の軸がブレてしまいます。

課題が曖昧だと、パートナーも動けないんですよね。
新卒採用支援サービス(例:Jobサイト、イベント)
新卒採用においては、学生との接点づくりが要です。
そこで活用されるのが以下のようなサービスです。
-
ナビサイト(リクナビ・マイナビなど)
企業情報の掲載やエントリー受付ができる定番チャネル。 -
ダイレクトリクルーティング型(OfferBox・キミスカなど)
企業側からアプローチができ、意欲の高い層と出会える。 -
合同説明会やオンラインイベント
短時間で多くの学生と接点を持ち、企業ブランディングにも寄与。
これらを活用する際は、母集団形成だけでなく“その先の歩留まり”を意識することがポイントです。
説明会で惹きつけ、選考で丁寧に見極める流れの中に、社内の魅力や文化を伝える工夫が求められます。
中途採用向けダイレクトリクルーティング活用例
近年、中途採用でも「攻めの採用」が主流となりつつあります。
ビズリーチやGreenなどのダイレクトリクルーティングを活用することで、企業は受け身から能動的な採用へとシフトできます。
特に有効なのは以下のケースです。
-
特定スキルやポジションで母集団が限られる場合
-
ブランディングよりも「想いを直接伝えたい」企業の場合
-
スピーディーに1名だけ採りたいとき
メッセージの文面、企業紹介文、社員インタビューなど、“候補者目線”の情報設計が成果のカギを握ります。

送ってる側の熱量って、意外と見透かされてるもんです。
効果的なパートナーの選び方と成果の測定基準
最後に、外部パートナーを選ぶ際に押さえるべき視点です。
【1】相性(担当者の理解力・対応スピード)
担当者が自社の業界や職種をどこまで理解しているかは、質の高い支援に直結します。
【2】過去実績(紹介数・定着率・単価)
過去にどんな企業にどれだけ人材を紹介し、どれだけ定着しているかも大事な指標です。
【3】KPIの明確化(目標CV数・面談率・採用数など)
「何人紹介されたか」だけでなく、「何人面談したか」「最終的に何人が定着したか」までを数値で追える設計にしましょう。
外部サービスはあくまで「道具」であり、使いこなすのは企業側です。
次章では、こうしたツールや支援を活かしながら、自社に最適な“採用ミックス”を考えるための実践ポイントをお届けします。
【第7章】まとめと感想|採用に“正解”はないが“最適解”はある
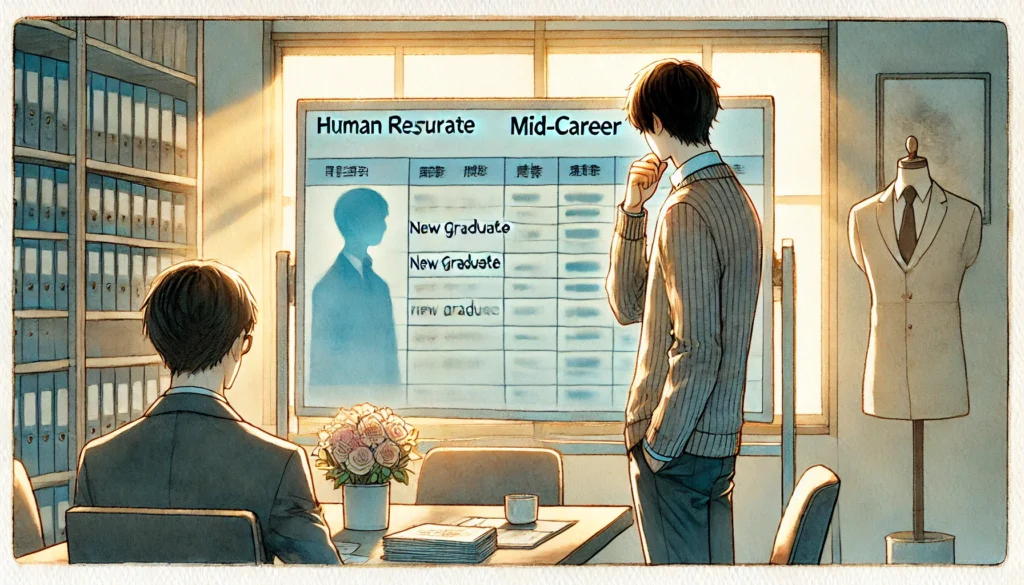
採用の世界には「絶対の正解」は存在しません。
しかし、自社にとっての“最適解”は、必ず見つけることができます。
そのためには、違いを知り、比較し、自社に合った選択を積み重ねていくことが不可欠です。
本記事の要点を総括
ここまで、新卒採用と中途採用の違いについて、定義や制度背景から始まり、メリット・デメリット、事例、外部連携のポイントまで整理してきました。
-
第1章では、新卒・中途の定義や採用チャネルの違いを明確に。
-
第2章・第3章では、それぞれのメリット・デメリットを多面的に。
-
第4章では、自社のステージに合った選び方を。
-
第5章では、実際に成果を上げている企業の事例から学び。
-
第6章では、外部パートナーの使い方と選び方を解説しました。
どちらの採用方法にも「強み」と「難しさ」があり、それらをどう組み合わせるかが“戦略”です。
今すぐ実践できる3つの行動
ここで、読者の皆さんが明日からでも動ける「具体的な一歩」を3つ挙げておきます。
① 自社の採用ニーズを明確に言語化する
採用は「とにかく良い人が欲しい」では動きません。
現場・経営の声をもとに、「どんなポジションに」「どんな成果を期待するか」を明確にしましょう。

目的が曖昧だと、採用活動はブレまくります。
② 新卒・中途それぞれの採用計画を立てる
どちらかに絞る必要はありません。
例えば「来年度は新卒2名、中途1名。新卒は秋採用に集中する」など、時期・役割・チャネルの“組み合わせ”を戦略的に設計していきましょう。
③ 外部パートナーと「戦略会議」を行う
コンサルや紹介会社に任せきりではなく、「一緒に作る」姿勢が成果を引き上げます。
現状課題や採用ターゲットを共有し、中長期のプランを描く時間をとることをおすすめします。

社外と真剣に語り合う場、意外と足りてないんですよね。
最後に:「違いを知ること」がすべての第一歩
新卒と中途。
それぞれの違いを知ることは、「どう採るか」だけでなく、「誰を、どんな想いで迎えるか」に直結します。
採用は、単なる人員補充ではなく、未来の組織をつくる“投資”そのもの。
だからこそ、目の前の1人1人に向き合う時間と考え抜く習慣が、あなたの会社を強くします。
本記事が、皆さんの採用活動における“判断軸”のヒントとなれば幸いです。