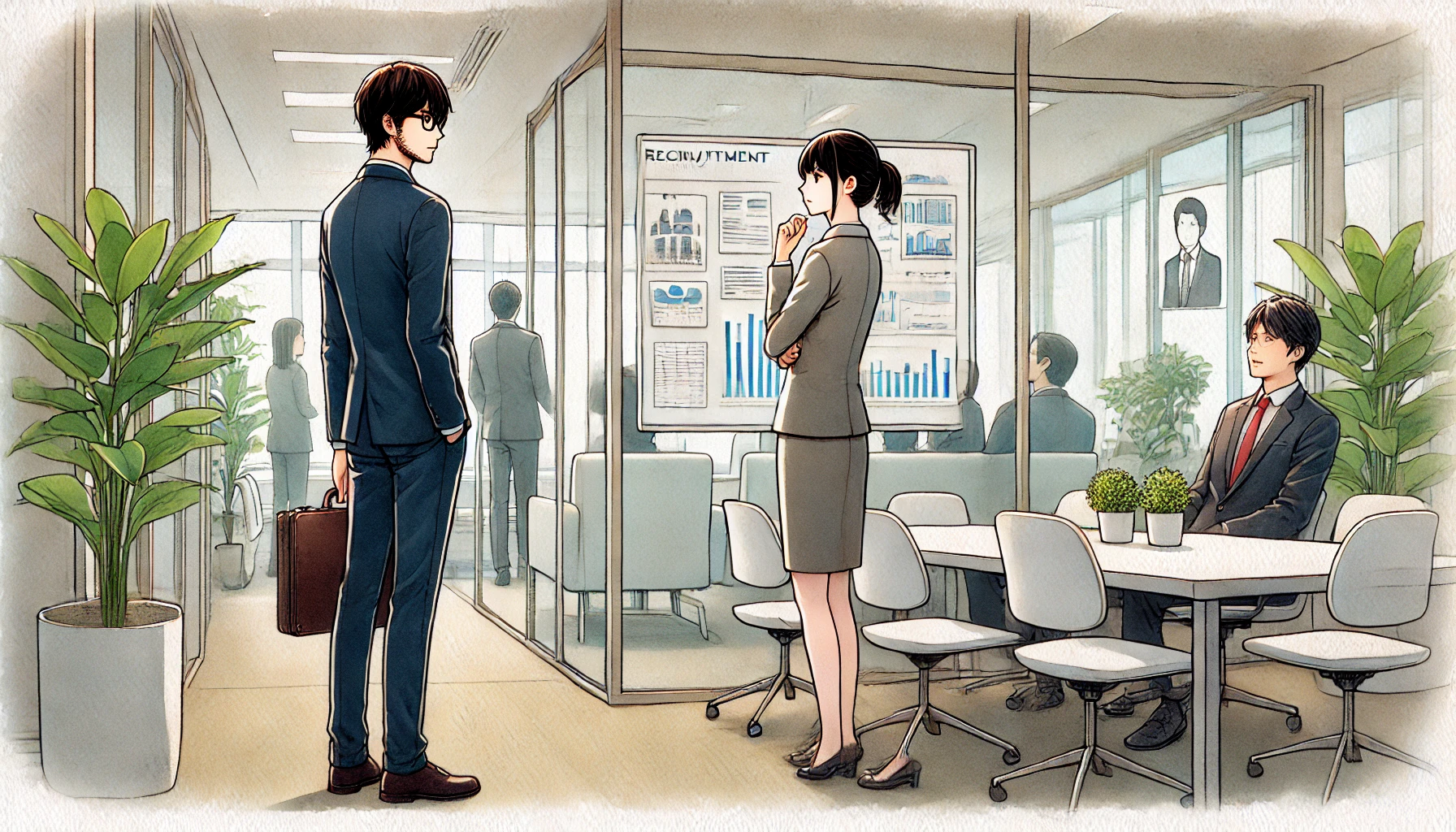「正社員にボーナスなしって、うちだけですか?」
中小企業やスタートアップの経営者から、実はよく聞くこの声。
法的な問題があるのか、社員にどう説明すべきか、不安を感じて検索している方も多いのではないでしょうか。
この記事では、賞与制度の基本から「なしでもOKにする」ための設計ノウハウ、トラブル回避のポイントまで徹底解説します。
【第1章】賞与なしは違法?法律と実務の境界線
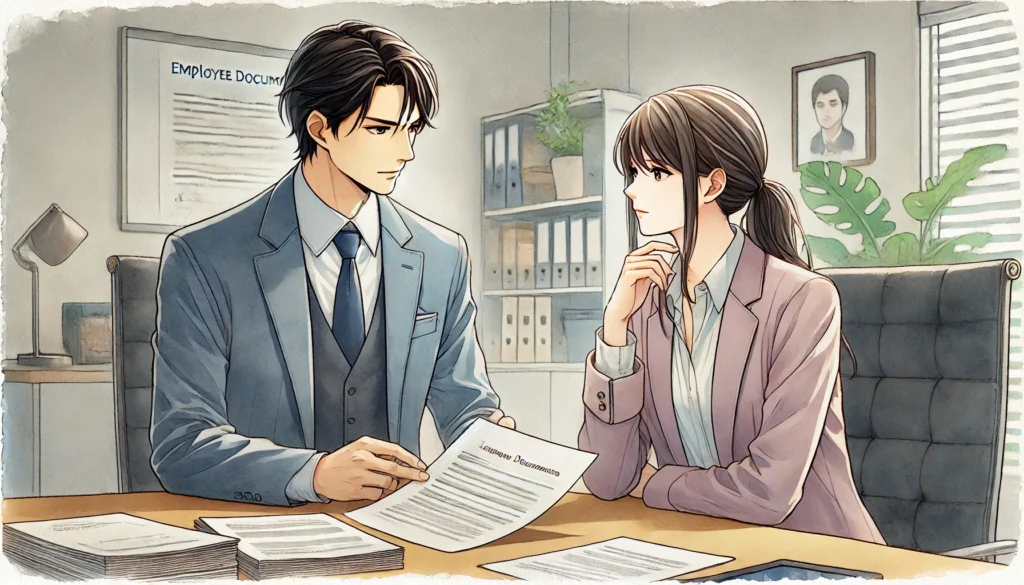
「賞与なし」は本当にダメなのか?
「正社員=賞与あり」というイメージが根強くあります。
ですが、現実には「正社員でもボーナスを出していない」企業も存在しています。
果たしてそれは違法なのでしょうか?
結論からいえば、賞与(ボーナス)の支給は法律上の義務ではありません。
これは労働基準法において、賞与が「賃金」ではなく、「任意の支給」と位置付けられているためです。
ただし、任意であるからといって「どんな扱い方でもOK」というわけではありません。
制度設計や労使間の合意がないまま「今年はゼロ」とすることは、トラブルの火種になりやすいです。
賞与の法的位置づけ|労基法と民法の観点から
労働基準法では、賞与は「賃金」の一部ではなく、あくまで“業績等を踏まえた特別手当”です。
このため、月給のように支給義務があるものではありません。
一方で、民法では「黙示の合意」による契約解釈があり、
「毎年支給されていたものが突然ゼロになる」
というケースでは、黙示の支給義務が認定される場合があります。
つまり、「賞与は任意」と言いつつも、運用次第では“義務”とみなされることがあるわけです。

うちは任意って言ってるけど、運用どうだったっけ?って焦った経験あります。
「支給義務あり」と「支給義務なし」の違い
賞与が支給義務のあるケースとは、以下のような場合です。
-
就業規則や労働契約書に明示されている(例:「年2回支給する」など)
-
長年の運用実績があり、支給が慣例化している
-
労働組合との協定等で明文化されている
これに該当する場合は、会社側の一存で「支給しない」とするのは避けるべきです。
一方で、以下のようなケースであれば「支給義務なし」と判断される可能性が高いです。
-
「業績や勤務成績を勘案し支給の有無を決定する」と明記されている
-
経営状況に応じて毎年支給有無を判断している実績がある
-
雇用契約や募集要項に「賞与なし」と明示している
判例・トラブルに見る“盲点”
裁判事例では、「賞与は任意」という企業の主張が通らなかったケースも存在します。
たとえば、過去に毎年賞与を支給していた企業が、何の説明もなくゼロにしたところ、
「労働契約の不利益変更にあたる」と判断されたケースがあります(東京地裁平成23年判決 など)。
このように、就業規則に書いている内容と、現場の運用が乖離していると、
法的リスクが生まれやすくなります。

「ゼロならゼロ」でいいけど、ルールと説明がセットじゃないと危ういです。
賞与なしにしたい企業が陥る4つの誤解
賞与を支給しない選択肢をとる企業にありがちな誤解をまとめます。
-
「正社員だから賞与は必要」という固定観念
→法律上は義務ではありません。 -
「制度に書いてなければ大丈夫」
→運用実態や過去の支給実績も判断材料になります。 -
「業績が悪いからゼロでいい」
→業績だけで説明すると納得を得られないことも。 -
「契約時に賞与について説明していない」
→説明不足が後の不満と誤解を生みます。
まとめ|「なし」なら「なし」と書く勇気を
賞与を出さないのは違法ではありません。
しかし、“どのように制度として設計し、運用しているか”が極めて重要です。
正社員だから賞与が必要――という感覚は、制度設計次第で変えられます。
その際に必要なのは、「透明性」と「ルールの整備」、そして「社内説明責任」です。
次章では、賞与なしを選択した企業の実例や、他社制度との比較を掘り下げていきます。
【第2章】賞与ゼロでも問題なし?他社制度との比較

「賞与ゼロ=違法」ではない
まず大前提として、賞与(ボーナス)の支給は法律で義務づけられていません。
つまり、正社員であっても「賞与ゼロ」は合法です。
ただし、法的に問題がないとしても、社員の納得感や制度設計の整合性は別の問題として存在します。
重要なのは、“出さない”という選択にルールと理由があるかどうかです。
合法な「賞与ゼロ」制度の実例とは?
実際に賞与なしで運用している企業は、次のような制度設計を取っています。
-
年俸制:年収を12分割 or 14分割して支給
-
月給一括制:毎月の給与に賞与分を含めて均等に支給
-
インセンティブ型:業績や目標達成に応じて手当を支給
これらの方式はいずれも、賞与を別途支給せず、「変動報酬を基本給に含めて設計」するという考え方に基づいています。

制度は変えられても、説明が変わらないと誤解されがちなんですよね。
各制度の比較ポイント|メリットと留意点
| 制度 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 年俸制 | 年収が明確。評価との連動もしやすい | 賃金台帳への反映が複雑になりやすい |
| 月給一括方式 | 手取りが安定。事務負担が少ない | 「ボーナスがない」という印象が残りやすい |
| インセンティブ型 | 成果を評価しやすい。やる気につながる | 不公平感が出やすく、基準設計が難しい |
それぞれに一長一短があります。
企業の文化や社員構成に応じて、「どれが納得されやすいか」という視点が重要になります。
就業規則に記載する際の注意点
制度設計と同時に不可欠なのが、就業規則や雇用契約書への明記です。
この記載が曖昧なままだと、後々「聞いてない」「期待していた」というトラブルにつながります。
最低限、以下のポイントを記載しましょう。
-
賞与が支給されるかどうか(任意か否か)
-
支給対象期間・査定方法(ある場合)
-
「賞与なし」の明示(制度上存在しないこと)
とくに「業績等に応じて支給することがある」といった曖昧な表現は避けるべきです。
明確な方針を示すことで、社員の誤解や不信感を防げます。
記載例:「支給しないこと」を明確に示す文言
以下は、実務で活用されている記載例です。
【賞与規定】
当社は、賞与の支給制度を設けておりません。
年間報酬は月例給与により支給され、賞与は支給の対象とはなりません。
あるいは、
【賞与規定】
賞与は業績や勤務成績を総合的に勘案して支給する場合があります。
ただし、支給の有無および額について会社が最終的に決定します。

ここまで書いておけば、説明の負担が格段に減るんですよね。
まとめ|「賞与ゼロ」は制度設計次第で“武器”になる
賞与なしという選択は、法的に問題がないだけでなく、制度として納得感を持たせることも可能です。
その鍵となるのが「制度の透明性」と「規定の明確さ」。
そして、何よりも大切なのは、社員との信頼関係を損なわない説明力です。
次章では、こうした設計を取り入れてうまく運用している企業事例を紹介していきます。
【第3章】賞与を支給しない理由が社員に通じるか?

「不公平」と感じる瞬間はいつか?
賞与制度がない企業で、もっともリスクとなるのが社員の不満です。
特に「正社員なのに」「知人の会社では年2回出ている」といった比較ベースの不満は根強く、対応を誤ると離職やモチベーション低下につながります。
では、どのような状況で「不公平」と感じられてしまうのでしょうか?
代表的なケースは次のとおりです。
-
隣の部署の待遇と比較される
-
面接時に「年収はこれくらい」と言われたが、賞与がなかった
-
インセンティブの支給基準が不明確
このようなケースでは、「納得していない」状態が社内に静かに広がってしまいます。

“不満”よりも厄介なのが、“静かな不満”なんですよね。
賞与に対する社員の期待と心理
賞与には、単なる金銭的報酬以上の意味があります。
それは、「評価された」という実感です。
定期的に支給される基本給とは異なり、賞与は「ご褒美」「評価」「節目」の象徴でもあります。
このため、賞与がゼロでも制度設計がしっかりしていれば納得される一方、説明が足りないと誤解が膨らみやすいのです。
さらに、「賞与は出て当然」という刷り込みは、就職情報サイトやSNSを通じて若手社員に広く浸透しています。
納得感を得るための制度説明と社内広報
賞与なしの制度を導入・維持するには、丁寧な説明と社内広報が必須です。
とくに以下の点を意識することで、納得感が高まります。
1. 制度の意図と背景を明示する
たとえば「当社では賞与をなくし、その分を毎月の給与に反映しています」といった形で、“合理性”を伝えることが重要です。
2. 人事評価との連動を説明する
インセンティブや年俸に含まれているなら、「こういう成果が給与に反映される」と説明すれば、“納得できる筋道”が見えてきます。
3. 面談や社内資料で繰り返し伝える
人事制度に関する説明は、1回で伝わるものではありません。
評価面談や社内マニュアル、社内報などを活用し、“繰り返し・定着”を意識しましょう。

1回の説明で伝わるなら苦労しないよなって、つい思います。
【実例】「うちはなぜ賞与がないのか」社員に納得された伝え方
ある製造業の中堅企業では、年俸制を導入しており、賞与は制度上存在しません。
しかし、新卒社員から「ボーナスはありますか?」という問い合わせが相次ぎ、現場で説明対応に追われていました。
そこで人事部では、制度説明用のスライド資料を新たに作成。
そこには以下のような文言が掲載されています。
「賞与」はありませんが、年俸に含めて月々の給与に均等配分しています。
評価は半期ごとに反映され、昇給のタイミングに加味されます。
成果が出れば、月給が増えていく仕組みです。
この資料を研修時に配布するようにした結果、“最初から納得して入社してくる人”が増えたとのことです。
制度そのものではなく、「どう伝えるか」が大きな分かれ目になります。
まとめ|「納得される制度」は設計と伝え方のセットで完成する
賞与なしの制度でも、社員が納得して働いてくれる組織は存在します。
その違いは、「制度の中身」だけではなく、“伝え方と継続したコミュニケーション”にあります。
次章では、実際に賞与制度を持たない企業の具体的な事例をご紹介します。
あなたの会社に活かせるヒントが、きっと見つかるはずです。
【第4章】制度設計の選択肢|代替制度をどう考えるか

「ボーナスなし」の代わりにできる設計とは?
賞与を支給しない方針を採用する場合、その“代わり”となる制度設計は避けて通れません。
制度が存在しないことへの不満ではなく、「評価や成果に対する見返りが感じられない」ことが不満になるからです。
この章では、賞与に代わる3つの主な制度設計とその特徴、導入時の注意点、そして組織全体への影響までを解説していきます。
年俸制・業績連動給・報奨金制度の特徴
年俸制(Annual Salary)
年俸制とは、1年単位で報酬を決め、12分割・16分割などで支給する制度です。
「賞与はなく、すべて月額給与に含む」スタイルが一般的で、制度的にはシンプルかつ透明性が高いのが特徴です。
設計例:
-
年俸600万円 → 月額50万円×12か月
-
昇給は年1回、評価制度と連動
注意点:
-
途中退職・長期休職時の対応設計が必要
-
成果が反映されにくい印象を持たれることも
業績連動給
企業業績や部門業績に応じて支給額を変動させる制度です。
いわば賞与の“成果連動型バージョン”で、組織全体のモチベーションを引き出すことが可能です。
設計例:
-
経常利益が前期比110%を超えた場合、全社員に月給×0.5を支給
注意点:
-
業績悪化時の納得感を担保する説明が必要
-
「管理不能な指標」に依存しすぎると逆効果
報奨金制度
特定の成果・行動に対して個別に報奨金を支払う制度です。
例えば新規契約獲得、資格取得、紹介採用などへのスポット報酬として活用されます。

営業職だと報奨金って“ニンジン”としてすごく有効なんですよね。
設計例:
-
月間売上目標120%達成 → 1万円支給
-
IT資格取得 → 2万円支給
注意点:
-
あくまで「おまけ」として設計し、ベース給与と混同させない
-
公平性・透明性が求められる
成果報酬型インセンティブ導入の注意点
成果報酬は社員のやる気を引き出す強力な手段ですが、導入の仕方を誤ると逆に不満の温床になります。
注意すべきポイントは次の通りです。
-
評価基準は数値+行動で設計する
売上だけでなく、プロセスやチーム貢献も評価対象に。 -
成果=支給のルールを明文化する
曖昧な基準ではなく、「どうすれば得られるか」を明示。 -
属人的な判断は排除する
上司の“主観”で変わる制度では納得されません。

「なんであの人だけ?」って声、絶対出てくるんですよね。
福利厚生・昇給制度とのバランスをとる
賞与の代わりにインセンティブや報奨金を取り入れる場合、トータルリワード(総報酬)設計の視点が重要になります。
特に意識すべきは次のポイントです。
-
基本給が上がりづらい設計にしない
→ 将来的に「生活が安定しない」と感じさせないよう注意 -
福利厚生で“安定性”を補完
→ 賞与はないけど、社宅・ランチ補助・研修充実で安心感を提供 -
昇給ルールも明確にする
→ 賞与がない代わりに「昇給率で還元する」方針を周知
これらをバランスよく整えることで、「賞与なしでも安心して働ける職場」に近づきます。
採用広報・モチベーションへの影響
最後に、制度の“伝え方”と“見せ方”にも触れておきましょう。
採用サイトや説明会で「ボーナスはありません」とだけ伝えると、求職者の印象は確実に悪くなります。
そこで大切なのが、次のような表現です。
-
「年俸制を採用しており、月額給与にすべて含んでいます」
-
「成果に応じた報奨制度があり、年1回の表彰制度も充実」
-
「ボーナスがない代わりに、昇給・評価制度を丁寧に運用しています」
制度は中身も大切ですが、伝え方次第で“納得感”も大きく変わります。
まとめ|“賞与の代わり”は制度の工夫でいくらでも設計可能
「賞与がない=悪」ではありません。
重要なのは、「何が代わりにあるのか」「どう設計されているのか」「どんな意図があるのか」を明確に伝えることです。
次章では、実際に賞与を設けずに制度設計で成功した企業の事例をご紹介します。
実務に落とし込むヒントを、ぜひ掴んでください。
【第5章】就業規則・雇用契約に明記すべきポイント
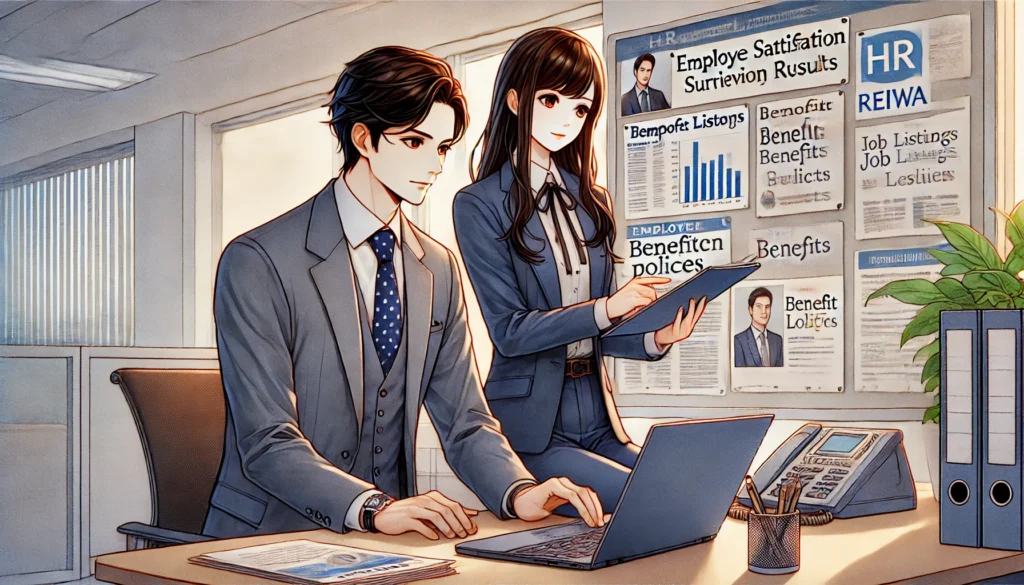
賞与を支給しない場合でも、また支給するとしても、その「扱い」を書面で明示しておくことはトラブル防止の観点から不可欠です。
この章では、就業規則や雇用契約書において明記すべき賞与関連のポイントや文例、そして実務で役立つ工夫を、社労士・弁護士との連携の視点も含めて整理していきます。
トラブルを防ぐ記載文例|基本は「支給の約束はしない」
賞与に関するトラブルで多いのが、「支給されるはずだったのに出なかった」という社員の誤解です。
これを防ぐためには、「原則として支給義務はない」ことを明文化する必要があります。
以下はよく使われる文例です。
<記載例(就業規則・雇用契約書共通)>
賞与は、会社の業績、本人の勤務成績等を総合的に勘案して支給の可否および金額を決定する。
賞与の支給はこれを保証するものではない。
この一文があるかどうかで、万が一の労使紛争リスクが大きく変わります。

「期待だけさせて出さない」状態がいちばん危ないんですよね。
「業績等を勘案して決定」だけでは不十分?
多くの企業が「賞与は業績等を勘案して…」と曖昧に記載していますが、この一文だけでは支給義務の否定が不十分な場合があります。
なぜなら、「これまでは毎年出していた」「上司が出ると言っていた」などの“黙示の期待”が成立してしまうと、義務があると見なされることがあるからです。
そこで重要になるのが次の一文の追加です。
<追加文例>
なお、支給実績がある場合においても、将来の支給を約束・保証するものではない。
これにより、過去の支給があっても、それが恒常的な権利ではないことを明確にできます。
経営が厳しい企業が採用している条文の工夫
資金繰りが常に読めない業種(飲食・建設・小売など)では、より柔軟な賞与設計を目指して、以下のような条文を採用しているケースがあります。
<柔軟な運用を想定した記載例>
会社の業績および経営状況を踏まえ、取締役会の決議に基づき支給の可否および支給額を決定する。
また、特定の部門・個人に対して支給する場合がある。
これにより、「全社員一律ではなく、状況に応じて選定・変動させることがある」という柔軟な運用が可能になります。

あくまで“支給の可能性”であって、“権利”ではないって線引きが大事なんです。
顧問社労士・弁護士と連携してチェックすべき点
賞与に関する条文を整える際は、社労士や弁護士との連携が不可欠です。
以下の観点からチェックを行うことが推奨されます。
チェックポイント:
-
就業規則・雇用契約に文言の矛盾がないか
-
他の規程(給与規程・人事評価規程等)との整合性が取れているか
-
過去の支給履歴との関係で、「暗黙の慣行」と見なされる余地がないか
-
従業員説明時の運用文書・説明資料にブレがないか
また、もし賞与制度の廃止・変更を予定している場合は、労働条件の不利益変更に該当する可能性があるため、慎重な進め方が求められます。
明文化=防衛線。曖昧さこそリスクになる
賞与を支給しない制度は、法律上“あり”です。
しかし、明文化されていなければ、後々“なし”が“あるべきだった”と主張されかねません。
制度は「作ること」よりも「どう書いて、どう伝えるか」が重要です。
そして、それが社内の納得を生み、トラブルを未然に防ぐ“盾”になります。
次章では、実際に賞与支給をやめた企業のリアルな事例と教訓を紹介します。
【第6章】スタートアップや中小企業に多い誤解と落とし穴

「今は余裕がないから、とりあえず賞与制度は後回し」
スタートアップや中小企業でよく聞くこの考え方。
ですが、これが制度設計上の大きなリスクになるケースが少なくありません。
この章では、創業初期や規模が小さい企業がやりがちな「賞与にまつわる誤解と落とし穴」について、実例を交えて整理します。
「賞与制度はあとで決めればいい」は本当に正解?
設立初期の企業や小規模組織では、「今はまだ人件費に余裕がないし、あとで賞与制度を整えればいい」といった判断がなされがちです。
たしかに合理的な面もありますが、制度が曖昧なまま運用を始めると、あとで“誤解”や“期待”を生む元になります。
たとえば、以下のような発言は要注意です。
-
「いずれ業績が出たらボーナスも出すよ」
-
「今期は厳しいけど、来期は何か出したいね」
これらの“前向きな言葉”が、のちに「約束された賞与」と認識され、トラブルにつながることもあります。

気軽な一言が“法的拘束力”を持ってしまうこと、意外と多いんですよね。
「賞与あり=0円」パターンが招く信頼崩壊
「賞与あり」と求人票や面談で伝えていたものの、実際には0円支給が続く。
こうしたパターンも、企業にとっては致命的です。
企業側からすれば「業績が厳しいから仕方ない」と言いたくなりますが、社員から見れば「約束されたのに裏切られた」という感情が強く残ります。
結果、SNSや口コミサイトでのネガティブな発信につながることも。
特に、採用広報で「インセンティブあり」「成果次第でボーナス支給」とうたっていた場合は、実態が伴わないと虚偽表示とみなされかねません。
VC・投資家が気にする「報酬設計の透明性」
スタートアップで資金調達を進める場合、投資家が注視するポイントの一つが“報酬制度の透明性”です。
たとえば、以下のような観点が見られます。
-
フェアな報酬体系が整っているか
-
経営層と現場の報酬バランスに偏りがないか
-
評価と報酬の整合性があるか
賞与やインセンティブ制度が不明確だったり、経営者の裁量で曖昧に運用されていたりすると、信頼を損なう材料になります。
また、従業員向けの説明不足が離職や人材流出を招き、それが組織の安定性に疑問を持たれることもあるため要注意です。
【リアル事例】制度を曖昧にして失敗したケース
あるスタートアップ企業(A社/従業員15名)は、創業初期に「業績が良ければボーナスを支給」とだけ社内口頭で説明。
実際には創業3年間、賞与は一度も支給されず、制度設計も不在でした。
結果、社員のモチベーションは低下し、エンジニアが一斉に退職。
「口約束だけで、評価制度もボーナスもなかった」と口コミに書かれ、採用活動にも悪影響を及ぼしました。
後から制度を整えようとしましたが、既に社内の信頼が崩れており、回復には時間がかかりました。

“その場しのぎ”の報酬設計が、一番コスト高になるって話、よくあるんですよね。
明文化・設計・説明、この3つが不可欠
賞与を支給しないのは合法です。
しかしそのためには、「明文化された制度設計」と「社員への適切な説明」がセットで必要です。
スタートアップや中小企業だからこそ、最初から筋の通った報酬制度を整える。
これが、信頼される組織の第一歩になります。
次章では、実際に賞与なしでも“納得される制度”を設計した企業の実例と、社内説明のポイントを紹介していきます。
【第7章】人事コンサル・社労士を活用した見直しステップ
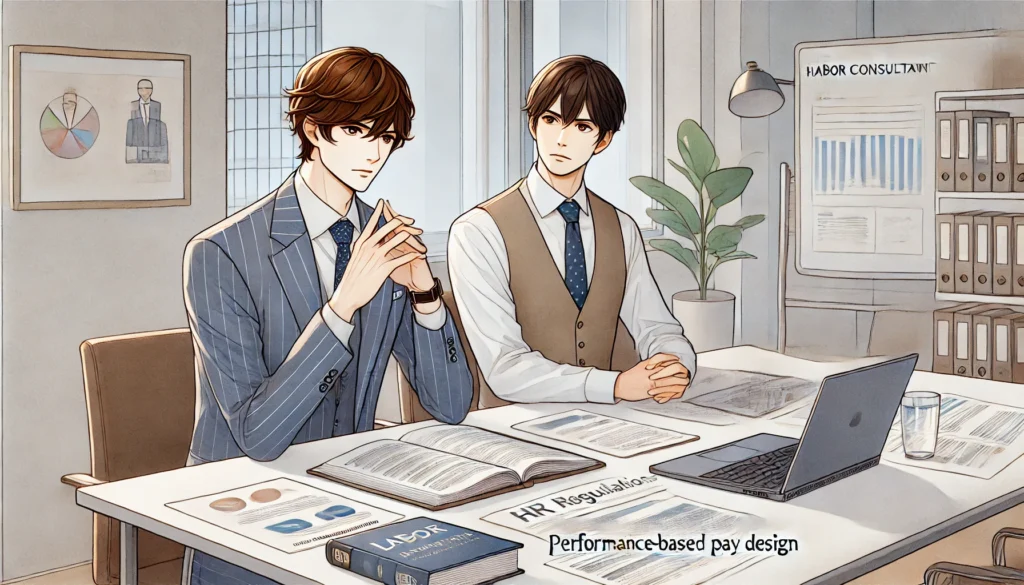
賞与制度の設計や見直しは、企業の“人の戦略”そのものです。
とはいえ、「自社だけではうまく整理できない」「法的なリスクも不安」という企業も少なくありません。
そんなときこそ、外部パートナーの知見を活かす場面です。
この章では、賞与なし制度を含む人事制度全体の見直しに役立つ、社労士・人事コンサルの活用方法と支援例をご紹介します。
制度見直しに使える外部パートナーの種類
制度を設計・改善するうえで活用される外部パートナーには、主に次のような専門家がいます。
1. 社会保険労務士(社労士)
労働法や就業規則に精通し、法的な整合性やトラブル回避の観点から制度設計をサポートします。
特に、賞与の就業規則明記や雇用契約の修正時に頼りになる存在です。
2. 人事コンサルタント
制度の「仕組み」だけでなく、評価制度や報酬制度全体のバランス設計を得意とします。
納得感・公平性・運用しやすさなどを重視した提案が可能です。
3. 専門サービス会社・SaaSベンダー
クラウド型の人事制度管理ツールや、診断・テンプレートサービスを提供。
初期コストを抑えて効率よく制度を見直すことができます。

制度構築=社労士、制度運用=コンサル、って分け方もアリですね。
依頼の際に押さえたい3つのポイントと費用感
実際に外部に依頼する際には、以下の3つを明確にしておくことでスムーズな連携ができます。
ポイント1:依頼の目的を明確にする
・「賞与をなくす代わりの説明資料が欲しい」
・「報酬設計全体を見直したい」
・「法的リスクがない就業規則を作りたい」など、範囲と目的を具体的に伝えることが重要です。
ポイント2:契約形態を理解する
スポット契約(単発)と顧問契約(月額制)があります。
社労士の場合、就業規則の見直しは5~15万円程度/回、
人事制度設計は50万円~100万円前後が相場です(企業規模・内容により変動)。
ポイント3:実績と業界知見をチェックする
特にスタートアップや中小企業の場合は、同規模・同業種の支援実績があるかを確認しましょう。
スキームが“机上の空論”で終わらないように、現場感のある提案ができるパートナーを選ぶことがカギです。
無料テンプレート・診断ツールの活用法
コストを抑えたい企業には、無料で使える支援ツールも有効です。
-
厚生労働省「モデル就業規則」(賞与欄あり)
-
J-Net21「就業規則作成支援ツール」
-
民間サイトの「人事制度設計チェックリスト」など
これらを活用することで、社内でのたたき台づくりや、外部に依頼する前の整理が可能になります。

無料テンプレでも精度は高い。手元に置いといて損なしです。
【支援事例】納得感と最適化を両立したA社のケース
最後に、筆者が支援した中小企業の成功事例をご紹介します。
従業員45名の製造業A社では、賞与を支給していないことに不満の声があがっていました。
そこで以下のようなステップで見直しを実施。
-
社労士と連携し、「賞与なし」の条文を適切に明文化
-
人事コンサルと協働で、年1回の“成果加点報奨金”制度を新設
-
運用マニュアルと社内説明資料をセットで整備
結果として、賞与という名称ではないが、成果が報われる設計に社員も納得。
さらに、求人広告で制度を打ち出したところ応募数が1.8倍に増加。
「賞与なし」から「賞与がなくても納得される会社」へ転換できました。
次章では、本記事全体を振り返りつつ、制度設計をこれから考える企業が“最初にやるべきこと”を整理します。
【第8章】まとめと感想|賞与なしでも信頼される企業になるには

「正社員なのに賞与がないのはおかしい」
こんな声に、経営者や人事担当者としてどう向き合えばいいのか。
ここまでの7章では、「賞与なし」という選択肢に対する法的な観点、制度設計、社員の納得感、落とし穴、そして支援体制の整え方まで、実務レベルで必要な情報を整理してきました。
法律・設計・伝え方・落とし穴:各章のポイント振り返り
第1章では、「賞与に法的支給義務はない」が、就業規則や過去実績との関係性に注意すべきことを解説しました。
第2章では、年俸制やインセンティブ制度など賞与の代替設計と就業規則の文言例を紹介。
第3章では、「なぜ賞与がないのか」という疑問に、納得してもらうための説明の工夫を。
第4章では、代替制度の活用と、福利厚生・採用とのバランスが大切だとお伝えしました。
第5章では、就業規則に書くべき具体文例と、社労士との連携ポイントを整理。
第6章では、スタートアップが特に陥りやすい「賞与あり=0円」という制度上の地雷を取り上げました。
そして第7章では、実務を前に進めるための、人事コンサルや社労士の活用法をまとめました。

一つひとつを読み返すと、「制度設計は信頼設計」って気づかされますね。
今すぐできるアクション3選
制度の見直しは一朝一夕にはいきません。
ただし、今日からできることもあります。
① 就業規則の賞与条項を確認する
まずは現状把握です。
「賞与は支給する場合がある」「業績に応じて支給」など、曖昧な文言が入っていないかチェックしてみましょう。
② 社員向け説明資料を作成・配布する
制度そのものよりも、説明不足が不信感を生みます。
「なぜうちは賞与がないのか」「その分どこに還元しているのか」など、資料化して共有するだけでも社内の空気が変わります。
③ 顧問社労士orコンサルに制度診断を依頼する
悩みすぎる前に、一度プロに壁打ちしてみる。
無料相談や制度チェックリストを活用して、現状を客観的に見る機会をつくることが、改善の第一歩です。

外部の視点を入れるだけで、見落としてた問題が浮き彫りになりますね。
最後に:賞与の有無ではなく、“納得されるかどうか”がカギ
「賞与がない=ブラック企業」と決めつける時代ではありません。
実際、賞与がなくても社員が長く働く会社もあれば、賞与があっても不満が噴出する会社もあります。
大切なのは、“何をどう設計するか”よりも、
“なぜその制度にしたのか”を誠実に伝える姿勢と仕組みです。
給与体系は、ただの数字の問題ではなく、企業の価値観と社員との信頼関係を映す鏡です。
この記事が、制度設計に悩む企業の皆さんの一歩を支えるヒントになれば幸いです。