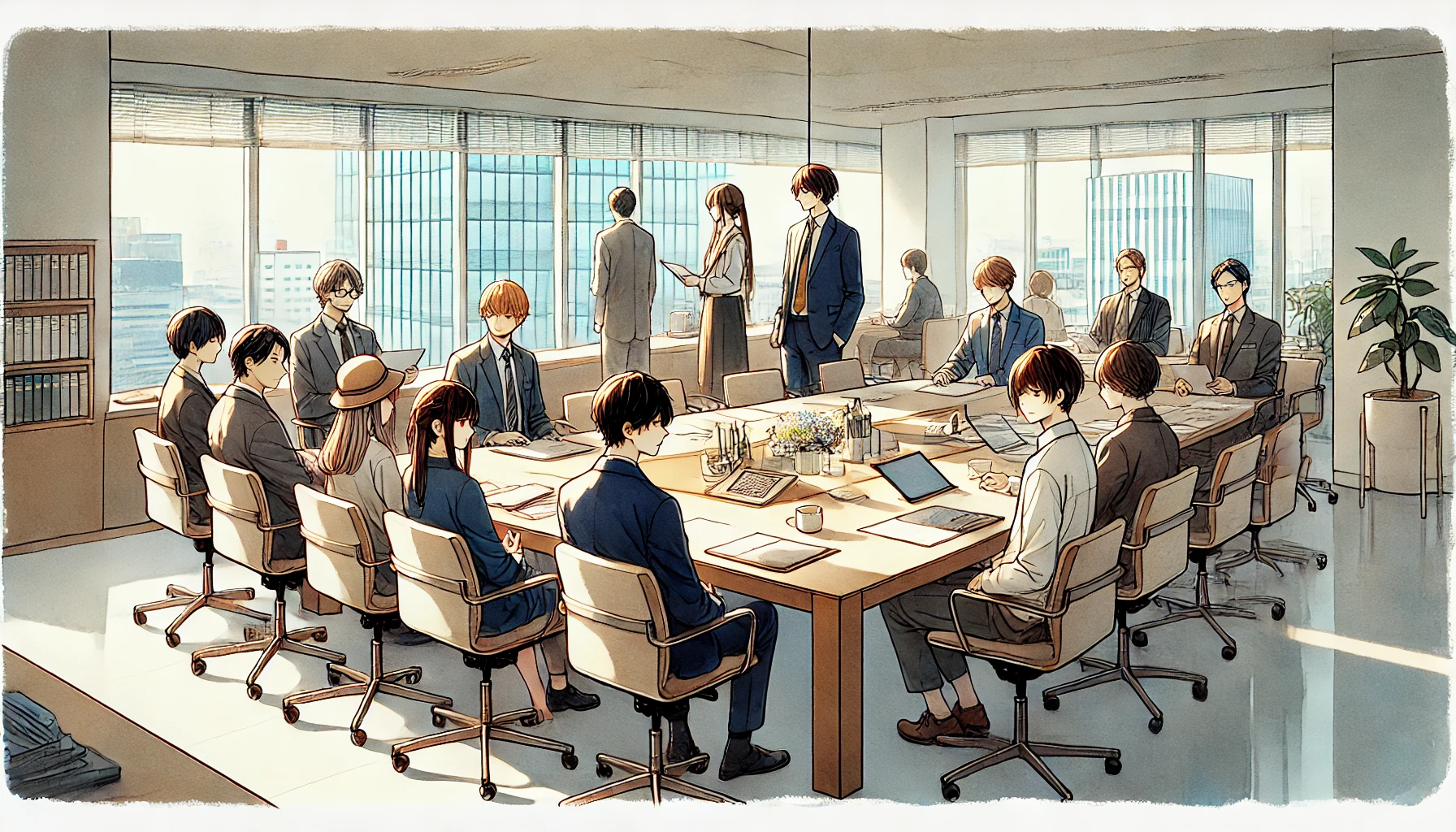健康経営は「理念」ではなく「戦略」です。
働き方改革や人手不足対策としても注目されており、政府の後押しも強まっています。
本記事では、健康経営の取り組み内容を基本から丁寧に整理し、導入のポイントと成功事例をご紹介します。
中小企業の視点で、現場で使える実践的な内容をお届けします。
【第1章】健康経営とは何か?基本概念と背景

健康経営の定義と目的
まず、健康経営という言葉をきちんと定義しておきましょう。
「健康経営」は、従業員の健康管理を経営的視点で考えることを指し、企業が戦略的に健康施策を推進する考え方です。
これは経済産業省が2014年に提唱した概念であり、厚生労働省も「働き方改革」や「生産性向上」の一環として後押ししています。
厚労省の資料では、「健康経営は企業の持続的成長に向けた投資」と位置づけられています。
単に健康診断を実施するだけではなく、メンタルヘルス対策・過重労働の是正・職場の活性化など、幅広い取り組みが対象となります。

健康診断だけで満足してないか?と自問する企業は多いようです。
今、健康経営が求められる社会背景
なぜ今、企業は健康経営に取り組む必要があるのでしょうか。
その背景には、日本全体の少子高齢化と労働人口の減少があります。
生産年齢人口(15〜64歳)は年々減少しており、企業は“健康で働ける人材をいかに長く確保するか”という命題と向き合う必要があります。
また、職場の多様化や精神的ストレスの増大により、メンタル不調による休職・離職リスクが増しているのも現実です。
企業が放っておけば、従業員の不調は生産性の低下や離職率の上昇に直結します。
逆にいえば、健康経営の取り組みは企業の競争力を守る手段でもあるということです。

「健康第一」は、もうスローガンじゃなくて“戦略”なんですよね。
経営戦略としての健康経営の位置づけ
健康経営は、人事や労務だけの話ではありません。
今や、経営戦略の一環として位置づけるべき重要なテーマです。
たとえば、「健康経営優良法人認定制度」のように、国が推進する枠組みがあります。
この認定を受けた企業は、社会的信頼の向上、採用広報での訴求、金融機関の優遇措置など、複数のメリットを享受できます。
また、ESG投資や人的資本の情報開示といった潮流の中でも、健康経営の実施は評価ポイントになります。
特に中小企業にとっては、これまで差別化が難しかった“働きやすさ”という点で大手と渡り合える強力な武器になる可能性があります。
まとめ
健康経営は、企業が“人”という資本にきちんと向き合い、投資する姿勢を明確にする経営手法です。
ただの福利厚生ではありません。
「健康=コスト」ではなく、「健康=利益に直結する資産」という発想の転換が、経営層にも現場にも必要なのです。
次章では、健康経営に取り組むことで得られる具体的なメリットを詳しく紹介していきます。
「本当に効果があるのか?」という声にも応える内容です。
【第2章】健康経営に取り組む3つのメリット
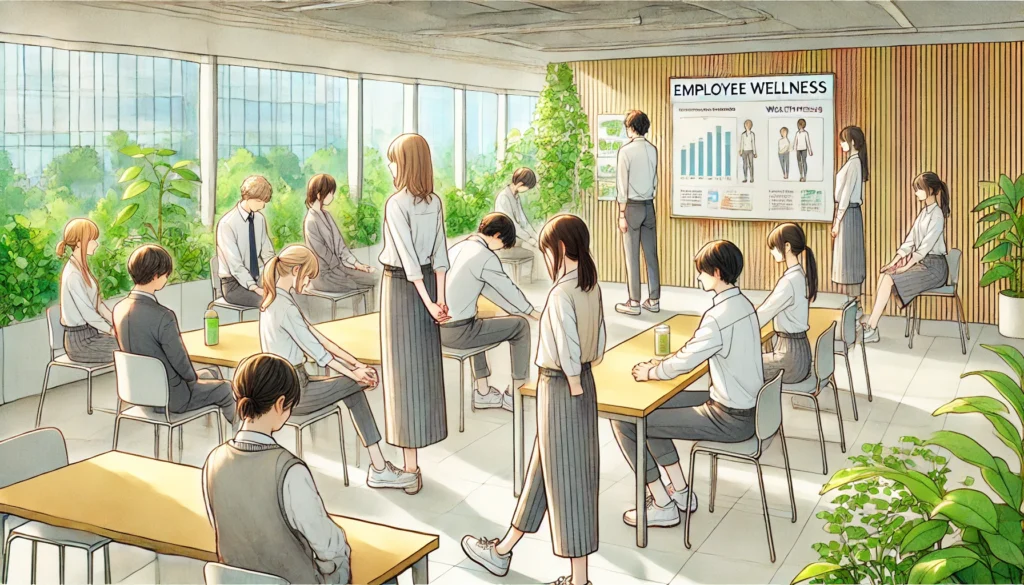
健康経営を導入することで、企業が得られるメリットは実に多岐にわたります。
中でも、経営者や人事が「これは大きい」と感じる3つの効果について、具体的に掘り下げていきましょう。
1. 離職率の低下と採用力の向上
社員が長く働ける環境を整えることで、離職率が下がる。これは健康経営のもっとも直接的な成果のひとつです。
ストレスチェックの活用、メンタルヘルス相談体制の強化、生活習慣病予防の支援などが代表的な施策です。
結果的に、社員のエンゲージメントが高まり、「この会社に長くいたい」と感じる人が増えます。
また、採用活動にもプラスの影響があります。
近年、求職者の企業選びの基準は「給与」や「福利厚生」だけでなく、“働きやすさ”や“健康支援”への姿勢に移行しています。
特に若年層では、健康経営優良法人のロゴマークが企業選定の参考情報として認知され始めています。

「健康を大事にしてくれる会社」って、思った以上に魅力的なんですよね。
2. 生産性・モチベーションの向上
健康経営は“働ける人を増やす”という視点でも大きな効果を発揮します。
ここで注目したいのが「プレゼンティーイズム」という概念です。
これは、出勤しているものの体調不良などで本来のパフォーマンスが出せていない状態を指します。
たとえば、慢性的な頭痛や睡眠不足、メンタル不調によって作業効率が落ちているケースです。
こうした見えにくい損失が、実は企業の収益に直結しているのです。
定期的な健康チェック、社内運動イベント、管理職の傾聴トレーニングなどを通じて、従業員の“働くコンディション”を底上げすることができます。

数字に表れない「何か不調」って、思ったより厄介ですからね。
3. 認定制度を活用し企業価値を高める
最後に注目すべきが、健康経営優良法人認定制度の活用です。
経済産業省と日本健康会議が実施するこの制度は、健康経営を実践する優良企業を「見える化」するもので、
企業規模を問わずエントリーできる仕組みになっています。
認定を受けることで、
-
採用広報での訴求力強化
-
金融機関からの金利優遇
-
地域自治体や関係団体からの表彰・支援
といった副次的メリットも得られるようになります。
特に中小企業にとっては、差別化の武器として有効です。
企業理念や社会的責任(CSR)との親和性も高く、
「社員を大切にする企業文化」を対外的に示すことができるのです。
まとめ
健康経営への取り組みは、企業の「やさしさアピール」ではなく、戦略的な投資です。
採用・定着・生産性・ブランド価値――すべての面で、具体的かつ測定可能なメリットがあります。
次章では、実際にどんな取り組みが行われているのか?
中小企業でもできる内容を、事例とともにご紹介します。
【第3章】中小企業でも実践できる健康施策とは?

「健康経営」と聞くと、「予算がかかる」「大企業だけの取り組み」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、実際にはコストを抑えて始められる施策がたくさんあります。
この章では、中小企業でも無理なく実践できる具体策を紹介します。
費用を抑えた施策例|まずは“できること”から
健康経営の基本は、日々の職場環境をちょっとずつ良くすることです。
次のような取り組みは、ほとんどコストをかけずに始められます。
-
朝のラジオ体操やストレッチを全員で実施
→ 始業前に数分行うだけでも、体の緊張がほぐれ、コミュニケーションのきっかけにもなります。 -
健康診断の結果を全体で共有(数値の平均値など)し、改善目標を立てる
→ 血圧・血糖などの項目を部内で“ゲーム感覚”で管理している企業もあります。 -
禁煙サポート、飲料やお菓子の“ヘルシー枠”設置
→ 社内の自販機や休憩スペースに、健康志向の選択肢を増やすだけでも、社員の意識が変わります。

高価な制度じゃなくても、意識を変える仕掛けはつくれます。
ストレスチェックとフォローアップの実践法
メンタルヘルス対策の第一歩として、多くの企業が導入しているのが「ストレスチェック制度」です。
年1回の実施が法律で義務づけられているのは従業員50人以上の事業所ですが、
それ未満の中小企業でも“任意導入”は強く推奨されています。
ストレスチェック導入時のポイントは以下の通りです:
-
匿名性の確保と安心感の提供
→ 「誰に見られるのか」が不安で、正直に書けない社員も少なくありません。 -
結果に基づいた面談・フォロー体制
→ 高ストレス者に産業医面談を促すだけでなく、管理職の“傾聴力”強化も大切です。 -
結果の集団分析で、組織の課題を可視化
→ 「部門Aだけストレスレベルが高い」など、チーム単位での改善策が立てやすくなります。

チェックだけで終わると逆効果。フォローまでが“健康経営”です。
食生活・運動支援・産業医との連携方法
健康維持の基本は、食事・運動・休養。
企業としてこの3本柱をどうサポートするかが鍵です。
-
食生活支援
・ランチに野菜を多く使ったメニューを出す
・コンビニと提携し、健康食チケットを配布する -
運動支援
・ウォーキングキャンペーン(歩数計アプリで部門対抗)
・就業前や昼休みに軽い運動プログラムを導入 -
産業医・保健師との連携
・月1回の訪問面談を取り入れる
・健康相談の“時間予約制”を設け、気軽に話せる場を確保
外部の保健指導サービスやオンライン産業医制度を使えば、社内に専門人材がいなくても始められます。
まとめ
中小企業こそ、柔軟で“顔の見える”取り組みがしやすいという強みがあります。
お金をかけるよりも、“社員のことを本気で考えている”というメッセージを、施策を通じて発信することが重要です。
次章では、健康経営を進めるうえでの「成功の鍵」を掘り下げていきます。
【第4章】健康経営優良法人認定を目指すステップ
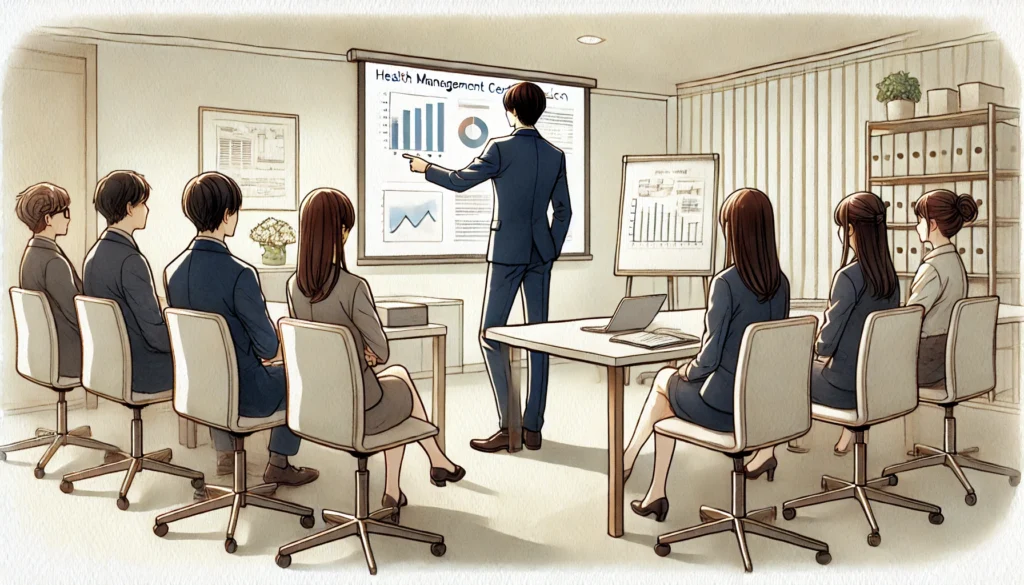
「健康経営を始めるなら、どうせなら認定も取りたい」
そう考える中小企業の経営者や人事担当者は少なくありません。
この章では、経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」について、実際の申請ステップを詳しく解説します。
認定制度の種類と対象法人
健康経営優良法人には、事業規模に応じた2つの区分があります。
-
大規模法人部門
従業員数300人以上の企業(上場・グループ企業含む) -
中小規模法人部門
従業員数300人未満(サービス業なら100人以下)の法人や個人事業主
中小企業の多くは「中小規模法人部門」の認定を目指すことになります。
この部門では、比較的身近で実践的な取り組みが評価対象になります。

自社の規模に合った申請区分を間違えないように!
認定項目と達成基準の解説
認定要件は、経産省が設けた「評価項目」に沿って自己申告・提出する形式です。
2024年版の中小規模法人部門では、次の5分野で取り組みを評価します:
-
経営理念・方針に基づいた健康経営の位置づけ
→ 社長メッセージや経営方針に「健康」が入っているか。 -
組織体制の構築
→ 担当者を置いているか。定例的な会議や共有の場があるか。 -
制度・施策の整備
→ 健診受診率100%、ストレスチェック実施、運動・食事支援など。 -
評価・改善
→ 取り組みの振り返りやPDCAを実践しているか。 -
法令遵守・リスク管理
→ 労働時間や安全衛生の順守状況、労基署からの是正がないか。
それぞれの分野で一定以上の取り組み実績を示すことが求められます。

「やっているけど書いてない」が一番もったいないですね。
書類準備と申請の実務プロセス
認定申請は、毎年秋ごろからWeb上で受付が開始されます。
ここでは、一般的な申請の流れを紹介します:
1. 情報収集と社内体制の整備
-
経産省サイト・地域の商工会議所等で申請ガイドラインを確認
-
健康経営推進担当者を明確にし、必要情報を集約
2. 評価項目に基づいた自己診断と証拠資料の整理
-
施策の実施記録やポスター、報告書などをPDFで保存
-
項目ごとに達成の有無と具体的なアクションを記載
3. Web申請システムから提出
-
日本健康会議の専用ページから企業情報を入力し、エビデンスをアップロード
-
登録にはGビズIDプライムアカウントが必要になる点に注意
4. 認定・公開
-
審査を経て、翌年3月ごろに「健康経営優良法人」として認定
-
経産省・地域経済産業局のWebサイトに社名が掲載されます(PR効果大)
まとめ
健康経営優良法人の認定は、制度や仕組みの“見える化”に繋がります。
中小企業にとっては採用・社外ブランディング・助成金申請時の信用強化にもなり、メリットは計り知れません。
認定を目指すプロセスそのものが、社内の健康経営レベルを底上げするきっかけにもなります。
次章では、認定取得後の「継続的な改善とエンゲージメントの高め方」について掘り下げていきます。
【第5章】成功事例から学ぶ実践のポイント
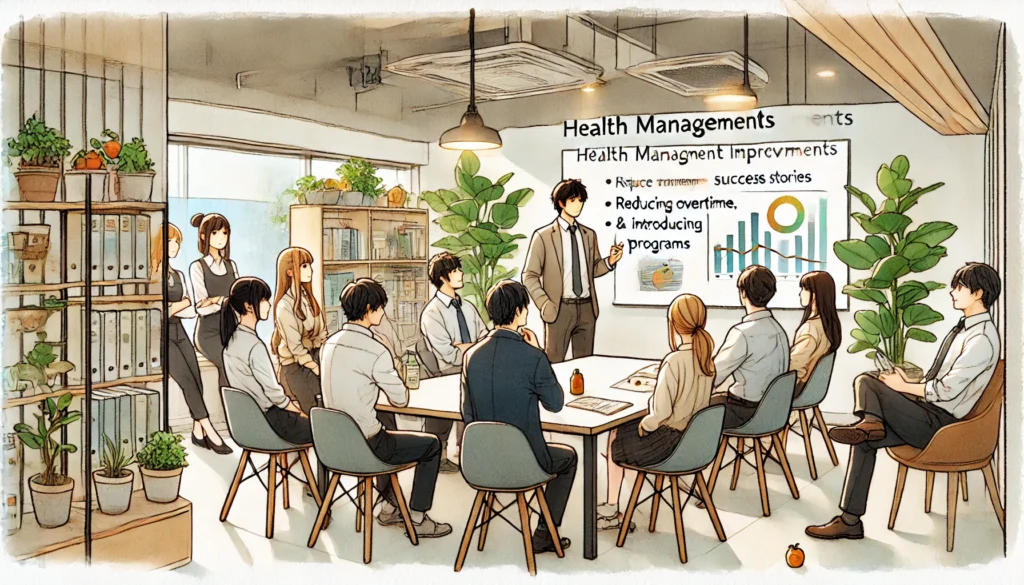
「健康経営って実際、どこまでやればいいのか?」
そう疑問を感じる中小企業の皆さんにこそ、他社事例はヒントの宝庫です。
この章では、実際に健康経営優良法人認定を取得した企業のリアルな取り組みと成果を紹介しながら、現場を巻き込むポイントや評価制度への落とし込み方を整理していきます。
A社(地方製造業):残業削減と運動促進で認定取得
従業員数約50名、地方に拠点を持つ製造業のA社は、「残業の多さと健康診断未受診者の多さ」が課題でした。
そこで取り組んだのが、以下の2つ。
● 週1回の「ノー残業デー」導入
-
上司が率先して定時退社
-
業務棚卸と作業標準化を進めて、生産性を確保
● 社内ウォーキングキャンペーンの開催
-
全社員に歩数計アプリを配布
-
チーム対抗戦で賞品あり(費用は月3,000円程度)
結果、残業時間は前年比で20%削減され、健診受診率も100%に到達。
2023年、見事「健康経営優良法人(中小規模法人部門)」に認定されました。

「お金をかけずにできる」が地方企業には最大の強みになります
。
B社(IT系ベンチャー):メンタルケアと働き方の柔軟化で離職率半減
首都圏に拠点を構えるIT系のB社(社員数約80名)は、若手社員の離職率とメンタル不調が課題でした。
実施した施策は以下の通り。
● 月1回の「カジュアル1on1面談」
-
上司と部下がテーマ自由で30分会話
-
評価とは切り離し、信頼関係を構築
● リモート勤務と時差出勤の制度化
-
体調やライフスタイルに応じた勤務を許可
-
育児・介護との両立もしやすく
あわせて、産業医との連携を強化し、ストレスチェック後の面談率も大幅向上。
結果として、離職率は1年で約50%も改善。定着率の向上が採用コストの削減にもつながりました。

IT業界のような変化の激しい現場では、柔軟性がカギになりますね。
成功の鍵は「現場を巻き込む仕組み」と「評価への反映」
これらの企業に共通していたのは、トップダウンだけでなく、現場を巻き込む仕掛けを設けていた点です。
● 健康推進プロジェクトチームの設置
-
管理部門だけでなく現場社員も参画
-
取り組みテーマを社員が決める「ボトムアップ型」
● 健康活動を人事評価に反映
-
例:健康目標(ウォーキング、禁煙など)の達成を自己評価項目に設定
-
上司が取り組みを確認し、期末面談で振り返り
こうした工夫により、形だけで終わらない「継続する健康経営」が実現されていました。
まとめ
「うちには無理だよ」と思いがちな健康経営ですが、実際は工夫と運用でどうにかなる部分が多くあります。
少しずつでも取り組みを始めることで、社員の定着率・満足度・企業イメージのすべてが底上げされていきます。
次章では、こうした取り組みを社内にどう浸透させるか、継続の工夫についてご紹介します。
【第6章】社内提案・実行時の注意点と乗り越え方
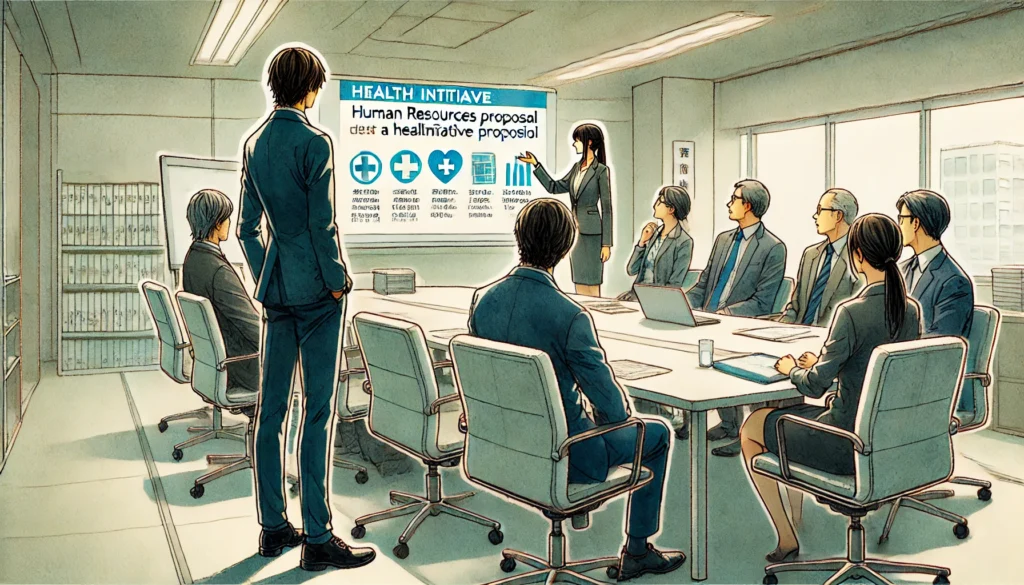
健康経営の必要性は理解されていても、いざ実行となると「動かない」「広がらない」と悩む企業は少なくありません。
この章では、社内提案から実行・定着までで起こりやすい“つまずき”とその解決策を紹介します。
経営層・現場の温度差をどう埋めるか
健康経営の取り組みを人事・総務が主導しようとしても、「経営層が本気でない」「現場がついてこない」といった“温度差”に直面することがあります。
● 経営層には「数値」と「企業価値」で訴える
-
離職率低下 → 採用コスト削減
-
健康経営優良法人認定 → 企業イメージUP・取引先評価UP
たとえば、「健康経営により求人応募数が増えた」など、数字で語れる成功事例を提示することで経営層の関心を引くことができます。

「理念」より「数字」から入ると、経営陣の態度は変わりやすいです。
● 現場には「負担感のない施策」からスタート
-
朝礼ストレッチ(3分)
-
健康診断の予約代行サポート
-
自販機に「特保」飲料を増やす
「やらされてる感」を減らし、自分ごと化してもらう工夫がカギになります。
導入初期にありがちな“形だけ”の失敗例
「とりあえず施策を入れて終わり」では、むしろ逆効果になることも。
形だけの健康経営は、社員に見透かされ、信頼を損なうリスクすらあります。
● ありがちなNG例
-
健康宣言を掲げただけで終わり
-
ストレスチェックをやるだけで、フォローなし
-
産業医面談が「形式的」で、本音が話せない
こうした「チェックリスト埋め」に陥らないためには、継続的な振り返りと社員からのフィードバックが重要です。

やってる感では続かない。現場の声が動力源になります。
コンサル・社労士など外部支援活用のコツ
「健康経営は本格的にやるとハードルが高い」と感じる企業にこそ、外部パートナーの活用は有効です。
● どんな支援が受けられるのか
-
健康経営優良法人申請の書類作成サポート
-
ストレスチェックや産業医面談の設計
-
社内制度(評価・就業規則)との連動提案
とくに健康経営エキスパートアドバイザーや、社会保険労務士(社労士)との連携は、助成金や法制度面でも安心です。
● 選ぶときのチェックポイント
-
中小企業支援の実績があるか
-
自社と似た業種の支援経験があるか
-
継続支援型かスポット型か(費用体系も含めて)
“餅は餅屋”に任せることで、社内の負担軽減と制度設計の質が大きく変わります。
まとめ
社内で健康経営を進めるには、「良いこと」だけでは動きません。
経営層・現場・制度の三者に対して、数値・納得・負担軽減という観点でアプローチすることが、成功の鍵です。
次章では、こうした実践をどのように成果につなげ、継続していくかを、まとめとしてお届けします。
【第7章】まとめと感想|健康経営は“経営そのもの”になる
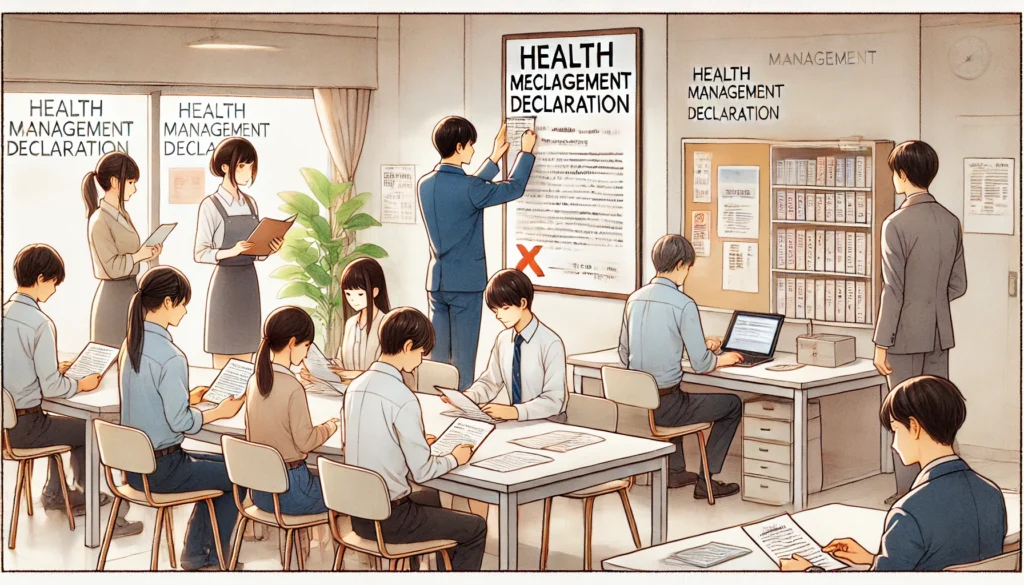
「健康経営」は、単なる福利厚生や健康管理の延長ではありません。
今や、経営戦略そのものに組み込まれるべき時代に突入しています。
ここではこれまでの内容を整理し、すぐに踏み出せるアクションと、最後に私からの視点をお伝えします。
各章の振り返り|健康経営の全体像を再確認
第1章では、「健康経営とは何か」という基本概念とその背景(人口減少や労働力の維持)について整理しました。
第2章では、健康経営が離職率低下・採用力向上・企業価値向上といった経営効果を持つことをお伝えしました。
第3章では、中小企業でも無理なく実行できる施策例を。
第4章では、「健康経営優良法人」の認定ステップを詳しく解説。
第5章では実践企業の成功事例から現場巻き込みのヒントを。
第6章では、導入時に起こりやすい社内の“ズレ”を乗り越える方法を共有しました。

制度だけ整えても、社員が動かなきゃ意味ないですからね。
今すぐできるアクション3選
「やりたい。でも何から始めるべきか…」という方へ。
以下の3つは、費用ゼロ・準備最小で始められる、最初の一歩です。
① 健康経営の“宣言文”を掲げる
社内ポータルや掲示板に「健康を大切にする企業である」ことを明言しましょう。
文言は短くて構いません。
例:「私たちは、社員一人ひとりの心と体の健康を大切にします。」
宣言は“方針”であり、すべての行動の根になります。
② 社員アンケートで現状把握
・「最近よく眠れているか?」
・「健康診断の結果は気になるか?」
・「職場の食生活、どうしてる?」
たった3〜5問でもOK。
現場の声を知ることが、正しい健康施策のヒントになります。

聞いてみると、けっこうギャップが見えてきますよ。
③ 小さくていい、“1つ”実行する
-
自販機のラインアップを変更
-
ランチ時間を5分長くして散歩推奨
-
メールで「今日の健康豆知識」を流す
「仕組みを変える」のではなく「行動が変わる」ことを意識した小さな一歩が、健康経営の文化づくりにつながります。
最後に|健康経営は「人材投資」の第一歩
社員の健康に投資することは、言い換えれば企業の未来に投資するということです。
生産性の高い組織、離職率の低い職場、魅力ある企業ブランド――すべての根底にあるのは、「人」です。
健康経営は短期で成果が出るものではありません。
だからこそ、“今日からできる小さなこと”を積み重ねることが、未来をつくる唯一の道です。
「健康経営」をきっかけに、組織がもっと“人に優しく強い”場所へ変わっていく企業が増えることを心から願っています。