人材不足は業界ごとに異なる課題を抱えています。
例えば、IT業界では即戦力のエンジニアが不足し、医療業界では長時間労働が離職を招いています。
企業が人材を確保するためには、採用手法を工夫し、魅力的な職場環境を整備することが重要。
本記事では、業界別の人材不足の実態と企業が実践すべき採用戦略について詳しく解説します。
第1章:なぜ今、人材不足が深刻化しているのか?

日本の労働市場では、かつてないほど人材不足が深刻化している。
求人を出しても応募がない、採用できてもすぐに辞めてしまう、そもそも働き手の確保が難しいといった悩みを持つ企業が増えている。
なぜここまで人材不足が進行しているのか。その背景を深掘りしていこう。
日本の労働市場で人材不足が加速する背景
人材不足の原因は一つではない。
長期的な社会構造の変化に加え、経済や労働環境の変動が重なり、複雑な要因が絡み合っている。
特に、以下の3つのポイントが大きく影響している。
1.少子高齢化による労働人口の減少
日本の総人口は減少傾向にあり、特に生産年齢人口(15〜64歳)は急激に減少している。
総務省の統計によると、1995年には8,700万人だった生産年齢人口は、2023年には7,000万人を下回った。
これは単純計算で1,700万人もの労働力が失われたことになる。
この減少傾向は今後も続くと予測されており、企業が人材確保に苦戦するのも無理はない。

「この数字を見ると、もはや人材不足は一時的な問題ではなく、構造的な課題になっていますね。」
2.団塊世代の大量退職と継承問題
2025年までに、団塊世代(1947~1949年生まれ)が75歳以上の後期高齢者に突入する。
これにより、長年現場を支えてきた経験豊富なベテラン社員が一気に退職し、企業の技術やノウハウの継承が課題になっている。
特に、製造業や建設業では、技術を持つ職人が減少し、若手への引き継ぎが追いつかない。
また、団塊世代が抜けた穴を埋めるために若手を採用しようとしても、そもそも若年層の人口が少なく、採用競争が激化している。
企業にとって、単に人を採るだけでなく、「技術の継承」「定着率の向上」も同時に考えなければならないのが現状だ。

「職人の世界では、『見て覚えろ』が通用しなくなったって話、よく聞きますね。」
コロナ禍後の労働環境の変化と企業の課題
コロナ禍は、日本の労働市場に大きな変革をもたらした。
リモートワークの普及、働き方の多様化、企業の雇用戦略の変化など、さまざまな要因が人材不足の問題と密接に関わっている。
1.リモートワークの普及による地方労働力の流出
コロナ禍を経て、テレワークやフルリモートを導入する企業が増えた。
これにより、従来なら地方で働いていた人材が都市部の企業でリモート勤務をするようになり、地方企業はさらに人手不足に陥っている。
地方企業にとっては、「通勤しなくても働ける仕事」が増えたことで、人材流出のリスクが高まっている。
2.働き方の価値観の変化
かつては「正社員=安定」という価値観が強かったが、現在は「ワークライフバランス」「やりがい」「収入の多様性」などが重視されるようになった。
フリーランスや副業を選択する人も増え、企業が求める「長期間勤める正社員」が減っている。
特に若年層は、「定年まで一社で働く」という考え方に縛られず、転職や独立を前向きに捉えている傾向がある。
これが企業の「人が定着しない」という悩みに直結している。
今後の予測(さらに厳しくなるのか?)
このままの流れが続けば、今後の人材確保はますます困難になると予測される。
政府は外国人労働者の受け入れ拡大や、女性・高齢者の活躍推進などの政策を打ち出しているが、根本的な解決には至っていない。
企業側は、従来の採用戦略だけに頼らず、新しい視点での採用手法を取り入れる必要がある。
特に、「企業が人を選ぶ時代」から「人に選ばれる企業になる時代」へと変わっていることを理解することが重要だ。
【エピソード】地方の製造業で起きている人材不足の現実
地方の製造業では、10年以上前から人材不足が続いていたが、コロナ後はさらに深刻になっている。
ある町工場では、以前はハローワークに求人を出せば数名の応募があったが、今では半年間募集してもゼロ。
「求人広告を出しても反応がない」「若い人が来ない」と経営者は頭を抱えている。
そこで給与を引き上げたり、勤務時間を柔軟にしたりと工夫をしているが、劇的な改善にはつながっていない。
このように、単なる「募集の問題」ではなく、働く人の価値観や市場の変化が影響しているのだ。
まとめ
人材不足は一時的なものではなく、社会構造の変化による「必然的な課題」だ。
少子高齢化、団塊世代の退職、働き方の変化など、多くの要因が絡み合い、企業はこれまでの採用方法では対応できなくなっている。
これからの時代、企業は「労働市場の変化を理解し、新しい採用戦略を取り入れる」ことが求められる。
次章では、特に人材不足が深刻な業界について詳しく見ていこう。
第2章:人材不足が深刻な業界の特徴とは?

人材不足はすべての業界に共通する課題だが、特に深刻な業界がいくつか存在する。
労働環境、賃金の問題、離職率の高さなど、業界ごとに異なる要因が絡み合い、採用難や定着率の低下を引き起こしている。
ここでは、特に人材不足が顕著な「医療・福祉」「建設」「飲食」「IT」の4つの業界について深掘りしていこう。
1.医療・福祉業界:人は足りないが、仕事は増える一方
医療・福祉業界は、常に人手不足が叫ばれている代表的な分野だ。
特に介護職は深刻で、厚生労働省の試算によると、2040年には約69万人の介護職員が不足するとされている。
なぜ人が足りないのか?
・労働環境の厳しさ:夜勤や長時間労働が避けられない
・賃金が低い:他の業種と比べて給与水準が低い(介護職の平均年収は約350万円)
・精神的・肉体的負担の大きさ:高齢者のケアや緊急対応の多さ
「やりがいはあるが、続けられない」—これが介護職の実情だ。

「給料を上げるだけではなく、職場の負担を減らす工夫が必要ですね。」
2.建設業界:ベテラン職人が引退し、若手が入ってこない
建設業界は、若手の採用が極めて難しく、業界全体で高齢化が進んでいる。
国土交通省の調査では、建設業の就業者の3割以上が55歳以上で、29歳以下は全体の10%未満というデータがある。
なぜ人が足りないのか?
・労働環境が過酷:屋外作業が多く、夏は猛暑、冬は極寒
・労働時間が長い:残業や休日出勤が当たり前の文化
・技術の継承が難しい:職人技を覚えるのに時間がかかる
結果として、「キツイ」「休めない」「将来のキャリアが見えない」という理由で若者が敬遠しがちだ。
【エピソード】
ある中小建設会社では、若手の採用ができず、ベテラン職人に頼らざるを得ない状況が続いている。
社長は「技術を継承したくても、そもそも若い人が来ない」と嘆く。
そこで外国人技能実習生を受け入れたり、3D建築技術を導入して作業を効率化するなどの工夫をしているが、根本的な人手不足は解消されていない。

「体力的な負担を軽減する技術革新が求められていますね。」
3.飲食業界:低賃金・長時間労働が人を遠ざける
飲食業界も慢性的な人手不足に悩んでいる。
特にコロナ禍を経て、一度離れた労働者が戻ってこないという現象が起きている。
なぜ人が足りないのか?
・低賃金:アルバイトの時給は上がっているが、正社員の給与はあまり伸びていない
・長時間労働:ランチ・ディナーのピークに合わせるため、不規則な勤務が多い
・コロナ後の人材流出:一度異業種に転職した人が戻ってこない
特に地方の飲食店では、求人を出しても応募がほとんどないという状況が続いている。
政府が外国人労働者の受け入れを拡大したこともあり、一部の店舗では外国人スタッフを活用しているが、それでも人手不足は解消されていない。
4.IT業界:需要はあるが、スキルを持つ人材が不足
IT業界は他の業界とは異なり、求人数が多いにもかかわらず「適切なスキルを持つ人材が不足している」という問題を抱えている。
経済産業省の予測によると、2030年には約79万人のIT人材が不足するとされている。
なぜ人が足りないのか?
・スキルギャップ:求められる技術水準が高く、未経験者が入りにくい
・給与が高いが競争が激しい:フリーランスや海外企業への転職が進む
・働き方が多様化し、企業に定着しない:リモートワークが増え、転職が容易になった
特にAI・クラウド・セキュリティなどの分野では、国内のエンジニアが不足し、外資系企業に人材が流出するケースも増えている。
企業側も、給与を引き上げたり、働きやすい環境を整えたりと工夫しているが、競争が激しいため根本的な解決には至っていない。
まとめ
人材不足が深刻な業界には、それぞれ共通する課題がある。
✔医療・福祉業界:労働環境の厳しさと低賃金
✔建設業界:高齢化と若手不足
✔飲食業界:低賃金と長時間労働
✔IT業界:スキルを持つ人材の不足
企業は「人がいない」ことを嘆くだけではなく、働きやすい環境づくりや新しい採用戦略を考える必要がある。
次章では、企業が具体的にどのような解決策を講じるべきかを掘り下げていこう。
第3章:人材不足解決のために企業ができること
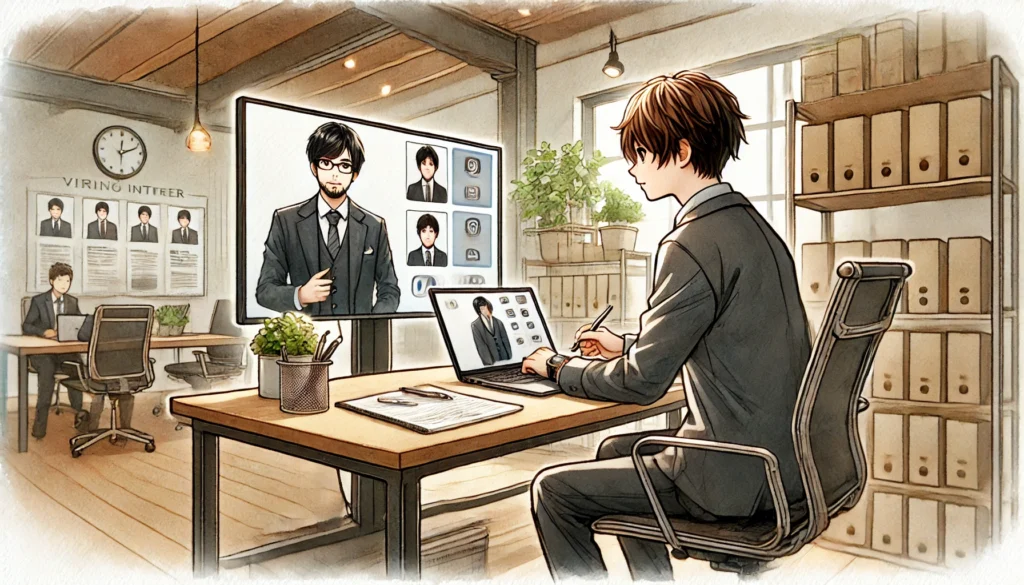
人材不足に悩む企業は多いが、「応募が来ない」「採用しても定着しない」といった問題は、従来のやり方に固執していることが原因の一つだ。
近年、採用手法の多様化や働き方の見直しが進んでおり、時代に合った対策を講じることで人材不足を解消している企業も増えている。
ここでは、具体的な解決策を4つの視点から解説していこう。
1.採用手法の多様化:待ちの採用から攻めの採用へ
従来の「求人サイトに掲載する」「ハローワークに登録する」といった方法だけでは、優秀な人材を確保するのは難しい。
求職者の行動が変わる中で、企業も新しい採用手法を取り入れる必要がある。
①ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングとは、企業が求職者に直接アプローチする採用手法だ。
LinkedInやビズリーチといったプラットフォームを活用し、企業が自ら「欲しい人材」にスカウトを送ることで、より適した人材とマッチングしやすくなる。
特にIT業界や専門職では、転職サイトでの応募を待つよりも、企業からアプローチしたほうが成功しやすい。

「スカウトを受ける求職者も、企業から声がかかると嬉しいものですね。」
②リファーラル採用(社員紹介制度)
リファーラル採用は、社員が知人や友人を紹介する採用方法だ。
この方法のメリットは、会社の雰囲気や業務内容を理解した人が紹介するため、ミスマッチが少ないことだ。
紹介者にはインセンティブ(紹介ボーナス)を支給する企業も多く、定着率の高い採用手法として注目されている。
2.労働環境の改善:働き方の柔軟性が鍵
採用に成功しても、働きにくい環境では人は定着しない。
特に現代の求職者は、収入だけでなく「働きやすさ」を重視しているため、企業は環境改善に取り組む必要がある。
①テレワークの導入
コロナ禍を機に、多くの企業でテレワークが普及した。
オフィスに出社しなくても仕事ができる環境を整えることで、働く場所を選ばない人材を確保しやすくなる。
また、テレワークを導入することで、子育て中の女性や地方在住の優秀な人材を採用しやすくなるメリットもある。
②フレックスタイム制の活用
フレックスタイム制を導入することで、社員は自分のライフスタイルに合わせた働き方ができる。
例えば、「朝早く出社して夕方に帰る」「昼から仕事を始める」といった柔軟な働き方が可能になり、ワークライフバランスを向上させることができる。
この制度を導入した企業では、社員の満足度が向上し、離職率が低下する傾向がある。
3.企業ブランディングの重要性:求職者に選ばれる会社になる
採用市場では、「企業が人を選ぶ時代」から「求職者が企業を選ぶ時代」へと変化している。
特に、若手人材は「給与」だけでなく、「企業のビジョン」「働く環境」「成長できるかどうか」を重視する傾向がある。
①採用ブランディングの強化
企業が魅力的に映るように、積極的な情報発信が必要だ。
・SNSでの採用情報発信(Instagram、X、TikTokなど)
・社員インタビューを活用したコンテンツ作り
・採用ページの充実(企業理念・キャリアパスを明確化)
実際に、「SNSで企業の取り組みを知り、応募した」というケースも増えており、特に若年層の採用には欠かせない手法となっている。
②社内カルチャーの発信
企業のカルチャーを発信することで、「この会社で働きたい」と思わせることができる。
例えば、社員の働き方やオフィス環境、社内イベントの様子を公開することで、求職者が企業の雰囲気をイメージしやすくなる。
4.人材の定着率を上げる施策:辞めさせない仕組みを作る
採用した人材がすぐに辞めてしまうのでは意味がない。
定着率を上げるためには、社員が「ここで働き続けたい」と思える環境づくりが重要だ。
①キャリアパスの明確化
企業が求職者にとって魅力的になるためには、「将来の成長イメージ」を提供することが大切だ。
例えば、入社後の昇進ルートやスキルアップの機会を明確にすることで、社員は「この会社で頑張れば成長できる」と感じる。
具体的には、以下のような取り組みが効果的だ。
・昇進の基準を明確にする(入社◯年でリーダー、◯年で管理職など)
・定期的なキャリア面談を実施する
②教育制度の強化
社員が成長できる環境を提供することも、定着率向上につながる。
【エピソード】
あるベンチャー企業では、社内教育制度を充実させた結果、新卒社員の定着率が80%から95%に向上した。
具体的には、入社後3ヶ月間の研修プログラムを設けたり、メンター制度を導入したりすることで、若手社員の不安を解消した。
社長は「会社が成長する環境を作ることで、人は自然と残る」と語っている。
まとめ
人材不足を解決するためには、「採用→定着→育成」という流れをしっかり作ることが重要だ。
✔攻めの採用(ダイレクトリクルーティング・リファーラル採用)を活用する
✔テレワークやフレックスタイム制を導入し、柔軟な働き方を提供する
✔企業ブランディングを強化し、求職者に選ばれる会社を目指す
✔キャリアパスと教育制度を整え、定着率を向上させる
これらの取り組みを実践することで、企業は「人が来ない」「人が辞める」といった問題から脱却できるはずだ。
次章では、最新の採用トレンドについて詳しく解説していこう。
第4章:採用を成功させるための最新トレンド

人材不足が深刻化する中、従来の採用手法では求職者にリーチすることが難しくなっている。
そこで、企業は「求職者に見つけてもらう」採用から「企業が積極的にアプローチする」採用へと移行しつつある。
特に、デジタル技術を活用した採用手法が注目を集めており、SNS採用や動画採用、AIを活用したスクリーニングなどが有効な手段として広がっている。
本章では、採用を成功させるための最新トレンドを詳しく解説する。
1.SNS採用や動画採用の活用:求職者との距離を縮める
SNSは、今や採用活動に欠かせないツールとなっている。
特に若年層の求職者は、就職活動の情報収集をSNS経由で行うことが増えており、企業もこの流れに対応する必要がある。
①SNS採用のメリット
・求職者との接点を増やせる
・企業の雰囲気やカルチャーを伝えやすい
・広告を活用すればターゲットにピンポイントでリーチ可能
特にInstagram・TikTok・X(旧Twitter)などのSNSは、視覚的な情報発信に強く、企業の「魅力」を直感的に伝えるのに適している。
また、社員の日常や社内イベントを発信することで、「この会社で働いてみたい」と思わせることができる。

「就活生は求人票よりもSNSで会社のリアルな姿を知りたがるんです。」
②動画採用の効果
動画はテキストよりも直感的に情報を伝えられるため、求職者の興味を引きやすい。
特にTikTokやYouTubeを活用した採用動画は、企業の認知度向上に大きく貢献する。
【エピソード】
あるIT企業では、TikTokを活用した採用動画を配信したところ、応募数が前年比の2倍に増加した。
動画では、社員のインタビューや職場の雰囲気をリアルに伝えることで、求職者が「この会社で働くイメージ」を持ちやすくなった。
若手求職者に向けた新しいアプローチが成功した事例として注目されている。
2.採用DX(デジタル化)の進展と効果:効率を上げて採用力を強化
近年、多くの企業が採用活動のDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めている。
これは、採用プロセスの自動化・効率化を図ることで、企業の採用力を向上させる取り組みだ。
①採用管理システム(ATS)の活用
ATS(Applicant Tracking System)は、採用プロセス全体を一元管理できるシステムだ。
ATSを導入することで、以下のようなメリットがある。
・応募者の情報を一括管理できる
・面接の日程調整や連絡を自動化できる
・採用データを分析し、より効果的な採用戦略を立てられる
多くの企業が、「JobSuite」「HRMOS」「HERP」などのATSを導入し、採用業務の効率化を図っている。
②オンライン面接の活用
コロナ禍をきっかけに、オンライン面接が一般的になった。
移動の負担がないため、地方在住の求職者ともスムーズに面接を行うことができ、採用の間口を広げることが可能だ。
また、AIを活用した自動面接ツールも登場しており、一次面接をAIが担当することで、採用担当者の負担を軽減できるようになっている。
3.AIを活用したスクリーニングや人材マッチング
AI技術は、採用活動にも大きな変革をもたらしている。
特に、スクリーニングや人材マッチングの分野での活用が進んでいる。
①AIによる書類選考の自動化
従来の採用では、採用担当者が履歴書や職務経歴書を一つひとつ確認し、選考を行っていた。
しかし、AIを活用することで、応募者のスキル・経歴を瞬時に分析し、企業の求める人材とマッチングさせることが可能になっている。
例えば、「リクナビHRTech」や「Eight Career Design」などのサービスは、AIを活用した書類選考を提供し、企業の採用業務を効率化している。
②AIによる適性検査・面接分析
AIは、面接の動画解析や音声解析を行い、求職者の適性を評価することも可能だ。
例えば、表情・声のトーン・話し方の特徴を分析し、面接官の主観に頼らない客観的な評価を行うことができる。
これにより、採用の公平性が向上し、企業にとって最適な人材を見極めることが可能になる。
まとめ
最新の採用トレンドを活用することで、企業はより効率的に優秀な人材を確保できる。
✔SNS採用・動画採用で求職者との距離を縮める
✔採用DXを進め、管理業務を自動化・効率化する
✔AIを活用し、書類選考や適性検査を高度化する
時代の変化に対応し、新しい採用手法を取り入れることで、企業は「人材不足」の課題を克服することができる。
次章では、人材不足を逆手にとった新しい採用戦略について詳しく解説していこう。
第5章:人材不足を逆手にとる!新しい採用戦略

人材不足は、多くの企業にとって深刻な問題だ。
しかし、見方を変えれば、これは「新しい働き方を取り入れるチャンス」でもある。
「人がいない」からこそ、既存の採用の枠組みにとらわれず、今まで活用できていなかった人材層や仕組みを見直すことが求められている。
本章では、人材不足を逆手にとり、企業が強くなるための新しい採用戦略を紹介しよう。
1.シニア・女性・外国人労働力の活用
今まで十分に活用されてこなかったシニア層・女性・外国人労働力に注目することで、新たな採用の可能性が広がる。
①シニア層の活用
日本は高齢化が進み、65歳以上の人口は3,600万人を超えている(総務省統計)。
これを「社会の負担」と考えるのではなく、「豊富な経験を持つ労働力」として活用する企業が増えている。
活用ポイント
・専門知識や技術を活かしたアドバイザー・指導者としての活用
・時間に余裕のあるシニアを短時間勤務で採用
実際、ある製造業の企業では、定年退職した職人を週3回のパート勤務で再雇用し、技術継承に成功している。
②女性の活躍推進
少子高齢化が進む中、女性の労働市場への参入は避けて通れないテーマだ。
特に、子育て中の主婦層は、働く意欲があっても、フルタイム勤務が難しいために労働市場に参加しづらい。
この層を活用するために、多くの企業が短時間勤務・時差出勤・リモートワークを導入している。
【エピソード】
ある飲食チェーンは、子育て中の主婦を積極採用し、短時間勤務の制度を整備。
その結果、離職率が大幅に低下し、人材不足を克服した。
主婦層は「時間の制約はあるが、責任感が強く定着率が高い」ため、企業にとって非常に頼りになる存在だ。
③外国人労働力の活用
建設業、介護、飲食業などでは外国人労働者の受け入れが増えている。
現在、日本では「特定技能制度」という仕組みを活用すれば、即戦力となる外国人を採用することが可能だ。
ただし、外国人労働者が定着するためには文化・言語の壁を取り除く工夫も必要だ。
例えば、あるホテルでは、外国人スタッフ向けに日本語研修や生活サポートを充実させることで、長期的に働ける環境を整えている。
2.アウトソーシングと業務委託の最適化
「自社で人材を確保する」という考え方に固執すると、人材不足の解決は難しい。
業務を外部に委託することで、採用の負担を軽減することも重要な戦略の一つだ。
①バックオフィス業務のアウトソーシング
経理・人事・総務などの定型業務は、外部の専門会社に委託することで社内のリソースをコア業務に集中できる。
例えば、クラウド会計ソフトを活用し、経理業務を外部のプロに任せる企業が増えている。
②フリーランスや副業人材の活用
特定のスキルが必要な業務(デザイン・マーケティング・エンジニアリングなど)は、フリーランスや副業人材を活用するのも一つの方法だ。
特に副業OKのプロフェッショナル人材を活用することで、短期間で高スキルの人材を確保できる。
すでにパーソルキャリアやランサーズなどのプラットフォームを通じて、多くの企業がフリーランスと契約している。
3.「自社で人を育てる」文化の重要性
「即戦力を採用する」という発想だけでは、人材不足を根本的に解決することは難しい。
そこで、「自社で人を育てる文化」を作ることが、長期的な人材不足解決のカギとなる。
①OJTと研修制度の充実
・メンター制度を導入し、若手が先輩社員から学べる環境を作る
・社内研修をオンライン化し、どこでも学べる仕組みを整える
あるIT企業では、「学び続ける文化」を作るために、社員の学習費用を全額補助する制度を導入し、結果として定着率が向上している。
②キャリアパスの明確化
社員が「この会社で成長できる」と感じることが離職防止につながる。
そのために、
・昇進の基準を明確化する
・スキルアップのロードマップを提示する
といった施策を導入する企業が増えている。
4.事業構造の見直しによる省人化の工夫
最後に、人手不足を根本から解決するためには、「そもそも人手を減らせる仕組みを作る」ことも重要だ。
①業務の自動化・DXの導入
近年、多くの企業がRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入し、単純作業を自動化している。
・チャットボットでカスタマーサポートを自動化
・AIを活用して営業リストの作成を効率化
こうした仕組みを活用することで、「人が足りないから業務が回らない」という問題を解消できる。
②店舗の無人化・セルフサービス化
飲食業界では、セルフレジやモバイルオーダーを導入し、省人化を進める店舗が増えている。
特にファストフード業界では、注文から支払いまでをアプリで完結させることで、従業員の負担を大幅に減らしている。
まとめ
人材不足を逆手にとる新しい採用戦略として、以下の4つのアプローチが有効だ。
✔シニア・女性・外国人労働力を活用する
✔アウトソーシングや副業人材を活用し、業務を最適化する
✔「自社で人を育てる」文化を作り、長期的に人材を確保する
✔事業構造の見直しによる省人化を進める
次章では、実際に人材確保に成功した企業の具体的な事例を紹介する。
第6章:成功事例から学ぶ、人材確保のヒント

人材不足に悩む企業は多いが、その中でも創意工夫によって人材確保に成功している企業も存在する。
成功した企業に共通するのは、「従来の採用手法に頼らず、新しい視点で人材確保の仕組みを構築した」ことだ。
本章では、リファーラル採用の成功例・完全リモートワークの導入・技能実習生制度の活用という3つのケースをもとに、具体的な成功の秘訣を紹介していこう。
1.リファーラル採用で人材確保に成功(飲食業の事例)
飲食業界は人材不足が特に深刻な業界のひとつだ。
「求人広告を出しても応募がない」「せっかく採用してもすぐに辞めてしまう」という悩みを抱える企業が多い。
しかし、ある飲食チェーンではリファーラル採用(社員紹介制度)を導入することで、採用難を克服した。
成功ポイント
✔社員が信頼できる人材を紹介するため、ミスマッチが少ない
✔紹介者にインセンティブ(紹介ボーナス)を支給し、積極的な協力を促す
✔紹介された人材の定着率が高く、採用コストを削減できる
この企業では、「紹介した人が3ヶ月定着すると、紹介者に5万円のボーナスを支給する」という制度を導入。
結果として、通常の求人媒体よりも定着率が1.5倍向上し、採用コストも30%削減できた。

「飲食業界は離職率が高いが、紹介採用なら働く側の安心感も違うよな。」
2.完全リモートワークの導入で全国の人材を確保(IT業界の事例)
IT業界では、スキルのある人材が不足しており、採用競争が激しい。
特に、地方企業や中小企業にとっては、「優秀なエンジニアを採用できない」というのが大きな課題になっている。
そんな中、あるIT企業では「完全リモートワーク採用」を導入することで、人材確保に成功した。
成功ポイント
✔勤務地を問わず、全国どこからでも優秀な人材を採用できる
✔通勤の負担がなくなり、社員の満足度と生産性が向上
✔「フルリモートOK」という条件が魅力となり、応募数が急増
この企業は、オフィスを持たずに「全社員リモート勤務」に切り替えた。
これにより、北海道から沖縄まで全国のエンジニアから応募が殺到し、人材不足を解消することができた。
また、働きやすい環境が整ったことで離職率も低下し、定着率が上がったという副次的な効果も得られた。
3.技能実習生制度を活用し、若手人材を確保(建設業の事例)
建設業界は若手の採用が難しく、職人の高齢化が進んでいる業界だ。
特に地方の中小企業では、新卒の採用がほぼ不可能という厳しい状況が続いている。
そんな中、ある地方の建設会社では、技能実習生制度を活用することで人材不足を克服した。
成功ポイント
✔外国人技能実習生を受け入れ、若手人材を確保
✔日本語教育や技術研修を充実させ、長期的な戦力に育成
✔文化の違いを理解し、職場環境を整備することで定着率を向上
【エピソード】
この企業では、ベトナムやフィリピンからの技能実習生を受け入れ、しっかりとした教育体制を整えた結果、定着率も向上。
最初は言葉の壁や文化の違いに苦労したが、日本語研修やメンター制度を導入することで、実習生が安心して働ける環境を作ることに成功した。
今では実習生の8割以上が3年以上勤務し、「若手がいない」という課題を克服することができた。

「受け入れ体制を整えれば、外国人労働者も長く活躍できるんです。」
まとめ
成功企業に共通しているのは、従来のやり方にこだわらず、新しい採用手法を取り入れていることだ。
✔リファーラル採用で「紹介による信頼できる人材」を確保する(飲食業)
✔完全リモートワークを導入し、全国の優秀な人材を獲得する(IT業界)
✔技能実習生制度を活用し、若手人材を確保する(建設業)
このような取り組みを参考にしながら、自社に合った採用戦略を考えることが重要だ。
次章では、これまでの内容をまとめ、今後の採用活動の方向性について考察する。
第7章:まとめと感想-企業が今すぐ取り組むべきこと
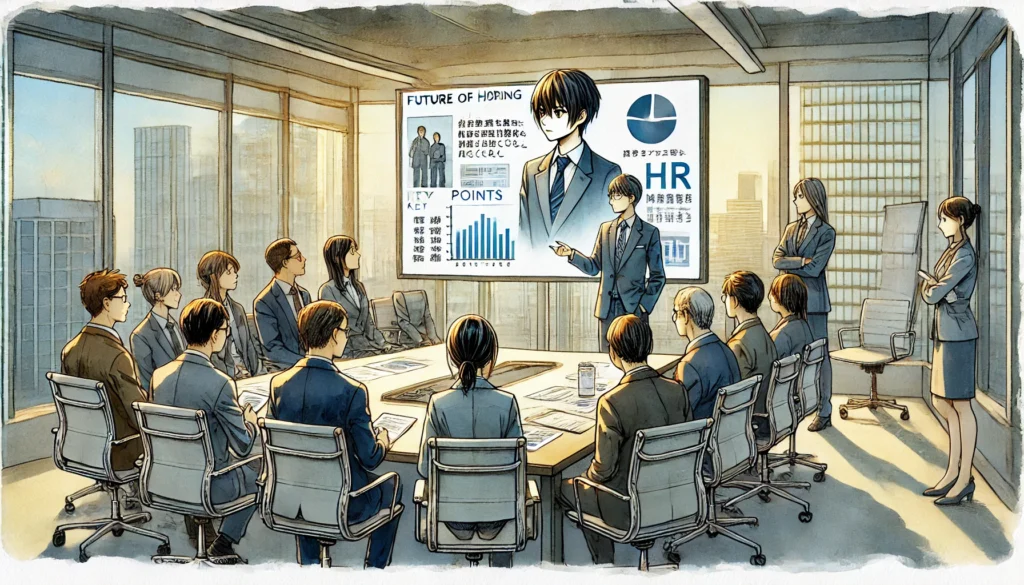
人材不足は、多くの企業にとって避けて通れない課題だ。
しかし、成功している企業は、この問題を単なる「困りごと」としてではなく、「成長のチャンス」と捉えている。
本章では、これまでの内容を振り返りながら、企業が今すぐ取り組むべきポイントを整理し、成功するための共通点を考察する。
1.人材不足の要因と解決策の整理
まず、人材不足が起こる主な要因を改めて整理しよう。
・少子高齢化による労働人口の減少 → シニア・女性・外国人の活用
・働き方の価値観の変化 → テレワーク・フレックスタイムの導入
・採用競争の激化 → リファーラル採用・ダイレクトリクルーティングの活用
・定着率の低下 → 教育制度の充実・キャリアパスの明確化
・業務負担の増加 → アウトソーシング・省人化の推進
どの業界でも「人材不足をどう乗り越えるか?」が問われているが、単に人を採用するだけでは根本的な解決にはならない。
大切なのは、「採用」だけでなく、「定着」や「業務効率化」までを一体的に考えることだ。
2.採用・定着・業務効率化の3つのポイント
人材不足を乗り越えるためには、次の3つの視点を持つことが重要だ。
①採用の工夫:人材を「引き寄せる」仕組みを作る
・SNS採用・動画採用を活用し、求職者との接点を増やす
・リファーラル採用を導入し、紹介による信頼できる人材を確保する
・完全リモートワークなど、働く場所に縛られない採用方法を取り入れる
特に、「企業が人を選ぶ時代」から「人に選ばれる時代」へと変化していることを理解しなければならない。
②定着の工夫:「辞めさせない」環境を作る
・キャリアパスを明確にし、「この会社で成長できる」と思わせる
・テレワークやフレックスタイムなど、柔軟な働き方を取り入れる
・教育制度を充実させ、スキルアップの機会を提供する
採用してもすぐに辞めてしまっては意味がない。
「この会社なら長く働ける」と思わせることが、長期的な成長の鍵になる。
③業務効率化の工夫:「人に頼らない仕組み」を作る
・AIやRPAを活用し、単純作業を自動化する
・アウトソーシングを活用し、業務負担を減らす
・事業構造そのものを見直し、省人化を進める
特に、業務のデジタル化を進めることで、少人数でも回る組織を作ることができる。
3.「採用活動は企業の未来投資」成功企業の共通点
人材戦略をうまく活用している企業には、いくつかの共通点がある。
・採用手法を多様化し、優秀な人材を確保している
・社員が成長できる環境を整え、定着率を高めている
・デジタル化やアウトソーシングを活用し、業務効率を向上させている
つまり、「採用」→「定着」→「業務効率化」のサイクルをしっかり作ることが、企業成長のカギになる。
【エピソード】人材戦略を変え、企業成長を実現した企業の事例
ある製造業の企業では、「人手不足に悩むのではなく、今いる人材を活かすことに注力しよう」と考えた。
そこで、
✔シニア社員の再雇用を推進(若手への技術継承)
✔AIを活用して生産ラインを自動化(単純作業を減らす)
✔リファーラル採用を導入(社員紹介による採用の効率化)
という施策を実施。
結果として、生産性が20%向上し、新規採用が困難だった人手不足の課題を克服することができた。
「人を増やすこと」だけにフォーカスせず、「今いる人材をどう活かすか?」に注目したことで、会社全体の競争力も高まった。
まとめ:企業が今すぐ取り組むべきこと
人材不足は、一時的な問題ではなく、今後も続く社会構造の課題だ。
しかし、成功企業の事例を見てもわかるように、
✔採用の工夫(SNS採用・リファーラル採用)
✔定着の工夫(キャリアパスの明確化・柔軟な働き方)
✔業務効率化の工夫(AI・RPA活用・アウトソーシング)
を取り入れることで、企業は「人手が足りない」状況を乗り越え、成長できる。
つまり、人材不足は「企業の生き残り戦略」を見直すチャンスでもある。
「人がいない」と嘆く前に、まずは「企業が人材に選ばれる仕組み」を作ることから始めよう。
今すぐ、採用戦略の見直しを実施し、企業の未来への投資を始めるべき時だ。




