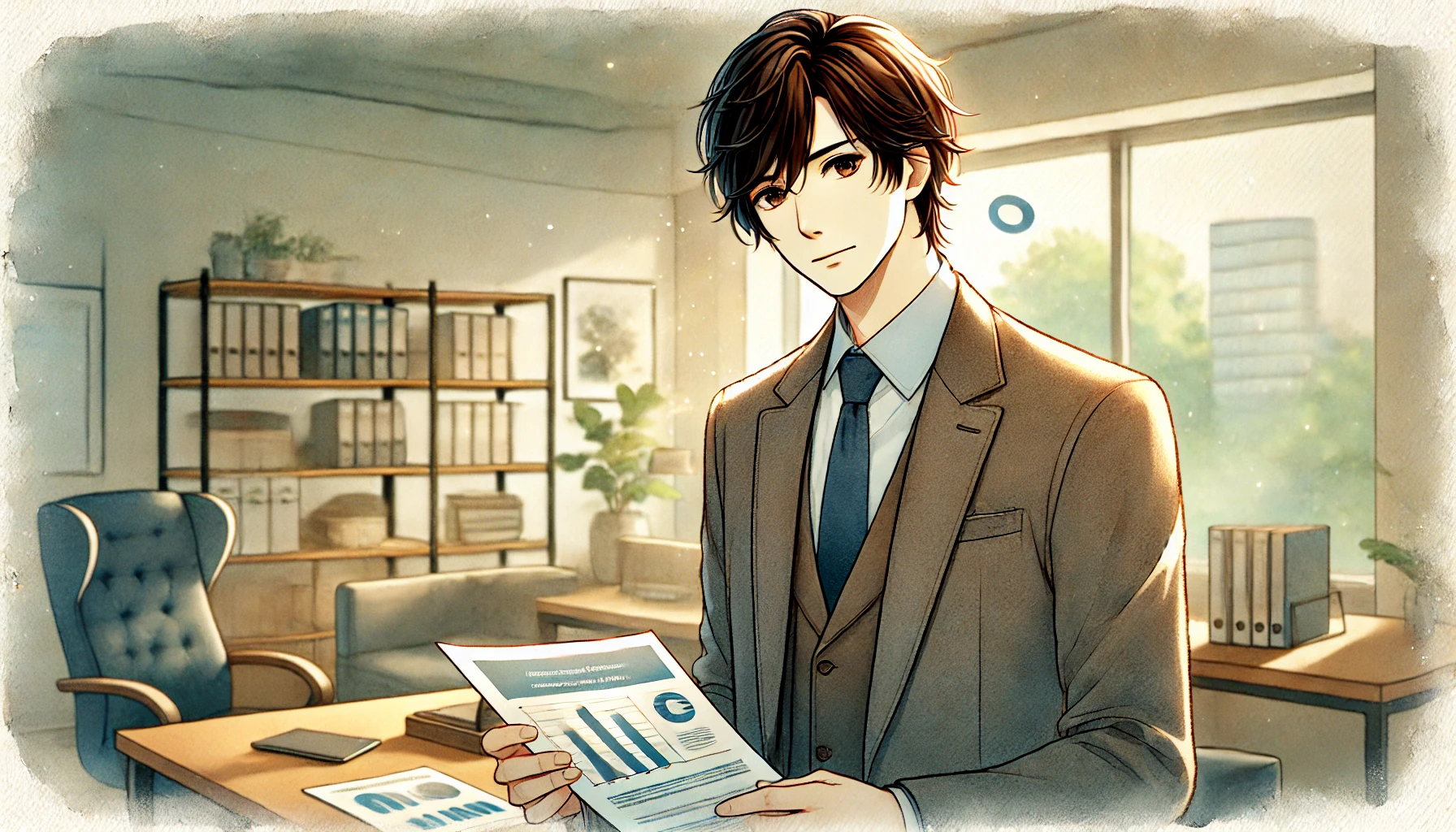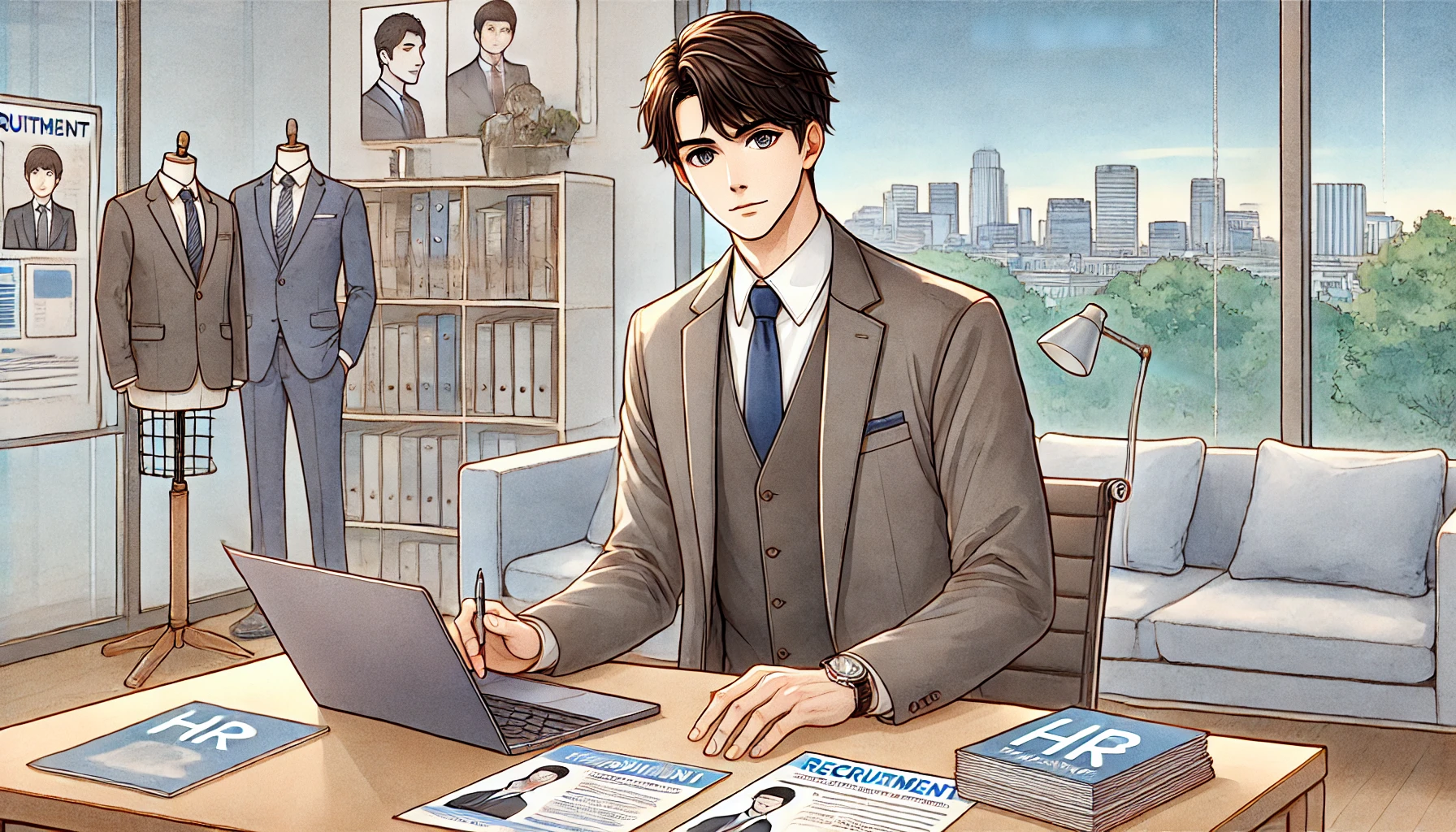「健康経営って本当に効果があるの?」そう思っていませんか?
近年、従業員の健康を経営の重要課題とする企業が増え、労働生産性や企業価値の向上に成功しています。
本記事では、健康経営の具体的なメリットと導入企業の成功事例を紹介。
さらに、導入のポイントや課題についても解説します。従業員の健康を守りつつ、会社の業績を上げたい経営者・人事担当者の方は必見です!
第1章:健康経営とは?なぜ今注目されるのか

健康経営の定義と概要
健康経営とは、従業員の健康を経営の重要な要素として捉え、戦略的に健康管理を推進する経営手法のことを指す。
これは単なる福利厚生ではなく、企業の生産性向上やコスト削減、さらには企業価値の向上にもつながるとされている。
この概念は1990年代にアメリカで「ヘルシーカンパニー」として注目され、日本では経済産業省が2014年に「健康経営銘柄」を発表したことで本格的に広がった。
現在では「健康経営優良法人認定制度」などの公的認証があり、導入企業が増えている。
従業員の健康状態が悪化すれば、欠勤率や離職率の増加、生産性の低下が起こる。
反対に、従業員の健康が守られ、働きやすい環境が整備されれば、モチベーションの向上や業績の向上につながる。

健康って個人の問題だと思われがちですが、企業にとっても無視できない要素なんです。
なぜ企業が健康経営を導入するのか?
企業が健康経営を導入する理由は、大きく3つに分類できる。
1. 生産性向上
従業員の健康状態が良ければ、集中力や判断力が向上し、業務効率も高まる。
特に、日本では過労やストレスが原因でのメンタルヘルス不調による休職が増えており、これを防ぐことが経営課題の一つになっている。
2. 企業イメージ向上と人材確保
健康経営を導入する企業は、求職者や取引先からの評価が高まりやすい。
実際に、「健康経営銘柄」に選ばれた企業は、採用活動において好影響が見られたというデータもある。
また、健康に配慮した企業文化は、従業員のエンゲージメントを高め、定着率を向上させる。
3. コスト削減
健康経営によって、医療費や保険料の負担が軽減される。
また、欠勤や休職の減少により、企業の業務リスクを低減できる。
長期的に見れば、健康経営にかかるコスト以上のリターンを得られるのが特徴だ。

企業側にとってもメリットが多いんだから、やらない手はないですね。
経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」とは
健康経営の推進を後押しするのが、経済産業省が実施する「健康経営優良法人認定制度」だ。
この制度は、健康経営に積極的に取り組む企業を「健康経営優良法人」として認定し、社会的に評価する仕組みである。
健康経営優良法人には、「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」があり、一定の基準を満たす企業が認定される。
例えば、「健康診断の受診率の向上」「ストレスチェックの実施」「運動促進の施策」など、従業員の健康維持に貢献する取り組みが評価される。
認定を受けることで、企業のブランド価値が向上し、採用活動にも好影響を与える。
また、一部の自治体では、健康経営優良法人に認定された企業に対して、税制優遇や助成金の支援が行われている。
健康経営に取り組む企業の増加傾向
近年、健康経営に取り組む企業は急増している。
経済産業省によると、2023年には「健康経営優良法人」に認定された企業が14,000社を超えた。
これは2017年の認定開始時の約4倍の数に相当する。
その背景には、労働人口の減少や、従業員の健康意識の高まりがある。
また、健康経営を導入することで企業価値が向上し、投資家や取引先からの評価も高まることが、大手企業を中心に導入を後押ししている。
【エピソード】健康経営を導入し、売上が増加した中小企業の話
ある地方の製造業の中小企業では、社員の健康意識の低さが課題だった。
欠勤率が高く、慢性的な人手不足に悩まされていた。
そこで、健康経営を導入。
まずは、朝礼でラジオ体操を実施し、全社員が一日10分間の軽運動をすることを義務付けた。
さらに、社員食堂での食事の改善を行い、低カロリー・高たんぱくのメニューを提供。
喫煙率が高かったため、社内で禁煙支援プログラムも実施した。
その結果、1年後には社員の平均BMIが改善し、体調不良による欠勤率が15%減少。
さらに、社内の雰囲気も向上し、エンゲージメントが高まったことで生産性が向上した。
それだけでなく、従業員のモチベーションが上がり、新規取引の受注件数も増加。
結果として売上が10%アップしたのだ。
このように、健康経営は単なる「福利厚生」ではなく、企業の成長戦略の一環として機能する。
まとめ
健康経営は、従業員の健康を守るだけでなく、企業の利益向上にも直結する。
生産性の向上、企業イメージの向上、コスト削減といった具体的なメリットがあり、多くの企業が導入を進めている。
経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」によって、健康経営が社会的に評価されるようになり、認定企業は増加の一途をたどっている。
特に、健康経営を導入した企業の成功事例を見れば、その効果は明らかだ。
健康経営は「企業の未来への投資」として、多くの経営者にとって必要不可欠な取り組みになっている。
第2章:健康経営がもたらす5つのメリット
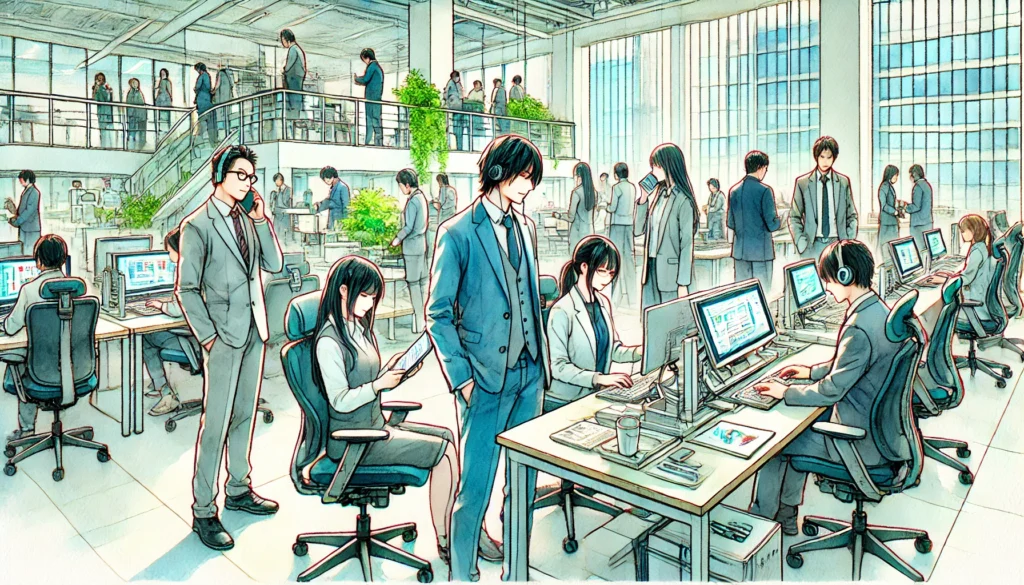
健康経営は、単なる従業員の健康管理ではない。
企業の経営戦略の一環として、生産性向上やコスト削減など、具体的なメリットをもたらす。
ここでは、健康経営が企業にもたらす5つの主要なメリットを解説する。
【メリット①】生産性向上:社員の健康改善が仕事の効率に与える影響
従業員の健康状態が良好であれば、仕事のパフォーマンスは自然と向上する。
これは単なる理論ではなく、多くの研究でも証明されている。
例えば、日本生産性本部の調査によると、体調不良による生産性低下(プレゼンティーズム)が企業の業績に大きな影響を与えていることが分かっている。
疲労やストレスを抱えた社員は、集中力が低下し、ミスが増える。
その結果、作業効率が悪化し、企業の業績にも悪影響を及ぼす。
反対に、健康経営に取り組むことで、適度な運動やストレスマネジメントが習慣化し、従業員のパフォーマンスが向上する。
例えば、ある企業では、社員の健康促進のために「朝のストレッチ」「定時退社デー」「オフィスにフィットネス機器を導入」することで、業務効率が10%向上したという。

「体調が良ければ仕事もスムーズに進むのは、誰でも経験ありますね!」
【メリット②】企業イメージ向上:健康経営で社会的評価が高まる理由
健康経営は、企業の社会的評価にも大きく影響する。
消費者や取引先、求職者の間で「健康経営に取り組んでいる企業=社員を大切にする会社」という認識が広まり、企業ブランドの価値が向上する。
特に、経済産業省が認定する「健康経営優良法人」の称号は、企業の社会的評価を高める大きな要素となっている。
この認定を受けた企業は、投資家や取引先からの評価が高まり、ビジネスチャンスが拡大する傾向がある。
また、消費者の間でも、社会的責任(CSR)を果たしている企業を支持する動きが強まっている。
「ブラック企業」や「過労死」が社会問題化する中で、従業員の健康を重視する企業は、ポジティブなイメージを持たれやすい。

「求人サイトでも『健康経営に取り組む会社』ってアピールされてるのをよく見ますね!」
【メリット③】離職率の低下:働きやすい職場づくりの成功事例
健康経営を導入すると、従業員の職場満足度が向上し、結果的に離職率が低下する。
例えば、あるIT企業では、社員のメンタルヘルスケアを強化し、産業医やカウンセラーの相談窓口を設置した。
これにより、メンタル不調による退職者が30%減少したという。
また、健康経営を進めることで、労働環境の改善につながる。
例えば、「残業時間の削減」「リモートワークの推奨」「健康管理プログラムの提供」などが実施されることで、社員のワークライフバランスが整い、離職を防ぐことができる。
離職率の低下は、企業にとっても大きなメリットだ。
新たに社員を採用し、育成するには大きなコストがかかる。
健康経営によって定着率を向上させることは、長期的な経営戦略としても有効な施策といえる。
【メリット④】医療費・福利厚生コスト削減:会社の負担を軽減する仕組み
健康経営は、企業のコスト削減にも貢献する。
特に、企業が負担する健康保険料や医療費の削減につながる。
例えば、ある企業では、定期的な健康診断だけでなく、「予防医療プログラム(生活習慣改善指導)」を導入した。
その結果、生活習慣病の発症率が低下し、医療費が年間で数百万円削減されたという。
また、福利厚生の一環として「フィットネスジムの利用補助」や「禁煙プログラム」を導入することで、長期的に見れば医療費の負担が軽減される。
健康経営は「コストではなく投資」であり、従業員の健康が向上すれば、結果的に会社の負担も軽くなるのだ。
【メリット⑤】採用力の強化:健康経営が優秀な人材を引き寄せる
優秀な人材を確保するためにも、健康経営の取り組みは大きな強みとなる。
近年、求職者は「給与や福利厚生」だけでなく、「働きやすさ」や「健康への配慮」も企業選びの重要な要素と考えている。
特にミレニアル世代やZ世代は、「健康的に働ける環境」を重視する傾向がある。
実際に、健康経営優良法人に認定された企業の採用説明会では、求職者から「健康経営にどんな取り組みをしていますか?」という質問が増えているという。
また、健康経営を推進することで、「働きやすい会社」として口コミやSNSでの評判も向上し、応募者の増加につながる。
採用市場において競争が激化する中、健康経営に取り組むことは「優秀な人材の確保」に直結する重要なポイントになっている。
まとめ
健康経営には、企業にとって大きなメリットがある。
-
生産性向上:社員の健康状態が良くなれば、業務効率が上がる。
-
企業イメージ向上:健康経営に取り組むことで、企業の社会的評価が高まる。
-
離職率の低下:職場環境の改善につながり、定着率が向上する。
-
医療費・福利厚生コスト削減:健康管理を徹底することで、企業の負担が軽減される。
-
採用力の強化:健康経営が求職者の関心を引き、優秀な人材の確保につながる。
健康経営は、単なる「従業員のための施策」ではない。
企業の成長戦略として欠かせない要素であり、導入することで長期的な利益を生むことができる。
今後、より多くの企業がこのメリットに気付き、健康経営を経営戦略に取り入れていくことになるだろう。
第3章:成功企業に学ぶ健康経営の実践事例
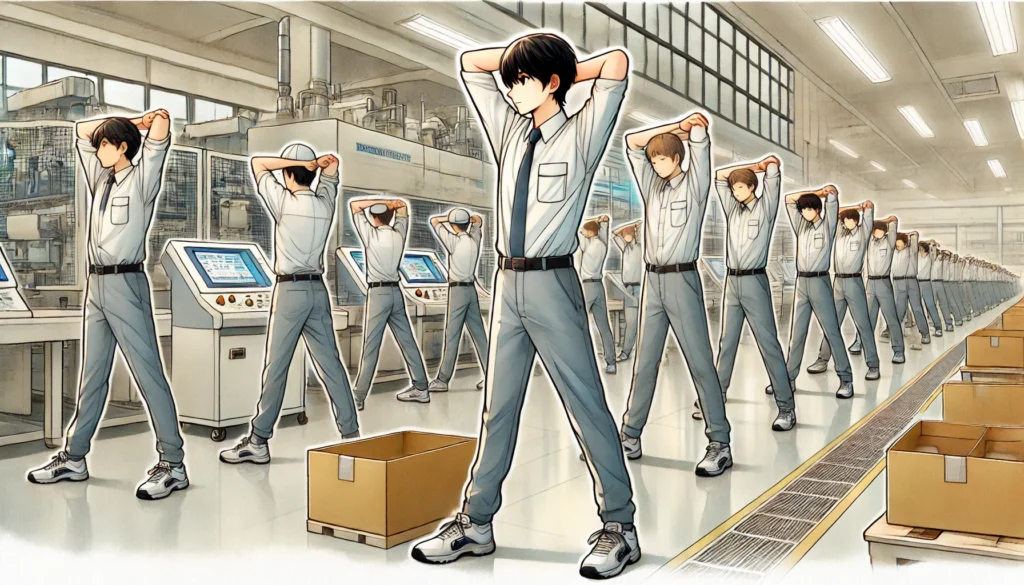
健康経営は、ただ理念を掲げるだけでは意味がない。
実際に取り組みを行い、成果を上げている企業の事例を学ぶことで、自社での導入のヒントを得ることができる。
本章では、健康経営によって具体的な成果を上げた4つの企業事例を紹介する。
業種や規模に関わらず、どの企業も工夫を凝らし、独自の施策で健康経営を成功させている。
事例① 大手IT企業:フルリモート×健康経営で生産性20%向上
背景:リモートワークの増加と健康リスク
ある大手IT企業では、コロナ禍をきっかけにフルリモートワークを本格導入。
しかし、従業員から「運動不足になった」「肩こりや腰痛がひどい」「メンタル面での不調を感じる」といった声が多く寄せられるようになった。
リモートワークは通勤時間の削減や生産性向上のメリットがある反面、運動不足や孤立感によるメンタルヘルスの問題が浮上する。
そこで、この企業は健康経営の観点から、リモートワーク環境でも健康を維持できる施策を実施した。
取り組み:バーチャル健康プログラムの導入
- オンライン朝ヨガ&ストレッチ:始業前に15分間のヨガを実施。自由参加だが、参加率は80%を超える。
- 歩数チャレンジ:従業員同士で1日の歩数を競うアプリを導入し、毎月表彰。
- メンタルヘルス支援:週1回、社内カウンセラーとの無料オンライン相談を実施。
成果:生産性20%向上、社員満足度アップ
・施策導入後、社員の体調不良による業務パフォーマンス低下が減少。
・リモートワーク環境でも、社員同士のつながりを感じられるようになり、生産性が20%向上。
・「会社が健康を考えてくれている」との声が増え、従業員満足度が前年より15%アップ。

「リモートだと健康管理が自己責任になりがちだけど、こういう仕組みがあると助かりますね!」
事例② 製造業の中小企業:朝のストレッチ導入で欠勤率50%減
背景:現場作業員の体調不良が多発
地方の製造業の中小企業では、従業員の腰痛や肩こりによる欠勤が増加。
特に、長時間の立ち仕事や重い荷物の運搬による負担が大きく、作業員の健康リスクが高まっていた。
取り組み:毎朝5分のストレッチを義務化
・就業前に、全員でストレッチを実施(専属トレーナーが動画で指導)。
・ラジオ体操とは異なり、現場作業員の身体に特化したストレッチを開発。
・ストレッチの前後で「体調チェックシート」を記入し、無理をさせないよう配慮。
成果:欠勤率50%減少、作業効率向上
・ストレッチ導入後、腰痛を理由とした欠勤が前年比50%減少。
・「朝にストレッチをすると、身体が軽くなる」との声が多数。
・業務の効率化につながり、製造ラインの生産性も向上。

「朝の5分でこれだけ効果があるなら、どの会社でも導入しやすいですね!」
事例③ 物流企業:歩数チャレンジで社員の健康意識向上
背景:運転業務が多く、運動不足が深刻
ある物流企業では、トラックドライバーの健康管理が課題だった。
長時間運転が続くと、運動不足や生活習慣病のリスクが高まり、健康診断の結果が悪化する従業員が増えていた。
取り組み:歩数チャレンジイベントを開催
・スマホアプリを活用し、社員同士で1日の歩数を競うイベントを実施。
・月ごとに歩数上位者を表彰し、健康に関する賞品を提供(例:ヘルシー弁当1カ月無料)。
・ウォーキング推奨ルートを作成し、休憩時間に歩く習慣を促進。
成果:運動習慣が定着し、健康診断の結果が改善
・半年後には、従業員の平均歩数が1日あたり3,000歩増加。
・健康診断の結果も改善し、高血圧や糖尿病のリスクを抱える社員が減少。
・「競争形式だから楽しく運動できる」と、社員の健康意識が向上。
事例④ 小売業:禁煙手当の導入で喫煙率30%減
背景:従業員の喫煙率が高く、健康リスクが懸念される
ある小売企業では、社員の喫煙率が40%を超えており、喫煙者の健康リスクや、休憩時間の長さが問題視されていた。
取り組み:禁煙手当とカウンセリング支援
・「禁煙成功者に毎月5,000円の手当」を支給。
・社内で「禁煙サポートプログラム」を導入し、産業医との無料カウンセリングを実施。
・喫煙所の削減とともに、禁煙者向けのリラックススペースを提供。
成果:喫煙率30%減、社員の健康意識向上
・1年後には喫煙率が30%減少し、禁煙成功者の多くが健康診断の数値を改善。
・「会社が本気で健康を考えてくれている」との声が増え、職場の雰囲気も向上。
【エピソード】健康経営で採用コストを大幅削減した企業の話
ある企業では、健康経営の取り組みを採用活動の武器として活用した。
「社員の健康を第一に考える企業」というブランディングが成功し、採用応募者数が前年の1.5倍に増加。
結果として、採用コストが30%削減された。
健康経営は、単なる「福利厚生」ではなく、企業の魅力向上にもつながる。
優秀な人材を引き寄せるためにも、健康経営は欠かせない要素となっている。
まとめ
本章では、健康経営の成功事例を紹介した。
これらの事例に共通するのは、「社員の健康を守ることが、企業の成長につながる」という考え方だ。
健康経営を進めることで、従業員の生産性が向上し、企業のブランド価値も高まる。
今後も、健康経営を実践する企業が増えていくだろう。
第4章:健康経営を導入するためのステップ

健康経営は、単なるスローガンではなく、企業戦略の一環として計画的に実施することが重要だ。
「とりあえず運動を奨励しよう」「禁煙支援をやってみよう」と場当たり的に施策を導入しても、従業員の健康改善にはつながらない。
そこで、本章では、健康経営を効果的に導入するための4つのステップを紹介する。
ステップ1:経営層のコミットメントを得る
健康経営を成功させるには、経営層が本気で取り組むことが不可欠だ。
トップが「社員の健康は会社の成長に直結する」と理解し、明確なメッセージを発信することで、従業員も本気で取り組むようになる。
経営層のコミットメントを得る方法
-
経営会議で健康経営の必要性をデータで説明(例:欠勤率・生産性のデータを提示)
-
健康経営推進を会社の経営方針の一部として明文化
-
経営層自ら健康施策に参加し、従業員と一緒に取り組む(例:朝のストレッチを社長が率先して行う)-

「経営陣が本気じゃないと、現場もやる気にならないんです!」
ステップ2:社内の健康課題を明確化する(従業員アンケート・データ活用)
健康経営を進めるには、「自社のどこに健康課題があるのか?」を把握することが重要。
やみくもに健康施策を導入しても、効果が出なければ意味がない。
まずは従業員の現状を知ることから始めよう。
健康課題を明確化する方法
-
従業員アンケートを実施(運動習慣・睡眠時間・メンタルヘルス状況などを調査)
-
健康診断結果の分析(生活習慣病リスクの把握)
-
プレゼンティーズム(体調不良による生産性低下)を測定(アンケート+データ分析)
例えば、「腰痛持ちの社員が多い」「メンタル不調による休職が増えている」など、データをもとに課題を把握する。
このステップを飛ばすと、従業員のニーズに合わない施策を打ち出してしまい、形だけの健康経営になってしまう。
ステップ3:健康施策を立案・実施(運動促進・メンタルケアなど)
課題を把握したら、次は具体的な健康施策の立案と実施だ。
企業によって健康課題は異なるが、一般的に以下の3つの施策が有効とされている。
① 運動促進プログラム
-
ウォーキングチャレンジの実施(スマホアプリで歩数を記録し、上位者を表彰)
-
オフィス内にスタンディングデスクを導入(座りすぎ防止)
-
朝のストレッチや体操を習慣化(負担なく始められる)
② メンタルヘルスケアの強化
-
ストレスチェックを定期的に実施(問題があれば早期対応)
-
社内カウンセリング窓口の設置(匿名で相談可能にする)
-
仕事量の適正管理(長時間労働の是正)
③ 食生活改善支援
-
健康的な社員食堂メニューの導入
-
栄養士によるセミナーを開催
-
社内にウォーターサーバーを設置し、水分補給を促進
これらの施策を「やらされている」と思われないよう、楽しさを取り入れることが成功のカギとなる。

「健康施策って、楽しめるかどうかが続くポイントなんです!」
ステップ4:成果の可視化(KPI設定とモニタリング)
健康経営は、取り組んだだけでは意味がない。
「実際にどれだけ効果があったのか?」をデータで可視化することが重要だ。
KPI(重要業績評価指標)の設定例
-
欠勤率の変化(施策導入前後で比較)
-
プレゼンティーズムの改善度(生産性向上の測定)
-
従業員満足度の向上(アンケートを定期的に実施)
-
健康診断結果の変化(生活習慣病リスクの低減)
KPIを設定し、定期的にモニタリングを行うことで、施策の効果を測定し、必要に応じて改善を加えていく。
【エピソード】健康経営の計画を立てたのに失敗した企業の例と成功の秘訣
ある企業では、経営層が「健康経営を導入しよう」と決めたものの、具体的な施策を従業員に丸投げしてしまった。
結果、「とりあえず運動会を開催」「とりあえずジムの割引を導入」といった場当たり的な施策が実施され、結局ほとんどの社員が参加しなかった。
さらに、施策の効果を測定する仕組みもなかったため、会社としての取り組みが続かず、2年後には形骸化してしまった。
成功のポイントは、「社員の意見を取り入れつつ、効果を測定し、経営層がコミットし続けること」だ。
例えば、成功した企業では、以下のような工夫をしている。
健康経営成功企業のポイント
✔ 社内アンケートを活用し、社員のニーズを把握(やりたくない施策はやらない)
✔ 健康プログラムを楽しく継続できるように設計(ゲーム感覚の歩数チャレンジなど)
✔ 経営層が率先して参加し、継続を支援(トップが動くと現場も動く)
✔ 成果をデータ化し、定期的に社内にフィードバック(改善のための指標を持つ)
まとめ
健康経営を導入するには、以下の4つのステップが必要だ。
-
経営層のコミットメントを得る(トップが本気になることが成功の鍵)
-
社内の健康課題を明確化する(従業員アンケートやデータ分析が重要)
-
健康施策を立案・実施する(運動・メンタルケア・食生活改善など)
-
成果を可視化し、KPIを設定してモニタリングする(長期的に継続する仕組みを作る)
この4ステップを実践することで、健康経営は「やっただけ」で終わらず、確実に成果を出せるものとなる。
経営層と現場が一体となり、継続的に取り組むことが成功のカギだ。
第5章:中小企業でもできる!簡単に始められる健康経営

健康経営というと、「大手企業がやるもの」「コストがかかる」と思われがちだ。
確かに、充実した健康施策を行うには、それなりの予算が必要な場合もある。
しかし、実際には 「低コスト」または「ゼロコスト」で始められる健康経営施策」 も多く存在する。
本章では、中小企業でも無理なく導入できる健康経営の取り組みを紹介する。
「健康経営を始めたいが、何から手をつければいいかわからない」という企業にとって、ヒントになる内容だ。
予算が少なくてもできる施策
中小企業の多くは、「健康経営をやりたいが、予算が限られている」という悩みを抱えている。
だが、予算が少なくても、ちょっとした工夫で健康経営を始めることは可能だ。
1. 休憩時間の「立ち上がりタイム」を設定する
デスクワークが多い職場では、長時間座りっぱなしになりがちだ。
「1時間に1回、1分間だけ立ち上がる」といった 「立ち上がりタイム」 を全社的に取り入れるだけで、血流が改善され、集中力もアップする。
コスト:0円
2. 社内チャットで「歩数報告」を習慣化する
健康管理アプリを活用し、毎日歩数を記録。
チームごとに「1日1万歩チャレンジ」などを実施し、歩いた歩数を報告し合うだけでも、運動の習慣化につながる。
コスト:0円(無料アプリを活用)
3. 簡単な健康コラムを社内メールで配信
月に1回程度、健康に関する情報をまとめた「健康ニュース」を社内メールで配信する。
例えば、「ストレスを軽減する食べ物」や「睡眠の質を上げる方法」など、手軽に実践できる情報を提供すると、自然と健康意識が高まる。
コスト:0円(社内で情報共有)

「こんなに簡単なことでも、積み重ねれば効果は絶大なんです!」
オフィスでできる簡単なストレッチ
デスクワーク中心の職場では、肩こりや腰痛が大きな問題になりやすい。
しかし、ジムに通う時間を確保するのは難しい。
そこで、オフィスのちょっとした時間でできるストレッチを取り入れるのが有効だ。
おすすめの簡単ストレッチ
-
肩回しストレッチ:両肩を大きく回す(肩こり防止)
-
立ち上がりスクワット:椅子から立ち上がる動作を10回繰り返す(下半身強化)
-
首のストレッチ:首を左右に傾け、10秒キープ(デスクワークの疲れ軽減)
朝礼や昼休みに3分だけ実施するだけでも、リフレッシュ効果がある。

「運動が苦手な人でも、これなら続けられますね!」
フリーの健康アプリを活用した歩数管理
スマホの無料健康アプリを使えば、簡単に歩数管理ができる。
企業向けの高額な健康管理システムを導入しなくても、手軽に「健康経営」を実践可能だ。
おすすめの無料健康アプリ
-
Google Fit(Android/iOS):歩数や心拍数、消費カロリーを記録
-
Nike Run Club(Android/iOS):ランニングやウォーキングを記録
-
あすけん(Android/iOS):食事の記録と栄養管理ができる
社内で「1カ月歩数チャレンジ」を実施し、優秀者を表彰するだけでも、運動習慣が定着する。
小規模企業向けの健康診断制度の活用
従業員の健康診断を実施することは、法律で義務付けられている。
しかし、小規模企業では「費用負担が大きい」「診断を受けに行く時間がない」といった理由で、未実施のケースも多い。
解決策として、自治体や商工会の支援制度を活用する方法がある。
例:小規模事業者向け健康診断の補助金制度
-
健康保険組合が提供する無料健康診断を活用(一部の協会けんぽでは年1回無料)
-
地方自治体の「健康診断助成金」制度を利用(市区町村によって異なる)
-
産業医の無料相談サービスを活用(中小企業向けに提供されている場合あり)
福利厚生としての健康経営施策(カフェテリアプランの活用)
「カフェテリアプラン」は、企業が用意した福利厚生メニューの中から、従業員が好きなものを選択できる仕組みだ。
大企業向けのイメージがあるが、実は 中小企業向けのカフェテリアプラン も存在する。
導入のメリット
✔ 食事補助(健康的な弁当を補助)
✔ フィットネスクラブの割引(社員の運動習慣を支援)
✔ マッサージ・整体の補助(肩こり・腰痛対策)
こうした福利厚生は、従業員の満足度向上につながり、離職率の低下にも効果がある。
従業員の巻き込み方(トップダウンとボトムアップのバランス)
健康経営を成功させるには、経営層が推進する「トップダウン」と、現場の意見を反映する「ボトムアップ」のバランスが重要だ。
✔ トップダウンの施策例:「健康経営の方針を明確化」「社長が率先して実施」
✔ ボトムアップの施策例:「社員アンケートで健康施策を決定」「健康プロジェクトチームを設置」
「やらされている健康経営」ではなく、「みんなで楽しく進める健康経営」 にすることで、より効果的な取り組みが可能になる。
【エピソード】予算ゼロで健康経営を成功させた小規模企業の実話
ある従業員30名ほどの中小企業では、健康経営に取り組む予算がなかった。
しかし、経営者の発案で 「無料でできることから始めよう」 という方針が決定。
✔ 毎朝、社長が先頭に立ってストレッチ(5分間の体操を全員で実施)
✔ 月1回「ヘルシーランチ会」を開催(持ち寄りランチで健康的な食事を共有)
✔ 社内に「歩数ランキング表」を掲示(無料アプリを活用し、ランキング形式で表彰)
結果として、わずか1年で欠勤率が20%減少し、従業員の健康診断結果も改善した。
「お金をかけなくても、意識を変えるだけで健康経営は成功する」ことを証明した好例だ。
まとめ
中小企業でも、予算ゼロまたは少額のコストで健康経営は可能だ。
✔ 簡単なストレッチや歩数チャレンジを導入
✔ 健康アプリを活用して運動習慣を定着
✔ 自治体の支援制度を利用し、健康診断を実施
無理なく始められる施策を積み重ねることで、企業全体の健康意識を高め、長期的な成果につなげることができる。
第6章:健康経営にかかるコストと投資対効果

「健康経営にはお金がかかるのでは?」
これは、多くの企業経営者が抱く疑問だ。
確かに、健康経営を実施するには 健康診断の強化、福利厚生の充実、健康プログラムの導入 など、一定のコストが発生する。
しかし、健康経営は単なるコストではなく、長期的に見れば企業の成長につながる投資 である。
本章では、健康経営にかかる主な費用項目と、それに対する投資効果 を解説する。
さらに、実際の企業データをもとに、健康経営がどれほどのコスト削減につながるのか を見ていこう。
健康経営にかかる主な費用項目(健康診断・研修・福利厚生など)
健康経営にかかる主な費用には、以下のようなものがある。
1. 健康診断・医療サポート関連
企業が従業員の健康を守るためには、定期健康診断の充実が不可欠 だ。
-
健康診断費用(一般的な健診は5,000円〜15,000円/人)
-
人間ドックの補助(1人当たり30,000円〜50,000円の企業負担が一般的)
-
ストレスチェック実施(1人当たり1,000円〜3,000円)
-
産業医やカウンセラーの導入(月額数万円〜)
2. 健康増進プログラム・研修
従業員の健康意識を高めるためには、研修やフィットネスプログラムの導入 も重要だ。
-
健康セミナーの開催(1回あたり50,000円〜100,000円)
-
運動習慣促進(ジム費用補助など)(1人当たり月5,000円〜10,000円)
-
メンタルヘルス研修(年間200,000円〜500,000円)
3. 福利厚生の充実
健康経営を推進する企業の多くは、従業員の生活習慣を改善するための福利厚生 を充実させている。
-
健康的な食事の提供(社食・弁当補助)(1人あたり月3,000円〜5,000円)
-
ウォーターサーバーの設置(月額5,000円〜10,000円)
-
禁煙支援プログラムの導入(1人当たり10,000円〜50,000円)
コスト削減効果の実証データ
「健康経営に投資することで、本当に企業のコストは削減できるのか?」
ここでは、実際の企業データをもとに、健康経営によるコスト削減効果を検証する。
欠勤・休職率の低下と生産性向上
従業員の健康状態が向上すると、欠勤や休職の減少 につながる。
例えば、経済産業省の調査では、健康経営に積極的に取り組む企業の方が、そうでない企業と比べて 欠勤率が30%低い というデータがある。
また、メンタルヘルス対策を強化した企業では、休職率が50%減少した事例もある。
例えば、あるIT企業では、ストレスチェックとカウンセリング支援を強化した結果、休職者が前年比40%減少し、生産性が15%向上 した。

「健康管理で欠勤率が減るなら、これほど分かりやすい投資効果はないですね!」
医療費・保険料の削減
従業員の健康が改善されると、企業が負担する医療費や保険料の削減 につながる。
経済産業省の「健康経営度調査」によると、健康経営優良法人に認定された企業では、医療費が年間で1人あたり30,000円削減された というデータがある。
また、アメリカのJohnson & Johnson社では、30年以上にわたる健康経営の取り組みの結果、医療費が年間2.3%削減され、総額で約250億円のコスト削減 を達成している。
健康経営による医療費削減は、企業の財務面に直接的なメリットをもたらす のだ。
「健康経営はコストではなく投資」である理由
ここまで見てきたように、健康経営にかかる費用は一時的なコストではなく、長期的に企業の成長につながる投資 である。
健康経営が「投資」と言える3つの理由
-
従業員のパフォーマンスが向上し、業績が伸びる
-
採用力が向上し、優秀な人材を確保しやすくなる
-
医療費・保険料・欠勤コストが削減され、財務面の負担が軽減される
例えば、ある大手企業では、健康経営の取り組みを強化した結果、従業員の離職率が25%減少し、採用コストが年間で2,000万円削減 された。
つまり、健康経営は単なる「従業員のための施策」ではなく、企業の競争力を高める戦略 なのだ。
【エピソード】コストを最小限に抑えて効果を最大化した企業の事例
ある中堅メーカーでは、「健康経営をやりたいが、予算がない」という課題を抱えていた。
そこで、コストを最小限に抑えつつ、効果的な施策を実施 することにした。
導入した施策(低コストで実現)
✔ 朝のストレッチを習慣化(無料)
✔ 禁煙チャレンジ制度を導入し、成功者に食事券を支給(年間10万円以下)
✔ メンタルヘルスの相談窓口を設置(外部の無料サービスを活用)
結果として、社員の体調不良による欠勤が20%減少し、医療費も前年比15%削減 できた。
たった数万円の投資が、数百万円のコスト削減につながったのだ。
まとめ
健康経営にかかる費用は一見高く感じるかもしれないが、その効果を考えれば「コスト」ではなく「投資」 である。
✔ 欠勤・休職率の低下と生産性向上 により、業績向上につながる
✔ 医療費・保険料の削減 で、企業の財務負担が軽減される
✔ 優秀な人材の確保と定着 により、採用コストが削減される
「健康経営は未来の利益を生み出す投資」であることを理解し、企業の成長戦略の一環として積極的に取り組むことが重要だ。
第7章:健康経営の落とし穴!失敗事例から学ぶ注意点
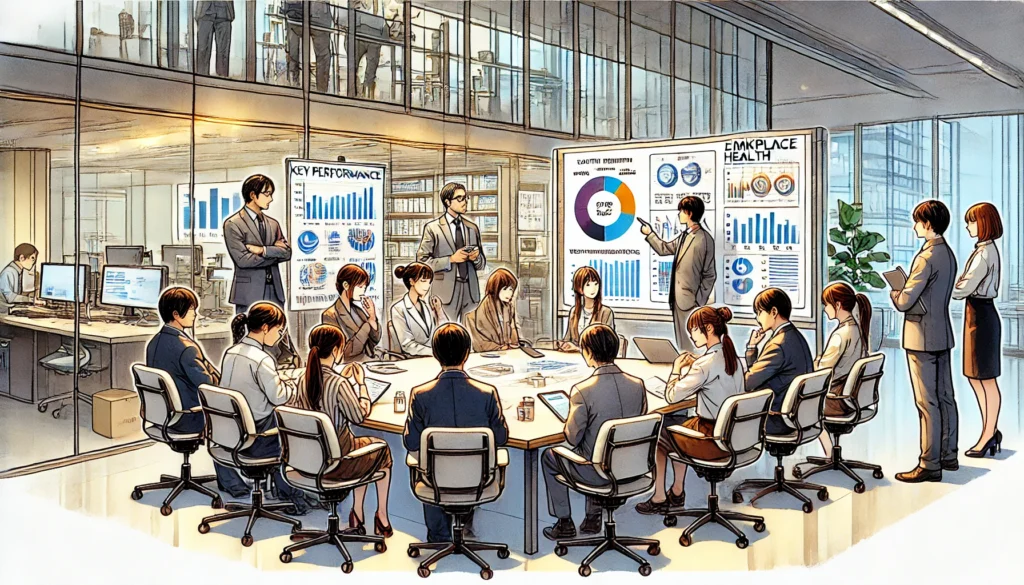
健康経営は、従業員の健康を守り、企業の成長につなげる素晴らしい取り組みだ。
しかし、「やっているつもり」 の健康経営では、むしろ逆効果になることもある。
現場の実態を無視した施策は、従業員の不満を招き、結果的に健康経営そのものが形骸化してしまうのだ。
本章では、実際にあった 健康経営の失敗事例 を紹介し、そこから学ぶべき教訓をまとめる。
さらに、成功するためのポイントも解説するので、これから健康経営を導入しようと考えている企業は必見だ。
失敗事例① 形だけの健康経営で従業員の不満が増大
ある企業では、健康経営の導入を決めたが、「とりあえず健康施策をやっている感」 を出すために形だけの施策を導入した。
その結果、従業員からの不満が爆発してしまった。
問題点
✔ 「経営陣が本気じゃない」と従業員が感じてしまった
✔ 施策の実施が一方的で、従業員の意見が全く反映されていなかった
✔ 本質的な健康課題の解決になっていなかった
例えば、この企業では「月1回の健康セミナー」を導入したものの、テーマが「ヨガの歴史」や「漢方の基礎知識」など、現場のニーズとまったく合っていなかった。
社員の多くは「もっと具体的に仕事に役立つ健康情報を知りたかった」と感じ、次第に参加者が激減。
半年後には誰もセミナーに出なくなり、形だけの施策として終了した。

「社員のニーズを無視すると、健康経営が逆にストレスになるんです!」
失敗事例② 健康施策がハードすぎて逆にストレスに
別の企業では、「社員の健康を守るためには運動が大事だ!」というトップの考えから、かなりハードな健康プログラムを導入した。
問題点
✔ 毎朝のランニングを義務化し、従業員の不満が増大
✔ 健康施策が「罰ゲーム」のようになってしまった
✔ 「健康経営=つらいもの」という認識が定着し、逆効果に
この企業では、「社員全員で毎朝30分のランニングをする」 という施策を強制的に導入。
その結果、「朝から疲れて業務に集中できない」「そもそも運動が苦手な人には地獄」といった声が上がり、モチベーションが低下。
最終的には、「健康経営はやめてほしい」という声が続出し、経営陣が施策を撤回する羽目になった。
失敗事例③ KPIが不明確で成果が見えず頓挫
健康経営を導入する企業の中には、「とりあえず何かやろう」と始めたものの、成果が見えないまま頓挫してしまうケース も多い。
問題点
✔ 目標(KPI)が曖昧で、効果測定ができなかった
✔ 「やった感」だけで終わり、実際の改善につながらなかった
✔ 経営陣の関心が薄れ、施策がフェードアウト
例えば、ある企業では、「健康経営をやるぞ!」と意気込んで「ウォーキングチャレンジ」を実施。
しかし、「どのくらい歩数が増えたのか」「生産性にどう影響があったのか」などの指標がなかったため、どの施策が効果的なのかが分からず、次第に関心が薄れてしまった。
結果、2年後には誰も話題にしなくなり、健康経営は事実上の終了を迎えた。
成功するためのポイント
では、健康経営を成功させるためには、どのようなポイントを押さえるべきなのか?
1. 従業員目線での施策設計
健康経営は、従業員が「やってよかった」と思えるもの でなければ意味がない。
✔ 事前にアンケートを実施し、社員の意見を反映させる
✔ 「やらされる」ではなく、「楽しめる」健康施策を設計する
✔ 一律の施策ではなく、多様な選択肢を用意する(例:運動・メンタルケア・食生活支援)
2. 継続的なPDCAサイクルの確立
✔ 施策の効果を数値で測定し、定期的に改善する
✔ 短期的な取り組みで終わらせず、長期的に健康経営を続ける
✔ 経営層が積極的に関与し、社内で継続する文化を作る

「健康経営は、やりっぱなしでは意味がですね!PDCAがすごく重要!」
【エピソード】健康経営の方向性を誤り、従業員の不満が爆発した企業の話
ある中堅企業では、「健康経営を推進する」と宣言し、経営陣が独自のアイデアで施策を決定。
しかし、それが 「経営層の理想」 であり、現場の実態とはかけ離れたものだった。
✔ 「オーガニックランチ必須」→健康的だが値段が高く、社員が困惑
✔ 「全社員で月1回マラソン大会」→運動が苦手な人にとっては苦痛
✔ 「禁煙者に特別ボーナス」→喫煙者からの不満が爆発
最終的に、従業員の間で「会社が余計なことをしている」と不満が高まり、健康経営が逆に職場の雰囲気を悪化させる結果となった。
まとめ
健康経営は、やり方を間違えると「逆効果」になりかねない。
✔ 形だけの施策は、従業員のモチベーションを下げる
✔ 健康施策が過度になると、逆にストレスになる
✔ KPIを設定せずに始めると、効果が見えずフェードアウトする
成功のポイントは、従業員の意見を取り入れ、継続的に改善していくこと だ。
企業と従業員が一緒に健康経営を進めることで、初めて「本当に意味のある健康経営」になる。
第8章:まとめと感想

これまで7章にわたって、健康経営のメリットや成功事例、導入ステップ、そして落とし穴まで 詳しく解説してきた。
「健康経営は企業の未来投資」と言われるが、単なる福利厚生ではなく、企業の競争力を高める戦略 であることが理解できたのではないだろうか。
本章では、これまでの内容を振り返りながら、「健康経営を明日から実践するための第一歩」 についても提案する。
本記事の振り返り
まず、本記事で解説してきた 健康経営の重要ポイント をおさらいしよう。
✔ 健康経営のメリットは、従業員の健康向上だけでなく、企業の生産性向上やコスト削減にもつながる
✔ 実際に成功した企業は、経営層が積極的に関与し、社員の意見を取り入れながら施策を設計している
✔ 失敗する企業の多くは、「形だけの健康経営」にとどまり、従業員の不満を招いている
健康経営のメリット5つ
健康経営には、以下の5つの大きなメリットがある。
-
生産性向上:社員の健康が改善されることで、業務の効率が向上する。
-
企業イメージの向上:健康経営に取り組むことで、社会的な評価が高まる。
-
離職率の低下:職場環境が改善され、社員の定着率が向上する。
-
医療費・保険料の削減:従業員の健康改善により、企業の負担が軽減される。
-
採用力の強化:健康経営が企業の魅力を高め、優秀な人材を確保しやすくなる。
成功企業の事例
健康経営に成功した企業の多くは、「従業員目線で施策を設計し、経営層が率先して実施している」 という共通点がある。
✅ 事例① 大手IT企業 → フルリモート×健康プログラムで生産性20%向上
✅ 事例② 製造業の中小企業 → 朝のストレッチ導入で欠勤率50%減
✅ 事例③ 物流企業 → 歩数チャレンジで健康意識を向上
✅ 事例④ 小売業 → 禁煙手当の導入で喫煙率30%減少
これらの事例を見ても分かるように、企業の規模を問わず、適切な施策を導入すれば、確実に成果が出る のが健康経営の特徴だ。
具体的な導入ステップ
健康経営を成功させるためには、場当たり的に施策を導入するのではなく、しっかりとした計画が必要 だ。
ステップ①:経営層のコミットメントを得る(トップが率先して健康経営を推進する)
ステップ②:社内の健康課題を明確化する(従業員アンケートや健康診断データを活用)
ステップ③:健康施策を立案・実施(運動促進・メンタルケア・食生活改善など)
ステップ④:成果の可視化(KPIを設定し、継続的に改善する仕組みをつくる)
健康経営は「企業の未来投資」
ここで強調したいのは、健康経営は「コスト」ではなく「未来への投資」 ということだ。
「健康経営を導入するのにお金がかかる」と感じるかもしれないが、実際には欠勤率の低下や医療費の削減によって、大きなコスト削減につながる ことが証明されている。
例えば、ある企業では健康経営の導入によって医療費が年間300万円削減され、結果的に利益を生む形になった。
このように、短期的な支出ではなく、長期的な企業の成長戦略として健康経営を捉えることが重要 だ。
明日からできる健康経営の第一歩
健康経営は、大掛かりな施策を導入しなくても、小さな取り組みから始めることができる。
✔ 朝のストレッチを習慣化する(5分間のストレッチで業務効率アップ)
✔ 歩数チャレンジを実施する(スマホアプリで歩数を記録し、健康意識を高める)
✔ 健康診断の受診率を向上させる(会社が積極的に受診を促す)
✔ ウォーターサーバーを導入し、水分補給を促す(脱水による集中力低下を防ぐ)
こうした小さな習慣が積み重なることで、社内の健康意識が高まり、最終的に企業の生産性向上や離職率低下につながる のだ。
【エピソード】健康経営が社内文化を変え、定着した企業の話
ある企業では、最初は「健康経営?うちは関係ない」と思っていたが、試しに朝のストレッチと歩数チャレンジを導入 してみた。
最初は一部の社員しか参加しなかったが、回数を重ねるごとに参加者が増加。
「体調が良くなった」「肩こりが減った」といった声が社内で広がり、気づけば健康経営が会社の文化として定着 していた。
現在では、従業員の意識が変わり、自発的に運動する社員が増え、健康診断の結果も改善 しているという。
この企業のように、健康経営は「企業が従業員に強制するもの」ではなく、「社員が自主的に取り組むもの」へと変化していくことが理想 だ。
まとめ
健康経営は、単なる流行ではなく、企業の持続的成長に欠かせない要素 である。
✔ 健康経営のメリットは、生産性向上・企業イメージ向上・離職率低下・医療費削減・採用力強化の5つ
✔ 成功する企業は、従業員の意見を取り入れ、継続的に施策を改善している
✔ 明日からできる小さな取り組みを積み重ねることで、社内の健康意識を高められる
健康経営は、「やらなければならないもの」ではなく、「やることで企業にとってプラスになるもの」だ。
今こそ、健康経営を企業の未来戦略の一つとして、本気で取り組む時代 だろう。